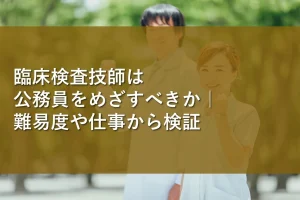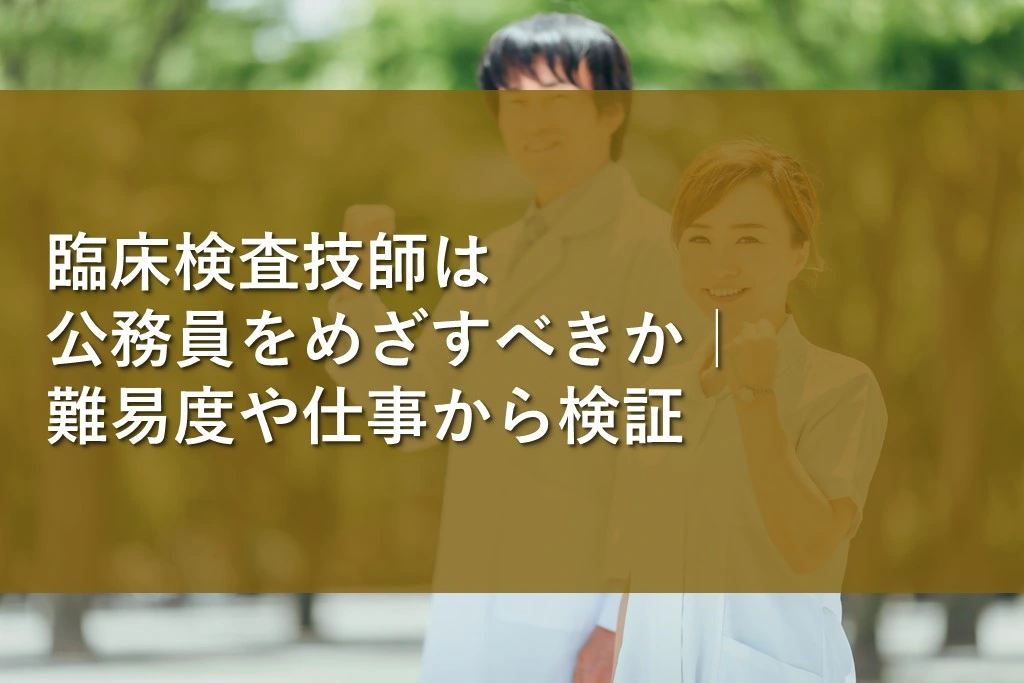
公務員として臨床検査技師の仕事に就きたい。
しかし、具体的にどのような仕事をするのか、また公務員として採用されるためにはどのような対策をすればよいのかわからない。
この記事ではそのような方に向けて、公務員として働く臨床検査技師の仕事内容と試験対策について解説します。
目次
公務員の臨床検査技師の仕事とは

公務員であっても、臨床検査技師の基本的な仕事内容は同じです。
とはいえ、働く場所によって違いはあります。
ここでは国公立病院、保健所、科学研究所の3つの職場について、公務員として働く臨床検査技師の仕事内容にどのような違いがあるのか解説します。
国公立病院
国公立病院で公務員として働く臨床検査技師の仕事内容は、基本的に民間病院と同じです。
- 血液検査
- 生化学検査
- 検体検査
- 生理機能検査
上記のような検査を行って患者さんの病気の原因を探したり、組織片から細胞の標本を作ったりします。
これらは民間病院でも行われており、違いは病院の運営母体が国公立か民間かだけです。
保健所
保健所で働く臨床検査技師の仕事内容は、主に公衆衛生に関する次のような業務です。
- 食品の細菌検査
- 水道施設の立入検査
- 食中毒などの発生時においての聞き取りや指導
これらは人が暮らしていくために必要な水や食料を、安全に人々に届けるための仕事です。
食中毒などが発生すれば指導を行うとともに、業務停止の行政処分を行うこともあります。
科学捜査研究所
科学捜査研究所は警察庁の付属機関です。科捜研とも呼ばれ、ドラマなどで名前を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。科学捜査研究所で行う仕事内容は以下のとおりです。
- 科学捜査
- 証拠物の鑑識、研究
科学捜査研究所では血液や汗といった体液を分析・研究、指紋の照合などを行います。科学的な証拠は警察の捜査に利用され、事件の解明に役立てられます。
事件によっては裁判所に出廷して証言することもあります。
臨床検査技師がすべき公務員試験対策とは
臨床検査技師が公務員として働くには公務員試験に合格しなければなりません。
国家公務員・地方公務員の試験対策が必須
国家公務員なのか地方公務員のかによって試験対策に違いはありますが、一般教養と臨床検査技師としての専門知識を問う筆記試験対策と面接対策が必要です。
公務員試験は筆記試験と人物試験に分かれています。
【筆記試験対策】
- 教養択一(基礎能力)試験
- 専門択一試験
- 教養論文試験
- 専門記述試験
【人物試験】
- 個別面接
- 集団面接
- 集団討論
筆記試験では基礎的な一般教養と臨床検査技師としての専門知識が問われます。
教養論文は800〜1,200字程度。課題に対して客観的な事実に基づいた答えを示し、自分の考えを盛り込んだ論理的な文章を書く能力が試されます。
面接は1対1の面接だけでなく、集団討論の対策もしておきましょう。
専門試験の対策も欠かせない
公務員試験にある専門択一試験では、当該職に関する専門知識が問われます。
臨床検査技師の場合であれば、医療や人体に関すること、栄養学、遺伝子などの内容です。
設問数は教養択一試験と比べて多くはありませんが、試験範囲の広さが特徴です。
受験する自治体によっては過去問が公開されています。具体的にどのような問題が出題されるのかイメージしやすくなるので、受験予定の自治体の公式サイトはチェックしておきましょう。
志望動機などの面接対策は民間対策と同様に
志望動機や面接対策は、民間企業と大きな違いはありません。
例えば志望動機や自己PRなどの面接対策は必須です。
個別面接の面接時間は15〜30分程度、受験者1人に対して、面接官3〜5名とじっくり話すことになります。
また、集団面接や集団討論といった、集団のなかで自分をアピールする試験が設けられることもあるので、受験する予定の自治体の傾向はしっかりと把握して対策をしておきましょう。
公務員をめざすなら試験対策を
臨床検査技師として公務員をめざすなら、公務員試験対策をしっかり行いましょう。
試験は単純に臨床検査技師としての能力だけでなく、公務員としての資質も問われる内容です。
臨床検査技師の年収がいくらくらいか気になる方は、次の記事をご覧ください。