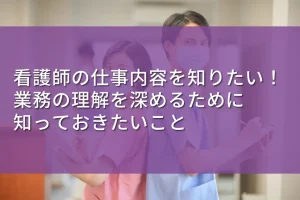看護師の新人はもちろん、集中治療室など特殊病棟に勤める看護師はAラインがあるため採血を行う機会が少ないでしょう。
そのため、いざ採血を行うとなったとき「失敗するんじゃないか」と不安になったことはないでしょうか。
採血を成功させるためには、経験や練習量も大切ですが、実は成功させるためのコツも複数あります。
ここでは採血のコツと確実な固定方法について、詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
看護師の採血にはコツがある

採血を得意にするためには経験も練習も必要ですが、まずは採血に適した血管を見つけることが成功のコツとなります。
まっすぐに走行している、弾力のある太い静脈を探すことがポイントです。
採血は適当に刺しても血管に入らないため、穿刺する前に採血に適した血管を選択する必要があります。
探す血管は、肘関節付近の正中皮静脈(肘の内側中央を走行する血管)ですが、見つかりにくい場合や、難しそうな場合には橈側皮静脈腕(腕の内側の親指側を通って走っている血管)や前腕皮静脈(腕のやや内側を走行する太い血管)を探すなど、比較的まっすぐかつ、太い血管を探しましょう。
抹消にいくほど痛点が多くなり、苦痛が強くなるため、見えるからといって安易に手背に刺すのは良くないでしょう。
採血のほか、看護師の仕事内容について興味がある人は、下記のURLに詳細が掲載されているため、確認してください。
採血のコツ|具体例
採血のコツの具体例を、下記の7つに分けて解説します。
- マッサージやホットタオルで温める
- 血管を指で確かめる
- 蛇行していない血管を選択する
- 駆血帯を適切な強さで締める
- 患者さん自身で手を握ってもらう
- 針は素早く挿入する
- 患者さんに血液採取時によく使う血管があるか聞く
マッサージやホットタオルで温める
血管は温まることで拡張しやすくなるため、静脈が浮き出て針を穿刺しやすくなります。
そのため、マッサージやホットタオルで温めることが効果的です。
しかし、緊急を要する採血時はホットタオルを準備している暇がないため、時間があるときに使えるコツとして覚えておくと良いでしょう。
叩くことを推奨していた時期もありますが、叩くことで赤くなりやすく、血管が見えづらくなる可能性があるためあまりおすすめしません。
血管を指で確かめる
血管が目視できたからといってすぐに刺してしまうと、想像以上に血管が深かったり、細かったりする可能性があり、うまく血管に刺さらないことがあります。
特に手背の血管は見えやすいですが、思いのほか細い場合や、弾力がなく血管に入っても破けてしまう恐れがあります。
目視できてもすぐには刺さず、実際に血管を指で触り、しっかりと弾力があるか、細すぎないかを確認することが重要です。
蛇行していない血管を選択する
蛇行している血管を選択すると、針先は血管内に挿入できても、針を進めた段階で血管を突き破ってしまう可能性があるため、針がまっすぐに挿入できるよう、蛇行していない血管を探すことがポイントとなります。
「針先だけ入れば良いのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、針先だけを挿入したまま安定させて固定することはとても難しいです。
採血中に針先が抜けるようなことがあっては、止血が遅れ内出血を作る原因になってしまうため注意しましょう。
駆血帯を適切な強さで締める
駆血帯を強く締めすぎると、動脈まで締めてしまうことで循環不良を起こし、余計に血管が見えづらくなる可能性があります。
逆に巻き方が緩すぎると、駆血できていないため血管が怒張しません。
駆血帯を締めるときは、橈骨動脈が触れているくらいの強さで駆血することがポイントです。
駆血帯を締めたあとに「手がしびれたりしませんか」と患者さんに声をかけるのも良いでしょう。
皮膚を挟んでしまい痛みがともなうなどの症状がある場合は、薄手の服をまくってその上から駆血すると、皮膚を直接締めないため痛みが緩和されます。ぜひ活用してください。
患者さん自身で手を握ってもらう
患者さんに手を握ってもらうことも、一つのコツです。
患者さんに「親指を中にして手をぎゅっと握りしめてください」と声をかけましょう。
手に力が入ることで、手指からの血流が増えて血管が怒張しやすくなります。
このとき、手を握ったり開いたりしてもらうこと(クレンチング)は避けましょう。
クレンチングをすると凝固能などに異常をきたしやすく、採血データを狂わせてしまう可能性があります。
どうしてもクレンチングを行う必要がある場合は、採血直前は避けるようにしましょう。
針は素早く挿入する
採血をする血管を選択したら、躊躇せずに素早く穿刺しましょう。
躊躇して血管に挿入すると、血管が動いてしまったり患者さんに必要以上の苦痛を与えてしまう可能性が増大します。
穿刺部位を決めたら、迷わずにすっと挿入することがポイントとなります。
誰でも採血をする前は不安ですが、自分自身を信じてトライすることも大切です。
この積み重ねが経験となって活きていくため、迷わず行いましょう。
患者さんに血液採取時によく使う血管があるか聞く
外来の患者さんなど、採血を何度かしたことがある患者さんであれば、いつもどの血管で採取できているかを知っている場合があります。
「ここでいつもとるよ」と教えてくれる患者さんもいますが、自分から「どのあたりの血管をいつも使っていますか?」と聞くことで、スムーズに採血を行うことができます。
血管を指定されることへのプレッシャーなどから、自分で探した血管が良いと思う場合もあるでしょう。
そのような場合は無理に確認せず、ほかのコツを活用して採血を行います。
採血時の確実な固定方法
上記のコツを活用し採血の穿刺ができても、しっかりと固定ができなければ必要量の血液を採取することは難しいです。
ここで採血時の確実な固定方法について、学んでいきましょう。
翼状針であれば針先がぶれないよう固定する
病院や施設によっては、翼状針と針を自由に使って良い場合があるでしょう。
ここではまず、翼状針の確実な固定方法について解説します。
翼状針は血管に入ったときに逆血が見えやすいため、好んで使用する看護師も多くいるでしょう。
しかし、シリンジで採取するときよりも針先が動きやすいという特徴があります。
そのため、しっかりと固定してからスピッツの出し入れをすることがポイントです。
慣れるまではしっかりと意識して固定しましょう。
シリンジは針先が抜けないようにゆっくりと引く
シリンジで採血をする場合は、翼状針のように自然と逆血がくることはありません。
そのため、自分の力でシリンジに陰圧をかける必要がありますが、必要以上に強く引いてしまうと溶血になり採血データがおかしくなってしまうほか、針先が抜けてしまう可能性があります。
針を挿入し血管に入ったと感じたタイミングで、刺入部を確認しながらゆっくりと引くようにしましょう。
少し引いても血液が上がってこない場合は、血管に留置できていない可能性があるため、針先を数mmだけ進めて、逆血を確認することがポイントです。
また針先が抜けないよう、血管に入ったことを確認して2㎜ほど針先を進めることで、陰圧をかけた際に針が誤って抜けるということを未然に防げるでしょう。
採血のコツを覚えて、採血マスターになろう
採血を成功させるためには、経験や練習量も必要ですが、コツを覚えておくことも効果的です。
本記事のようなコツを一つずつトライしていくうちに、採血に自信がもてるようになります。血管が見えづらい患者さんがいたとき「採血お願いしても良いかな」といわれるような、採血マスターをめざすことができるでしょう。
採血は患者さんの苦痛が目に見えてわかりやすいため、どうしても苦手意識をもちやすいですが、少しずつステップアップしていける分野でもあります。
この記事で採血の苦手意識を払拭できることを祈っています。