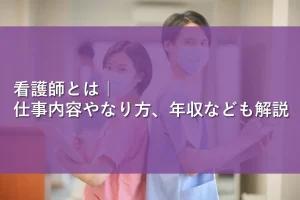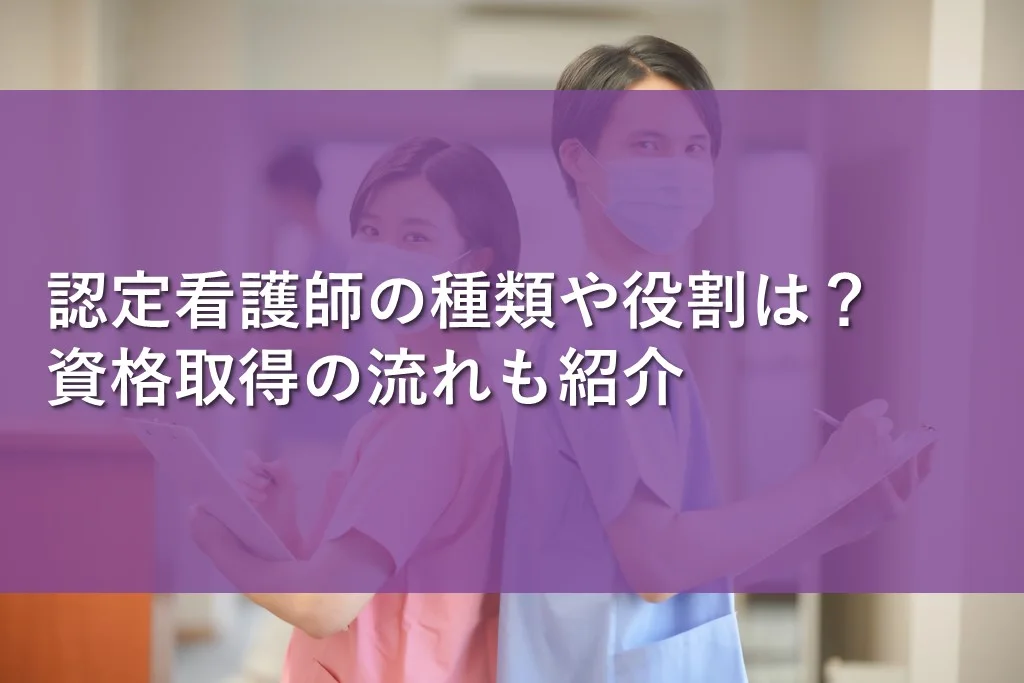
看護師として働く方がキャリアアップをめざすとき、「認定看護師」の資格を取得するという選択肢があります。
日々看護ケアを実践するなかで、「もう少しスキルや知識をつけて患者さんに良い看護を提供したい」と感じることがあるかもしれません。
認定看護師の資格を取得すれば、認定分野においてより高度な知識・スキルが身につき、看護師として質の高い医療の提供を実践できるようになるでしょう。
この記事では、認定看護師の種類や役割、資格取得までの流れを解説します。
目次
認定看護師とは?

認定看護師とは、認定分野において高度な知識・スキルを用いて患者さんにより良い看護を実践できる看護師です。
認定看護師の資格は、日本看護協会によって審査・認定されます。
日本看護協会の調査によると、認定看護師の勤め先としては病院が89.9%と大半を占めますが、その他にも訪問看護ステーションや診療所など活躍の場はさまざまです。
また、その知識とスキルを活かして役職に就く認定看護師も多く、管理職や中間管理職として働く方の数は6割を超えています。
認定看護師の3つの役割
認定看護師には、「実践」「指導」「相談」という3つの役割が求められます。
- 実践
認定看護師は患者さんやそのご家族に対して、認定看護分野における高い臨床推論力と病態判断力を発揮して、適切な看護を実践しなければなりません。 - 指導
自らも現場で看護を行いつつ、他看護師のお手本となったり直接指導したり、研修を計画するなど他看護師への教育を行う必要があります。 - 相談
患者さんへのケア方法を迷っている看護師の相談に乗る、改善策を提案するなどのコンサルテーションを行い、看護職員をサポートすることも認定看護師の役割です。
認定看護師と似て非なる資格として、専門看護師があります。
認定看護師と専門看護師では求められる役割が異なるため、どちらの道に進むべきか迷っている方は次の記事も参考にしてみてください。
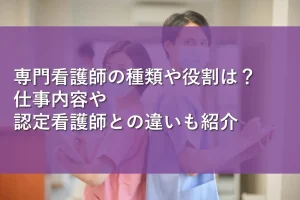
認定看護師の種類一覧
認定看護分野は、医療の複雑化や高度化などの社会的なニーズに応えるため、再編が行われました。
これにともない、2023年現在は認定看護師になるための教育課程としてA課程とB課程の2つが存在しています。
新しい教育課程であるB課程は2021年度から始まっており、もともと存在していたA課程は2026年に教育課程が終了、認定審査自体も2029年に終了となる見込みです。
それぞれの課程は、特定行為研修の有無やカリキュラムの面で違いがあります。
認定看護師をめざす際には、混同しないようにしましょう。
A課程:21分野
A課程の認定看護分野は、以下の21分野になります。
| A課程(21分野) | 内容例 |
| 救急看護 | 救急医療現場における適切な救命技術、災害時のケア |
| 集中ケア | 生命の危機状態にある患者さんへの重症化予防、早期リハビリの実施 |
| 緩和ケア | 疼痛、呼吸困難など苦痛症状の緩和 |
| がん性疼痛看護 | 疼痛に対するアセスメントと評価、薬剤の適切な使用の提案 |
| がん化学療法看護 | 抗がん剤の適切な投与管理、副作用に対するケア |
| 訪問看護 | 在宅療養患者へのセルフケア支援 |
| 不妊症看護 | 不妊治療などの生殖医療を受ける患者さんへの自己決定支援 |
| 透析看護 | 安全な透析治療の実施 |
| 摂食・嚥下障害看護 | 摂食・嚥下機能のアセスメントと安全な訓練の実施 |
| 小児救急看護 | 救急時の子どもに対する救命技術 |
| 脳卒中リハビリテーション看護 | 脳卒中の患者さんに対するケア、早期リハビリの実施 |
| 慢性呼吸器疾患看護 | 呼吸機能のアセスメント、呼吸管理、リハビリの実施 |
| 慢性心不全看護 | 病期に応じた生活調整やセルフケア支援 |
| 皮膚・排泄ケア | 褥瘡(じょくそう)などの創傷管理や排泄管理 |
| 感染管理 | 院内での感染リスクの評価と予防対策 |
| 糖尿病看護 | 血糖コントロールやフットチェックなどの療養生活支援 |
| 新生児集中ケア | リスクの高い新生児の重症化予防 |
| 手術看護 | 周手術期の安全管理や継続看護の実践 |
| 乳がん看護 | 患者さんの自己決定支援、心理・社会的問題の支援 |
| 認知症看護 | 療養環境の調整やケア体制の構築 |
| がん放射線療法看護 | がん放射線治療に対する副作用の支援、セルフケア支援 |
参考:認定看護師 | 看護職の皆さまへ | 公益社団法人日本看護協会
A課程で認定看護師の資格を取得した場合は、特定行為研修を追加で受講し手続きを行うことで、B課程の認定看護師に移行できます。
B課程:19分野
B過程における19の認定看護分野と教育課程の内容例は、以下のとおりです。
A課程と比較して、薬剤投与量の調整やカテーテル交換など通常医師が行う業務の一部を特定行為として研修し、実施できることが特徴です。
| B課程(19分野) | 内容例 |
| クリティカルケア | 持続点滴投与中の薬剤投与量の調整を実施できるスキル |
| 緩和ケア | 患者さんのQOL向上に向けた症状マネジメント |
| がん薬物療法看護 | 自宅療養中に副作用対策や治療管理を適切に行うための患者教育 |
| 在宅ケア | 気管カニューレ、胃瘻カテーテルなどの交換が安全にできるスキル |
| 生殖看護 | 妊孕性温存や受胎調節の指導 |
| 腎不全看護 | 血液透析器や血液透析濾過器の操作ができるスキル |
| 摂食嚥下障害看護 | 摂食嚥下機能の訓練方法の選択、リスク管理 |
| 小児プライマリケア | 虐待予防と早期発見、子どもの事故防止 |
| 脳卒中看護 | 抗けいれん剤、抗精神病薬の臨時投与ができるスキル |
| 呼吸器疾患看護 | 人工呼吸器を装着している患者さんに対する鎮静薬投与量の調整 |
| 心不全看護 | カテコラミンや降圧剤などの投与量の調整が安全にできるスキル |
| 皮膚・排泄ケア | 褥瘡や慢性創傷の壊死組織の除去が安全にできるスキル |
| 感染管理 | 病態をアセスメントし、感染兆候のある患者さんに薬剤の臨時投与ができるスキル |
| 糖尿病看護 | インスリン投与量の調整ができるスキル |
| 新生児集中ケア | ハイリスク新生児の全身管理 |
| 手術看護 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の管理や投与量の調整 |
| 乳がん看護 | 創部ドレーンが安全に抜去できるスキル |
| 認知症看護 | 抗けいれん剤や抗不安薬の臨時投与ができるスキル |
| がん放射線療法看護 | 医療被曝を最小限に抑えるための放射線防護策 |
参考:認定看護師 | 看護職の皆さまへ | 公益社団法人日本看護協会
【分野別】認定看護師の仕事内容
どの認定看護分野においても認定看護師の役割は実践・指導・相談の3つですが、具体的な仕事内容は分野ごとに少しずつ異なります。
ここでは、「皮膚・排泄ケア認定看護師」「感染管理認定看護師」「認知症看護認定看護師」をピックアップして、主な仕事内容を見てみましょう。
皮膚・排泄ケア認定看護師
皮膚・排泄ケア認定看護師はWOCナースとも呼ばれ、創傷(Wound)・オストミー(Ostomy)・失禁(Continence)分野に対して高い看護スキルや知識を持っています。
具体的な仕事内容の例は以下のとおりです。
- 皮膚トラブル・創傷の発生予防や適切なスキンケアの実施
医療現場では、ルート固定用のテープや術後の弾性ストッキングなど皮膚に負担のかかる処置を患者さんに実施するケースも珍しくありません。
皮膚・排泄ケア認定看護師は、事前に皮膚状態を総合的に判断し、皮膚障害リスクの高い患者さんに対して皮膚トラブルの予防策を提案したりケア計画を立案したりします。 - ストーマ造設予定の患者さんに対する看護
ストーマ造設後の生活について情報提供するとともに、ストーマ造設後に自宅で安心して生活ができるようにセルフケア指導を行います。
感染管理認定看護師
感染管理認定看護師は、働いている施設の状況に応じた感染管理を実施する看護師です。
具体的な仕事内容には、以下のようなものが挙げられます。
- 感染症対策
院内で感染対策が適切に実施されているか確認するほか、感染症が発生した際に対策を講じることが感染管理認定看護師の仕事です。
例えば、院内ラウンドなどで看護師の手指消毒の状況やPPEの着脱順番を確認し、院内の看護師が適切に感染予防対策を実施できているか判断するケースなどがあります。
加えて、必要時に職員に感染対策指導を行うこともあるでしょう。
感染症対策の一環として、感染対策マニュアルの作成にも関与します。
- 医療関連感染のサーベイランス
院内でのアウトブレイクの危険をいち早く発見するために、耐性菌の検出状況や手術部位感染などのデータを収集し、分析します。
必要時には、具体的な感染対策を立てることが求められるでしょう。
認知症看護認定看護師
認知症看護認定看護師とは、介護や福祉サービスと連携し、認知症の患者さんに対して質の高い看護を提供する看護師のことです。
精神科病院や介護老人保健施設をはじめとした保健福祉施設などで活躍しています。
具体的な仕事内容は以下のとおりです。
- 認知症患者さんへのケア
患者さんとの関わりを通してアセスメントを行い、適切な看護ケアを実施します。
例えば、症状の悪化防止や事故防止を目的として、病室を自宅の環境に近づけるなど環境整備を行うことなどが挙げられるでしょう。 - 他職種との連携、教育
認知症の患者さんへの対応方法を他職種に共有するほか、勉強会を実施します。
また、ケア方法に困っている看護師や介護士に対してアドバイスを行い、問題解決に取り組むことも仕事の一つです。 - ご家族からの相談対応
認知症症状のある患者さんとの関わりに悩んでいるご家族の相談に乗り、アドバイスを行います。
認定看護師になるには?
認定看護師の資格を取得するまでの流れは、次のとおりです。

認定看護師になるには、一定期間の実務研修を経て、認定看護師に必要なカリキュラムを受講し、認定審査に合格しなければなりません。
認定審査の受験資格や教育、試験概要をチェックしてみましょう。
認定審査の受験資格
認定看護師の資格認定審査を受けるには、以下3つの受験資格を満たす必要があります。
<認定審査の受験資格>
- 日本の看護師免許を持っている
- 実務研修が5年以上あり、そのうちの3年間は認定看護分野の研修であること
- 認定看護師教育機関(A課程・B課程)に通い、必要なカリキュラムを受講していること
まずは看護師資格を取得するべく、指定の養成学校で3年以上学び、看護師国家試験に合格することから始めましょう。
そのうえで実務研修を5年以上行い、一定のカリキュラムを受講することが必要です。
通算5年以上・認定分野で3年以上の実務研修を積む
認定看護師になるためには、通算で5年以上、認定分野で3年以上の実務研修を積まなければいけません。
認定分野によって、実務研修の内容に求められる基準が異なります。
例えば、がん薬物療法看護(B課程)認定看護師をめざすのであれば、がん薬物療法を行う病棟に3年以上勤務している経験に加えて、以下の基準を満たすことが推奨されています。
- がん薬物療法を受ける患者さんの看護を5例以上経験していること
- がん薬物療法薬の経静脈投与管理を1例以上経験していること
- 現在がん薬物療法を受けている患者さんの多い病棟・外来に勤務していること
また、認定看護師の教育機関に入学するときに実務研修の基準を満たしていることを示す必要があります。
認定分野によって基準は異なるため、前もって確認しておくと安心です。
認定看護師の教育課程を受ける
取得したい認定看護分野の教育課程を受けましょう。
教育課程は看護協会や教育センターなどで実施されており、B課程の場合には800時間程度のカリキュラムをこなす必要があります。
<B課程カリキュラム構成>
| 共通科目 | 380時間 | 特定行為のために必要な理解力や判断力を養う |
| 専門科目 (認定看護分野) |
225〜180時間 | 認定看護分野において看護師が特定行為のために必要な理解力や判断力を養う |
| 統合演習 | 15時間以上 | 実践した看護について文献を使って振り返るケースレポートを通し、総合的な看護実践能力を養う |
| 臨地実習 | 150時間以上 | 期待される能力や教育目的に必要なスキルを身につけるとともに、認定看護師の役割を担える能力も養う |
認定審査の試験概要
認定看護師の認定試験は、年に1回実施されます。
試験形式は筆記試験(マークシート形式)となっており、試験時間は100分です。
問題は、共通科目を含めた各認定看護分野のカリキュラム内容から出題されます。
<認定試験の構成>
| 出題方式 | 出題数 | 配点 |
| 一般問題 | 20問 | 50点 |
| 状況設定問題 | 20問 | 100点 |
150点満点中105点以上を取れたら合格です。
登録と5年ごとの更新
認定審査に合格したら、認定料を振り込み認定看護師として登録をしましょう。
なお、認定看護師の資格取得後は5年ごとの更新が必要です。
更新の際は、直近5年間に認定看護師として3つの役割を実践できているかどうか確かめるために、以下の要件が定められています。
<更新資格>
- 看護実践時間(看護師として現場で働いた時間)が2,000時間以上ある
- 自己研鑽時間(学会や院内研修プログラムへの参加)が50点以上ある
認定看護師になるための費用
認定看護師になるにあたっては、認定看護師の教育課程を受けるための費用や登録費用などを含め120〜170万円ほどかかります。
認定看護師をめざす際には、これらの費用が発生することも念頭に置いておきましょう。
| 費用項目 | 金額 |
| 入試受験費用 | 約5万円 |
| 入学費用 | 約5万円 |
| 授業料 | 約100〜150万円 |
| 審査費用 | 51,700円 |
| 認定費用 | 51,700円 |
※上記の項目に加えて実習などでも費用が発生する場合があります。
なお日本看護協会では、認定看護師をめざす方を対象に1年間に120万円まで借りられる奨学金制度を用意しています。
資格取得にあたって費用の工面に悩んでいる方は、奨学金制度を利用するのも一つの方法です。
認定看護師になるには一定の経験やカリキュラム受講が必要
認定看護師として働くには、一定の看護師経験が必須となるとともに、日本看護協会が定めるカリキュラム受講などの条件を満たす必要があります。
そのうえで、試験に合格した方だけが認定看護師を名乗ることが可能です。
容易な道ではないものの、認定看護師になれば専門分野への高度な看護実践能力が身につき、患者さんにより質の高い看護を提供できるようになります。
認定看護師の資格取得をめざす際には、まず興味のある認定分野の研修基準を確認し、今後やるべきことを明らかにしてみましょう。