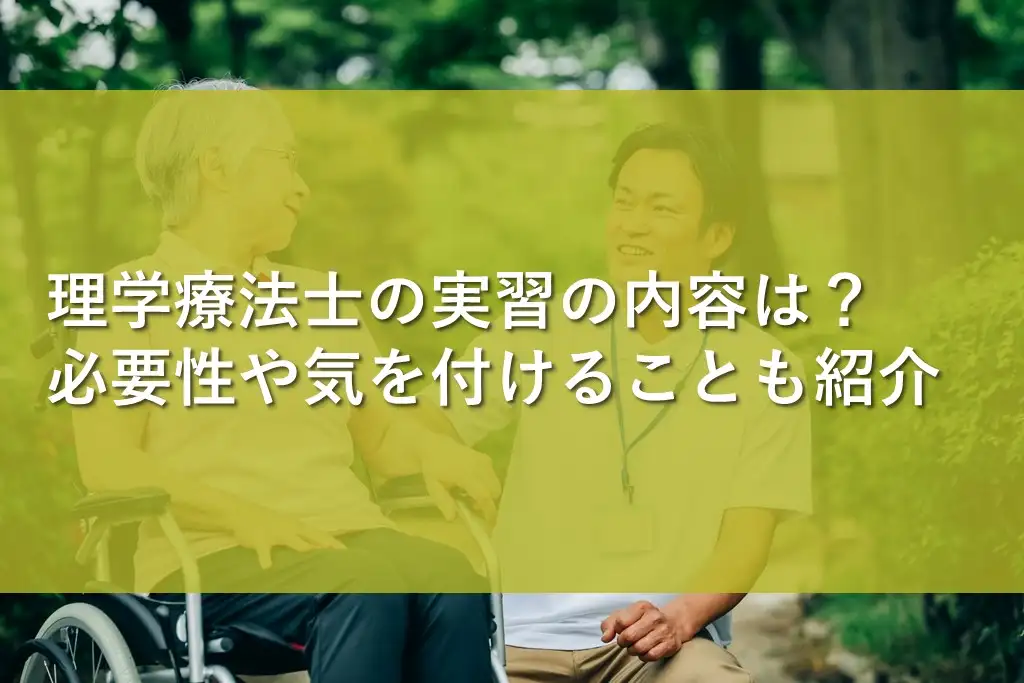
理学療法士の国家資格を取得するためには、実習を行うことが必要です。
この記事では理学療法士の実習の必要性や内容を解説しています。
また、実習を受けるうえで気を付ける点も紹介しているので参考にしてください。
目次
理学療法士の実習の必要性

理学療法士の実習は、大学などの養成施設で習得した知識や技術をもとに、養成施設では体験できない実践的な臨床経験を積むために行われます。
教科書を中心に理解した知識を、適切に実施できる技能へと成長させることが目的です。
また、臨床ではさまざまな医療従事者が連携して患者さんをサポートする「チーム医療」が展開されています。
実際に医療現場のなかで、患者だけでなく、他の理学療法士、看護師などの医療関係者と触れ合うことで、コミュニケーション能力や臨床時の接遇などの資質を養います。
CCSにおける理学療法士の実習で学ぶこと

理学療法士の実習は、過去にはデイリーノートや症例レポートなどの課題提出を中心とした内容となっていました。
しかし、現在はCCS(クリニカルクラークシップ)と呼ばれる診療参加型の実習が主流です。
ここでは、CCSにおける実習で学ぶ内容を紹介します。
見学実習
理学療法士の実習において、まず行われるのが見学実習です。
見学実習は大学1年生で行われるケースが一般的 となっており、その名のとおり、実際に理学療法士の臨床現場を見学します。
医療や福祉施設などの業務に触れ、理学療法士の役割を体験的に理解することが目的 です。
見学実習では、実際に患者さんの評価や治療を行うことは基本的にありませんが、患者さんや他の医療スタッフとコミュニケーションをとることは可能です。
事前にスタッフや患者さんに聞きたいことを想定しておくことで、実のある実習にしていけるでしょう。
患者さんや他の医療スタッフとのコミュニケーションを通じて、理学療法士以外の職種も含めたチーム医療を実践している臨床現場全体の理解を深めます。
チーム医療の中で理学療法士が患者さんに対して、どのように関わっているか学びます。
評価実習
評価実習は、理学療法の観点から患者さんの心身機能を評価する実習です。
患者さんの身体の可動域や筋力、心身の健康状態などを検査・測定して、適切な現状把握ができるようになることが目的です。
患者さんの症状を改善するためには、現在の状態を適切に問診し、治療につなげることが重要となります。
適切な現状把握には、理学療法士の目線で情報収集し、問題点の抽出、仮説の立案が必要です。
評価実習は、理学療法士として重要な技能の習得ができる機会です。
また、利用する養成施設によっては、評価実習内の検査の項目を別に検査実習として行うケースもあります。
検査実習と評価実習が分かれている場合は、まず検査実習で患者さんの現状把握技術を身につけ、評価実習を通じて問題点抽出のスキルを培うという流れとなります。
総合実習
総合実習は、患者さんの希望に合わせて、具体的なリハビリ目標を立て実践していきます。
見学実習や評価実習で得た知識や技術を統括して、実際の理学療法士と同様の仕事を体験することが目的です。
今までの実習と異なる点は、患者さんに治療を行うことです。
指導者のアドバイスを受けながら、患者さんの現状を評価し、治療を計画・評価していきます。
実際にチーム医療の一員として実務や管理を経験できるので、理学療法士として働くイメージをつかめるでしょう。
実習期間は養成施設によって変わりますが、2ヵ月〜3ヵ月間のケースが多いです。
非常に長期的な実習となりますが、その分得られる経験も大きく、講義では学べない技能やスキルも身につきます。
また、患者さんと触れ合う機会も多くあるため、個性に合わせたコミュニケーションの重要性も経験できるでしょう。
理学療法士の実習がつらいと言われる理由

理学療法士になるためには避けては通れない実習ですが、インターネット上には「つらい」という文言も散見されます。
ここでは、理学療法士の実習がつらいと言われる理由を紹介します。
指導者とのコミュニケーション
実習先での指導者との人間関係がつらいと感じる人もいます。
実習をスムーズに進めるためには、指導者とのコミュニケーションは何よりも大切です。
指導者とのコミュニケーションが不足するとすれ違いも生まれやすくなり、「やる気が感じられない」「実習の受け方が悪い」と誤解される可能性もあるでしょう。
一度悪い評価が付く と、挽回するのが難しくなるため、実習中につらいと感じるケースも多くなると予想できます。
課題が多すぎて終わらない時代もあった
CCSでの実習が主流となる以前は、デイリーノートや症例レポートなどの課題が多すぎてつらいと感じることが多くありました。
2017年に厚生労働省が理学療法士の学生、卒業生にとったアンケートでは、全体の76.2%の実習生が毎日自宅に課題を持ち帰っていたことがわかっています 。
また、課題に費やす1日あたりの時間は、3時間以上かかったとの回答が63.6%と最多です。
実習後に3時間以上も毎日課題をこなさなければいけないことを想像すると、過去の実習がいかに大変だったかもわかるでしょう。
理学療法士の実習で気を付けること

理学療法士の実習を円滑に進めるためには、注意すべきポイントがあります。
ここでは理学療法士の実習で気を付けることを紹介します。
社会的なマナーを大切にする
理学療法士の実習に限った話ではありませんが、一般的な社会人としてのマナーを守ることは大切です。
指導者や患者さんから社会的マナーを持ち合わせていると認識されれば、良好な関係を築きやすいです。
例えば、「始業時や終業時にきちんと挨拶する」 「説明を受けるときはメモを取る 」といった姿勢を持つようにしましょう。
また、質問をする際は一度断りを入れるだけでも、相手からの印象は大きく変わります 。
謙虚に学ぶ姿勢
理学療法士の実習では、謙虚に学ぶ姿勢を忘れてはいけません。
実習生は、患者さんの治療時間を使って学ばせてもらう立場です。
さらに患者さんだけでなく、指導者も本来の業務にプラスして、実習生の面倒を見てくれています。
そのようななかで、実習生から謙虚に学ぶ姿勢が見られないと、誰も良好な関係を築こうとは思ってくれないでしょう。
実習中は学ばせてもらう立場であることを自覚し、アドバイスには謙虚に耳を傾けることが大切です。
また、もらったアドバイスを実際に行動やレポートに反映させることも大切です。
実際に行動に移すことができれば、指導者からも信頼を得られるでしょう。
失敗を経験ととらえる
実習中の失敗は、経験ととらえることも大切です。
はじめて患者さんを評価、治療していくなかで、十分に注意していても失敗することはあるでしょう。
失敗を反省するのはたしかに大切ですが、あまりにも失敗にフォーカスしてしまうと積極的に実習に参加するのが怖くなってしまいます。
失敗をもとに「なぜ失敗したのか」「どうすれば失敗を防げたのか」を考え、次に活かすようにしましょう。
理学療法士の実習内容や注意点を知りしっかり学ぼう

今回は、理学療法士に必要な臨床実習の内容や注意点を紹介しました。
理学療法士になるためには、見学実習や評価実習など、臨床経験を積む実習への参加が必要です。
しかし、実習中のコミュニケーションや接遇に気をつけなければ、患者さんや指導者と良好な関係を築けず、つらいと感じてしまうものです。
実習中は謙虚な気持ちを忘れずに、自ら挨拶をするなどして積極的にコミュニケーションを図ってみましょう。
自ら積極的に学ぶ姿勢で臨めば、指導者も快くアドバイスをくれ、実りある実習にすることも可能です。







