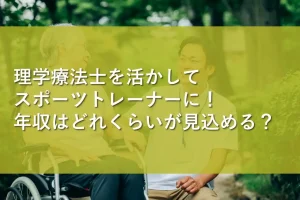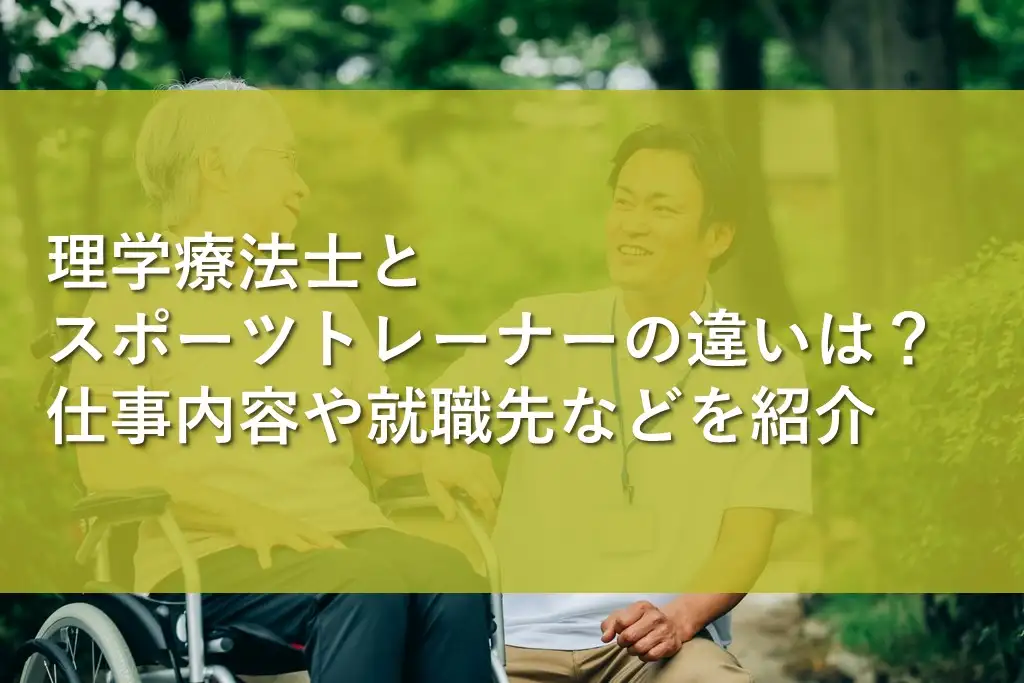
スポーツトレーナーになりたいと思った方は、似ている仕事として理学療法士と比較することがあるかもしれません。
両者ともに運動やスポーツに関わる仕事ですが、それぞれ対象にする人や求められている役割が異なります。
この記事では、理学療法士とスポーツトレーナーの違いについて、仕事内容や就職先といった点から解説していきます。
また、理学療法士がスポーツトレーナーをめざすにはどうしたら良いのかなども紹介しているので、スポーツトレーナーになりたいと少しでも思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
理学療法士とスポーツトレーナーの違い

理学療法士は国家資格ですが、スポーツトレーナーという資格はありません。
スポーツトレーナーになるには、医療系の国家資格やアスレティックトレーナー、NSCA認定パーソナルトレーナーなどの民間資格を取得するのが一般的です。
ここでは、理学療法士とスポーツトレーナーのそれぞれについて、仕事内容や就職先、年収の違いなどを解説していきます。
仕事内容の違い
理学療法士は主に運動機能が低下した人を対象に基本的動作の改善をめざしたサポートを行うのに対し、スポーツトレーナーはパフォーマンスの向上に特化した仕事です。
理学療法士とスポーツトレーナーの両者における、仕事内容の違いを紹介します。
理学療法士
理学療法士の仕事は、対象も治療内容も多岐にわたります。
基本的にはケガや病気などで身体に障がいのある人に対して、基本動作能力の改善や維持を目的に、運動療法や物理療法を中心としたリハビリテーションを行うことです。
対象には、脳卒中などの中枢神経疾患、骨折やヘルニアなどの整形外科疾患、肺炎などの呼吸器疾患などがあります。
医師からの処方に応じて患者さんの症状を評価し、適切な理学療法を提供します。
スポーツトレーナー
スポーツトレーナーの仕事は、スポーツ選手に対してそれぞれの世代や個人に合わせたトレーニング指導やサポートを行うことです。
具体的な仕事内容としては、以下のようなものがあります。
- 運動能力やパフォーマンスを高めるためのトレーニング指導
- ケガのリハビリおよびケガ予防のための指導
- 試合でベストパフォーマンスを発揮するためのコンディショニング
就職先の違い
両者で大きく異なるのは、理学療法士は病院で働くことができますが、医療資格を持っていないスポーツトレーナーの場合は病院で働くことができない点です。
理学療法士とスポーツトレーナーの活躍できる場所の違いを見てみましょう。
理学療法士
日本理学療法士協会の調査では、理学療法士の大部分が医療施設で働いているという結果が出ています。
一方で、理学療法士のなかには少数ですがスポーツ関係施設、フィットネス施設で働く人もいます。
よって理学療法士は、病院でもスポーツ施設でも活躍できるといえるでしょう。
スポーツトレーナー
スポーツトレーナーの活躍場所としては、プロのスポーツチームに所属、スポーツ選手と契約、企業で働くなどがあげられます。
ここでいう企業とは、実業団チームを持つ企業やプロチーム、フィットネスクラブなどです。
このなかでも、プロのチームに所属したり、スポーツ選手と専属契約することはとても難しく、狭き門となっています。
理由としては、選手のコンディショニングや試合中のケガの対処といった高度な知識と経験を要するためです。
年収の違い
理学療法士の平均年収は、賃金基本統計調査によると約413万円です。
公益財団法人日本スポーツ協会の調査では、スポーツトレーナーの約40%は年収1万円~100万円という結果でした。
スポーツトレーナーの場合は、経験や実績で年収が大きく左右されるため、病院などの医療施設に勤務する理学療法士よりも格段に高い年収を獲得できる可能性があります。
その一方で、スポーツトレーナーは能力や実績が重んじられるため、高い収入を得られる人は一握りです。
また、プロチームなどは年単位で給与の総額が決まる年棒制が一般的であり、チームの成績が良くなかったりすると減額されたり解雇されてしまうことがあるため、年収は不安定といえるでしょう。
理学療法士がスポーツトレーナーになるには?

理学療法士がスポーツトレーナーになるには、スポーツやフィットネス関連の資格を取得するのが良いでしょう。
理学療法士とのダブルライセンスで、病院以外に活躍できる場所を広げることができます。
アスレティックトレーナー(AT)を取得する
一つ目は、アスレティックトレーナー(AT)の資格を取得することです。
アスレティックトレーナーとは、トップアスリートやプロスポーツ選手に対して、コンディション調整やケガの予防、スポーツ現場での外傷への応急処置など医療的ケアを行う人のことです。
公益財団法人日本スポーツ協会の調べでは、アスレティックトレーナーは5,002名います(令和4年10月時点)。
日本では、日本スポーツ協会が公認するアスレティックトレーナー(JSPO-AT)資格が有名です。
NSCA認定パーソナルトレーナーを取得する
二つ目は、NSCA認定パーソナルトレーナーを取得することです。
世界的に権威のあるストレングス&コンディショニングの教育団体であるNSCA(National Strength and Conditioning Association)ですが、CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)とNSCA-CPT(NSCA認定パーソナルトレーナー)の2資格は日本語で取得できます。
CSCSは、アスリートやスポーツチームの傷害予防とスポーツパフォーマンス向上を目的として、安全で効果的なトレーニング計画を立案、かつ指導を行えることを認める資格です。
NSCA-CPTは、アスリートだけでなく年齢や性別、経験を問わず幅広い層のトレーニング指導を行う、健康と体力のニーズに関する専門的能力をもつことを認める資格です。
これらは国際的にも知名度が高い資格であるため、理学療法士とのダブルライセンスをめざすと、他の療法士との差別化ができ、スポーツ現場への就職など活躍の場を広げることができます。
理学療法士の資格を取得するとスポーツトレーナーとしての可能性も広がる
理学療法士とスポーツトレーナーの仕事内容や就職先などを解説してきました。
理学療法士は、主に病気や障がいを抱える方を対象に基本的動作の改善・維持を目的とし、一方でスポーツトレーナーは、アスリートのパフォーマンス向上やコンディショニングを目的としています。
理学療法士がスポーツトレーナーになることを考えた場合は、アスレティックトレーナーやNSCA認定パーソナルトレーナーとのダブルライセンスを取得すると、活躍の場が広がります。