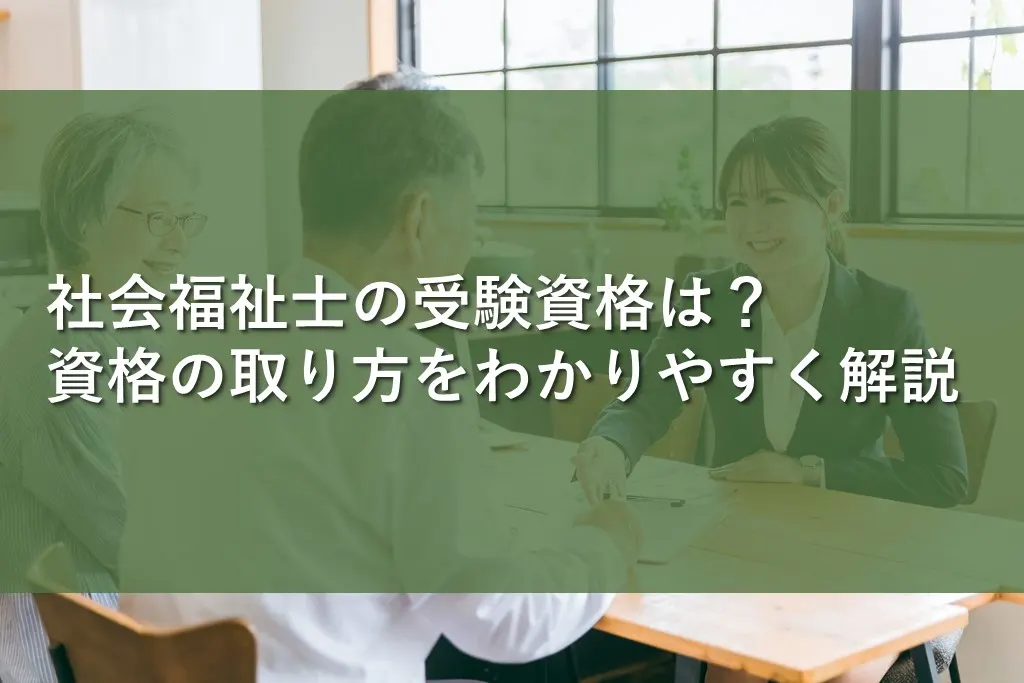
社会福祉士国家試験の受験資格は、どのようにすれば得られるのでしょうか。
受験資格を得るルートは3つあり、それぞれ必要とされる学歴や実務経験が異なります。
本記事では、社会福祉士国家試験の受験資格を得る方法を紹介したうえで、実際に受験し、社会福祉士になるまでの流れも解説していきます。
社会福祉士をめざす方は、ぜひ参考にしてください。
目次
社会福祉士の受験資格を得るルートは大きく分けて3つ

社会福祉士の受験資格を得るためのルートは、以下の3つです。
- 福祉系大学・短大等
- 短期養成施設等
- 一般養成施設等
それぞれ見ていきましょう。
1.福祉系大学・短大等
福祉系の大学や短大で指定科目を履修した方は、下記の条件を満たすと社会福祉士の受験資格を得られます。
- 福祉系大学等(4年)で指定科目を履修
- 福祉系短大等(3年)で指定科目を履修+相談援助実務1年以上
- 福祉系短大等(2年)で指定科目を履修+相談援助実務2年以上
4年制の福祉系大学で指定科目を履修していた場合は、そのまま受験が可能です。
3年制もしくは2年制の短大などで指定科目を履修した方は、相談援助の実務経験が求められます。
2.短期養成施設等
続いて、短期養成施設等に通う必要のあるルートを見ていきましょう。
福祉系大学で基礎科目を履修していた場合は、下記の条件を満たすと受験資格を得られます。
- 福祉系大学等(4年)で基礎科目を履修+短期養成施設等で6ヵ月以上
- 福祉系短大等(3年)で基礎科目を履修+相談援助実務1年+短期養成施設等で6ヵ月以上
- 福祉系短大等(2年)で基礎科目を履修+相談援助実務2年+短期養成施設等で6ヵ月以上
4年制の福祉系大学で基礎科目を履修した方は、短期養成施設等で6ヵ月以上学ぶと、社会福祉士試験の受験が可能です。
3年制もしくは2年制の福祉系短大を卒業した場合は、相談援助で所定の実務経験を積み、短期養成施設等で6ヵ月以上学習すると、受験資格を取得できます。
また、児童福祉司や身体障害者福祉司、査察指導員などで実務経験が4年以上ある方も、短期養成施設に通う必要があります。
詳しくは以下のとおりです。
- 社会福祉主事養成機関を卒業後、相談援助実務2年+短期養成施設等で6ヵ月以上
- 児童福祉司・身体障害者福祉司・査察指導員・知的障害者福祉司・老人福祉指導主事で実務4年+短期養成施設等で6ヵ月以上
3.一般養成施設等
福祉系大学・短大等を卒業していない方や、相談援助実務が4年以上ある方は、一般養成施設に通うルートで受験資格を得ることができます。
詳しくは以下のとおりです。
- 一般大学等(4年)を卒業後、一般養成施設等で1年以上
- 一般短期大学等(3年)を卒業後、相談援助実務1年+一般養成施設等で1年以上
- 一般短期大学等(2年)を卒業後、相談援助実務2年+一般養成施設等で1年以上
- 相談援助実務4年+一般養成施設等で1年以上
一般の4年制大学を卒業した方は、一般養成施設等で1年以上学習すると、社会福祉士の受験が可能です。
短期大学等を卒業した場合は、相談援助の実務経験を積んで一般養成施設等で学ぶと、受験資格を取得できます。
社会福祉士の受験資格を得るために必要な実務経験は?
社会福祉士の受験資格を得るためには、4年制の福祉系大学で指定科目を学ぶルートを除き、「相談援助業務の実務経験」が求められます。
相談援助業務に該当する分野は、以下の5つです。
- 児童分野
- 高齢者分野
- 障害者分野
- その他の分野
- 現在廃止事業の分野
例えば、児童分野は児童福祉司や児童指導員などです。
高齢者分野では、支援相談員や生活指導員などが該当します。
実務経験の対象となる施設や職種は定められているため、事前に公益財団法人社会福祉振興・試験センターの公式サイトで確認しておきましょう。
出典:社会福祉士国家試験
受験資格を得てから社会福祉士になるまで

受験資格を得てから、社会福祉士になるまでの道のりは、以下のとおりです。
- 試験に合格する
- 登録申請を行う
順番に見ていきましょう。
試験に合格する
社会福祉士国家試験の試験概要は、以下のとおりです。
| 試験日 | 2月上旬 |
| 申し込み期間 | 9月上旬から10月上旬 |
| 試験地 | 全国24ヵ所 |
| 費用 | 社会福祉士のみは19,370円 |
| 合格発表 | 3月上旬~中旬 |
出典:社会福祉士国家試験
合格基準点は総得点の60%程度です。
また、18科目群すべてで1点以上得点する必要があります。
合格率は毎年20~30%台と低めで、令和3年度は31.1%でした。
社会福祉士の試験を突破するのは容易とはいえないため、しっかりと対策しましょう。
登録申請を行う
試験に合格しても、すぐに社会福祉士として働けるわけではありません。
以下の流れに従い、登録申請を行う必要があります。
- 必要書類を簡易書留で郵送
- 試験センターが受理
- 登録証が交付される
提出書類に不備がなければ、およそ1ヵ月程度で登録証が交付され、社会福祉士を名乗ることができるようになります。
合格から手続きまでスムーズに進むよう、記入ミス・漏れに注意しましょう。
出典:資格登録
カリキュラムの改正で社会福祉士の受験資格はなくなる?
社会福祉士のカリキュラムが改正されるため「受験資格も変更になるのでは」と心配になる人もいるでしょう。
しかし、過去に現行の制度で受験資格を得ている方は、改正後もそのまま受験できます。
教育内容の見直しについては、厚生労働省の公式サイトに掲載されているため、あわせて確認しておきましょう。
受験資格を得て社会福祉士になろう
社会福祉士国家試験を受験するために必要な資格要件を解説しました。
受験資格を得るためのルートは、福祉系大学・短大等で指定科目を履修するルート、短期養成施設等に通うルート、一般養成施設等に通うルートの3つが用意されています。
受験資格を得たあと、試験に合格し、登録申請を行うと登録証が交付されます。
試験に合格しても、登録手続きを行わなければ社会福祉士を名乗れないため、注意してください。






