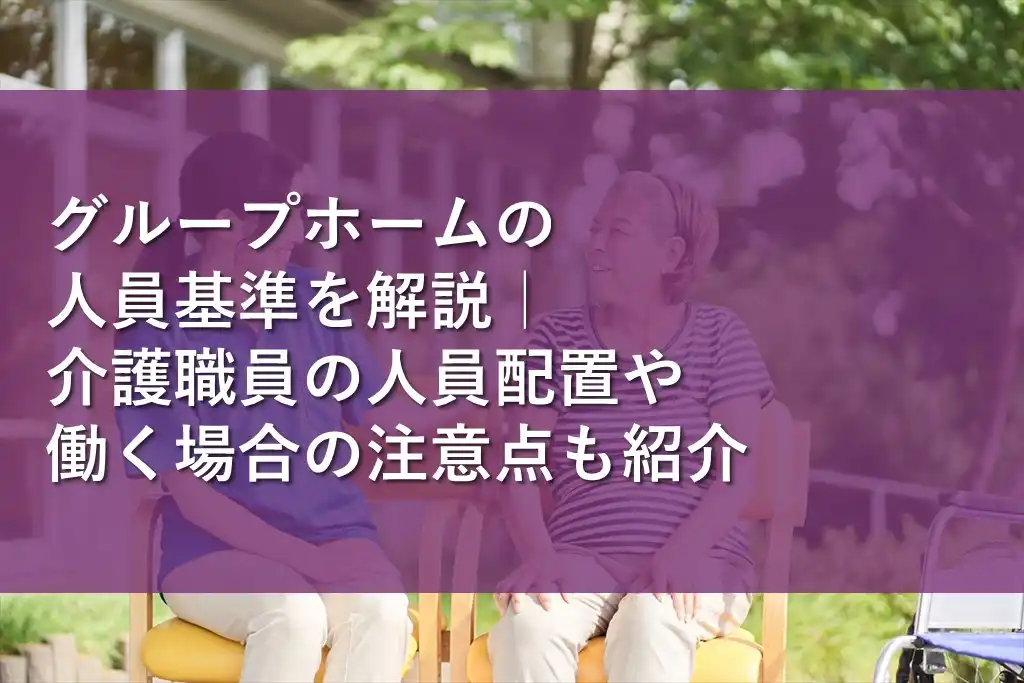
グループホームで働く介護職や管理者などには、独自の人員基準が定められています。
人員の配置の仕方は各施設で異なり、そのグループホームがどの時間帯、どのサービスに比重を置いているのかを理解するのに役立つでしょう。
今回の記事ではグループホームの人員基準を解説するとともに、働くうえでの注意点も紹介します。
共同生活介護施設での勤務を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
グループホームの人員基準

人員基準とは、介護施設における適切なサービス提供のために、専門資格を持つ人材の配置にルールを義務付けたものです。
グループホームでは、以下の4つの職員に人員基準が定められています。
- 介護職員
- 計画作成担当者
- 管理者
- 代表者
それぞれの基準や配置の要件を、詳しく見てみましょう。
介護職員の人員基準
介護サービスを主に提供するグループホームにおいて、介護職員の配置は必須です。
具体的には、入居者3人に対し介護職員一人以上を配置する必要があります。
複数の介護職員がいる場合、常勤のスタッフを一人以上置かなければなりません。
夜間は1ユニット(利用者ごとの個室と共有スペースで構成された生活空間)につき一人以上の介護職員の配置がルールです。
夜間の人員基準の詳細は、のちほど詳しく解説します。
計画作成担当者の人員基準
適切な介護を提供するためのサービス計画を作成する職員が、計画作成担当者です。
計画作成担当者は、ユニットごとに1名配置する必要があります。
計画作成担当者として配置するスタッフは、実務者研修基礎課程もしくは認知症介護実践者研修を修了し、かつその職務に従事した者でなければなりません。
また、配置されている計画作成担当者のうち1名は、介護の計画を立てる専門職である介護支援専門員(ケアマネジャー)であることが必須です。
管理者の人員基準
管理者はグループホームで働くスタッフの人事や労務、施設の経営と収支、運営の管理をします。
ときには自ら現場の業務に入る場合もあるでしょう。
管理者は1ユニットごとに1名必要となり、配置にあたっては以下の要件に当てはまる人物であることが条件です。
- 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上働いた経験がある
- 厚生労働省が規定する管理者研修を修了している
管理業務に支障がなければ、他の業務との兼任ができます。
現場の仕事にも入る点では、認知症の方への対応に関して、スタッフの見本となれる経験値が必要でしょう。
代表者の人員基準
代表者は、グループホーム全体の管理を担います。
施設につき1名の代表者を配置する必要があり、要件は以下のとおりです。
- 施設で認知症高齢者の介護に携わった経験がある
- 医療や保険、福祉サービスを提供する事業所の経営に関わった経験がある
- 厚生労働省の定めた「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了している
このうち1と2は、どちらかを満たしておけば問題ありません。
代表者は管理者より幅広い視点を持ちつつ、現場の経験も持ち合わせている必要があります。
グループホームにおける介護職員の人員配置基準
前述のとおり、介護職員の人員基準は利用者3人に対して介護職員一人が基本です。
しかし、常にこの基準を満たす必要はありません。
実際の配置について、さらに詳しく見ていきましょう。
日中の時間帯に人員基準の3:1を満たせば良い
グループホームにおける介護職員の人員基準では、日中の時間帯は3:1を満たすよう定められています。
一方、夜間や深夜に関しては、上記の人員基準を満たしていなくても問題ありません。
夜間は1ユニットごと介護職員を常時一人以上配置するよう、別途で人員基準が設けられています。
利用者の人数が何名であろうと、この規則どおり配置するルールです。
例えば1ユニット2名の利用者だからといって、他のユニットと兼務して配置することは認められません。
日中でも常に3:1を満たす必要はない
グループホームの人員配置の考え方は、実際に働いている職員の数ではなく、職員の労働時間をもとに計算されています。
施設の運営時間を日中、夜間、深夜の3つに分けたとき、日中の時間帯に勤務している職員の労働時間が24時間以上であることが前提です。
例えば業務量が多く忙しい時間帯に人員を多く配置したのであれば、日中に人員が少ない時間があっても問題ないとされています。
実際にグループホームでは日中9:2の人員配置が多く見られ、3:1の基準を必ずしも満たしているわけではありません。
グループホームにおける医師や看護師の人員配置基準
医師や看護師、理学療法士などのリハビリをサポートする医療スタッフは、グループホームの人員基準では定められていません。
つまり必須の配置ではないため、基本的に医療スタッフは不在です。
グループホームには、看護師の配置に応じて報酬がもらえる医療連携体制加算という仕組みが設定されています。
これを算定している施設は、看護師が配置されているかもしくは外部の診療所や訪問看護ステーションと連携しているでしょう。
医師や看護師がどのように人員配置されているかは、施設ごとに確認が必要です。
グループホームで働く場合に知っておきたい人員基準の注意点
グループホームで働く前に、いくつか知っておきたい注意点があります。
人員基準と照らし合わせながらチェックしてみましょう。
介護職員の全員が常勤とは限らない
上述したとおり、グループホームにおいては利用者3人に対して介護職員一人以上の配置が定められています。
しかし、配置する職員の全員が常勤である必要はありません。
一人以上は常勤でなければいけないものの、他の職員はパート・アルバイトでも良いとされています。
人員が多く配置されているからと入職しても、実は常勤は自分だけという事態もありえるでしょう。
この場合、想像以上に多くの責任と役割を負うことになりかねないため注意しましょう。
時間帯によって介護職員が少ない場合がある
利用者と介護職員の割合が3:1でなければならないのは、日中だけです。
夜間や深夜の時間帯は、介護職員をユニットごとに一人以上配置していれば良く、人員が多く見えても、一人で働かなければいけない時間が長い場合があります。
また、施設ごとに日中の人員配置にも差があるでしょう。
食事や排泄が重なるなどの一定時間に配置人数を多く置いている場合は、それ以外の時間が手薄になるかもしれません。
施設によって人員配置に対する考えは異なるため、事前に確認してみてください。
医師・看護師不在時は利用者急変の対応も
医師や看護師の人員配置は必須でなく、医療的ニーズに常に応えられるわけではありません。
利用者の急変時には、施設の職員の臨機応変な対応が必要になることもあるでしょう。
ただしグループホームのなかには、外部の医師との連携が十分であったり、看護師が常駐していたりするところもあります。
もし利用者急変の対応が不安な場合は、そのような職場を検討するのも一案です。
施設によって人員配置やサービス内容が異なる
グループホームの運営基準では、家事は原則として利用者と介護従事者が共同で行うものとされています。
しかし、人員配置や入居者の介護度によって実施されるサービスの内容には差があるため、注意が必要です。
利用者の方とゆったり関わりを持てる介護をしたい場合は、入職前に施設見学をするなどして、人員配置が手厚いかどうか確認するようにしましょう。
グループホームの人員配置を事前に確認して施設の特徴を把握しよう
グループホームの人員基準は、介護職員をはじめとして代表者、管理者、計画作成担当者の4つの役割に定められています。
医師や看護師などの医療スタッフについて基準はなく、不在の施設も珍しくありません。
配置スタッフによって介護職員の担う役割に違いがあるため、事前に確認するようにしましょう。
また人員配置基準は設けられているものの、実際は施設によってその限りではなく、配置が少ない時間帯もあります。
グループホームへの入職を希望している方は、どの時間帯にどのような配置をしているか、施設ごとの状況を把握しておくことが大切です。






