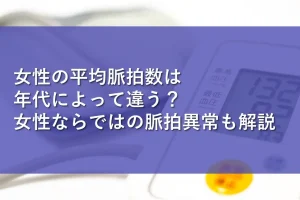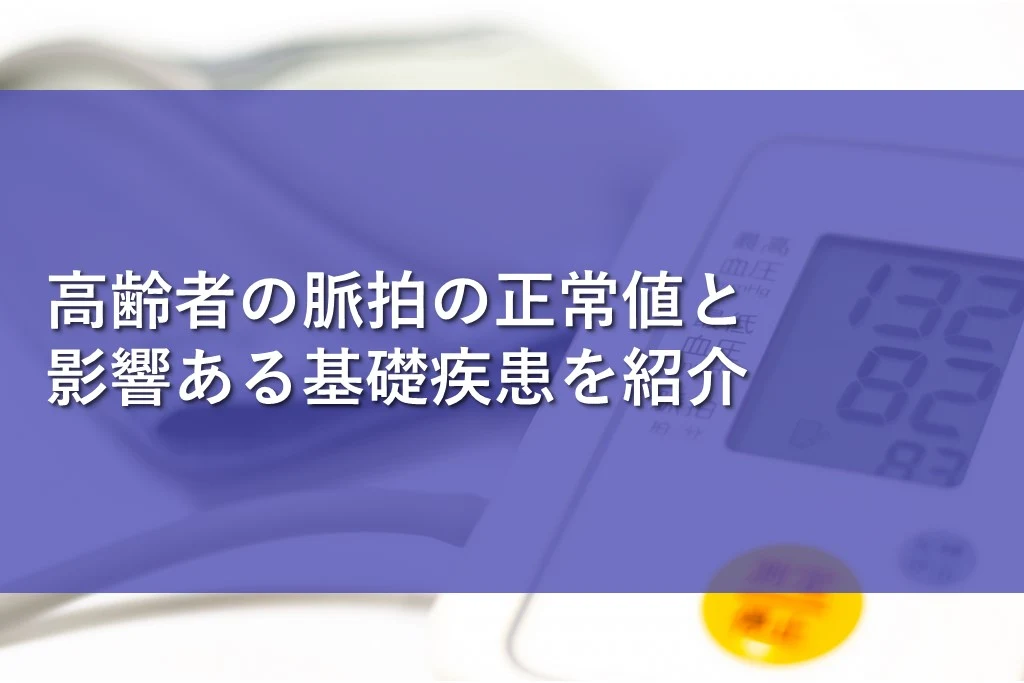
「高齢者の脈拍の正常値はどれくらい?」
「どのような疾患が脈拍に影響するの?」
高齢の患者さんを看る医療従事者にとって、脈拍は患者さんの状態を知る指標の1つです。
今回は、高齢者の脈拍の正常値とその特徴を解説します。
また、脈拍に影響のある基礎疾患と対応方法についても言及しています。
目次
高齢者の脈拍の正常値は?

高齢者の脈拍数の正常値は50〜70回/分です。
成人の正常値である60〜90回/分に比べるとゆっくりになります。
高齢者の脈拍数が低下する理由は、日常生活での活動量や代謝が低下して酸素消費量が減少することで、心臓が全身に酸素を届ける回数が減るためです。
なお、脈拍数には個人差があるため、その患者さんの普段の脈拍数から大きく変わっていないのであれば、正常値から逸脱していても異常だとは限りません。
また、脈拍数は気温や食後、測定時の緊張具合、入浴後などの要因でも増加します。
脈拍数が増加する要因をできる限り排除した状態で測定するようにしましょう。
脈拍に影響のある高齢者疾患
高齢者に多い病気のうち、脈拍に影響のあるものはこちらの3つです。
- 心疾患
- 高血圧
- 糖尿病
どのように脈拍に影響しているのか、順番に説明していきます。
心疾患
心疾患は、不整脈を引き起こし、心拍数にも影響を及ぼします。
不整脈とは、脈拍が速くなったり、遅くなったり、不規則になったりする状態です。
不整脈は命に関わるケースもあるため、正常値と併せて、患者さんの普段の脈拍数や、基礎疾患の有無は、事前に把握しておきましょう。
高血圧
高血圧の状態では、心臓が強い力で血液を押し出すため、心臓の筋肉が通常よりも厚くなる心肥大を引き起こします。
心肥大になると不整脈になりやすくなるため、高血圧の患者さんの脈拍の変化、心電図異常には注意を払いましょう。
糖尿病
糖尿病の合併症の1つに自律神経障害があります。
糖尿病によって自律神経障害が引き起こされると、心拍数のコントロールがうまくいかなくなってしまいます。
その結果、安静時の心拍が低値を維持できなくなり、常に脈拍数が多い状態になります。
安静時でも脈拍数が高い場合は、既往歴に糖尿病がないか確認しましょう。
高齢者の脈拍は異常を知るきっかけになる
高齢者の脈拍の正常値は50〜70回/分ですが、正常値ばかりを信用してはいけません。
安静時の脈拍を把握しておき、脈拍に異常をきたす基礎疾患があるかどうか確認しておく必要があります。
通常時の脈拍から逸脱した際は、患者さんに何かが起きているサインの可能性があるため、すぐに状態を把握しておきましょう。