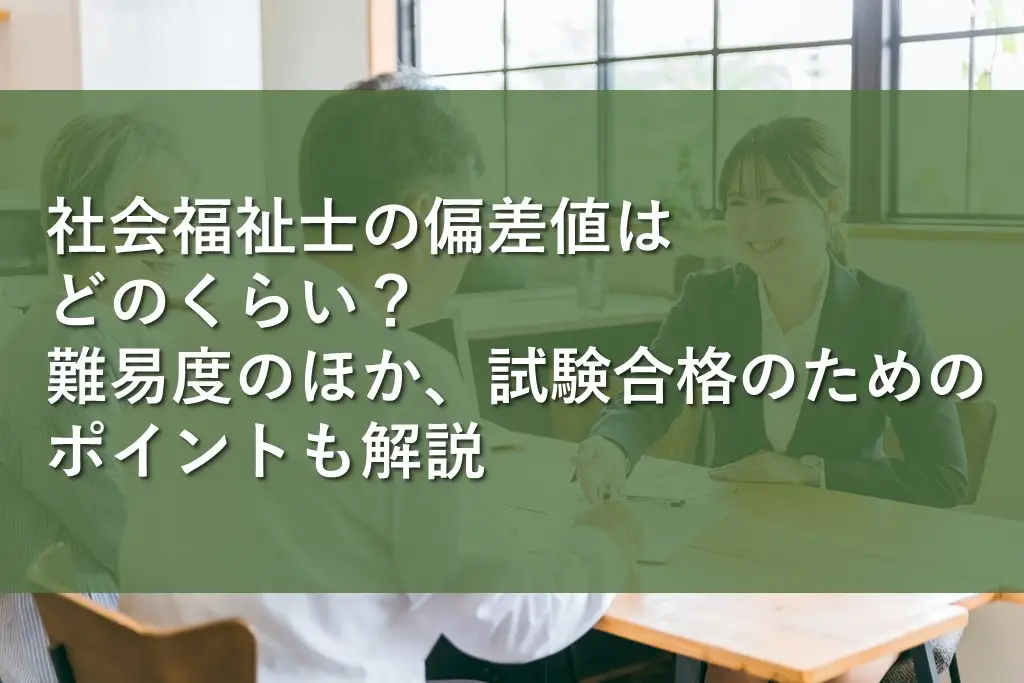
社会福祉士の仕事に就くための必須資格です。
社会福祉士の仕事に興味がある方は、ぜひ取得をめざしましょう。
この記事では、社会福祉士国家試験の偏差値や難易度、合格するためのポイントについて解説します。
目次
社会福祉士国家試験偏差値はどのくらい?

社会福祉士の国家試験は、難易度が高い試験として知られています。
社会福祉士国家試験の偏差値は「57」
社会福祉士国家試験の偏差値は、一般的に「57」といわれています。
宅地建物取引士(宅建士)など、一般に難関とされる他資格と同程度の偏差値であり、社会福祉士試験の難易度の高さがうかがえます。
社会福祉士国家試験の難易度は下がった?
社会福祉士試験の合格率は、これまで30%前後でしたが、2024年(令和6年)3月に行われた第36回社会福祉士国家試験の合格率は58.1%と大幅に上昇しました。
そのため、難易度が下がったと考える人もいるかもしれません。
しかし、2025年(令和7年)に行われる第37回社会福祉士国家試験から、新カリキュラムに基づいた問題が出題されるため、「合格率が上がっているから大丈夫」ということにはなりません。
しっかりと対策を講じて試験に臨む必要があります。
社会福祉士の新しい養成カリキュラムと受験資格について、詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
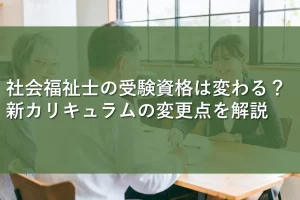
社会福祉士の合格率が低い理由
社会福祉士の合格率が低い理由は、いくつかあります。
出題科目・範囲が広い
社会福祉士の国家試験は、出題科目が19科目と非常に幅広く、勉強する範囲が広いことが特徴です。
出題科目は以下のとおりとなります。
- 医学概論
- 心理学と心理的支援
- 社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策
- 社会保障
- 権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制
- 障害者福祉
- 刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職
- ソーシャルワークの理論と方法
- 社会福祉調査の基礎
- 高齢者福祉
- 児童・家庭福祉
- 貧困に対する支援
- 保健医療と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
- ソーシャルワークの理論と方法(専門)
- 福祉サービスの組織と経営
合格基準は、問題の難易度で若干の補正が入りますが、問題の総得点の60%程度となっています。
また、「得点のない科目が1つでもあると合格できない(更生保護と就労支援サービスは1科目群)」という点も難しいといわれる原因の1つでした。
しかし、科目群の設定を見直し、60%の正答率のハードルを満たした者のうち、以下の6科目群において得点のあった者と改正されています。
- 医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎
- 高齢者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支援、保健医療と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)
各科目の中で、0点科目があると不合格であったことに比べると、ハードルは下がったように感じますが、苦手分野を克服し知識に偏りが出ないように学習しなければなりません。
300時間ほどの学習時間を必要としている
社会福祉士の国家試験合格に求められる幅広い分野をくまなく学習するためには、300時間程度の学習時間が必要だといわれています。
毎日1時間勉強したとしても、10ヵ月程度の期間が必要です。
大学生では卒業論文の執筆やアルバイト、社会人では仕事や家庭運営などに時間を取られ、十分な学習時間を確保することが難しい人が多く、合格の大きな壁となります。
独学で合格することが難しい
社会福祉士の国家試験受験資格は、社会福祉士のカリキュラムのある施設で一定期間学ばなければ取得できません。
受験勉強は独学でもできますが、受験資格を満たすために大学や養成施設で学ぶ必要があります。
社会福祉士の国家試験は2025年から変更になる
社会福祉士の国家試験は、2025年2月実施の試験より新カリキュラム対応となり、出題内容が大きく変わります。
指定・基礎科目の必修化や特定科目の時間数の拡充など、より実践力が高められる学習内容に改定されています。
さらにしっかりと知識を定着させないと、合格することは難しいでしょう。
社会福祉士に合格するためのポイント

社会福祉士の国家試験に合格するためには、以下のポイントを押さえましょう。
自分に合った勉強方法を確立する
社会福祉士をめざすなかで、自分に合った勉強方法を見つけておくことは非常に重要です。
試験が近くなると、そわそわして集中できなくなったり、逆にまだ大丈夫と思ってしまい集中できない人がいます。
どのようなときでも集中できる方法を見つけることが大切です。
例えば、スクールや通信講座を早期から申し込む、勉強する環境を変えてみる、なども良いでしょう。
過去問題を活用する
過去問の活用も、合格をめざすために大切です。
たとえ出題範囲が一部変更になったとしても、過去の試験に出題された問題から、出題傾向や重要ポイントを把握することができます。
また、実際に時間を図りながら問題を解くと、時間配分などを考えながら問題を解くことができるため、本番対策にも役立ちます。
試験日まで計画を立てて臨む
試験日まで日数があると、ついだらけてしまい、時間をうまく活用できないことがあります。
試験日まで計画を立てて臨むことが重要です。
社会福祉士の試験は1年に一度しかないため、落ちてしまうと、また1年間努力しなくてはなりません。
1回で合格できるように、試験日から逆算した計画を立てて学習を進めましょう。
社会福祉士の偏差値を参考に勉強して理想の未来へ進もう
社会福祉士の国家試験は難易度が高いですが、合格すればソーシャルワーカーとして活躍できる道が開かれます。
この記事で紹介した内容を参考に、社会福祉士の偏差値や難易度、合格するためのポイントなどを理解し、計画的に学習を進めていきましょう。
そして、理想の未来に向かって進んでください。


-e1717472318883-150x150.webp)




