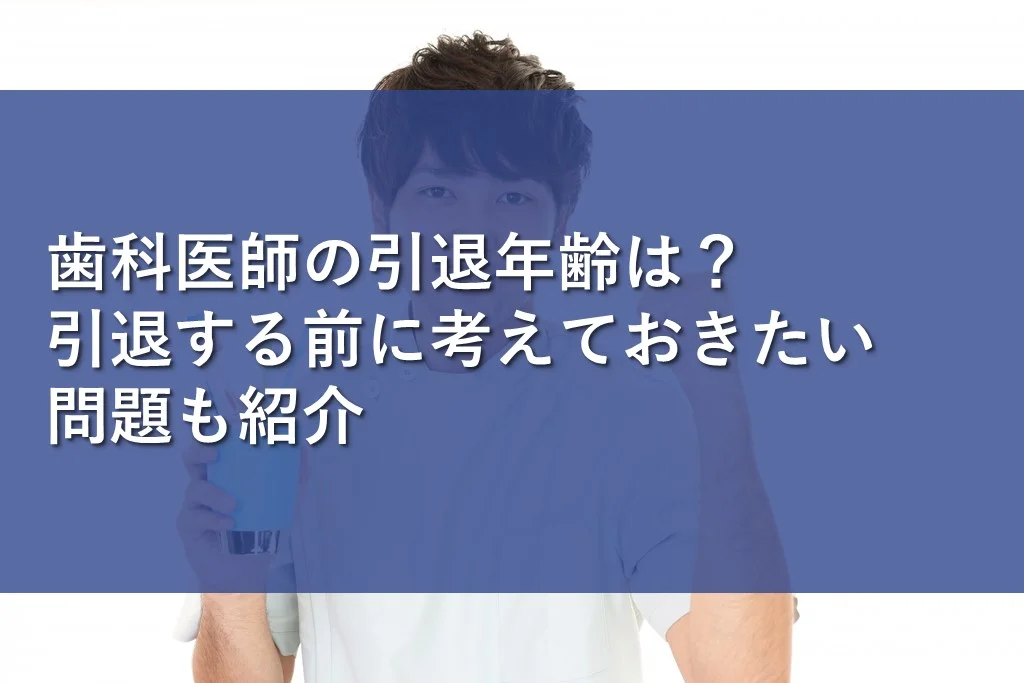
歯科医師の引退年齢は、開業医と勤務医で傾向が異なります。
開業医の場合は定年がないため、本人の意思次第で現役を続けることが可能です。
一方、勤務医の場合は65歳~70歳での引退が主流となっています。
開業医が引退する際は、後継者問題や借入金返済などを考えておくことが課題です。
問題について深堀するために、歯科医師の引退年齢の傾向も知っておきましょう。
目次
歯科医師の引退年齢

歯科医師には、開業医と勤務医がいます。
歯科医師の引退年齢は、開業医と勤務医でそれぞれ違うケースが多いです。
開業医の場合は定年がないため、健康状態と能力次第で長く現役を続けることができます。
その一方で、勤務医の引退年齢は、65歳〜70歳が主流です。
ここでは、開業医と勤務医それぞれの場合について解説します。
開業医の場合
厚生労働省が公表している概況によると、2022年時点では70歳以上の歯科医師数は12,833人となっています。
開業医の場合、定年というルールが存在しないので、引退する年齢は個人差が大きいでしょう。
開業医は、医師としての能力と体力が維持できれば、90代まで本人の意思次第で現役でも働き続けることができます。
勤務医の場合
公務員の勤務医は、国家公務員法第八十一条の二により、60歳が定年となっています。
一方で民間病院で働く勤務医の定年は、65歳や60歳に設定されているケースが多いです。
なかには65〜70歳と長く設定されているケースや、定年制度自体を廃止しているケースもあります。
そのため公務員の勤務医に比べると、民間病院の勤務医のほうが、引退する年齢に自由度があるといえます。
歯科医師(開業医)が引退する前に考えておきたい問題
開業医が引退する際は、後継者問題や借入金返済など、さまざまな課題について考えておく必要があります。
引退後の資金計画も重要な問題の一つです。
後継者に関する問題
開業医の歯科医師は引退を考えていても、後継者がいないことがあります。
後継者が見つからないなかで自身が健康を害し、やむを得ず廃院する事例も少なくありません。
後継者問題を防ぐためには、親族への承継だけでなく、第三者への承継も含めて選択肢を検討することが重要です。
引退時期を考えるうえで、後継者問題に対処することは大きな課題だといえます。
借入金返済に関する問題
引退時に借入残高がある場合は、以下のことを行う必要があります。
- 借入残高の返済方法に関して検討する
- 引退するタイミングを計画する(引退後の資金確保も考慮)
開業時や設備投資の借入金が引退時期に残っている場合、返済の有無は廃業か事業承継かによって異なります。
引退後の資金に関する課題
引退後の資金源としては、公的年金と個人年金および貯蓄などの金融資産の取り崩しとなります。
引退後の資金問題は、引退時期やライフスタイルを大きく左右する要因といえるでしょう。
引退する際は、引退後に必要な生活費を含めた資金計画を考えておくことが重要です。
歯科医師の引退年齢の傾向を知って参考にしよう
歯科医師の引退年齢は勤務医の場合は65歳~70歳が主流ですが、開業医の場合は定年がありません。
開業医が引退する際は、後継者問題や借入金返済、引退後の資金計画など、さまざまな課題について考えておく必要があります。
歯科医師の引退年齢の傾向を知り、自身の引退時期を計画する際の参考にしましょう。







