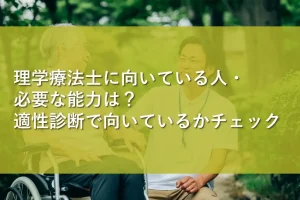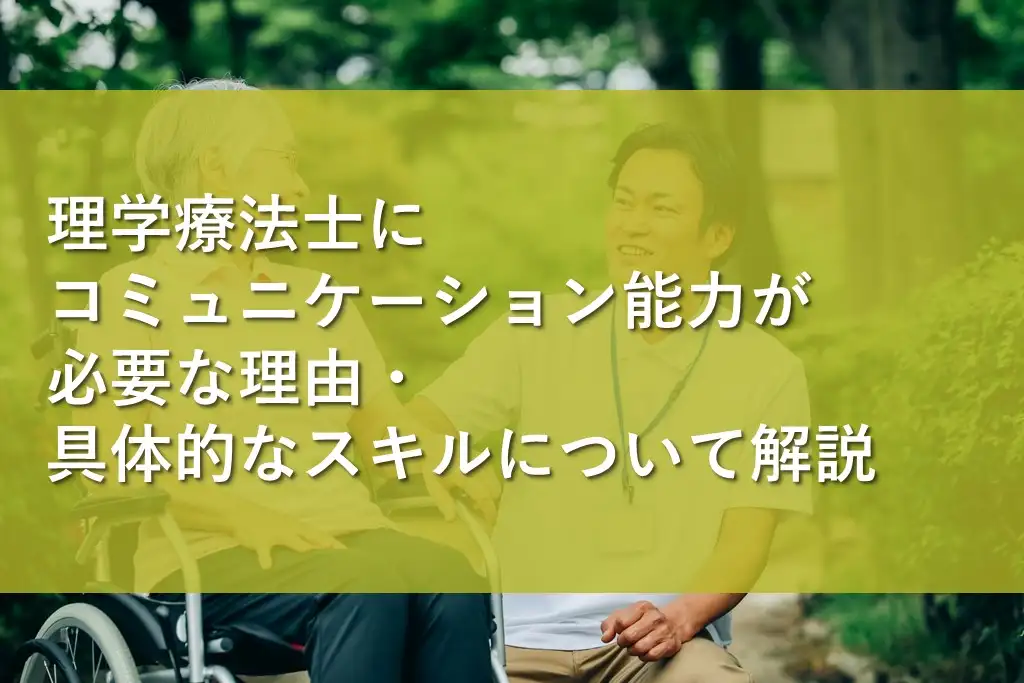
理学療法士は、患者さんの身体機能の回復・維持を支援する専門職です。
リハビリテーションの実践には、理学療法に基づく専門的な知識やスキルが求められることはもちろん、コミュニケーション能力も欠かせません。
そのため、患者さんやご家族との関わりだけでなく、他職種との連携時にも、コミュニケーション能力の高い理学療法士は重宝されるでしょう。
本記事では、理学療法士にコミュニケーション能力が必要とされる理由や、能力が活かせる場面を解説します。
目次
理学療法士はなぜコミュニケーション能力が必要なのか?

医療や福祉の現場で活躍する理学療法士にとって、リハビリに関する知識・技術とともに求められるのが、高いコミュニケーション能力です。
理学療法士は、患者さんやご家族、さらに他職種とも関わる機会があります。
長期にわたることも多いリハビリを円滑に進めるうえで、理学療法士の専門性を発揮するためにも、他職種とのコミュニケーションは欠かせません。
ここでは、理学療法士にコミュニケーション能力が必要とされる主な理由を3つ見てみましょう。
患者さんからの信頼を得やすくなるから
理学療法士にコミュニケーション能力が求められる第一の理由は、患者さんとの信頼関係を構築するためです。
リハビリは、長期間にわたって患者さんと一対一で取り組み続ける必要があります。
最初のコミュニケーションで患者さんに好印象を抱かれていると、それからのリハビリもスムーズに進めやすくなるでしょう。
また、患者さんと信頼関係が構築できれば、理学療法士の指示にも抵抗感を抱かれにくく、リハビリへの意欲を高める効果も期待できます。
患者さんのご家族と関わる場合もあるから
理学療法士は患者さん本人だけでなく、ご家族と接する機会も多くあります。
患者さんのご家族にリハビリの進め方を説明したり、自宅での介助について指導を行ったりする場面では、ご家族の気持ちと家庭の事情に配慮した対応が求められるでしょう。
特に、患者さんの自宅を訪問する場合、同居するご家族とのコミュニケーションは不可欠です。
質の高いリハビリを提供するうえで、理学療法士は、患者さんとご家族それぞれから信頼を獲得する必要があります。
ご家族から理解と協力を得られれば、患者さんの日常生活全体をサポートしやすくなり、リハビリの効果も高まるでしょう。
他職種と連携してリハビリテーションを行うから
リハビリを円滑に進めるためには、医師や看護師など他職種と連携し、患者さんに対して包括的なケアを実施することが重要です。
理学療法士から見た患者さんの評価や介助のときの注意点、リスクなどを医療スタッフへ適切に報告することで、患者さんに合わせたリハビリ方針を定められます。
他職種と意見を交換する際には、職場に応じた専門性とともに、高いコミュニケーション能力が求められるでしょう。
また、理学療法士が実践するリハビリの全体的な方針は、医師の指示に原則従わなければなりません。
医師と密なコミュニケーションを図り、患者さんの注意点を含めた情報共有を円滑に行うことは、最適な治療計画の策定と事故の防止につながります。
コミュニケーション能力が高い理学療法士にできること
高いコミュニケーション能力を持つ理学療法士は、そのスキルを次のような形で発揮できます。
- 相手の気持ちに寄り添う
- 相手の話を傾聴する
- 話しかけやすい雰囲気をつくる
- 患者さんの変化に気付く
患者さんとご家族、さらに他職種からも信頼される理学療法士は、リハビリの質の向上に大きく貢献し、チーム医療に欠かせない存在となるでしょう。
コミュニケーション能力が高い理学療法士にできることを4つ紹介します。
相手の気持ちに寄り添う
理学療法士に求められるコミュニケーション能力の一つに、相手の気持ちに寄り添う共感力が挙げられます。
患者さんの体の痛みだけでなく、心の痛みに寄り添うことも理学療法士の重要な役割です。
患者さんの気持ちをくみ取り、日常生活の課題や自立を助けるための助言・支援を行い、不安を軽減できるよう努めましょう。
また、理学療法士が共感の姿勢を示すことで、患者さんから「この人は自分のことをわかってくれている」という信頼を獲得し、リハビリに取り組む意欲も高めやすくなります。
患者さんの心と体の両面からサポートして、より効果的な治療の提供につなげられることは、コミュニケーション能力の高い理学療法士の特徴です。
相手の話を傾聴する
コミュニケーション能力に長けた理学療法士は、傾聴スキルを備えています。
患者さんやご家族から心を開いてもらうためには、一人ひとり異なる事情やニーズを抱えていることを念頭に置いたうえで、相手を理解しようとする姿勢が大切です。
理学療法士が真剣に話を聞かなかったり、機械的な対応を繰り返したりしていると、相手は心を閉ざしてしまいかねません。
患者さんやご家族の話を聞くときは、目線と体をきちんと相手のほうに向け、適宜あいづちを打ちながら、話に関心を持っていることを態度で示しましょう。
また、相手の話が一段落したタイミングで、内容を要約して伝え返すと「自分の話をきちんと聞き、理解してくれている」と感じてもらいやすくなります。
話しかけやすい雰囲気をつくる
理学療法士のコミュニケーション能力は、患者さんが話しかけやすい雰囲気づくりにも反映されます。
不機嫌そうな顔や声のトーンで話したり、会話が少なかったりすると、患者さんに悩みがあるときでも相談しづらいと感じさせてしまうでしょう。
結果として、患者さんの異変を把握するのが遅れ、適切なサポートを提供できなくなる恐れがあります。
話しかけやすい雰囲気づくりのためには、理学療法士から患者さんへ積極的に話しかけることが重要です。
日々のあいさつはもちろん、共通の話題があれば信頼を深めやすくなります。
患者さんの趣味や興味を尋ねながら会話を広げるのも良いでしょう。
また、患者さんと接するときには、安心感を与えられるよう笑顔を意識してみてください。
患者さんとコミュニケーションがうまくとれない場合、同僚や先輩から客観的な意見を聞くことで、表情、話し方、会話の進め方などの改善点が見つかる可能性があります。
患者さんの変化に気付く
コミュニケーション能力がある理学療法士は、患者さんのわずかな変化に気付く観察力も身につけています。
患者さんのなかには、自分の体調や気持ちを言葉で表現するのが難しい方も少なくありません。
理学療法士は、患者さんの表情、しぐさ、声のトーンなど、非言語的なサインからわずかな異変を読み取り、状況に応じた適切なリハビリ方法を選択する必要があります。
患者さんの細かな変化に気付くためには、観察力を磨くことが大切です。
日頃からさまざまなことに興味・関心を持ち、視野を広げる努力をしましょう。
また、リハビリに関する知識だけでなく、幅広い知識を身につけることで、患者さんとの話題も増えます。
趣味や家事の話など、リハビリには直接関係しないような話題でも、患者さんの変化を察知する手がかりとなる可能性があるでしょう。
理学療法士には高いコミュニケーション能力が必要
理学療法士の仕事には、高いコミュニケーション能力が必要です。
患者さんと信頼関係を築くとともに、ご家族による理解と協力を得ながら、チーム医療の一員となって最適なリハビリを提供するためです。
理学療法の専門知識・技術だけでなく、相手の気持ちに寄り添い、状況に応じた適切なコミュニケーションを心がけましょう。
また、コミュニケーション能力を高めるうえで、傾聴する力や観察力、話しかけやすい雰囲気づくりも重要視したいポイントです。
患者さんと関わるなかで不安を軽減できれば、リハビリへの意欲を高めやすくなります。
専門性とともにコミュニケーション能力の向上を図り、理学療法士としての素質に磨きをかけながら、患者さんとご家族、そして医療従事者からも信頼される存在をめざしましょう。