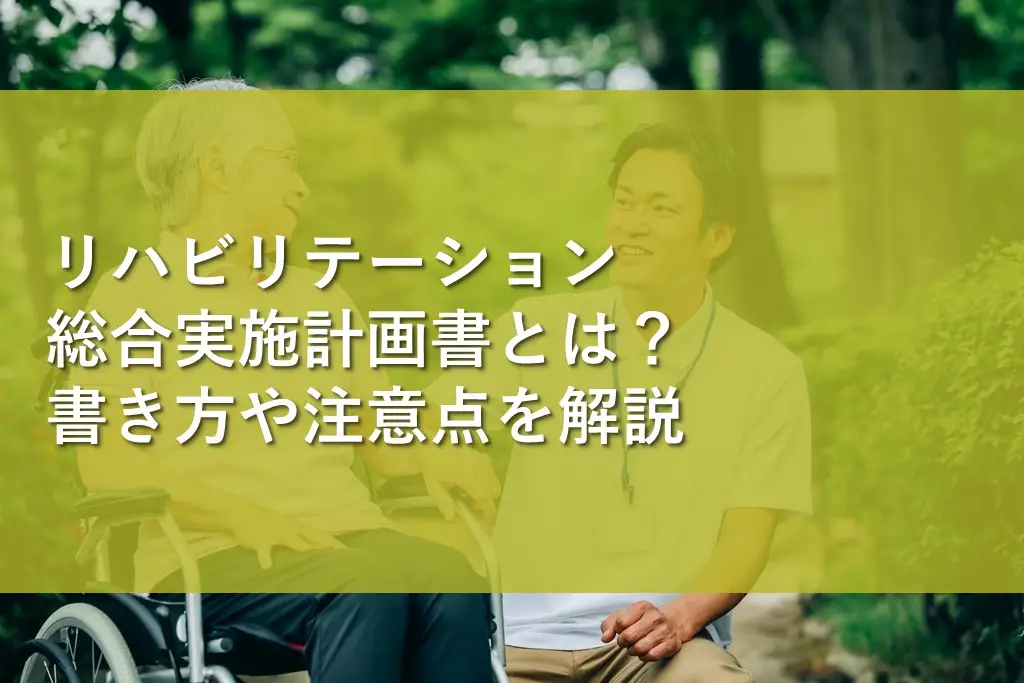
リハビリテーション総合実施計画書は、患者さんの回復を支援するうえで欠かせない書類です。
この計画書は、医療保険によるリハビリテーションを実施する際に作成され、患者さんの状態や目標、具体的なアプローチ方法を文書で明確にします。
医療機関が得る診療報酬にも関わるため、リハビリスタッフをはじめ計画書の作成に携わる方は、記入項目や書き方を正しく理解しておきましょう。
本記事では、リハビリテーション総合実施計画書の概要や書き方、作成時の注意点を解説します。
目次
リハビリテーション総合実施計画書とは

リハビリテーション総合実施計画書は、医療保険によるリハビリテーションを実施する際に必要不可欠な文書です。
計画書には、患者さんの現在の状態やリハビリの目的、具体的なアプローチ方法などを詳細に記載します。
作成にあたっては、医師をはじめ、リハビリスタッフや看護師など多職種の連携が欠かせません。
リハビリテーション総合実施計画書は、患者さんとご家族にリハビリ内容や目標を説明し、同意を得るためのツールとして活用されます。
また、計画書作成に対する報酬として「リハビリテーション総合計画評価料」を算定できるなど、医療機関の診療報酬にも大きく関わるのが特徴です。
回復期の病棟に入院している患者さんの場合、「回復期リハビリテーション病棟入院料」を算定する際にも必要になります。
また、他施設や他サービスとの連携の際にも、リハビリテーション総合実施計画書が活用されます。
医療と介護のリハビリを切れ目なく実施するために、通所リハビリや訪問リハビリの事業所は、入院中に作成されたリハビリテーション計画書の入手が必要です。
このようにリハビリテーション総合実施計画書は、患者さんの回復支援とともに、医療機関が適切な診療報酬を得たり、介護サービスとスムーズな連携を図ったりするうえで重要な書類です。
リハビリテーション総合実施計画書の書き方・記入例
リハビリテーション総合実施計画書を適切に作成するためには、患者さんの状態を多角的に評価し、リハビリの目標とアプローチ方法を詳細に記載する必要があります。
計画書の主な記入項目は、以下5つです。
- 疾患・合併症・既往歴
- 心身機能・構造
- 活動・参加
- 本人・家族の希望
- 目標・具体的アプローチ
各項目の書き方や記入例を見てみましょう。
疾患・合併症・既往歴
疾患・合併症・既往歴の項目では、患者さんがリハビリを必要とするに至った原因疾患や合併症を記入します。
生活に影響を及ぼしている既往歴のほか、これまで受けたリハビリの履歴も詳細に記載しましょう。
なかでも原因疾患は、発症日や手術日、計画書作成までの経過を具体的に記載しなければなりません。
以下の記入例のように、時系列に沿って必要な情報を抜け漏れのないよう盛り込みます。
5月24日 当院に転院し、在宅復帰をめざしてリハビリを開始。
リハビリの方針を決定する大切な項目になるため、できるだけ正確かつ詳しく記入するよう心がけましょう。
心身機能・構造
心身機能・構造の項目では、患者さんの身体的および精神的な機能について、幅広い視点での評価内容を明らかにします。
筋力や関節可動域、麻痺の状態などの身体機能はもちろん、認知機能、精神機能、嚥下機能、疼痛の状態なども含めた総合的な評価を記載しましょう。
評価が必要な項目は広範囲にわたるため、単一の職種のみが作成を担当するのではなく、チーム内で協力し、情報を共有しながら記入を進めるようにします。
例えば、筋力や関節可動域は理学療法士、認知機能は作業療法士、嚥下機能は言語聴覚士が担当するなど、各専門職の知見を活かして正確な評価を反映させることが重要です。
活動・参加
リハビリテーション総合実施計画書には、患者さんの日常生活における活動状況や社会参加の内容を記入する項目があります。
病棟などで日常的にできる動作と、訓練時に能力を把握している動作、社会参加に関する活動それぞれで記入欄が異なるため、区別して情報をまとめましょう。
また、杖や車椅子などの福祉用具の使用状況も詳しく記入します。
社会参加の状況には、患者さんがこれまで行ってきた余暇活動や家庭内での役割、仕事内容などを具体的に記載してください。
いずれも患者さんの現在の生活能力を把握し、適切な目標設定を行うとともに、リハビリ終了後の生活設計を立てるために重要な情報です。
本人・家族の希望
本人の希望・家族の希望は、リハビリの目標設定に関わる項目です。
患者さん本人やご家族から、リハビリを通じて達成させたい具体的な目標を聞き取り、計画書の当該欄に記載します。
記入例として、次のような内容が考えられるでしょう。
- 杖を使い、屋内を自立して歩けるようになりたい
- 近所のスーパーへ一人で買い物に行けるようになりたい
具体的な希望を聞き出し、目標に設定することで、患者さんのリハビリに対する意欲を高めやすくなります。
患者さん本人とご家族の希望に相違がある場合、リハビリの基本方針を記入する欄に、双方が納得できる生活スタイルを見極めていく旨を記載してください。
目標・具体的アプローチ
目標・具体的アプローチの項目には、社会参加や活動・機能の到達目標などを記載します。
主目標として、退院後は自宅もしくは医療機関で過ごすのか、復職をするのか、家庭内でどのような役割を果たすのかなどを、患者さんとご家族の状況に合わせて設定しましょう。
心身機能に関する記入欄では、目標を達成するために必要な日常生活動作や社会生活上の行為を明らかにし、それぞれの獲得に向けた具体的なアプローチを考えます。
環境面の調整や介護者の必要性がある場合、それらの要素にも言及してください。
「一人で屋外を歩けるようになる」などの漠然とした目標は、「自宅から500m先のスーパーまで一人で歩いて行き買い物ができる」のようにより具体化するのがポイントです。
目標が明確であれば、達成のためのアプローチも細かく計画しやすくなります。
リハビリテーション総合実施計画書を作成する際の注意点
リハビリテーション総合実施計画書を作成する際は、以下2つの注意点を念頭に置いておく必要があります。
- 初回は計画書への署名が必要
- 計画書は多職種で協力して作成
診療報酬制度に定められたルールの遵守を前提に、患者さんの回復に最大限貢献できる効果的な計画書の作成をめざしましょう。
初回は計画書への署名が必要
リハビリテーション総合実施計画書の初回作成時は、患者さん本人やご家族の署名が必須です。
署名は、計画書の内容を患者さんやご家族が理解し、同意していることの証となります。
2回目以降の作成であれば、状況に応じて柔軟な対応が可能です。
例えば、患者さんが署名困難な状態にある場合やご家族が遠方にいる場合、電話などの通信機器を用いて計画書の内容を説明し、同意を得ることで署名を省略できます。
ただし、署名の有無に関わらず、作成した計画書は患者さんやご家族に交付しなければなりません。
計画書の交付は診療報酬の算定にも影響するため、忘れず文書を渡しておきましょう。
計画書は多職種で協力して作成
リハビリテーション総合実施計画書は、多職種が協力して作成を進める必要があります。
リハビリの基本方針は医師の指示下で決定されるため、計画書の作成も、基本的には医師が行うことになるでしょう。
しかし、患者さんの状態を多角的に評価し、適切な目標とアプローチを設定するには、医師をはじめ、看護師やリハビリスタッフ、栄養士など、幅広い専門職の知見が不可欠です。
チーム医療のメンバーがそれぞれの専門性を発揮し、協働することで、個々の患者さんに応じたより良いリハビリ計画の策定を実現できます。
なお、多職種が協働し計画書を作成した場合でも、患者さんやご家族への説明は医師が行わなければなりません。
計画書の説明・交付は、診療報酬の算定にも関わるため十分注意しましょう。
リハビリの計画書を正しく作成して診療報酬を算定しよう
リハビリテーション総合実施計画書は、医療保険でリハビリを受ける患者さんの回復支援と、適切な診療報酬算定の両面で重要な役割を果たす文書です。
計画書の記入項目は、疾患・合併症・既往歴や心身機能・構造の評価、リハビリの目標とアプローチなど多岐にわたります。
多職種が協力して情報共有を行うとともに、患者さんやご家族の希望を反映させ、より効果的な計画書の作成をめざしてみてください。
また、初回作成時の署名や内容の説明、作成した文書の交付など、診療報酬の算定に関わる要件を満たすことも忘れてはいけません。
正しい手順で計画書の作成・運用を進め、患者さんの回復と医療機関の安定的な運営を両立させましょう。







