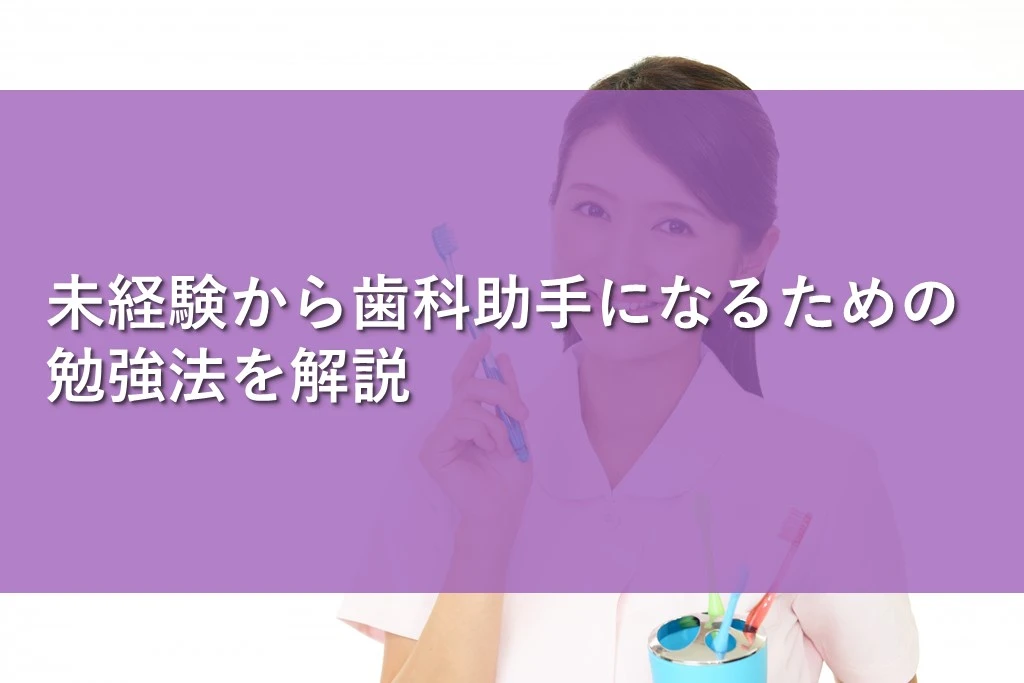
「未経験でも歯科助手になれる?」
「歯科助手になるために必要な勉強は?」
歯科助手になることを検討している方は、上記のような疑問を持つこともあるかもしれません。
歯科助手になるために必須となる資格はありませんが、事前に勉強しておくと、いくつかのメリットがあります。
そこで本記事では、未経験の方が歯科助手をめざすうえでの、おすすめの勉強方法を紹介します。
目次
歯科助手として働くには勉強が必要
歯科助手になるためには、必要となる資格はありません。
そのため、勉強をしていない方でも求人に応募して採用されれば、歯科助手として働くことはできます。
しかし、歯科助手として働くうえでは歯科用語などの知識が必要となるため、勉強せずに歯科助手になった方も、就業後は働きながら勉強しなければなりません。
事前に勉強をしておけば、就業後の勉強時間を減らし、すぐに業務に入っていくことができます。
また、ある程度の知識を得てから求人に応募することで、有利な条件で採用されやすくなるでしょう。
未経験から歯科助手として就職を希望する方や、ブランクがある方は、面接で知識があることをアピールするために、事前に勉強をしておくのがおすすめです。
未経験から歯科助手になるための勉強法

未経験の方が歯科助手をめざす際の勉強方法には、主に以下の3つがあります。
- 独学
- 通信教育
- 歯科助手専門学校
それぞれ見ていきましょう。
独学
お金をかけずに自分のペースで勉強したい方には、独学がおすすめです。
独学には、参考書を用いた勉強方法とアプリを用いた勉強方法があるため、ここでそれぞれの特徴を紹介します。
以下の記事では、歯科助手の勉強をするうえでのノートの使い方を紹介していますので、この記事とあわせて参考にしてください。
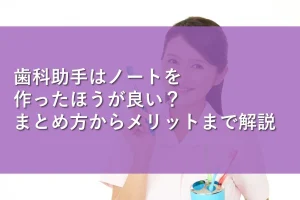
参考書
自分で参考書を買って勉強すれば、他の方法よりも費用をかけずに勉強を進めることができます。
また、自分が「理解しやすい」と思える参考書を、自分で選べる点もメリットです。
ただし、スケジュールの管理やモチベーションの維持も自分で行うため、他の方法と比べて勉強の継続が難しい点がデメリットといえるでしょう。
アプリ
スマートフォンのアプリを利用して勉強する方法です。
歯科助手検定専門のアプリはあまりありませんが、学習アプリを活用しましょう。
アプリを利用するメリットは、持ち運びしやすいため通勤中や通学中などの隙間時間に勉強できる点です。
間違えた問題を繰り返し学習できる機能や、忘却曲線を生かした暗記方法を採用していたりと、効率的に勉強が進むよう設計されているものもあります。
正答率を記録してくれるアプリであれば学習の進度が可視化されるため、モチベーションを維持しやすいでしょう。
ただし、アプリによる品質のばらつきが大きく、なかにはプライバシーが保護されていないものがある点がデメリットです。
また、入門編しかないアプリや、長期間アップデートされておらず情報が古いアプリでは、十分に学習を進めることができません。
通信環境が悪いと利用できなかったり、突然配信が終了する可能性があったりすることも、アプリならではのデメリットといえるでしょう。
通信教育
通信教育なら、勉強時間を自由に決めることができ、要点を押さえながら自分の生活スタイルに合わせて勉強を進められます。
独学よりは費用がかかりますが、専門学校に通うよりは費用を抑えることが可能です。
通信教育の学習期間には個人差がありますが、およそ半年で歯科助手の民間資格を取得するための知識を学べます。
通信教育のデメリットとしては、タイムラグが発生するということがあります。
テストなどの添削を依頼した場合、返答が返ってくるまでに一定期間日数がかかるため、すぐに解答の見直しができないことがデメリットでしょう。
歯科助手専門学校
専門学校はカリキュラムが決まっているので、専門学校に通う時間とお金の余裕があれば、歯科助手に必要な知識を効率良く身につけることができます。
また、歯科助手の専門学校の通学期間は1年間です。
専門学校に通うデメリットは、お金がかかることと、決まった時間に通学する必要があることです。
歯科助手の資格をとるのに必要な勉強時間
歯科助手になるために必須の資格はないものの、民間資格を取得することで自分のスキルを客観的に証明できます。
資格は、講座や講習を受けると資格が取得できるものと、試験を受験して資格を取得するものがあります。
資格取得に必要な勉強時間は、早くて3~4ヵ月程度です。
公益社団法人日本歯科医師会が行っている歯科助手資格認定制度の講習時間は、甲種と乙種で異なり、甲種では420時間以上必要です。
しかし、甲種は3年以上業務に携わらないと資格の取得ができないため、未経験の方はまず乙種の取得をめざしましょう。
歯科助手の勉強は独学でも学べる
歯科助手になるために必須の資格はありませんが、事前に勉強をしておくことで就職活動や就業後の仕事が有利に進むでしょう。
民間資格を取得すれば、客観的に証明することにもつながります。
歯科助手の勉強をするには、独学、通信教育、専門学校に通う方法の3種類があります。
資格取得までの費用を抑えたい方には、独学がおすすめです。
書店で自分にあった参考書を見つけたり、アプリを利用して隙間時間を有効活用し、効率的に勉強しましょう。






