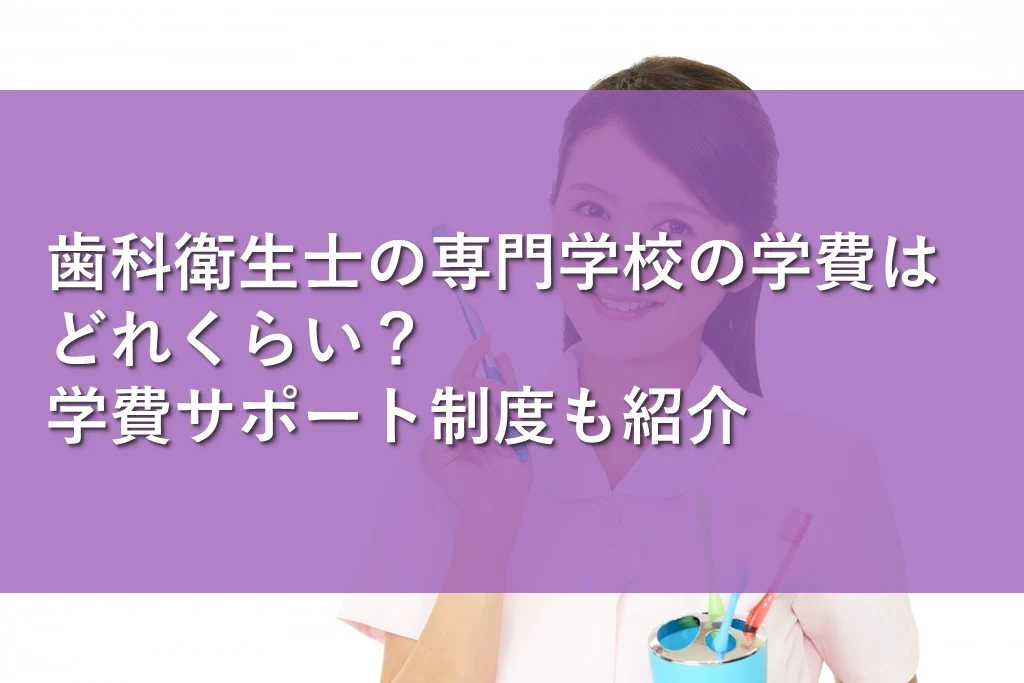
歯科衛生士をめざすにあたって、学費がどれくらいになるのか気になっている方は多いでしょう。
歯科衛生士になるためには3年以上の通学が必須となっており、通学する年数分の学費が必要です。
本記事では、歯科衛生士の専門学校・大学の学費と、進学する際に使える学費サポート制度を紹介します。
歯科衛生士の専門学校へ進学を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
歯科衛生士の専門学校の学費はどれくらい?

歯科衛生士になるための学校には専門学校や大学、短期大学があり、学校の種類ごとに学費の相場は異なります。
また、歯科衛生士の受験資格を得るには3年以上の通学が必須なため、どの学校を選んでも3年分以上の学費が必要になります。
専門学校に進学する場合
専門学校に進学する場合、学費の相場は300〜400万円程度です。
学費の内訳は以下のとおりです。
- 入学金:10万円程度(初年度のみ)
- 授業料:60万円程度/年
- 教材費、白衣代、実習費:30~50万円程度/年
- その他諸費用:10~30万円程度/年
専門学校は3年制の学校が多いので、4年制の大学と比較すると費用は安く済むでしょう。
また、夜間部などの定時制の学費は、全日制よりも若干低い傾向があります。
働きながら歯科衛生士をめざす人や、経済的に余裕がない人におすすめです。
大学・短期大学に進学する場合
4年制の大学に進学する場合、国公立と私立で学費が異なります。
国公立大学の学費は250万円程度、私立大学では500〜600万円程度が相場です。
また、短期大学に進学する場合、国公立で150万円程度、私立で300万円程度必要になります。
4年制大学より学費を安く抑えられ、短期大学の方が校数が多いです。
歯科衛生士の専門学校に通うための学費サポート

歯科衛生士の専門学校・大学の学費は、決して安いとはいえません。
学費を捻出するのが難しい場合、学費サポート制度の利用も検討してみましょう。
ここでは、歯科衛生士の専門学校で利用できる学費サポート制度を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
奨学金
奨学金制度には、返済が必要な貸与型奨学金と、返済不要な給付型奨学金の2種類があります。
奨学金を利用する条件は、主に学業成績と世帯の収入です。
採用基準が厳しいほど返済額が低くなる傾向にあります。
逆に採用されやすい奨学金は利子付きで返済しなければなりません。
ここでは、日本学生支援機構の奨学金を例に解説していきます。
貸与型奨学金
貸与型奨学金とは、大学や専門学校などを卒業したあとに返済が必要な奨学金です。
日本学生支援機構の貸与奨学金には、第一種奨学金と第二種奨学金があります。
第一種奨学金は無利子で借りられる一方で、第二種奨学金より採用基準(学業成績、経済状況)が厳しく設定されています。
第二種奨学金は、第一種奨学金より多くの人が採用されやすい奨学金制度です。
ただし、第二種奨学金は返済時に最大3%の利子が付く点に留意しておきましょう。
また、貸与奨学金は、基本的には学生本人が返済しなければなりません。
しかし、卒業後に就職する歯科医院によっては、奨学金の代理返還を実施している場合もあります。
給付型奨学金
給付型奨学金とは、卒業後に返済する必要がない奨学金です。
ただし、日本学生支援機構の給付奨学金は、以下の3項目の条件を満たさなければ利用できません。
- 学力基準
- 収入基準
- 資産基準
給付奨学金の学力基準は以下のとおりです。
【1年次(2021年度秋入学者を含む)】
次の1~3のいずれかに該当すること。1.高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
2.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
3.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
【2年次以上】
次の1、2のいずれかに該当すること。1.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
2.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
引用元:日本学生支援機構
収入基準は以下のとおりです。
| 支援区分 | 収入基準 |
|---|---|
| 第1区分 | あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること 具体的には、あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円未満であること |
| 第2区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
| 第3区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
資産基準に関しては、学生本人と生計維持者(保護者など)の資産額の合計が2,000万円未満の場合という条件をクリアする必要があります。
歯科衛生士の専門学校に進学する場合は、学校独自の奨学金や、歯科医院や民間企業が出資する奨学金も利用できます。
歯科医院の奨学金を受けるには、卒業後に出資元の歯科医院への就職が条件になっている場合が多いので、歯科医院についても調べましょう。
教育ローン
教育ローンとは、保護者が子どもの学費・教育費を工面するためのローンです。
「国の教育ローン」と「民間の教育ローン」があります。
国の教育ローンは、原則として進学・在学する子ども一人につき350万円以内、固定金利1.80%で借りることができ、加えて最長18年の返済期間が設けられています。
民間の教育ローンとは、銀行や労金などの民間機関で取り扱っているローンです。
融資限度額や金利は機関によって異なります。
民間の教育ローンでは下限収入が定められている場合があり、収入によっては借りられないケースもあるのでご注意ください。
授業料等減免制度
授業料等減免制度とは、一定の条件を満たす場合に学費の支払いを一部免除される制度です。
歯科衛生士の専門学校でも、授業料等減免制度が適用される場合があります。
2020年4月より、国の「高等教育の修学支援新制度」が始まりました。
この制度では、一定の条件を満たす学生に対して、日本学生支援機構の給付奨学金と授業料等減免制度の両方が適用されます。
また、学校独自の減免制度の利用も検討してみましょう。
例えば、学業成績・人物ともに優れた学生や兄弟姉妹・親子で同じ学校に進学した場合に授業料等減免制度が適用される場合があります。
詳細は各学校のホームページや個別相談会などから確認することが可能です。
歯科衛生士の専門学校の学費は各学校で異なる
歯科衛生士の専門学校の学費は、300〜400万円程度が相場です。
定時制の学費は全日制と比較すると若干低い傾向にあり、「とにかく学費を抑えたい」と考えている方は定時制も選択肢に入れると良いでしょう。
4年制大学の場合は、国公立大学は250万程度、私立大学では500〜600万円程度です。
短期大学は国公立で150万円程度、私立で300万円程度です。
また、自費だけで学費を捻出するのが難しい場合は、奨学金など学費サポート制度の利用を検討しましょう。






