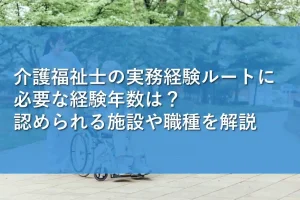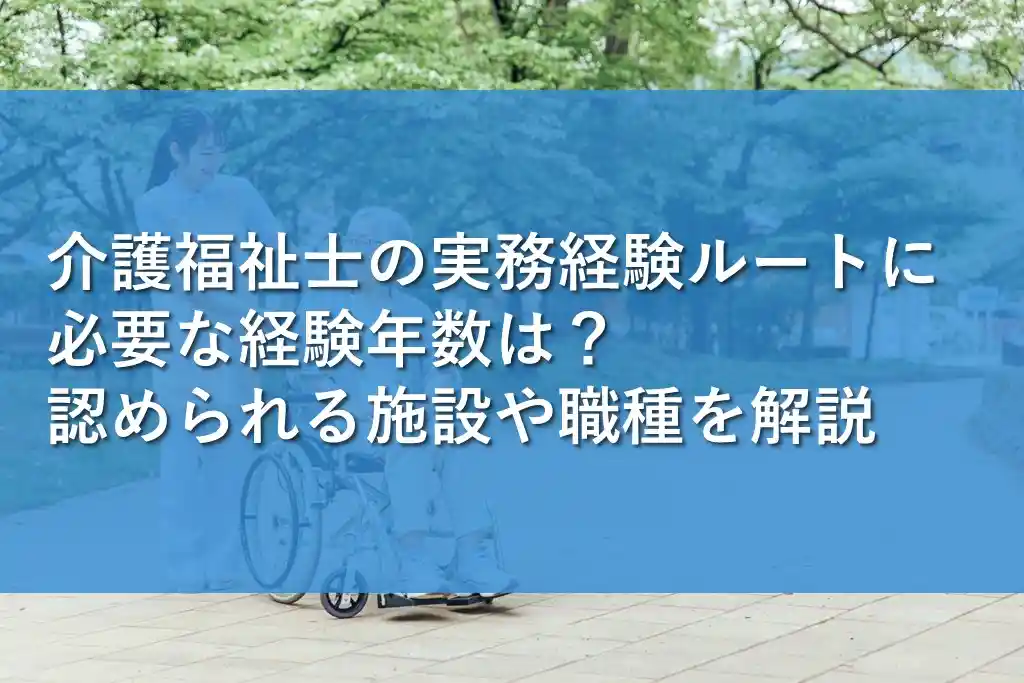
介護福祉士は専門知識と技術を活かして、介護が必要な人を手助けしたり、介護をする人に対して助言・指導を行ったりする仕事です。
介護職で唯一の国家資格であり、やりがいのある職業としてめざす人もいるでしょう。
介護福祉士になるには、介護福祉士国家試験に合格しなければなりません。
国家試験の受験資格を得るには、養成施設や福祉系高校で学ぶ方法や経済連携協定(EPA)に基づいて受験資格を取得する方法のほかに、介護業務の実務経験を積む方法もあります。
今回は、実務経験ルートから介護福祉士になるために必要な経験年数や、実務と認められる施設・職業についてくわしく解説します。
目次
介護福祉士の受験資格を取得するのに必要な実務経験とは

実務経験ルートで介護福祉士をめざす場合、国家試験の受験資格を満たす期間、介護業務に勤め、実務経験の証明をしなければなりません。
実務経験があると認められれば、介護福祉士の国家試験の受験資格を得られます。
必要条件さえ満たされれば国家試験を受けられるため、実務経験ルートで介護福祉士をめざすケースが一般的です。
ここからは、介護福祉士の受験資格を取得するために必要な実務経験期間や、満たすべき条件について解説します。
介護福祉士の実務経験は従業期間3年以上・従事日数540日以上
介護福祉士の国家試験を実務経験ルートで受ける場合、満たすべき条件として挙げられるのが従業期間と従事日数です。
実務経験者として認められるための必要期間は、次のように定められています。
- 従業期間3年以上
- 従事日数540日以上
この2点だけみると、介護の仕事を3年続ければ条件が満たされるように感じるかもしれません。
しかし、従業期間も従事日数も、単純に出勤した日数というわけではありません。
従業期間は、介護施設や事業所で介護職員として勤めた期間です。
従事日数は、介護業務を主体に行った日数を指します。
つまり、受験資格として認められた職場で3年以上勤め、介護業務を540日以上行わないと、介護福祉士国家試験を受けられません。
さらに、従業期間3年以上・従事日数540日以上という条件は、認められた職場・業務内容における数字であることを理解しておきましょう。
介護福祉士の実務経験は実務経験証明書で証明する
実務経験証明書とは、実際に介護業務についていた日数を客観的に証明するためのものです。
介護福祉士の国家試験を受けるときに必要なもので、勤めていた施設や事業所に連絡し発行してもらいます。
パート・アルバイトとして働いていると、複数の施設や事業所に所属することもあるでしょう。
その場合は、自分が勤めていたすべての施設・事業所へ連絡し、実務証明書の発行を依頼してください。
また、介護福祉士の国家試験を受験するには、実務者研修修了証明書も必要です。
実務研修修了証明書とは、実務者研修を受けて必要な知識や技術を学び、修了したことを証明するもので、介護福祉士国家試験の受験資格としても必須です。
実務経験ルートから国家試験を受ける人は、必ず実務経験証明書・実務者経験修了証明書、または実務者経験修了見込証明書を揃えましょう。
介護福祉士の実務経験証明書について「もっとくわしく知りたい」という人は、以下の記事を参考にしてください。
介護福祉士の実務経験に認定される施設・職種とは

実務経験ルートから介護福祉士の受験資格を取得するためには、介護業務を行う施設や事業所で働くことも条件の一つです。
主な業務内容が介護であれば、勤務形態がパート・アルバイトであっても、実務経験と認定されます。
以下より、実務経験と認められる施設や職種の具体例をご紹介します。
実務経験が認められる施設
介護福祉士の受験資格として実務経験が認められる施設は、主に次のような分野に分けられます。
- 児童分野
- 障がい者分野
- 高齢者分野
- その他の分野
- 介護等の便宜を供与する事業
それぞれの分野で認められる施設には、次のような例が挙げられます。
| 児童分野 | ● 知的障害児施設 ● 自閉症児施設 ● 盲児・ろうあ児・難聴児の施設 ● 肢体不自由児を対象とした施設 ● 重症心身障害児を対象とした施設 ● 児童発達支援施設・センター ● 放課後等デイサービス ● 障害児入所施設 ● 保育所等訪問支援 ● 居宅訪問型児童発達支援 |
| 障がい者分野 | ● 生活介護障がい者デイサービス ● 療養介護 ● 短期入所 ● 障害がい者支援施設 ● 共同生活介護(ケアホーム) ● 共同生活援助(グループホーム) ● 自立訓練 ● 就労移行支援 ● 就労継続支援 ● 知的障害者援護施設 ● 身体障害者更生援護施設 ● 精神障害者社会復帰施設 ● 児童デイサービス ● 福祉ホーム ● 地域活動支援センター ● 居宅介護 ● 重度訪問介護 ● 行動援護 ● 同行援護 ● 障がい者の生活サポート事業等 |
| 高齢者分野 | ● 養護老人ホーム ● 有料老人ホーム ● 軽費老人ホーム ● 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) ● 介護老人保健施設 ● 介護医療院 ● 老人向け短期入所施設(ショートステイ) ● 通所介護(デイサービス) ● ケアハウス ● サービス付き高齢者向け住宅 ● 介護予防事業 ● 入浴・生活の訪問介護事業 ● 小規模多機能型の居宅介護事業 ● 指定通所リハビリテーション等 |
| その他の分野 | ● 病院・診療所 ● 救護施設 ● 更生施設 ● 地域福祉センター ● 労災特別介護施設 ● 原子爆弾被害者の介護事業 ● ハンセン病療養所 ● 隣保館デイサービス事業等 ● 家政婦紹介所 ● 訪問看護事業 |
| 介護等の便宜を供与する事業 | ● 各地方自治体の条例や実地要綱に基づく事業 ● 介護保護法の基準に該当する住宅への介護予防サービス ● 障がい者総合支援法の基準に該当する人への福祉サービス等 |
参考:[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
これまでの勤務先と照らし合わせ、実務経験として認められるか確認してみましょう。
実務経験が認められる職種
実務経験ルートから介護福祉士をめざすためには、受験資格として認められる職種で働いていることも重要な確認事項です。
実務経験が認められる職種には、次のような例が挙げられます。
| 児童分野 | ● 保育士 ● 介助員 ● 看護補助者 ● 看護助手 ● 介護職員がおらず、介護業務も行っている指導員(児童発達支援・放課後等デイサービス) ● 主に介護業務を行っている児童指導員 ● 主に介護業務を行っている障害福祉サービス経験者 ● 訪問指導員 |
| 障がい者分野 | ● 介護職員 ● 盲ろう者向け通訳などを行う介助員 ● 施設の寮母 ● 訪問介護員 ● ホームヘルパー ● ガイドヘルパー ● 介護職員がおらず、主に介護業務を行っている以下の職種 ○ 保育士 ○ 生活支援員 ○ 指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター) ○ 精神障害者社会復帰指導員 ○ 世話人 |
| 高齢者分野 | ● 介護職員 ● 介護従事者 ● 介護従業者 ● 介助員者 ● 支援員(養老老人ホーム)の支援員 |
| その他の分野 | ● 介護職員 ● 介助員 ● 介護員 ● 看護補助者 ● 看護助手 ● 原爆被爆者家庭奉仕員 ● 家政婦 |
| 介護等の便宜を供与する事業 | ● 介護職員 ● 訪問介護員 |
上記の例以外にも、主な業務が介護であれば実務経験と認められる可能性があります。
まずは職種を確認し、実務経験として認められるかどうか検討してみましょう。
実務経験の従事期間と業務従事日数の計算方法
従事期間と業務従事日数は、実務経験ルートから介護福祉士をめざすうえで、気をつけなければならない項目です。
正しい方法で計算しないと、国家試験の申し込みのときに慌てる可能性があります。
従事期間とは、介護業務を行う施設や事業所に勤めていた期間のことです。
一つの施設・事業所に3年以上勤めていたという条件ではなく、Aの施設で2年、Bの施設で1年勤めていたという場合でも、この二つの実績を合わせて3年以上の従事期間とみなします。
従事日数とは出勤日のうち、主に介護業務を行った日のことです。
勉強会や研修に出席したり育児休暇などをとったりした日は、従事日数に換算されません。
また、1日で複数の事業所をかけ持ちしていた場合も、日数は個別に換算されず総合して1日とします。
例えば、パート・アルバイトで1日に二つの施設をかけ持ちしていた場合、それぞれで1日ずつ働いたとは考えず、1日として計算しなければなりません。
従事期間と従事日数は、正しい計算方法で確認するようにしてください。
実務経験なしで介護福祉士になる方法
介護福祉士は実務経験なしでも受験資格を取得できます。
具体的な方法は以下のようになっていますので、一つの選択肢として検討してみましょう。
- 養成施設に通う
介護福祉士の養成施設に2年以上通い、1,800時間程度の教育カリキュラムを修了すると、国家試験の受験資格を取得できます。
なお、福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設などを卒業している場合、通学期間は1年以上となり、カリキュラムの一部が省略されます。 - 福祉系高校に通う
福祉課程のある高校で専門知識と技術を学び、国家試験の受験資格を取得する方法です。
1,800時間程度の教育カリキュラムを修了し、国家試験に合格できれば介護福祉士になれます。
なお、実務経験ルートの条件を満たしており、すでに介護職員基礎研修(2012年度末に廃止)を修了している場合は、喀痰(かくたん)吸引等研修を修了すると、介護福祉士国家試験の受験資格を取得できます。
この場合、喀痰吸引等研修の修了時期が国家試験に間に合うかどうかを確認してください。
介護福祉士の実務経験ルートは現場経験が3年必要
実務経験ルートで介護福祉士になるためには、実際に現場で3年以上働くことが条件です。
また、540日以上の介護業務経験がなければ、たとえ3年以上の従事年数があっても条件は満たせません。
さらに、実務経験を積める職場に勤めていたとしても、主な仕事が介護業務でなければ、受験資格は得られません。
つまり、介護業務を主体として540日以上働き、そのうえで3年以上の従業期間を満たさなければならないのです。
実務経験ルートから介護福祉士の国家試験を受けるときは、従業期間・従事日数を正しい計算方法で確認し、条件を満たしてチャレンジしましょう。