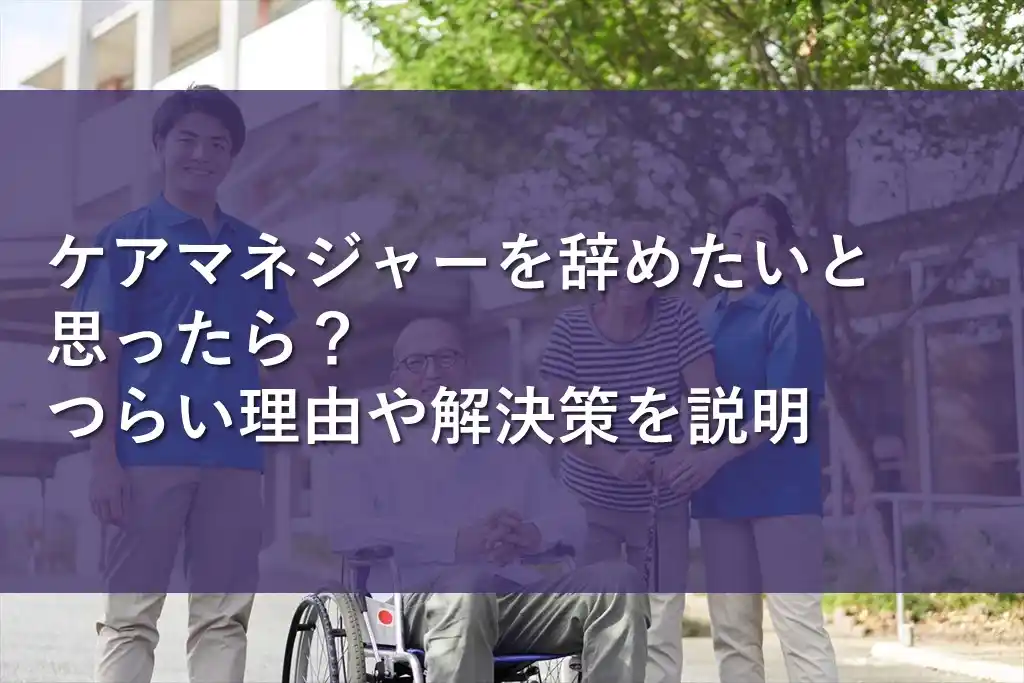
ケアマネジャーは、介護を必要とする人に寄り添い、ケアプランの作成や、サービス事業者との連絡調整をする重要な職業です。
一方で、ケアマネジャーの仕事には大変な面も多く、辞めたいと思っている人もいるでしょう。
本記事では、ケアマネジャーを辞めたいと思う理由としてよく挙げられるものや、その解決策を紹介していきます。
目次
ケアマネジャーを辞めたいと思う理由は?

ケアマネジャーを辞めたいと思っている人は、どのような悩みを抱えているのでしょうか。
ここでは、ケアマネジャーとして働いているとぶつかりやすい悩みを紹介していきます。
責任が重い
ケアマネジャーを辞めたいと思っている人のうち、仕事の責任が重いと感じている人もいます。
ケアマネジャーが作成するケアプランは、利用者が受けられるサービスを決める重要なものです。
ケアプランの重要さはケアマネジャーのやりがいに直結するものですが、なかには責任の重さからストレスを感じてしまう人も少なくありません。
また、社会の高齢化が進み、介護を必要とする人が急速に増えるなかで、介護をとりまく環境は常に変化しています。
したがってケアマネジャーは、知識を最新のものにアップデートし続ける責任があり、そのような面もストレスの要因になりがちです。
仕事量が多い
ケアマネジャーを辞めたいと思う理由として、仕事量の多さも挙げられます。
ケアマネジャーの主な業務は、ケアプランの作成や多職種間の連絡調整ですが、他に事務作業も多くこなさなければいけません。
さらに、同じ事務所に勤めるケアマネジャーが少ない場合には、時間外にもかかわらず利用者のご家族からの電話相談が来ることもあります。
そのため、せっかくの休みでも仕事のことが頭から離れず、疲弊しているケアマネジャーもいるのです。
雑務が多く、本来やりたい仕事ができない
勤務先によっては、人手不足からケアマネジャーの仕事だけではなく、介護士や看護師など保有している資格の仕事も兼任しなければならないことがあります。
また一人暮らしの高齢者が増加していることから、ケアプランにない援助や、日常生活の手伝いを頼まれることもあります。
このようなことが続くと、ケアマネジャー本来の仕事が満足に行えず、モチベーションが下がってしまいがちです。
職場の人間関係が悪い
ケアマネジャーを辞めたいと思っている人からは、職場の人間関係が悪いという意見も聞かれます。
人間関係の問題は、ケアマネジャーにかかわらず、多くの人が仕事を辞めたいと悩む原因です。
特に居宅ケアマネの場合は、施設に配置されるケアマネジャーの人数が少ないため、苦手な同僚や上司がいても関わらないわけにはいきません。
また、ケアマネジャーは看護師や医師など多職種と多く関わる仕事です。
ケアマネジャー同士の連携はうまく図れても、医療関係者との人間関係が悪いとストレスを感じる機会も多いでしょう。
利用者やご家族の対応が難しい
利用者やご家族への対応が難しいという理由もあります。
介護サービスの利用者やご家族のなかには、ケアマネジャーに対して無理な要求をしたり、納得がいかないと理不尽にクレームを言ったりする人もいます。
特に、「介護保険のルールから外れる対応はできない」点は、利用者に理解されていないケースも多く、説明に疲れてしまいがちです。
ケアマネジャーが転職や休職を考えるべき基準

ここからは、ケアマネジャーの転職や休職を考えるべき基準について説明します。
次の項目に当てはまる場合は、心身に強い負担がかかっているおそれがあります。
自分の気持ちと向き合って今後のキャリアプランを見直してみましょう。
人間関係にストレスを感じる場合
人間関係の軋轢はどの職場でも起こりえます。
少し苦手な人がいるのなら、接し方を変えることで、ストレスの少ない付き合い方が見えてくるかもしれません。
しかし、人間関係の悩みは、自分一人の力では解決できないこともあります。
明らかないじめやパワハラを受けている場合は、周囲の人に相談する、もしくは転職を検討しましょう。
残業が多すぎる場合
時間外労働が多すぎる場合も、転職を検討したほうが良いでしょう。
月平均80時間、一日あたり4時間程度の残業は、労働基準法により禁止されています。
過度な労働は心身に負担をかける原因になります。
自分の時間外労働が上記の時間を超えていないかを確認してみてください。
吐き気や不眠など、身体的症状が出てきた場合
吐き気や不眠など、ストレスによる身体的症状が出てきた場合も、休職や転職を考えたほうが良いでしょう。
人はストレスが長期間にわたって続くと、だんだんとストレス反応が十分に行えなくなり、その結果、吐き気や不眠などの症状が現れます。
このような状態に陥ると、回復までに適切な療養期間が必要になります。
自分一人で判断せず、産業医や医療機関を受診してみましょう。
何もやる気が起きない憂鬱な日が続く場合
身体的症状が出なくても、注意が必要なケースはあります。
憂鬱とした気分が続いたり、疲れすぎて休みの日に何もやる気が起きなかったりなどの症状がある場合は、うつ病など心の病気の初期症状かもしれません。
この場合、専門医に相談し、適切な治療を受ける必要があります。
身体は元気だからと無理をせず、自分の休みの日や心の様子を振り返ってみてください。
まだケアマネジャーを続けたい気持ちがある人の解決策
ケアマネジャーを続けていきたいと考えている方のために、仕事がつらいときの解決策をいくつか用意しました。
それぞれ見ていきましょう。
辞めたい理由を書き出し、解決策を考える
辞めたいと思ったときには、勢いで転職するのではなく、自分の状況を客観視することが大切です。
まずは、自分が辞めたいと思う理由を一つずつ書き出してみましょう。
書き出したら、それを解決できるものとできないものに分けます。
解決できるものに優先順位をつけ、仕事に反映させていきましょう。
自分の感情を言語化し、分解することで、問題の解決策が明確になります。
上司や同僚に相談する
上司や同僚に相談できる人がいる場合は、悩みを打ち明けてみると良いでしょう。
誰かに話すことによって、自分の気持ちが整理されることもあります。
身の回りに相談できる相手がいない場合は、労働組合や行政が設置する相談窓口など、公的機関への相談も視野に入れてみましょう。
職場を異動する
勤務先の会社が複数の施設を運営していれば、法人内の別の施設に異動できる可能性があります。
転職をした場合、実績は始めからになってしまうものの、社内間の異動をすることで実績をそのまま引き継ぐことができます。
今すぐケアマネジャーを辞めたい人の解決策
心身に不調が現れた場合は、無理せずに休職や転職を検討しましょう。
ここでは、ケアマネジャーを辞める際にできるアクションをいくつか紹介します。
休職できるかどうかを確認する
うつ病や適応障害などの症状が現れたら、休職し適切な療養期間を設ける必要があります。
休職までの主な流れは以下になります。
- 医療機関への受診
- 診断書の発行
- 勤務先での休職手続き
しかし、休職制度は法律による決まりではなく、あくまで勤務先が自主的に行っている制度です。
休職中の給与といった細かい規定は勤務先によって異なるため、勤務先の職務規定を確認しましょう。
また、他のケアマネジャーへの引継ぎなどをスムーズに進めるためにも、休職の意思を固めた段階で上司や主任に相談できると理想的です。
退職したい旨を上司に伝える
退職を決めたら、早い段階で上司に伝えます。
遅くとも、退職希望日の1~2ヵ月前には伝えておいてください。
勤務先にも代わりの人員を確保するための準備期間が必要なためです。
また、お盆休みや年末年始などの繁忙期では、退職が難しいこともあります。
勤務先の事情にも理解を示しつつ、円満な退職をめざしましょう。
介護福祉士や看護師の職に戻る
ケアマネジャーの多くは、看護師や介護福祉士などの国家資格を持ち、それらの職業の実務経験もあります。
そのため、ケアマネジャーを辞めて、元の職業に戻る道を検討しても良いでしょう。
ケアマネジャーの経験は、看護師や介護福祉士に戻っても活かしやすく、無駄になりません。
転職サイトで新しい職場を探す
退職を決めたら、転職サイトを利用して次の職場を探しましょう。
転職サイトのなかには、プロのキャリアアドバイザーが希望条件に合った求人を探してきてくれるエージェントサービスもあります。
自分で求人を探す余裕がない人でも、エージェントサービスであれば働きながら転職活動を進めることが可能です。
ケアマネジャーを辞めたいと思ったら冷静に自分を見つめて今後を考えよう
ケアマネジャーが仕事を辞めたいと思う理由や、その対策について紹介しました。
辞めたいと思ったら、まずは考えていることを紙に書き出したり、身の回りの人に相談したりして、自身の悩みを客観視することから始めると良いでしょう。
そのうえで、いかにストレスを減らしながらケアマネジャーを続けていくのか、あるいは休職や転職などの選択肢を選ぶのかを考えていきます。






