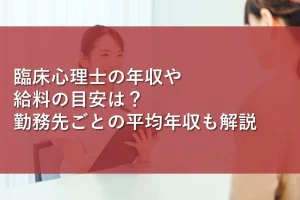臨床心理士の活躍できる場は幅広く、なかでも医療分野では病院が主な就業先に挙げられます。
病院勤務の臨床心理士は、患者さんの心の健康を支える重要な存在です。
チーム医療の一員となり、患者さんやご家族、そして周囲を取り巻く環境にアプローチするため、さまざまな仕事に関わることになります。
診療科によっても患者さんの特性は異なり、配属先に応じたスキルが求められるでしょう。
本記事では、病院勤務の臨床心理士の仕事内容と一日の流れ、配属先ごとの特徴、年収などを解説します。
臨床心理士をめざしている方や医療分野の心理専門職に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
病院勤務している臨床心理士の仕事内容

病院勤務の臨床心理士の主な仕事内容は、次の4つです。
- 心理アセスメント
- 心理面接
- 心理地域援助
- 臨床心理研究
臨床心理士はこれらの業務を通じて、病院を利用する患者さんの心理的な問題にアプローチを行います。
仕事内容をより具体的に見ていきましょう。
心理アセスメント
心理アセスメントは、病院に勤務する臨床心理士の仕事のなかでも、医師の治療方針の決定や問題解決に役立てられる大切な要素です。
面接や行動観察、心理検査などを通じて、患者さんの心理的特徴を把握していきます。
精神疾患は一括りにできるものではなく、生活史や個々のパーソナリティ、問題の状況などによっても必要な支援は異なるものです。
そこで臨床心理士は、心理アセスメントを通じて患者さん一人ひとりの心理状態を明らかにし、最適な支援方法を見出します。
例えば、同じ「うつ病」の診断でも、その背景にある要因や症状の表れ方は千差万別です。
心理アセスメントによって、患者さん特有の問題を把握した結果、より効果的な治療計画を立てられるようになります。
心理面接
心理面接は、臨床心理士が患者さんと直接向き合い、心の問題解決につなげるための業務です。
心理療法やカウンセリングを通じて、患者さんの内面に寄り添いながら問題の本質を探り、解決への道筋を見出していきます。
心理療法では、精神分析法や認知行動療法などの実践的な手法を用い、治療的に患者さん自身の考えを整理して、認知の歪みを解消したり、自身を見つめなおしていく過程をサポートをしていきます。
カウンセリングでは、患者さんの自己成長をうながすため、臨床心理士が積極的に解決策を提案するというよりも、今後どのような道を歩んでいくのかをともに考え、伴走していきます。
社会生活のなかで困難に直面したときに、患者さんが自分らしい意思決定をできるよう、考える力や対処能力の回復をめざすことが重要です。
心理地域援助
病院勤務の臨床心理士は、地域援助の役割も担っています。
地域援助とは、より効果的な援助を行うために、学校や職場、地域社会に働きかけをし、本人を取り巻く環境全体に対して調整を図るコーディネート業務のことです。
患者さんの精神状態やアプローチ方法などを、他職種スタッフやご家族に共有するコンサルテーション業務も含まれます。これにより、患者さんの回復を地域や家族全体でサポートできる体制を整えていきます。
必要に応じて、他の医療機関・司法機関・行政などと連携する場面もあるでしょう。
具体的には、退院後の心理支援や職場復帰のサポート、ご家族への心理教育などに取り組み、臨床心理士は患者さんの社会復帰と生活の質の向上をめざします。
臨床心理研究
臨床心理士の仕事には、研究調査活動も含まれます。
臨床心理士の資格は取得後5年ごとに更新する必要があり、研究調査活動による専門性の維持・向上が欠かせません。
さまざまな研究調査を通じて、より効果的な心理支援の手法の確立を試み、臨床心理学の発展に寄与します。
臨床心理士の研究調査活動として代表的なものは、学会発表や論文執筆などです。
自らが行った援助を検証し、その結果を学術的に発表します。
また、自身の臨床スキルを向上させるため、他病院で行われた援助方法や過去の事例を学ぶこともあるでしょう。
こうした活動は臨床心理士の専門性を高め、より質の高い支援の提供につながります。
病院勤務の臨床心理士の配属先
病院勤務の臨床心理士が配属されるのは、主に次のような診療科です。
- 心療内科
- 精神科
- 小児科
他にも、脳神経内科、児童精神科、産婦人科、緩和ケアなど活躍の場は幅広く、診療科によって臨床心理士の役割や対象となる患者さんの特性は異なり、所属先に応じた知識とスキルの獲得が求められます。
心療内科
心療内科は、心の専門家である臨床心理士が活躍できる配属先の一つです。
心療内科は、心理的な問題が引き金となって身体の不調をきたしている患者さんが対象となり、心理検査やカウンセリングも頻繁に実施されます。
心療内科で働く臨床心理士の役割は、心理検査やカウンセリングを行い、患者さんの話を丁寧に聞き取りながら、心身症の緩和を図り、健康的な生活のサポートをすることです。
ストレスが原因で起こる頭痛の症状に悩む患者さんであれば、身体的治療もしながらストレスの原因を探り、心理的アプローチで改善を図ります。
精神科
精神科は、病院に勤務する臨床心理士の主要な配属先です。
うつ病や統合失調症などの精神疾患そのものに対処する診療科であり、外来や入院の患者さんに対して心理検査や心理療法を行います。
心療内科と精神科は併設されている場合もあり、業務自体に大きな違いはありませんが、精神科デイケアが併設されている医療機関では、リハビリテーションの場面で患者さんと関わることもあります。
デイケアでは、患者さんと一緒に活動しながら話を聞いたり、社会生活技能訓練(SST)を実施したりするなかで、自己理解や心理的安定を支援していきます。
これらの支援を通じて、人との付き合い方やストレスへの対処法を身につけてもらい、患者さんの社会復帰や日常生活の質の向上をめざします。
精神科における臨床心理士は、薬物療法と並行して患者さんの心理的サポートを行う、チーム医療に必要な存在です。
小児科
小児科も、病院に勤務する臨床心理士の配属先に挙げられます。
より精神的な問題を抱えている場合は、児童精神科を紹介されることもあります。
ここで臨床心理士が関わるのは、不登校や発達障害、自傷行為や自殺未遂、心的外傷などを抱える子どもたちとご家族です。
臨床心理士は、医師から依頼を受けて、患者さんである子どもに心理検査やカウンセリングを実施します。
まだ年齢が低くカウンセリングが適用でない子どもには、遊戯療法(プレイセラピー)を行いながら心理的治療を行います。
また、ご家族から子育ての悩みについて相談を受けるケースも珍しくありません。
子どもの心身の健康や発達を支えるため、子ども本人に対するアプローチだけでなく、ペアレントトレーニングを通じて保護者の援助も行うこともあります。
臨床心理士として病院勤務する人の一日の流れ
病院勤務の臨床心理士は、勤め先の開院時間に合わせて働く形になり、その一日は多くの業務で構成されています。
ここでは、病院に勤務する臨床心理士の一日のスケジュール例を見てみましょう。
- 10時:出勤
開院より早めの時間に出勤し、当日の予約を確認してカルテなどの準備を行います。
同じ診療科内のスタッフとミーティングを行い、情報共有を行うことも重要な業務です。 - 10時30分:予約分のカウンセリング開始
開院時間になったら、午前分のカウンセリングの開始です。
個人カウンセリングのほか、患者さんの状態に合わせて集団カウンセリングや認知行動療法などの心理療法を実施するケースもあります。 - 13時:休憩
- 14時:午後の予約分の実施
午前中に引き続き、午後の業務もカウンセリングや心理検査がメインです。 - 16時:病院から依頼された心理テストの実施
入院患者の相談に応じるほか、他診療科から依頼を受けて各種心理検査を実施する場合もあります。 - 18時:業務終了
一日のカウンセリング内容を記録し、資料を整理したら業務終了です。
検査が長引いたり、患者さんのトラブルが発生したりした場合、退勤時間が通常より遅くなることもあるでしょう。
勤める病院や配属先によって業務の進め方は異なりますが、臨床心理士の一日は患者さんとの関わりが中心になります。
病院に勤務している臨床心理士の年収
日本臨床心理士会が定期的に行っている臨床心理士の動向調査によると、月給や時給のボリュームゾーンは次のようになっています。
| 雇用形態 | 収入のボリュームゾーン |
| 常勤 | 月給:20万~30万円 |
| 非常勤 | 時給:1,000~2,000円 |
常勤職員の年収は300万~400万がボリュームゾーンです。
これに対して、国税庁が2022年に実施した「民間給与実態統計調査」によると、日本の平均年収は458万円となっています。
このことから、臨床心理士は、日本の平均と比較すると年収は低めになると予想できるでしょう。
ただし、勤務する病院の規模やエリア、雇用形態、実務経験の長さなどによって、実際の収入は相場と異なる可能性もあります。
臨床心理士としてのキャリアを考える際は、収入面だけでなく、自分自身の関心や得意分野、支援を提供したい対象者なども考慮して、活躍の場を選ぶことが大切です。
臨床心理士は病院において重要な役割を担う
病院勤務の臨床心理士は、患者さんが抱える心の悩みに寄り添い、主治医や医療スタッフと協働しながら、心理的な問題解決に向けたサポートを行う存在です。
心理アセスメントやカウンセリング・心理療法、地域援助などを通じて支援を実践するほか、より質の高い心理支援を提供するための研究調査活動も仕事内容に含まれます。
臨床心理士が病院に勤務する場合、主な配属先は心療内科、精神科、小児科です。
勤務先ごとで一日の仕事の流れは違ってきますが、チーム医療の一員となり、患者さんのケアに貢献するという点では共通しています。
メンタルヘルスケアの需要が高まるなか、医療の現場で活躍できる臨床心理士の役割はますます重要になっていくでしょう。