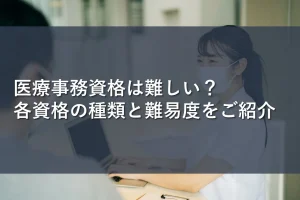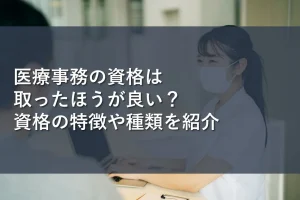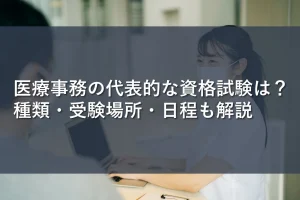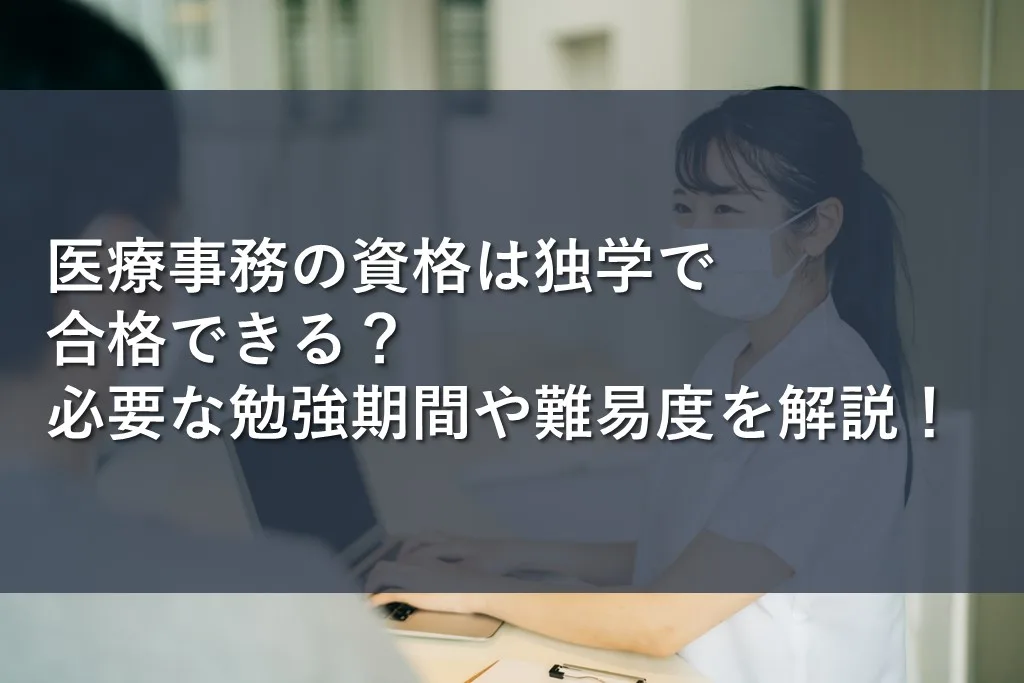
医療事務の資格を取得するには、専門学校への通学や通信講座の受講など、いくつかの方法があります。
働きながら資格取得を目指している方や、とにかく費用を抑えたい方には、独学での資格取得がおすすめです。
しかし、「独学で本当に資格が取れるのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
そこで今回は、医療事務の資格を独学で取得する場合の勉強方法や取得までにかかる期間、独学のメリット・デメリットについて解説します。
目次
医療事務の資格は独学で合格できる
結論からいうと、医療事務の資格は独学でも取得が可能です。
医療事務系の資格は数多くありますが、すべて民間資格で、それぞれ内容や難易度が異なります。
全体的に見ると合格率60%以上の資格が大半であり、独学で合格している人も多くいます。
ただし、医療事務が未経験の人は専門用語が理解できずに挫折してしまう場合もあります。
未経験の人が独学で取得を目指す場合は、難易度が比較的低い資格からチャレンジすることをおすすめします。
代表的な資格とその難易度は、以下の表のとおりです。
| 医療事務の代表的な資格 | 難易度(合格率) |
|---|---|
| 医療事務技能認定試験 | 約85% |
| 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク) | 約60~80% |
| 医療事務認定実務者試験 | 約60~80% |
| 診療報酬請求事務能力認定試験 | 約30% |
医療事務技能認定試験は合格率が約85%なのに対し、診療報酬請求事務能力認定試験では約30%という結果です。
独学する場合は、取得する資格がどのくらい難しいかを理解したうえで取り組む必要があるといえるでしょう。
医療事務資格の種類と難易度について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
医療事務の資格の取り方

ここからは、医療事務の資格の取り方として、以下の2つを紹介します。
- 資格取得までの流れ
- 独学で勉強期間・スケジュールを組むときの考え方
資格取得までの流れ
医療事務の資格取得の方法は、以下のとおりです。
- 取得したい資格を決める
- 試験日・申込期日を調べる
- 受験申込書を提出し、受験費用を支払う
- 資格試験を受ける
まずは、どの資格を取得するか決めましょう。
次に試験日と申込期日を調べます。
医療事務の試験は、毎月行われるものから年に数回のものまで幅があります。
受験の申込書は、資格試験実施機関のホームページより入手できます。
申込書に必要事項を記入して提出し、受験費用を支払いましょう。
受験費用は当日持参の場合もあります。
資格試験を受けるときには、試験場へのアクセスや持ち物などを事前にしっかり確認しておくことが大切です。
受験が完了したら、合格発表を待ちましょう。
1ヵ月以内に合否がわかるケースが一般的です。
独学で勉強期間・スケジュールを組むときの考え方
資格の難易度によって、取得に必要な勉強期間も異なります。
例えば、医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)は、3~4ヵ月の勉強で合格可能といわれています。
それに対して、最難関とされる診療報酬請求事務能力認定試験に合格するには、6ヵ月程度かかるとされています。
勉強期間は、通学や通信講座の受講期間が目安になります。
実際に必要な勉強期間は、自分の経験や確保できる勉強時間などで変わるため、その点を考慮して計画を立てましょう。
独学の場合はスケジュール管理も重要です。
試験日から逆算して計画を立てる際には、必ずスケジュールに余裕を持たせましょう。
思うように勉強が進まなくても、計画に余裕があれば組み直しも可能です。
また、独学ではモチベーション維持も課題になります。
習熟度を確認するための確認問題などを勉強計画に組み込んでおくと、自分の成長が数値として確認できるので、モチベーションアップにつながります。
医療事務の勉強を独学で進めるときのコツ
ここからは、独学で医療事務の資格取得をめざすための勉強方法をご紹介します。
テキスト以外の手段であるアプリやサイトを使った方法、取得までにかかる期間や効率的なスケジュールなど、独学での勉強方法を徹底解説します。
テキストや過去問を活用する
独学で資格取得をめざすのにおすすめなのが、市販で販売されているテキストを活用することです。
できれば、問題集や診療報酬の診療点数早見表(点数表)などがついているものが良いでしょう。
資格によっては受験時にテキストの持ち込みがOKのものもあるため、付箋を貼るなどして必要な情報をすぐに探せるようにしておくと安心です。
また、テキストだけではなく、過去問を活用するのも有効です。
その場合には、本番の試験時間と同じ時間を設定し、時間配分を考えるようにしましょう。
繰り返し問題を解いておくことで、スピードアップも期待できます。
独学で医療事務にチャレンジしようと思っている方は、こちらの記事を参考にしてください。
医療事務の資格取得におすすめのテキストを紹介しています。
診療点数早見表を使いこなせるようにする
試験では問題を解く時間が限られているため、診療点数早見表(点数表)を読み解く力をつけておくことが大切です。
そのためには、勉強するときに常に診療点数早見表を活用し、どこに何が書いてあるのかを把握しておくと良いでしょう。
普段から使い慣れていないと、試験のときに迅速に読み解けできません。
言葉の言い回しが難しい場合もあるため、通則を読んで決まりを理解することも必要です。
また、よく出てくる用語の意味を調べ、しっかりと覚えておくようにしましょう。
アプリやサイトを活用する
独学で一般的なテキストや参考書を使った勉強法は、集中して勉強し、知識をつけるには最適です。
しかし、医療事務の資格取得を目指す人のなかには、仕事や子育ての合間など、限られた時間で効率よく勉強したい方も多いでしょう。
そんなスキマ時間を活用した勉強には、資格対策アプリやサイトの活用がおすすめです。
過去問も充実しており、スマートフォンを利用すれば、通勤の電車内や仕事の合間に、効率良く過去問を勉強できます。
無料で使えるものも多く、費用が抑えられるのもうれしいポイントです。
独学で資格取得をめざそう

医療事務の資格は独学でも取得できますが、費用を抑えて自分のペースで勉強できるというメリットがある反面、すべて自分でやらなければならず、モチベーションの維持や最新情報の把握などが難しい面もあります。
大切なのは、自分の知識レベルと、取得を目指している資格のレベルが合っていることです。
合格率30%の試験は未経験者には難しいかもしれませんが、医療事務の実務経験者なら独学で取得を目指すことも可能です。
まずは、それぞれの資格に求められる知識レベルや勉強期間の目安を把握し、独学で取得可能かどうかを判断しましょう。