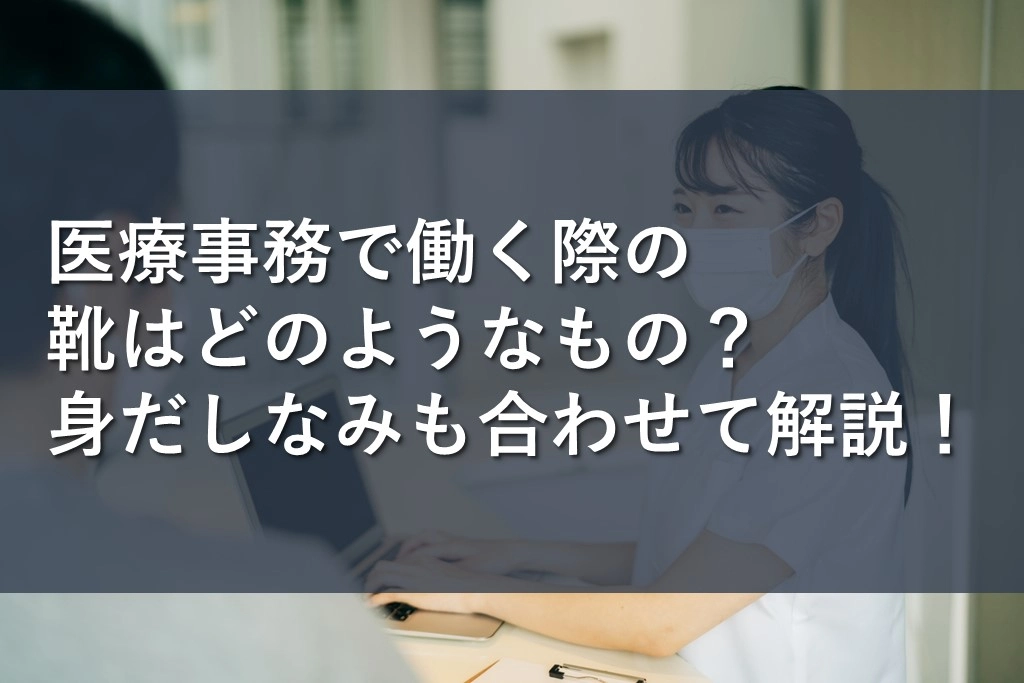
医療事務として働く場合、どのような靴を履けば良いのか迷う人も多いのではないでしょうか。
今回は、医療事務の仕事に適した靴の種類や選び方、身だしなみのポイントについてわかりやすく解説します。
目次
勤務中に履く靴は決められている?

勤務中に履く靴を支給されるかどうかは、医療機関によって異なります。
3つのパターンでみていきましょう。
決まった靴が支給される場合
勤務先が診療所やクリニックの場合、決められた靴を支給されるケースが多いため、あらかじめ自分の靴のサイズを伝え、用意された靴を履いて勤務します。
自分で用意する手間はかかりませんが、自分の足に合ったものを選べないため、履き慣れないと疲労や痛みを感じるかもしれません。
指定された金額内で好きな靴を購入する場合
指定された金額内で好きな靴を買ってくるように指示される場合もあります。
指定の金額をオーバーした場合、超過分は自腹になるので注意しましょう。
黒い靴は避け、白やピンクといった色を選ぶのが賢明です。
不安であれば、あらかじめ色の指定があるかどうか確認しておくと安心です。
指定も支給もされない場合
病院の医療事務の場合は、靴の支給はされない場合が多く、原則自由であるため、自分の足に合った靴を選べます。
ただし、色の指定があるかもしれませんので、あらかじめ確認しておきましょう。
疲れにくい靴がいいならナースシューズがおすすめ!

ナースシューズは、看護師が履く定番シューズです。
動き回ることが多い看護師のために作られた靴であり、長時間履いていても足が疲れにくいように設計されています。
最近では、オフィス勤務の女性の間でも人気が高まっています。
ナースシューズの特徴を種類別にご紹介しましょう。
サンダルタイプ
つま先が開いているものが多いため、通気性が良く蒸れにくいです。
手を使わずに着脱が可能なので、脱ぎ履きの多い医療現場においてサンダルは重宝されます。
しかし、注射針などが足の上に落ちる危険性があるため、サンダルタイプをNGにしている医療機関もあります。
スニーカータイプ
足にしっかりフィットするため非常に動きやすいのが特徴です。
クッション性にも優れているため、足への負担を最小限に抑えてくれます。
足全体が覆われているため、怪我のリスクが少ない点はメリットですが、着脱しづらい点がややネックです。
ヒール付きタイプ
デザイン性と機能性の両方を兼ね備えたタイプで、多くの女性から人気を集めています。
基本的に動きやすさ重視で設計されていますが、ヒールがある分、他のタイプと比べるとやや動きづらいため、デスクワーク中心の方におすすめです。
スリッポンタイプ
スリッポンタイプは靴紐やマジックテープなどがないため、脱ぎ履きをすることが多い方におすすめです。
また、手を使わずに着脱できるため、衛生面でも安心です。
その一方で、靴紐やマジックテープによる調整ができないため、履いているうちに靴が脱げやすくなるおそれがあります。
2Wayタイプ
シーンで使い分けたいという人におすすめなのが、2Wayタイプのナースシューズです。
かかとを立ててスニーカーのように履く方法と、かかとを踏んでスリッポンのように履く方法があります。
靴選びで押さえておきたいポイント

靴は日々の業務で欠かせないアイテムですが、実際にどのような点に気を付けて選べば良いのでしょうか?
自分で用意する場合は、以下でご紹介する5つのポイントを押さえましょう。
クッション性
足への負担を最小限に抑えるには、クッション性の優れた靴を選ぶことがポイントです。
クッションやエアーが入っていれば着地時の衝撃も吸収してくれるため、業務中に動き回ることが多い場合におすすめです。
蒸れにくさ
靴の中が蒸れて足回りが気持ち悪く感じると、仕事に集中できないおそれがあります。
特に、スニーカータイプやスリッポンタイプのナースシューズはすき間が少ない分、熱や湿気がこもりやすくなります。
スニーカータイプやスリッポンタイプを買う場合は、通気性の良いメッシュ素材などを選んでください。
自分に合うサイズ
ナースシューズは、一般的な靴よりも一回りサイズが大きく設計されているものが多いため、自分の足にしっかりフィットするかを確認して選びましょう。
普段履いている靴と同じサイズ感覚で選んでしまうと、足にフィットしない可能性もあるので注意してください。
自分にぴったりのサイズを選べば、勤務中も快適に過ごせます。
軽さ
軽量設計されているものを選べば、足腰の疲れを軽減できます。
しかし、あまりにも軽すぎる靴は、クッション性や耐久性が劣っている可能性があるため、よく確認して選びましょう。
脱ぎ履きのしやすさ
医療現場では靴を脱いだり履いたりする場面が多いため、脱ぎ履きのしやすさも考慮して選びましょう。
とはいえ、医療事務はデスクワークが中心であり、医療機関によっても脱ぎ履きが必要になるかどうかは異なります。
実際に働いている医療事務の方に、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
医療事務として働くならどのような身だしなみが適している?

医療事務は、患者さんと直に接する仕事です。
そのため、ネイルや髪型・髪色、メイク、アクセサリーなどがどこまでOKなのか気になるところです。
これから医療事務として働く予定の方は、以下でご紹介する内容をぜひ参考にしてみてください。
ネイルについて
仕事の大部分が窓口業務であるため、手先のネイルは患者さんの目に留まりやすくなります。
ネイルOKとしているかどうかは医療機関によって異なりますが、医療関連の仕事である以上、派手で装飾のあるネイルは控えましょう。
爪が長いと衛生上好ましくなく、キーボードを打つ際に邪魔になる可能性も考えられます。
髪型や髪色について
髪型や髪色の指定があるかは、医療機関ごとに異なりますが、いずれにせよ清潔感が求められます。
派手なスタイルや奇抜なカラーは避け、落ち着きのある見た目を心がけましょう。
また、医療事務は診療補助としてサポートに入る場合もあるので、髪が長い人は業務に支障がないように結んでおきましょう。
メイクについて
まつげエクステや、つけまつ毛、色の濃いリップやアイシャドウなど、派手な印象を与えてしまうようなメイクは控えましょう。
医療機関には小さなお子さんから高齢者まで、幅広い世代の人々が訪れます。
誰もが親しみを持って話しかけられるような印象を与えることが大切です。
アクセサリーについて
医療機関によって異なりますが、ピアスやリング、ネックレス、腕時計などのアクセサリーは、華美なデザインのものを避けてください。
基本的に業務に支障をきたすようなアイテムはNGです。
例えば、揺れるタイプのピアスは患者さんに当たったり業務中に落ちてしまったりするリスクがあるため、控えたほうが無難です。
職場によってはアクセサリーの着用自体をNGとしているケースもあるため、身につけたいと考えている方は確認しておきましょう。
医療事務の仕事に適した靴を選んで身だしなみも整えよう

今回は、医療事務で働く際の靴や身だしなみについてご紹介しました。
ナースシューズはそれぞれ機能性が異なります。
自分の足に合うか、長時間履いていても疲れないかなど、実際に履いてみると良いでしょう。
患者さんと最初に接する医療機関の顔として、親しみやすく清潔感のある身だしなみを心がける必要があります。
これから医療事務として働く予定がある人は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。






