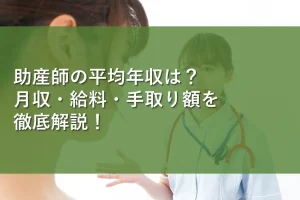助産師は、妊娠・出産・産後のケアを行いますが、専門性と需要の高さから、多くの人が関心を持つ職業の一つとなっています。
しかし、助産師の実際の状況を詳しく知る機会は少ないかもしれません。
本記事では、
- 助産師の平均年齢
- 助産師の就業人数の推移
- 助産師の就業状況
を詳しく解説します。
これから助産師をめざす方やすでに助産師として働いている方にとって、
助産師という職業の実態や将来性について分かるため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
助産師の平均年齢

助産師の平均年齢は、おおむね45歳前後となっています。
この数字は、助産師という職業の特性を反映しています。
助産師は、厚生労働省が定める国家資格であり、看護師などの他の医療職と同様に、一度取得すれば更新の必要がないため、長期にわたってキャリアを継続できる職業といえるでしょう。
長年の経験で専門性が高まり、病院だけでなく地域での訪問事業や助産院開業などさまざまなキャリア形成を行えることが、助産師の平均年齢を押し上げる要因の一つとなっています。
助産師という職業に興味を持ち、実際に資格取得をめざしている方は、以下のリンクで詳細な情報を確認することができます。
助産師の年齢層
助産師の年齢層で最も多いのは、25~29歳ですが若手から熟練者まで幅広く分布しています。
それぞれの年齢層によって、特徴や役割が異なることもわかっています。
ここでは、助産師の年齢層別の特徴について、詳しく見ていきましょう。
| 実人員(人) | 構成割合(%) | |
| 総数 | 38,063 | 100.0 |
| 25歳未満 | 2,251 | 5.9 |
| 25~29歳 | 5,992 | 15.7 |
| 30~34歳 | 4,721 | 12.4 |
| 35~39歳 | 4,651 | 12.2 |
| 40~44歳 | 4,798 | 12.6 |
| 45~49歳 | 4,789 | 12.6 |
| 50~54歳 | 4,136 | 10.9 |
| 55~59歳 | 3,200 | 8.4 |
| 60~64歳 | 1,962 | 5.2 |
| 65歳以上 | 1,563 | 4.1 |
最も多い25~29歳
厚生労働省が発表した令和4年度の統計によると、就業助産師の年齢階級別割合で最も多いのが25~29歳で、全体の15.7%を占めています。
この年齢層が最も多い理由としては、体力や意欲が充実しており、フレッシュな知識と情熱を持って働き始める時期であるからだと考えられます、
また、この年齢層の助産師は、妊婦さんと同年代であるケースも多く、コミュニケーションを取りやすいという利点もあるため、若い妊婦さんの不安や悩みに寄り添いやすい立場にあるといえるでしょう。
役職がつく40代
40~44歳・45~49歳の助産師は、それぞれ全体の12.6%を占めており、25~29歳に次いで多い年齢層となっています。
この年齢層の特徴として、以下のようなことが挙げられます。
- 主任や副師長など、大きなキャリアアップにつながる役職につき始める時期である
- 豊富な経験と専門知識を持ち、後輩の指導にも携わる
40~44歳は、助産師としてのキャリアが成熟する時期です。
長年の経験を活かしたさまざまなケースにも対応できる能力を持っているためです。
また、この年齢層が多いことは、助産師という職業が長く働き続けられることを示しています。
若手がいながらも平均年齢が40代になることから、より上の世代でも活躍の場があることがわかります。
定年後も働くことができる
助産師は、定年(施設によって前後はありますが、一般的に60~65歳)を迎えたあとも、働き続けることができる可能性があります。
これには、以下のような理由が考えられます。
- 助産師資格には、年齢による制限がない
- 豊富な経験と知識が、若い世代の助産師の育成に活かせる
定年後の助産師は、リーダー業務や役職から外れることで、さまざまな場所で働くことができます。
- 病院やクリニックでの勤務
- 看護学校や助産師学校での学生指導
- 地域の母子保健活動
また働き方も多様化しており、雇用延長制度を利用して正規職員のまま勤務を継続する方やパート・アルバイトで時間に余裕を持った働き方をしている方もいます。
このように、助産師は生涯にわたってキャリアを続けられる魅力的な職業といえるでしょう。
助産師の人数の推移
助産師の人数は年々増え続けており、少子高齢化ではありますが一人の子どもに対するケアの需要と供給は高まっています。
本章では、助産師の人数の推移、現在の状況、少子高齢化社会における助産師の需要について解説します。
助産師の人数は年々増えている
厚生労働省の発表によると、助産師の人数は年々増加傾向にあります。
具体的な数字を見てみましょう。
| 平成28年 | 35,774名 |
| 平成30年 | 36,911名 |
| 令和2年度 | 37,940名 |
| 令和4年度 | 38,063名 |
このように、助産師の人数は着実に増加しています。
助産師の人数が増加していることは、この職業への需要の高さを示しています。
助産師の年収について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
少子高齢化社会でも需要はあるのか?
日本は少子高齢化社会に突入していますが、そのなかでも助産師の需要は依然として高いといえます。
その理由には、以下のようなものがあります。
- 助産師外来や院内助産所のニーズが高まっている
- 訪問看護ステーションでの出産前後のケアや不妊治療など新たな需要が増えている
- 晩婚化にともなう高齢出産が増加に伴い、ハイリスク分娩に対応できる助産師の確保が必要
このように、助産師の活躍の場は広がっており、社会のニーズに応じて柔軟に対応しています。
助産師は、これからの社会でも必要不可欠な存在であり続けるでしょう。
助産師の平均年収
助産師の年収は、働き方や勤務先によって大きく異なります。
ここでは、正社員として働く場合と非正規雇用の場合に分けて、助産師の平均年収を詳しく見ていきましょう。
それぞれの特徴や、年収に影響を与える要因についても解説します。
正社員の場合
正社員として働く助産師の場合、年収は比較的安定しています。
一般的に、以下のような特徴があります。
- ボーナスが支給される
- 残業代がきちんと支払われる
- 夜勤手当が加算される
これらの要因により、病院勤務で夜勤もしている場合、年収は500万円前後になることが多いです。
ただし、実際の年収は勤務先の規模や地域、経験年数などによって変動します。
助産師の働き先として人気が高いのは病院です。
特に分娩数の多い病院を選択することで、以下のようなメリットがあります。
- より多くの経験を積むことができる
- 高度な医療技術を習得できる
- さまざまなケースに対応する能力が身につく
これらの経験や能力は、将来的なキャリアアップや年収アップにつながる可能性があります。
助産師の年収についてより詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
非正規雇用の場合
非正規雇用の場合、給与は正社員と比べて低くなりますが、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができるというメリットがあります。
また、経験を積みながら、将来的に正社員への転換をめざすことも可能です。
長く働ける助産師をめざそう
助産師は、長く働き続けられる魅力的な職業です。
25~29歳の若手が最も多い一方で、40代以降も活躍の場が広がっており、定年後も働き続けられる可能性があります。
人数も年々増加傾向にあり、少子高齢化社会においても需要が高まっています。
妊婦外来や訪問看護など、活躍の場も広がっており、ライフステージに合わせた働き方を選択することが可能です。
年収面でも、正社員であれば500万円前後と安定しており、非正規雇用の場合でも柔軟な働き方ができるというメリットがあります。
助産師として長く働き続けるためには、常に最新の知識と技術を習得し、経験を積むことが大切です。
また、自身のライフスタイルに合わせて働き方を選択し、ワークライフバランスを保つことも求められます。
助産師は、母子の健康を支える重要な職業です。
やりがいと専門性を持ち、社会に大きく貢献できる素晴らしい仕事だといえるでしょう。