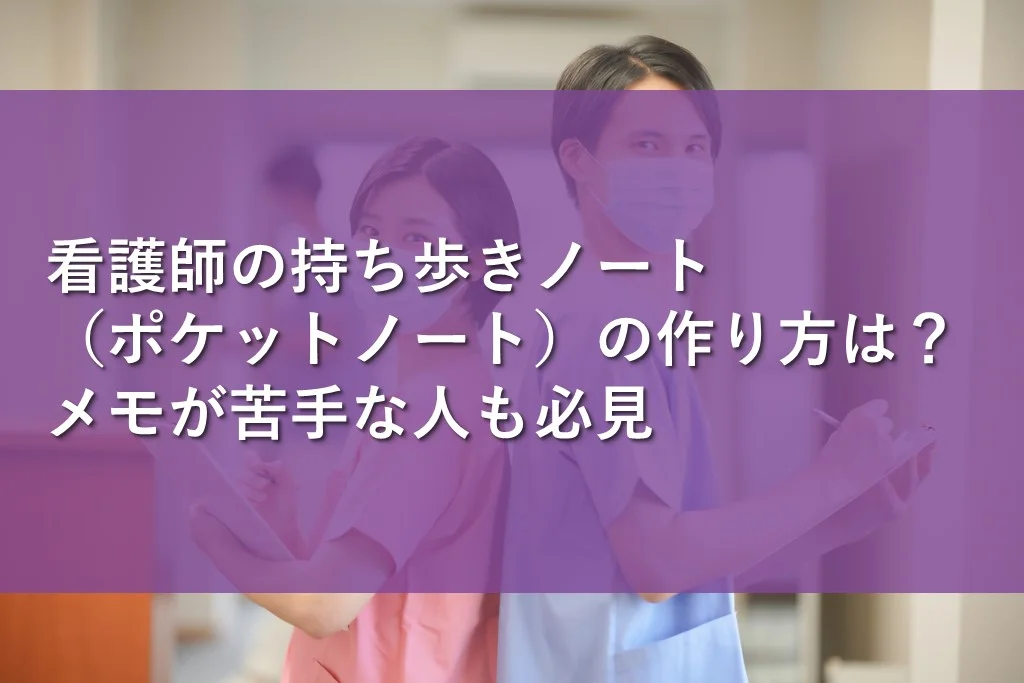
医療現場で処置やケアの看護業務のほか、退院処理や入院書類管理などの事務作業も担当する看護師にとって、必要な情報をすべて覚えておくことは困難です。
そこで活躍するのが、持ち歩きノート(ポケットノート)です。
持ち歩きノートは、業務での重要な情報をメモしたり、あとから読み返して確認するために使用します。
今回の記事では、業務で活用できるノートの取り方を解説していきます。
目次
看護師の持ち歩きノートを使う場面は?
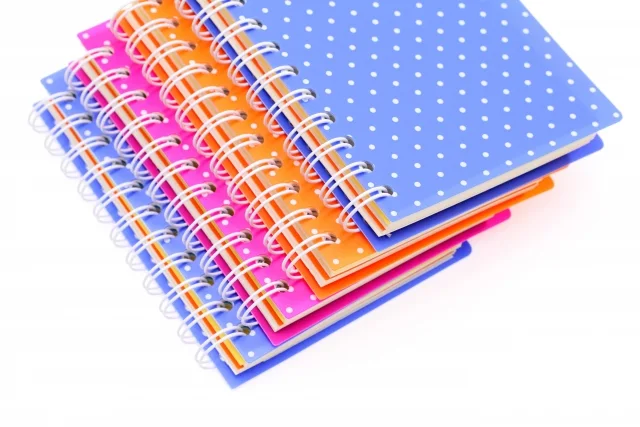
看護師の学校で勉強し、国家資格を取得した看護師であっても、実際に業務に携わることになれば1年目はわからないこともたくさんあります。
何度も同じことを先輩に確認したり、わかっていないのにわかったふりをしたままにすれば、業務に支障が出るのはもちろん、患者さんの命を預かる身として重大なトラブルを引き起こす事態にもなりかねません。
そのためにも、自分用に業務内容などをまとめた持ち歩きノートを作ることはとても大事です。
すべての症状や観察項目、薬効、業務内容を覚えて、完璧にこなせる新人看護師はまずいません。
新人の段階では、ノートを見ながら正しく業務を遂行できる状態をめざすと良いでしょう。
看護師の持ち歩きノートの作り方
看護師の持ち歩きノートの作成方法は、以下のとおりです。
〇自分が関わることの多い疾患の病態や症状、検査、治療、観察項目や看護のポイントについて、文献を参考にまとめる
ノートを作成する際は、ただ文献を書き写すのではなく、あとで読み返したときに見やすく、ポイントがわかるように整理しておくと便利です。
〇先輩から教わった業務内容を書き留めておく
先輩から教わったことや病棟内の業務ルールについて、「なぜそうするのか」根拠とともに整理しましょう。
看護師の業務は、急変などの緊急事態を除けばルーティンワーク、または、準備時間を設けることができる処置のため、メモを見ながらスピーディーに対応できれば、病棟の即戦力として活躍できます。
本格的に受け持ちが始まる前のシャドウイング(医師やベテラン看護師などに同行し様子を観察する教育方法)の段階で習ったことは一通り完成させておくのが理想です。
〇自分の部署でよく目にする薬についてまとめる
作用や副作用はもちろんのこと、使用上の注意点、投与方法、対象疾患についても整理しておきましょう。
業務中にいちいち薬の辞書やインターネットを開く手間が省け、大変便利です。
また、薬を理解しておくと「血圧が低下しているからこの薬は飲まないほうがいいかな。
医師に確認しよう」と医師への指示確認もスムーズになります。
持ち歩きノートを作るときのポイント
続いて、持ち歩きノートを作るときのポイントを解説します。
あとから自分が困らないように、見やすく整理されたノートを作りましょう。
書く文字量を少なくする
持ち歩きノートに書く文字量は極力少なくしましょう。
特に、先輩から助言を受けながらメモをとる場合、言われたことをすべて書きとめようとしてペンが追いつかず、聞くことがおろそかになってしまいがちです。
メモをとる際には、要点やキーワードを箇条書きでまとめたり、あとから見たときにわかるのであれば、略語を使ったりしても良いでしょう。
こうしたメモの取り方は、ポイントがわかりやすいだけでなく、情報を整理する練習にもなります。
読めれば走り書きでOK
持ち歩きノートは、他人ではなく自分が読むものなので、自分さえ理解できれば走り書きでも問題ありません。
無理に丁寧に書こうとせず、情報を正確に拾うことに集中しましょう。
余白は多めにとる
余白は多めにとりましょう。
ノートを見やすくするためだけでなく、あとから気付いたことを追記できるからです。
あらかじめノートの端に空白欄を作ったり、改行を多めに入れたりしながら書いておけば、より見やすく、追記しやすいノートになります。
カテゴリごとで分ける場合は、各カテゴリの後ろに追記できるスペースを残しておきましょう。
あとから見たときにわかりやすく書く
ノートを作る際は、あとから見たときにわかりやすいかどうかを意識しましょう。
ポイントや重要項目は赤字、先輩からの助言は青字などというように、自分がわかりやすいように色分けすることもおすすめです。
ただし、色を多く使いすぎてしまうとかえって内容がわかりづらくなるため、黒・赤・青など3色程度に抑えておきましょう。
わかりづらい内容は図解で
文字だとわかりづらい場合は、積極的に図解を取り入れるのもコツです。
せっかくノートを作成しても、文字の説明のみでまとめてしまうと、見返したときにうまく理解できないこともあります。
たとえば、疾患の部位を示したい場合や、業務の流れをまとめたい場合、処置の物品準備などは、イラストやフロー図なども使ってまとめてみましょう。
図解にすることで、業務中に読み返したときの理解も早まり、業務がスムーズになります。
メモの内容を相手に確認する
業務中のメモは、急いでとることが多いものですが、時間に余裕がある場合には、メモした内容を復唱し、先輩や同期に間違いがないか確認してもらいましょう。
第三者による確認が入ることで、間違えた内容で覚えることを防止できます。
メモをその日のうちに見返す
メモは、とっただけで終わりではありません。
その後の業務に活かすことで、はじめてメモとしての機能が発揮されるのです。
とったメモは、休憩時間や帰宅後の隙間時間を利用して、その日のうちに一度は見返すよう習慣づけましょう。
「そういえばこんなこと言われたな」「こうやって教わったな」と思い返すだけでも、頭のなかで情報が整理されていきます。
数少ない処置であった場合はなおさら一回ずつの学びが重要であるため、定期的に見直しておくと久しぶりの処置にあたっても焦らず対応することができます。
そして、できるだけ早く清書することも重要です。
もちろん、メモした段階のもので自分が理解できるものであれば必ずしも清書の必要はありません。
看護師の持ち歩き用におすすめのノート
看護師は、業務中病棟内外を動き回るので、使いやすく丈夫なノートを選びましょう。
ここからは、看護師の持ち歩き用におすすめのノートをご紹介します。
アンファミエスリムノート(2冊セット)

ナースグッズメーカーのアンファミエから販売されている、アンファミエスリムノート2冊セットは、ポケットから出し入れしやすい縦長のスリムなノートです。
ドット方眼で、図やイラストなどが書きやすいのも特長です。
★Pastelloツイストノート(A6サイズ)

同じくアンファミエから販売されている★Pastelloツイストノート(A6サイズ)は、閉じ具が開いてリーフ交換ができるため、あとからメモを整理しやすいノートです。
ポリプロピレン製の表紙は、ポケットに入れても折れることなく、長く快適に使えます。
wemoウェアラブルメモ

こちらは通常のノートとは異なる、腕時計のように手首に巻いておけるメモです。
指や消しゴムで簡単に消せるため、何度でも繰り返し使えるのもうれしいポイントでしょう。
別のノートに清書する必要がありますが、ポケットからメモ帳を取り出す時間も惜しいような場面で、咄嗟にメモを取るためのツールとしては優れたアイテムです。
あとで持ち歩きノートを作るための、簡易的なメモ用として併用すると良いでしょう。
デメリットとしては、清潔区域を維持する処置のとき、手首付近に無滅菌なものがあると不潔操作になるリスクがあるため、場面を意識して使い分けが必要です。
持ち歩きノートを上手に活用して看護師の仕事をスムーズにこなそう
看護師の持ち歩きノートの必要性や作り方のポイント、ノートの選び方を解説しました。
新人看護師は覚えることも非常に多く、すべてを一度に覚えるのは難しいものです。
自分用の持ち歩きノートを常にポケットに忍ばせておけば、先輩に何度も同じことを聞き直したり、曖昧な理解のまま進めてトラブルを引き起こしたり、といったことも防げます。
看護師が使用することを想定した商品も数多く作られているので、自分にピッタリのノートを探してみてください。







