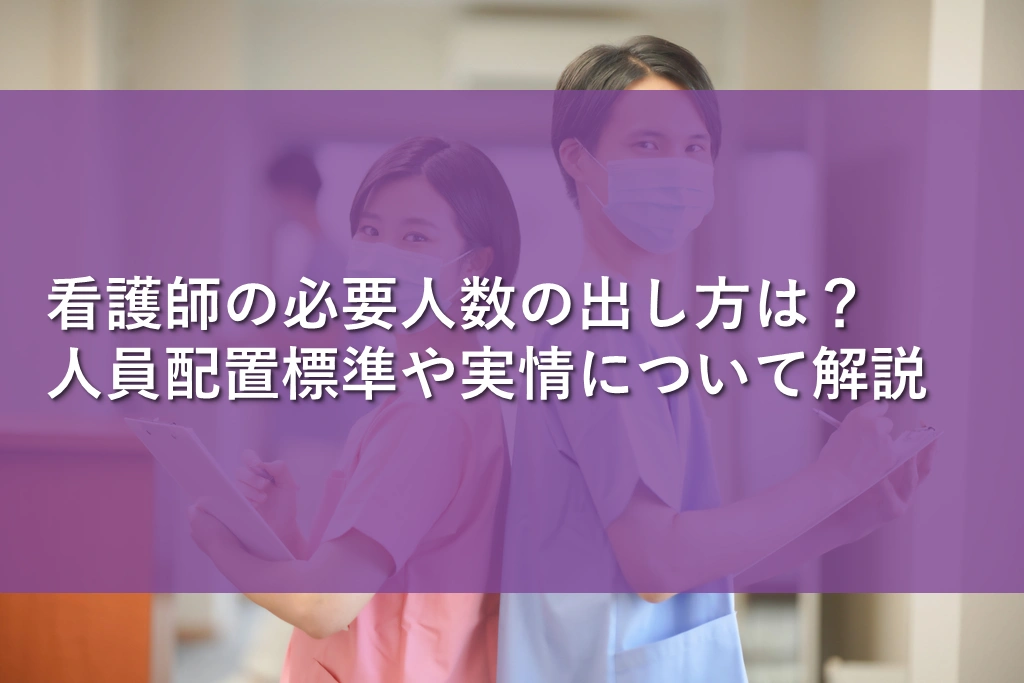
勤務する病院や施設を探す際などに、「〇:1看護」といった表記を目にしたことはありませんか?
看護師の必要人数は、病院や病棟、施設ごとに定められています。
今回は、看護師の必要人数の出し方について、人員配置標準や実情を解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次
看護師の必要人数は人員配置標準に基づいている

各病院や施設における看護師や医師、介護職員などの必要人数は、人員配置標準に基づいて定められています。
人員配置標準とは、適切な医療を提供するために一定水準以上の人員を確保する目的で、厚生労働省によって定められた基準です。
人員配置標準における考え方は、最低基準ではなく、標準です。
その理由は、人員配置標準を満たさない場合でも、患者さんの傷病の程度や医療従事者間の連携により、一定の医療水準を確保することが十分可能な場合もあるとされているためです。
病院や施設では、この基準をもとに必要な看護師数を計算しています。
看護師の必要人数の出し方
ここでは、看護師の必要人数の出し方を解説します。
正看護師比率を明らかにする
看護師の必要人数の計算では、准看護師は含めず、正看護師のみが対象です。
これは、患者さんに対して入院基本料を請求する際に、看護要員の配置が「当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること」と定められているためです。
そこで必要となるのが、正看護師比率の算出です。
正看護師比率とは、その部署に必要な看護要員に対する正看護師の割合のことであり、人数ではなく、月ごとの勤務時間数をもとに計算します。
正看護師比率は、以下の式で求めることができます。
正看護師比率=正看護師の月延べ勤務時間数÷病棟に必要な看護職員の月延べ勤務時間数×100
(病棟に必要な看護職員の月延べ勤務時間数=8時間×必要看護配置数×月日数)
部署に必要な看護師数を求める
続いて、部署に必要な看護師数の求め方についての解説です。
ここでは、7:1看護体制で50床満床の病棟を例に考えてみましょう。
この場合、単純に計算して50床÷7人=7.14人の看護師が必要だと考えがちですが、それは誤っています。
なぜなら、50人の患者さんは24時間病棟にいますが、看護師は勤務時間しか病棟にいないためです。
看護師の必要人数を求める際には、24時間のなかで必要となる人数を検討しなければなりません。
看護師一人の1日あたりの勤務時間を8時間とした場合、24時間÷8=3人の看護師が必要となります。
つまり、その病棟における1日に必要な看護師数は、3×7.14人=21.4人となります。
この病棟では、1日に最低でも22人の看護師が必要です。
看護師の必要人数
配置基準では、患者さんの医療必要度が高い病院や病棟ほど、看護師を多く配置するように定められています。
代表的なものには7:1看護、10:1看護、13:1看護があり、〇:1の〇の数字が小さくなればなるほど手厚い看護となり、診療報酬も高くなります。
7:1看護
2006年の診療報酬改定の際に、急性期の患者さんを対象とする現場向けに定められた基準が「7対1入院基本料」です。
7人の患者さんに対して一人の看護師を配置しなければならないという基準であり、看護の質は高まります。
看護師一人あたりの担当患者数が少なく業務負担が減ることや、勤務している看護師数が多く労働状況が良いことなどがメリットとして挙げられます。
10:1看護
10:1看護は、7:1看護と同様に急性期の患者さんを対象とするものの、医療必要度や看護必要度は7:1看護よりも低いのが特徴です。
入退院の頻度も7:1より少ない傾向にあり、看護師の業務負担や忙しさの面においても7:1より落ち着いています。
13:1看護
13:1看護では、急性期ではなく退院や復帰をめざす療養期・慢性期の患者さんを対象とします。
医療必要度や看護必要度は10:1よりもさらに低くなり、ケアミックス病院や回復リハビリテーション病棟などが多いです。
常勤換算
看護師の人員配置では、〇:1という考え方以外に常勤換算といわれるものもあります。
常勤換算は、看護師の労働力を看護師の人数ではなく労働時間でカウントする方法であり、パート・アルバイトの職員が多いなど、さまざまな働き方をしている看護師が多い職場の人員計算に役立ちます。
看護師の必要人数は病院や病棟の規模・特徴によって異なる
今回は、看護師の必要人数の出し方を解説しました。
看護師の必要人数は人員配置標準により定められていますが、病院や病棟の規模や特徴によって異なります。
必要人数を計算する際には、自分の病院や病棟がどの基準に該当するのかを確認し、正しく計算しましょう。






