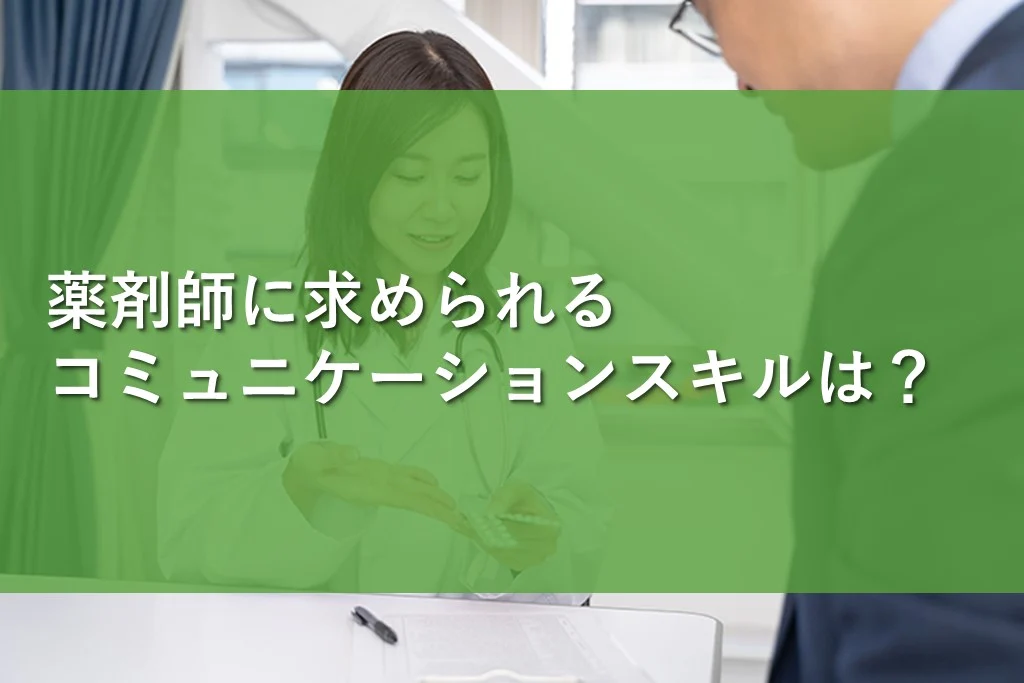
薬剤師は「薬」の専門家です。処方せんに基づいて調剤や患者さんへの服薬説明を行うほかに、薬をより効果的に安全に使っていただくために働いています。
病気や怪我による不安を抱えた患者さんに寄り添い、より適切な薬物療法を実施するためには、コミュニケーションスキルが求められます。
患者さんと接するときだけでなく、他の医療従事者と連携を図る際にも、コミュニケーションスキルが活用できるでしょう。
本記事では、薬剤師にコミュニケーションスキルが求められるシーンや、円滑なコミュニケーションを図るためのコツを解説します。
目次
薬剤師にコミュニケーションスキルが必要な理由

薬剤師にコミュニケーションスキルが必要とされるのは、2つの理由があります。
- 患者さんに信頼され適切な薬物療法を実施するため
- チーム医療の一員として他の医療従事者と連携するため
服薬指導だけが薬剤師の仕事ではありません。
薬の専門家として、患者さんにより良い薬物療法を提供するためにも、他の医療従事者との積極的なコミュニケーションが求められます。
患者さんに信頼され適切な薬物療法を実施するため
調剤薬局やドラッグストア、病院などさまざまな場所で従事する薬剤師は、身近な医療従事者として患者さんの悩みに寄り添う必要があります。
患者さんとのあいだに信頼関係を築いておけば、副作用などのリスクを早期に発見し、適切な薬物療法を実施しやすくなるでしょう。
「主治医には言いにくいことも薬剤師には話せる」という関係性があれば、よりその人にあった医療を提供することができます。世間話のなかで、気になることがあれば、薬剤師から受診を促すことも可能です。
患者さんとの積極的なコミュニケーションは、患者さんが自分の病気を受け入れて、医師の指示にしたがって積極的に薬を用いた治療を受けること(服薬アドヒアランス)を可能にし、信頼の獲得、リスクの早期発見にもつながります。
チーム医療の一員として他の医療従事者と連携するため
薬剤師は、チーム医療の一員として他の医療従事者と連携する必要があります。
処方箋の疑義を照会しリスクを未然に防ぐことは、薬剤師の重要な役割の一つです。
また、医師や看護師と情報交換をして患者さんの状態を詳しく把握できれば、専門知識を活かしたより良い処方提案・処方設計も可能になります。
在宅医療の現場においても、チーム医療の一員としての薬剤師は重要です。
薬剤師が参加することで、患者さんの飲み合わせや服薬方法、管理状況などの安全性・信頼性が向上するでしょう。
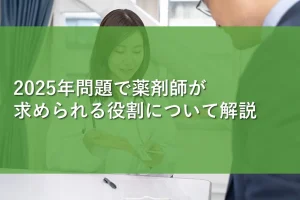
薬剤師にコミュニケーションスキルが求められるシーン
薬剤師にコミュニケーションスキルが求められるのは、主に次のようなシーンです。
- 患者さんとのやり取り
- 医師とのやり取り
- 同僚・上司とのやり取り
シーンによって薬剤師が果たすべき役割は異なりますが、いずれの場合でもコミュニケーションスキルが役立ちます。
患者さんとのやり取り
患者さんに対する服薬指導、薬歴の把握、訪問薬剤管理指導などのやり取りには、コミュニケーションスキルが求められます。
服薬指導の際は、なぜこの薬が処方されたのか、正しい使用方法や注意点を患者さんに、わかりやすく説明しなければなりません。
薬歴の把握でも、患者さんから正確な情報を引き出すために聞き取る力が必要になります。
訪問薬剤管理指導では、訪問先での薬の管理状況を確認するとともに、患者さんとそのご家族が薬と安全に付き合えるように指導を行います。コミュニケーションスキルを使えば、薬の説明や必要性を理解してもらいやすくなるでしょう。
医師とのやり取り
疑義照会や処方計画書の立案など、薬剤師と医師の連携が必要な場面でも、コミュニケーションスキルが求められます。
疑義照会は、処方箋の内容に疑問点や問題点があった場合に、薬剤師が薬の専門家として医師へ問い合わせを行うことです。
また、病棟薬剤師が行う処方計画書の立案では、患者さんの状態に合わせた薬物療法の意図を伝えるために、医師とのコミュニケーションが欠かせません。
密な情報共有によって、医療事故などのリスクを回避し、より適切な薬物療法を実施できるようになります。
同僚・上司とのやり取り
薬剤師が同僚・上司とやり取りをする場面としては、調剤に関する相談時や監査業務、新人の指導、休暇取得時の引き継ぎなどが想定されます。
調剤に関する相談時や監査業務では、情報を手短に伝え、受けたアドバイス・指示の内容をスムーズに伝達する必要があるでしょう。
新人指導を担当する場面にも、対象となる新人薬剤師のレベルに合わせた説明や指導が求められます。
また、休暇の取得や急な外出などには、業務に支障が出ないよう同僚・上司に対して効率的かつ明確で漏れのない引き継ぎが必要です。コミュニケーションスキルを使えばよりスムーズな引継ぎが可能になるでしょう。
薬剤師に求められるコミュニケーションスキルは?
薬剤師が身につけるべきコミュニケーションスキルは、具体的に次のような能力を指します。
- 傾聴する力(傾聴力)
- 言葉の真意をくみ取り状況を理解する力(理解力)
- 相手にとってわかりやすい説明をする力(説明力)
- 非言語コミュニケーション
ただ聞く・話すのではなく、相手の伝えたいことを正確に聞き取る力、自分の伝えたいことを明瞭に説明できる力を身につけましょう。
傾聴する力(傾聴力)
傾聴力とは、相手の話にきちんと耳を傾ける力のことです。
服薬指導では、患者さんが抱えている不安や疑問を聞き取り、適切なアドバイスを行う必要があります。
相槌を打ちながら、しばしば目をあわせて最後まで話を聞くことで、患者さんの安心感や信頼感につながるでしょう。
また、薬剤師は患者さんだけでなく医師や看護師、栄養士などの他職種ともやり取りをする機会があります。
必要な情報を正しく聞き取るために、傾聴力は欠かせません。
相手の真意をくみ取り状況を理解する力(理解力)
言葉の真意をくみ取って状況を理解できる力を身につけると、相手が本当に伝えたいことは何か、何を必要としているのかを判断できるようになります。
患者さんの話す内容を額面どおりに受け取るのではなく、表情や声色・顔色、仕草など、さまざまな視点で観察してみてください。
また、疑義照会などで医師との意思疎通がうまくいかないと、処方の目的や副作用、飲み合わせなどのリスクが放置される結果にもなりかねません。
あいまいな理解のまま服薬指導を行えば、患者さんからの信頼を失うだけでなく医療事故を招きかねません。
相手の言葉の真意をくみ取り状況を理解する力は、薬物療法の安全性を保つためにも必須のスキルといえるでしょう。
相手にとってわかりやすい説明をする力(説明力)
コミュニケーションスキルにおける説明力とは、相手の立場や背景を理解したうえでわかりやすい言葉を選び取り、誤解を与えずに情報を伝える能力のことです。
患者さんのなかには、医療従事者が普段使用している言葉にはなじみがなく、違和感を持つ人も少なくありません。
限られた時間のなかで情報共有を的確に行うには、相手の状況をふまえて説明の仕方を変える必要があるでしょう。
患者さんは薬の専門家ではありません。専門用語はできるだけ使わずに、相手が求める情報をわかりやすく提供する必要があります。
非言語コミュニケーション
非言語コミュニケーションとは、服装や表情、視線、仕草のような言葉以外のコミュニケーションツールのことです。
心理学者であるアルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」によると、人同士のコミュニケーションのうち、言葉が与える影響は7%に過ぎません。
これに対し、見た目や表情などの視覚情報は55%、声の大きさ、話し方といった聴覚情報は38%を占めています。
特に第一印象に悪い印象を持たれないよう清潔で派手過ぎない服装を選ぶ、少し前傾した姿勢で言葉と表情が一致するように話をするなど、見た目や表情に気を付けるのは大切なことです。
患者さんやチーム医療のメンバーと信頼関係を築くうえで、非言語コミュニケーションの活用は大いに役立つでしょう。
薬剤師が知っておきたいコミュニケーションのコツ

薬剤師が大切にしたいコミュニケーションスキルを身につけるために、以下の4つについてコツを押さえておきましょう。
- 傾聴
- アサーティブに話す
- 矛盾した感情を想定する
- ペーシング
相手の話に耳を傾けるとともに、自分自身の表情や話し方、身振り手振りなどの非言語的コミュニケーションにも気を配ることで、会話を円滑に進められます。
傾聴
傾聴のポイントは、相手に体を向けて目線を合わせ、「きちんと話を聞いている」という姿勢を示すことです。
適切なタイミングで相槌を打ちながら、患者さんの話を途中でさえぎることなく、最後まで真剣に聞くようにしましょう。
相槌が雑だと話の内容が伝わっているか不安になります。姿勢が悪い、表情が硬いなども非言語のメッセージになり、不安を抱かせる原因になります。
相手の立場に立った傾聴スキルで患者さんから信頼を得られれば、服薬指導もスムーズに受け入れてもらえるでしょう。
アサーティブに話す
アサーティブとは、自分の主張をはっきりと伝えることです。
チーム医療の質を高めるには、相手の考えを受け止めたうえで、必要とあらば自分の意見も共有しなければなりません。
リスクがあると判断した場合、医師や上司などが相手であっても、積極的な主張が求められます。
その際、ただ否定的に意見するのではなく、事実の共有・事実に対する主観的な評価の共有・相手への提案という手順を踏むようにしましょう。
アサーティブなコミュニケーションでは、相手の考えも尊重したうえで自分の意見を主張することがポイントです。
矛盾する感情を想定する
患者さんの発する言葉の裏側には、複雑な感情や問題が隠れていることもあります。
例えば「薬を飲みたくない」と訴える患者さんの場合、治療には前向きであるものの、薬の副作用に不安を抱えているのかもしれません。
薬剤師は、患者さんの矛盾した感情を想定しながらコミュニケーションを取る必要があります。
共感的な繰り返しを行ったり、質問を変えたりしながら、複雑な感情を推しはかりましょう。
会話のなかで矛盾の感情が明確になったら、患者さんにその感情を認識してもらい、今後どのようにしたいか患者さん自身で決定できるよう促してみてください。
ペーシング
ペーシングは、信頼関係を構築するために有効なコミュニケーションスキルです。
相手のペースに合わせて自分の言動を調整し、会話や意見を受け入れてもらいやすくする効果があります。
ペーシングのテクニックであるバックトラッキング、ミラーリング、マッチングについて順に見てみましょう。
バックトラッキング
バックトラッキングは、相手の発言から重要なキーワードを拾って言い換えたり、要約して返したりするテクニックです。
相手の考え方を理解し関心を持って、受け止めていることを伝えられます。
患者さんに対してバックトラッキングを行うことで、患者さんは自分の話に耳を傾けてもらえたと感じ、親近感や信頼感、安心感を抱いてくれるでしょう。
ミラーリング
ミラーリングとは、相手の非言語コミュニケーション(表情や姿勢など)を意識的に真似て、相手と同調することです。
患者さんが顔を傾けたら同じように傾ける、笑顔になったら自分もにっこりと笑うなど、相手の動作を模倣します。
これは、人が自分と似た動作をする相手に対して好意を抱きやすくなるという心理効果を活用したテクニックです。
ミラーリングを実践する際は、不自然に思われないよう、相手の動作からワンテンポ遅らせてさりげなく真似をしてみてください。
マッチング
マッチングは、相手の言葉遣いや声のトーン、話すスピードに合わせて会話を行うテクニックです。
例えば、くだけた口調の患者さんの場合、自分自身も親しみやすさを意識して話すようにします。
相手の非言語コミュニケーションに合わせることで「自分に寄り添ってくれている」と感じさせ、信頼を獲得しやすくなるでしょう。
コミュニケーションスキルを身につけてワンランク上の薬剤師をめざそう
薬剤師のコミュニケーションスキルは、適切な薬物療法や、チーム医療の一員として円滑に連携を図るために必要不可欠です。
わかりやすく説明する力をはじめ、傾聴する力、真意をくみ取って理解する力、非言語コミュニケーションなど、相手や状況に合わせたスキルが求められます。
また、患者さんからの信頼を獲得するためには、ペーシングも上手に取り入れましょう。
具体的には、相手の発言を要約してオウム返しするバックトラッキング、動作を真似るミラーリング、話し方や言葉遣いを合わせるマッチングなどのテクニックがあります。
これらのポイントを押さえてコミュニケーションスキルを磨き、患者さんや他の医療従事者から信頼されるワンランク上の薬剤師をめざしてみてください。







