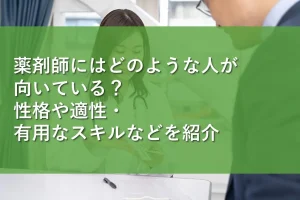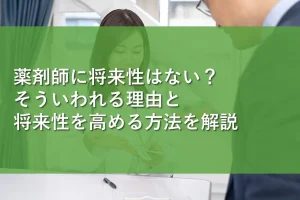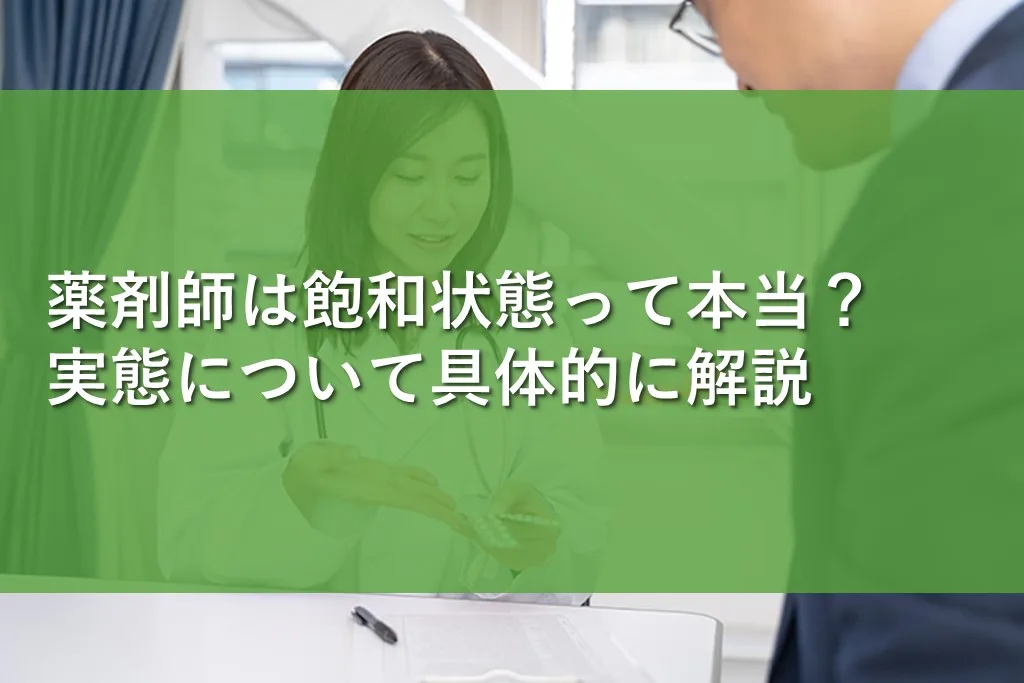
「薬剤師は飽和している」という話を、耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。
薬剤師として働いている人や、薬剤師をめざしている人にとっては、大変気になる話題です。
そこで今回の記事では、薬剤師が飽和状態といわれる実態について具体的に解説します。
目次
薬剤師は現在飽和していない!その実態は?

結論からいうと、現在のところ薬剤師は飽和していません。
薬剤師数は少ない
薬剤師数の多い・少ないは、求職者数に対する求人数の割合を示す、有効求人倍率から読み取れます。
厚生労働省の令和4年6月分一般職業紹介状況(パート除く)によると、医師・薬剤師等の有効求人倍率は2.76倍です。
同調査における同時期かつすべての職種での有効求人倍数は1.23倍ですので、薬剤師は有効求人倍率が高く、売り手市場であるといえます。
女性が多く、結婚・出産・育児による退職が多い
厚生労働省の令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概要によると、薬剤師のうち男性が38.6%、女性が61.4%と、女性のほうが多くなっています。
そのため、人生のライフイベントなどにより現場から離れる薬剤師も一定数おり、薬剤師資格保有者数の割に、現場に出る薬剤師数が不足している現状があると考えられます。
地域によっては薬剤師不足が深刻な問題となっている
薬剤師の充足状況は地域によって大きく異なり、特に地方で薬剤師が不足している状況です。
厚生労働省の令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概要によると、都道府県別に薬剤師数をみた場合に、沖縄県や福井県、青森県において薬剤師が少なくなっています。
薬剤師資格で他の仕事をしている人もいる
なかには、薬剤師の資格を有しつつも他の仕事をしている人もいます。
そのため、データや統計上では飽和状態にあるようにみえても、実際に現場で働いている薬剤師は不足しているという事態が起こっている可能性があります。
薬剤師に向いている人について知りたい人は、以下の記事もご覧ください。
薬剤師に過不足が生じる原因は?
現状、薬剤師は飽和していませんが、今後供給過多となり飽和する可能性があると考えられているのは事実です。
そこで、薬剤師に過不足が生じる原因について解説します。
薬剤師が不足する原因
薬剤師が不足する原因は、超高齢化社会、女性薬剤師の多さ、医薬分業の推進などによる影響が考えられます。
なかでも、医薬分業は近年急速に拡大されており、調剤薬局やドラッグストアの数が増加しています。
それに対し、薬剤師の供給が追いつかない状況があるのも原因の一つです。
また、薬剤師には女性が多く、ライフイベントなどの影響で現場から離れる薬剤師が多いのは先述のとおりです。
これらの原因で、薬剤師が不足しやすくなっています。
薬剤師が過剰となる原因
一方、薬剤師が過剰となる原因としては、薬剤師業務の機械化、都心部への薬剤師偏在、薬学部の新設により薬学生が増加したことなどが考えられます。
薬剤師業務のAI化が注目されており、近い将来、調剤や一包化などの業務において人の手がいらなくなる可能性があるでしょう。
また最近では、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、一時的に薬剤師の需要が大幅に低下したこともありました。
今後も、感染症のパンデミックなどが原因で同じことが起こる可能性があります。
【職場別】将来的に薬剤師が飽和する可能性は?
薬剤師の将来性は、職場によっても異なります。
薬剤師の働き先としてよくある4つの職場の将来性について、それぞれ解説します。
調剤薬局
調剤薬局は薬剤師の主要な勤務先です。
しかし、近年では薬局事務員のピッキングが一部認められるようになりました。
今後も、これまで薬剤師しか担えなかった業務で、他のスタッフに代替可能となる業務が出てくる可能性があります。
また、消費税増税にともなう薬価改定なども行われており、調剤薬局の収益に影響を及ぼしていることもあります。
このような理由から、調剤薬局で働く薬剤師の場合は、人材的にも、給料的にも、将来性が安定しているとは言い難いかもしれません。
ドラッグストア
ドラッグストアは、医薬分業の推進により年々市場規模が拡大しています。
調剤併設型薬局も増加傾向にあり、今後も薬剤師が大いに活躍できることでしょう。
ドラッグストアは人々の生活に密着した店舗であり、なかには24時間体制で営業しているところもあります。
薬剤師だけでなくスタッフ総数が不足しがちであり、薬剤師業務以外の業務が求められることさえ覚悟しておけば、将来的にも安定した雇用が望めると考えられます。
病院
病院では、薬価改定や調剤報酬改定が収益に影響を及ぼすことは少なく、将来性は比較的安定しているといえるでしょう。
病院薬剤師は夜勤などで業務がハードとなりやすいこと、他の職場と比較すると給与が低い傾向にあることなどから、薬剤師が不足しやすい状況にあります。
このような理由から、今後も病院薬剤師の需要は高まることが予測できます。
企業
製薬会社など、企業に勤める薬剤師は将来性に不安な部分があります。
その背景には、ジェネリック医薬品の普及により、新薬に関する営業がしにくくなっていることがあります。
また、MRやMSは薬価改定などの影響を直に受けるため、収益減少にともない収入が減少してしまう可能性も否定できません。
将来飽和することがあっても薬剤師として生き残るためには?
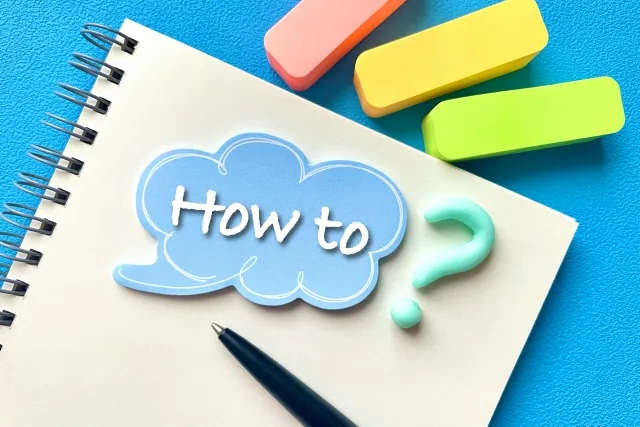
薬剤師を取り巻く環境は年々変化しており、その影響で将来的に飽和状態になる可能性も否定できません。
もしそのような状況になってしまっても、薬剤師として生き残るために心がけたいことについて解説します。
資格を取得し、専門スキルを身につける
専門的なスキルがある薬剤師は重宝されます。
薬剤師のダブルライセンスには、認定薬剤師や専門薬剤師、認定実務実習指導薬剤師、サプリメントアドバイザーなどがあります。
さらに詳しくみると、認定薬剤師にはがん薬物療法認定薬剤師や、在宅療養支援認定薬剤師などがあり、取得によって今後需要が高まるであろうがんや在宅医療の分野で活躍できる可能性が高いです。
自分の強みを持っている薬剤師は、飽和状態のなかでも生き抜いて、活躍し続けることができるでしょう。
コミュニケーション能力を高める
薬剤師の業務がAIに代替されてしまう可能性があることは先述のとおりです。
そこで高めておきたいのが、コミュニケーション能力となります。
薬剤師は、単に薬を調剤し患者さんに渡せば良いのではありません。
患者さんとのコミュニケーションをとおして、安全な服薬をサポートしたり、患者さんの悩みをヒアリングしたりすることが大切です。
業務がどんなに機械化したとしても、患者さんとのコミュニケーションは人間にしかできないことです。
コミュニケーション能力を磨き患者さんから信頼される薬剤師であることは、将来薬剤師として生き残るために必須であるといえるでしょう。
マネジメント能力を身につける
マネジメント業務も、コミュニケーションと同様AIにはできない業務です。
今後薬剤師が供給過多になっていくことを踏まえると、薬剤師や職場を管理する能力を持つ、管理薬剤師の能力を身につけておくことをおすすめします。
管理薬剤師は、調剤薬局やドラッグストアなどに配置されるため、今後も需要が維持されると考えられます。
地域密着型の薬剤師になる
地域密着型の薬剤師になることも、飽和状態を生き抜くうえで大きな強みとなります。
高齢化による影響を受け、在宅医療へのニーズは高まるばかりです。
地域密着型の薬剤師の主な業務内容は、患者さんのもとに薬を届け、服薬指導を行う訪問薬剤管理指導となります。
さまざまな年齢、疾患の患者さんを対象とするため日々のスキルアップは必要不可欠ですが、将来性は安定しているといえるでしょう。
副業・複業により収入の柱を複数もつ
飽和状態をみすえて、副業や複業により収入源を分散させておくこともおすすめです。
薬剤師の資格を活かせる副業や複業もあるため、興味がある人は検討してみてはいかがでしょうか。
薬剤師の飽和状態を過度に恐れる必要はないが、将来への備えは考えよう
今回は、「薬剤師は飽和状態となる」といわれる真相や実態、薬剤師の将来性について解説しました。
薬剤師はいまのところ飽和状態とはなっていませんが、薬剤師をとりまく状況の変化や世の中の動きによっては、将来的に薬剤師が供給過多状態になってしまう可能性もあります。
過度に不安になる必要はありませんが、たとえ飽和状態に陥ったとしても薬剤師として生き残れるよう、少しずつ備えていきましょう。