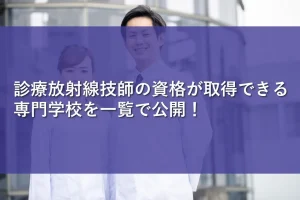診療放射線技師国家試験合格をめざすなら、まず受験科目や合格基準など、試験の概要の把握から始めましょう。
試験の概要を把握したうえで対策を立てることで、効率よく勉強を進められます。
この記事では診療放射線技師国家試験の受験資格と試験科目、合格基準・合格率、試験合格までの道のりを解説します。診療放射線技師をめざして国家試験の受験を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
第74回診療放射線技師国家試験の概要
2022年2月17日に実施された第74回診療放射線技師国家試験の概要は次のとおりです。
| 試験日 | 2022(令和4)年2月17日(木曜日) |
| 試験会場 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県および福岡県 |
| 受験手数料 | 11,400円 (収入印紙を受験願書に貼り付けて納付) |
| 願書の受付期間 | 2021(令和3)年12月14日(火曜日)から2022(令和4)年1月4日(火曜日)まで |
| 必要書類 | ● 受験願書 ● 写真 ● 返信用封筒 ● 修業証明書もしくは修業見込証明書または卒業見込証明書(※) ● 診療エツクス線技師免許証の写しなど(※) ※該当者のみ |
| 合格発表日時 | 2022(令和4年)3月23日(水曜日)午後2時 |
| 合格発表 | 厚生労働省ホームページ「資格・試験情報」のページに受験地および受験番号を掲載して発表 |
診療放射線技師国家試験の受験資格

診療放射線技師国家試験を受験するには、診療放射線技師養成課程のある大学や専門学校で3年以上学び、診療放射線技師として必要な知識と技能を修習していなければなりません。
【診療放射線技師国家試験 受験資格(令和3年度試験)】
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第20条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(令和4年3月15日(火曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの
(3)58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。)
診療放射線技師国家試験の科目
診療放射線技師国家試験は、以下の14科目から午前100問、午後100問の計200問が出題されます。
| 科目名 | 概要 |
| 基礎医学大要 | 人体の構造や機能、疾病の成り立ち、医療安全管理学 |
| 放射線生物学 (放射線衛生学を含む) |
放射線の細胞に対する作用、人体への影響、生物学的効果、放射線治療 |
| 放射線物理学 | 放射線の基礎、原子と原子核、放射線の発生、物質の相互作用、超音波、核磁気共鳴 |
| 放射化学 | 元素、放射性核種の製造、放射化学分離と純度検定、放射性標化合物、放射性核種の化学的利用 |
| 医用工学 | 電気・電子工学、診療画像機器の基礎 |
| 診療画像機器学 | 診療画像機器 |
| エックス線撮影技術学 | 診療放射線技師の役割と義務、X線撮影技術、画像解剖 |
| 診療画像検査学 | 診療画像検査、画像解剖 |
| 画像工学 | 医用画像(画像評価) |
| 医用画像情報学 | 医用画像(アナログ画像、デジタル画像、画像処理) |
| 放射線計測学 | 放射線量計測の基礎・理論、放射線計測装置、放射線計測技術 |
| 核医学検査技術学 | 放射性医薬品、核医学測定装置、核医学検査技術、核医学データ解析、臨床核医学検査 |
| 放射線治療技術学 | がん治療総論、放射線治療聞き、吸収線量の評価、照射術式、放射線治療 |
| 放射線安全管理学 | 関係法規、放射線防護の基本概念、施設・環境測定と個人の放射線被ばく管理、放射線取扱施設の管理、放射線管理の方法と事故対応、医療におけるリスクマネジメント、医療における健康被害、救急医療(合併症治療を含む) |
【10年間】診療放射線技師国家試験の合格率の推移

診療放射線技師国家試験ではどのくらい得点すれば良いのか、合格基準と過去10年の合格率を見てみましょう。
診療放射線技師の合格基準
厚生労働省による全科目受験者の合格基準は以下のとおりです。
【合格基準(全科目受験者)】
※第74回診療放射線技師国家試験(2022年2月17日実施)
配点1問1点、合計198点満点として、次の基準を満たした者を合格とする。
- 総得点 119点以上/198点
- 0点の試験科目が1科目以下
参考:第74回診療放射線技師国家試験の合格発表について|厚生労働省
200点満点に対して120点以上(得点率6割以上)、かつ0点の科目が1科目以下で合格となります。
0点の科目が2科目あると総得点が合格基準を上回っても不合格となるため、満遍なく得点しなければなりません。
第74回試験では出題ミスがあり、満点が本来の200点から198点、合格基準が120点から119点に変更されています。
しかし、得点率6割以上という基準は変わりませんでした。
診療放射線技師国家試験の過去10年間の合格率
第65回(2011年度)から第74回(2021年度)まで、過去10年の診療放射線技師国家試験の合格者数と合格率は以下のように推移しています。
【診療放射線技師国家試験の合格者数と合格率の推移】
| 受験者(人) | 合格者数(人) | 合格率 | |
| 第65回 | 2,426 | 1,615 | 66.6% |
| 第66回 | 2,907 | 2,224 | 76.5% |
| 第67回 | 2,839 | 2,094 | 73.8% |
| 第68回 | 3,016 | 2,377 | 78.8% |
| 第69回 | 2,939 | 2,511 | 85.4% |
| 第70回 | 2,971 | 2,237 | 75.3% |
| 第71回 | 3,202 | 2,537 | 79.2% |
| 第72回 | 2,914 | 2,397 | 82.3% |
| 第73回 | 2,953 | 2,184 | 74.0% |
| 第74回 | 3,599 | 3,245 | 86.1% |
参考:診療放射線技師国家試験の合格発表について|厚生労働省より作成(第65回〜第74回)
合格率は第65回試験を除いて70%を超えています。
直近の第74回試験の合格率は86.1%、新卒者に限れば93.6%とかなり高い水準です。
高い合格率だからといっても油断は禁物です。しっかりと対策して試験に備えましょう。
診療放射線技師国家試験に受かるには?

診療放射線技師になるには、診療放射線技師養成過程がある大学または専門学校などで学んで受験資格を得て、国家試験に合格する必要があります。
まずは大学と専門学校、それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。
診療放射線技師養成課程がある大学に通う
診療放射線技師になるために大学に通うメリットとデメリットは以下のとおりです。
大学のメリット
大学に通うメリットは以下の3つです。
- 就職先の選択肢が広がる(大卒資格が得られる)
- 初任給が専門学校の卒業生より高い
- 研究や学会発表などを経験できる
大卒資格が得られる点は大学で学ぶ大きなメリットです。大卒が応募条件になっている求人は多く、診療放射線技師はもちろん、それ以外の道に進むことになっても就職先の選択肢が広がります。
専門分野をより深く学び、研究や学会発表といった経験ができたり、教養課程で幅広い知識を学べたりする点も大学の魅力です。
大学のデメリット
大学のデメリットは以下の2つです。
- 入学の難易度が高い
- 私立大学は学費が高い
大学入試は一般的に複数科目の受験が必要であり、入学の難易度は専門学校よりも高めです。私立大学の場合、4年間の学費だけで500万円を超える大学もあり、進学先によっては負担がかなり重くなります。
私立大学に進学する場合は、学費の負担を抑えられる特待生や奨学金の制度がないか調べておくと良いでしょう。
診療放射線技師養成課程がある専門学校に通う
診療放射線技師養成所として都道府県知事の指定を受けた専門学校を卒業して受験資格を得るルートもあります。
大学と比較すると、専門学校には次のようなメリットとデメリットがあります。
専門学校のメリット
専門学校で学ぶメリットは以下の3つです。
- 入学の難易度が低い
- 大学より1年早く受験資格を得られる
- 夜間に通える学校がある
まず、専門学校の受験は1科目と面接や小論文が主流で、科目数の多い大学入試と比べて入学の難易度は低めです。
また一部を除いて専門学校は3年制なので、4年制の大学に比べて1年早く受験資格を得られます。国家試験に1回で合格すれば、最短3年で臨床検査技師になれるのです。
夜間に通える学校があることもメリットです。働きながら診療放射線技師をめざす場合、夜間部であれば仕事との両立がしやすいといえます。
専門学校のデメリット
専門学校のデメリットは以下の2つです。
- 学校に通う期間が短い
- 大学と比べて就職先の選択肢が少ない
専門学校は一部を除いて3年制です。大学より修業期間が1年短いですが、試験内容は変わらないため、限られた時間で必要な知識や技能を身につけなければなりません。
また、応募条件を大卒者に限定した求人も多く、就職先が限られる場合もあります。
通学との併用で勉強効率を高める方法
大学や専門学校は国家試験の合格に向けて、学生を適切にサポートしてくれます。
しかし確実に合格するためには、自ら行う試験対策も欠かせません。
最も効果的な試験対策は、過去問を繰り返し解くことです。
過去問を解くことで、試験問題の全体像や傾向をつかめます。
出題範囲は決まっており、その中から重要なポイントが問われるため、年が変わっても同じような問題が出題されるのです。
そして試験問題の全体像や傾向をつかむためには、少なくとも5年分、できれば10年分こなすのが理想です。
ただ問題を解くだけでなく、内容や出題の意図を理解できるまで繰り返し解きましょう。
臨床放射線技師国家試験は内容を把握して効率よく合格をめざそう
この記事では臨床放射線技師国家試験の概要と効率よく勉強を進める方法を紹介しました。
それぞれの科目の配点や過去問から傾向をつかみ、効率よく勉強を進めて一発合格をめざしましょう。