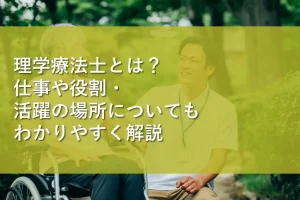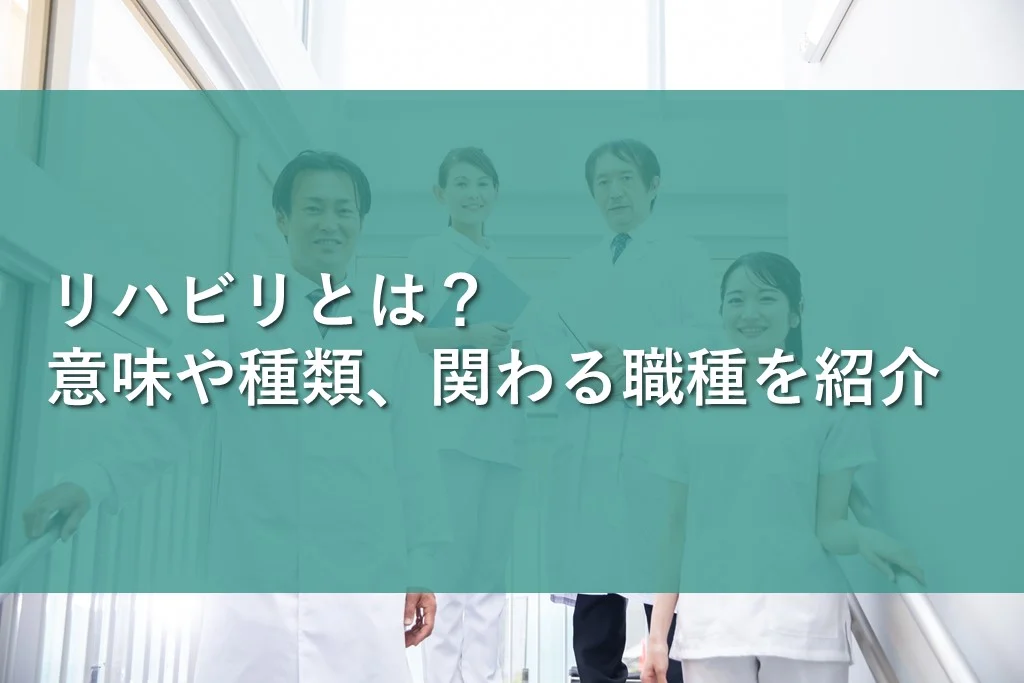
リハビリとは、リハビリテーションの略で、患者さんが自分らしく生きるための機能回復に向けた、さまざまなアプローチの総称です。
本記事ではリハビリの分野5種類と、3種類のアプローチについて解説します。
リハビリに関わる職種も紹介しますので、興味のある方は参考にしてください。
目次
リハビリの意味を語源や歴史から知る

リハビリと聞くと「機能を回復するための訓練」と思われやすいですが、それだけではありません。
リハビリとはリハビリテーションの略で、英語で書くと「Rehabilitation」となります。
これはラテン語の「re(再び)」と「habilis(適した・ふさわしい)」を組み合わせたものです。
古くは、教会から異端とされたなかで亡くなったガリレオ・ガリレイやジャンヌ・ダルクに対する、再審による名誉の回復を指して「リハビリテーション」という言葉が用いられています。
また、世界大戦の時代には、戦争で負傷した兵士が社会復帰をするための治療をリハビリと呼ぶようになりました。
現在におけるリハビリとは、「病気や高齢により日常生活に制限が生じたり、障がいをもったりした場合でも、自分らしい生活を取り戻す」ことを指します。
機能を回復するための訓練はもちろん、日常生活の動作を工夫したり、生活の環境を整えたりと、さまざまなアプローチが含まれます。
リハビリにおける5つの分野
リハビリは、医療現場だけでなくさまざまな場面で行われるものです。
具体的には、以下の5つの分野があります。
- 医学的リハビリテーション
- 社会リハビリテーション
- 職業リハビリテーション
- 教育リハビリテーション
- リハビリテーション工学
それぞれ解説します。
医学的リハビリテーション
医学的リハビリテーションは、主に医療機関で実施されるリハビリです。
医師や看護師に加えて、理学療法士などのリハビリ専門職などがチームとなり、患者さんの心身機能の維持回復に向けた治療を行います。
リハビリの5分野のなかでも、一般的にイメージされやすいものといえるでしょう。
病気や怪我の治療はもちろん、高齢者や子どもの日常生活に関する障がいに対しても、動作の改善や悪化の予防、環境の調整などを図ります。
社会リハビリテーション
社会リハビリテーションとは、障がいがある人が「社会生活力」を高め、社会の資源を活用しながら生活ができるよう支援することです。
社会の資源の例としては、公共交通機関や相談窓口などが挙げられます。
これらの活用方法を身につけることで、障がいがあっても自分らしく暮らせる状態をめざします。
社会リハビリテーションに参加するのは、障がいのある当事者や、専門職、地域の住民などです。
お互いにアイデアを出し合い、制度や環境の調整を行います。
職業リハビリテーション
職業リハビリテーションとは、障がいがあっても働いたり、経済的に自立したりできるようにするための取り組みです。
具体的な取り組み内容としては、以下のようなものがあります。
- 職業の選択や就職に関する指導
- 特定の職業に関するスキルを身につける訓練
- 就職の困りごとに対する相談
- 就職先の紹介
職業リハビリテーションは、公共職業安定所(ハローワーク)や障害者職業センター、障害者職業能力開発校などで実施されます。
教育リハビリテーション
教育リハビリテーションは、障がいがあっても持っている潜在能力を引き出し、自分らしく生活できるようにするための支援です。
児童に対する療育や特別支援教育、社会人に対する生涯学習の支援があります。
現在では身体的、知的な障がいや発達の偏りなどがあっても、特別支援学校や特別支援学級で一人ひとりの特性に合わせた教育を受けることが可能です。
教育リハビリテーションは、障がい者教育や特別支援教育とほとんど同じ意味として使われています。
リハビリテーション工学
リハビリテーション工学とは、義肢装具やコミュニケーション機器、住宅改造、建築や交通機関のバリアフリーなどの工学的なアプローチのことです。
リハビリテーション工学により、障がいがあっても自分らしく活動するための、新たな用具や機器が続々と開発されています。
具体例としては、自分の意思で滑らかに動く電動義手や、不整地でも進める電動車椅子などです。
リハビリには3種類のアプローチがある

リハビリのアプローチは、大きく分けて以下の3種類があります。
- 理学療法
- 作業療法
- 言語聴覚療法
それぞれ見ていきましょう。
理学療法
理学療法は、起きる・立つ・歩くといった、基本動作の維持向上を目的としたアプローチです。
病気や怪我、障がい、高齢化によって基本動作が困難になった人を対象とし、自宅での生活や仕事、スポーツ活動への復帰をめざします。
理学療法の主な方法は、運動療法と物理療法の2種類です。
運動療法には、関節の動きを改善する関節可動域練習や、筋力を高める筋力トレーニング、動作を分析して改善をめざす動作練習などがあります。
物理療法は、温熱や電気、超音波など物理的な刺激を利用して、痛みや動きの改善をめざす治療です。
また理学療法を実施する際には、体の動きや動きを制限している原因を把握するために検査や測定をする「評価」が実施され、評価結果をもとに具体的な支援が決められます。
作業療法
作業療法は、調理や掃除などの家事動作や、趣味、余暇活動など、自分らしく生活するための作業を維持向上するためのアプローチです。
作業に必要な手の動きの維持向上や作業の組み立て、補助的な用具の活用を支援します。
作業療法は、体だけではなく、精神や発達に対する課題へアプローチをする場合もあります。
例えば、調理をするためには、包丁や鍋を手で操作するのはもちろん、料理の工程を理解し、考える作業も必要になるためです。
そのため、社会リハビリテーションや職業リハビリテーション、教育リハビリテーションなどさまざまな分野で作業療法は実践されています。
言語聴覚療法
言語聴覚療法は、話す、聞く、食べるなどの口や耳に対する課題へのアプローチです。
具体的には言語訓練や嚥下(えんげ)訓練、聞こえの評価、対応方法の工夫などを行います。
言語訓練は、脳の障がいや発達の偏りにより会話が難しい場合に、発声の練習や言葉を思い出す練習を行います。
聴覚の評価や補聴器の選定などを含め、コミュニケーションに必要な能力を維持向上させるアプローチが言語聴覚療法の特徴の一つです。
嚥下訓練では、食べ物や唾液が食道ではなく気管から肺に流れてしまう誤嚥(ごえん)を防ぐために、飲み込む力を鍛えます。
口周辺の筋肉の働きや舌の動きなどを評価して、個別のプログラムを実施していきます。
リハビリに関わる職種
リハビリを専門に行う職種は、主に理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)です。
その他にも、医師や看護師といった医療従事者や、介護福祉士や社会福祉士といった介護職も、リハビリと関係の深い職種です。
下表は、リハビリに関わる職種の名前と役割を簡単にまとめたものです。
| 資格名 | 役割 |
| 理学療法士 | 医療や介護、スポーツの現場で理学療法を実践する。 |
| 作業療法士 | 医療や介護の現場で作業療法を実践する。 |
| 言語聴覚士 | 医療や介護の現場で言語聴覚療法を実践する。 |
| 医師 | リハビリの指示を行ったり病気の治療管理をする。 |
| 看護師 | 医師の補助や全身状態の管理を行う。 |
| 視能訓練士 | 視力が低下した方に必要な補助具の選定や使用方法の説明をする。 |
| 音楽療法士 | 音楽を使用したリハビリプログラムを実践する。 |
| 臨床心理士 | メンタル面のリハビリを実践する。 |
| 介護福祉士 | 身の回りの世話をしながらできるだけ自立できるような支援をする。 |
| 社会福祉士 | リハビリ後の生活に必要な調整・連絡業務を実践する。 |
| 管理栄養士 | 栄養管理や食事の工夫に関する助言・実践をする。 |
| 柔道整復師 | 骨折や打撲、脱臼などの怪我をした方に応急処置や治療をする。 |
| あん摩・マッサージ指圧師 | あん摩やマッサージによる治療をする。 |
| 義肢装具士 | 失われた体の一部や機能を補助する義手や義足、装具などを作成する。 |
リハビリは幅広い分野やアプローチがあり関わる職種も多い
リハビリは医療やスポーツの現場だけでなく、就職や教育に関わる現場でも実施されています。
リハビリの専門職は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3つです。
しかし、それ以外にも、医療従事者や介護職など、多くの職種がリハビリに関わります。
リハビリに関わる仕事がしたいと思った人は、どのような分野でどのような職種があるのか、ぜひ確認してみてください。