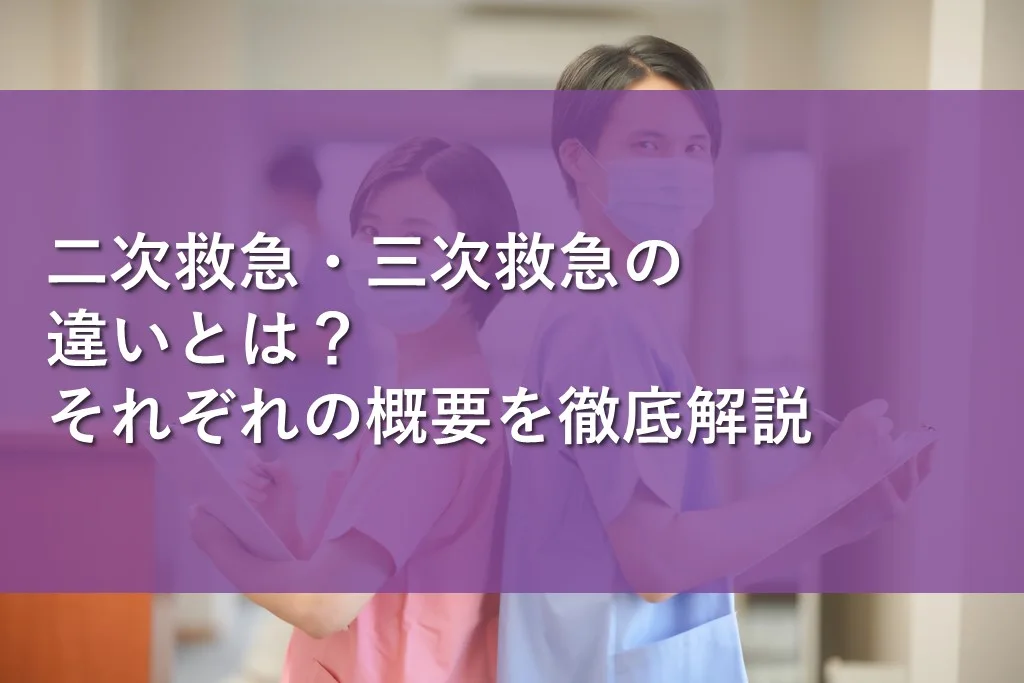
急な病気・怪我に対応するための救急医療体制は、患者さんの重症度や緊急度に応じて一次救急、二次救急、三次救急に分類されています。
なかでも二次救急と三次救急の区別は、受け入れる患者さんの容態が大きく関係しており、必要な医療を必要な場面で提供するためにも適切な判断が欠かせません。
本記事では、受け入れ患者と来院方法、受け入れ医療機関の観点から二次救急と三次救急の違いを分析し、それぞれの役割を解説します。
医師や看護師として働く方は、一次救急や二次救急、三次救急の違いを知り、救急医療についてさらに理解を深める一助として見てください。
目次
二次救急・三次救急など救急医療体制の分類

救急医療体制は、一次救急、二次救急、三次救急の3つに分類可能です。
これらは患者さんの重症度や緊急度に違いがあり、それぞれ異なる機能を担うことで、効率的に医療を提供できるようになっています。
通常の診療時間はもちろんのこと診療時間外においても患者さんを受け入れて、応急処置や治療などの救急医療を提供する機関が救急病院です。
都道府県知事から指定・告示されるため、救急指定病院や救急告示病院とも呼ばれます。
「救急病院等を定める省令」に基づき、救急病院は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 救急医療を提供するに相当する知識・経験を持つ医師が常時診療を行うこと
- エックス線装置や心電計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備が備わっていること
- 救急隊が傷病者を搬送しやすい場所かつ構造設備であること
- 救急医療を必要とする傷病者のための専用病床、あるいは優先的に使用できる病床があること
こうした要件を満たすことで、救急医療を提供できる施設として認められます。
一次救急
一次救急では、軽症患者の外来診療を行います。
主な対象は、自力で来院し、入院の必要性のない患者さんです。
救急指定を受けた地域の医師が在宅当番医となるほか、各都道府県に設置された休日・夜間救急センターなどが対応します。
また、一般急性期病院において、その日のうちに帰宅可能な患者さんに対して医療を提供し、一次救急を担うこともあるでしょう。
救急歯科診療室なども一次救急に含まれます。
二次救急
二次救急では、救急患者の初期診療とともに、重症患者の入院治療・手術を行います。
手術や入院を必要とする状態で搬送された患者さんを、24時間365日体制で受け入れ可能です。
脳卒中、心筋梗塞などの救急患者には、自施設で対応できる範囲での高度専門医療を提供し、複雑な疾患により院内では対応できないなど状況に応じて三次救急指定病院へ紹介します。
二次救急を提供するには、入院治療設備や救急患者のための病床を適切に持ち、救急医療に関する知識・経験豊富な医師が常駐していなければなりません。
一般的に、患者さんが救急車を呼ぶと二次救急指定病院へ搬送されます。
三次救急
三次救急では、二次救急指定病院などでは対応できないより重症な患者さんに、高度な救急医療を提供します。
緊急手術や集中治療が必要になったとき、24時間365日いつでもハイレベルな医療を提供できるのが三次救急のメリットです。
また、三次救急は最後の砦といわれており、基本的には救急搬送されたすべての重症患者さんに対応します。
三次救急を提供できる医療機関には、救命救急センターや高度救命救急センターといった施設が挙げられます。
二次救急と三次救急の違いを分析
軽症患者を受け入れる一次救急に対し、二次救急と三次救急はより患者さんの重症度や緊急性が高くなります。
下表は、二次救急と三次救急の違いを、受け入れる患者さんの容態・来院方法・受け入れ医療機関の3項目で比較したものです。
| 二次救急 | 三次救急 | |
| 受け入れ患者 | 手術や入院を必要とする患者さん | 二次救急では受け入れが難しい重篤者や多発外傷患者、または特殊疾患の患者さん |
| 来院方法 | ・患者さんの自家用車 ・タクシー ・公共交通機関 ・救急車 |
・救急車 ・ドクターヘリ |
| 受け入れ医療機関 | 指定病院や救急告示病院が、共同利用型病院方式または病院群輪番制などで対応 | 高度救命救急センターや救命救急センター |
それぞれの違いをより詳しく見てみましょう。
受け入れ患者
二次救急では、24時間365日体制で、地域の救急患者の初期診療を行うとともに、手術や入院が必要な重症患者を受け入れています。
三次救急も24時間365日体制という点では同じですが、二次救急では受け入れられないような重篤な患者さんや特殊疾患を抱えている患者さんなども受け入れが可能です。
一度、二次救急で受け入れた患者さんであっても、容態の変化などにより対応できない場合は、三次救急の病院に転院することもあります。
来院方法
二次救急では、医療機関に患者さんが来院する手段として、自家用車やタクシー、公共交通機関、救急車などが考えられます。
これに対し三次救急では、二次救急では対応しきれない患者さんが救急車やドクターヘリによって搬送されるのが特徴です。
受け入れ医療機関
上記の表のとおり、二次救急は指定病院や救急告示病院が「共同利用型病院方式」「病院群輪番制」などの方法で対応しています。
共同利用型病院方式とは、地域の病院などが開放している一部施設に医師が足を運び、診察を行う方法です。
病院群輪番制では、二次救急指定を受けたいくつかの病院が当番制を敷き、患者さんを受け入れて診療を行います。
対する三次救急の受け入れ機関は、高度救命救急センターや救命救急センターです。
これらの三次救急指定病院は、教育機関としての機能も持っており、研修医や救急隊員が救急医療を学ぶ場でもあります。
三次救急を担う高度救命救急センターや救命救急センターなどは、重篤救急患者を一定数以上受け入れていることや、救命救急医療に必要な施設や設備を有することなどの複数の条件を満たすことが必要です。
なお、三次救急を担う病院であっても、三次救急の患者さんのみを対象としているわけではありません。
病床やスタッフ数などの院内状況を踏まえて、一次救急や二次救急も可能な限り対応しています。
二次救急と三次救急の違いは受け入れる救急患者の重症度による
二次救急と三次救急の主な違いは、受け入れる救急患者の重症度や来院方法、受け入れる医療機関にあります。
二次救急は、手術・入院が必要な重症患者を24時間365日体制で受け入れていますが、さらに重篤な患者さんや特殊疾患の患者さんについては、三次救急で対応が可能です。
また、二次救急では患者さんの自家用車や公共交通機関による来院のほか、救急車で指定病院・救急告示病院へと搬送されます。
これに対し三次救急では、主に救急車やドクターヘリで搬送された患者さんを、高度救命救急センターや救命救急センターで受け入れるのが特徴です。
このように救急医療体制を一次から三次に分類することで、患者さんの重症度や緊急度に応じた適切な医療の提供を叶えています。







