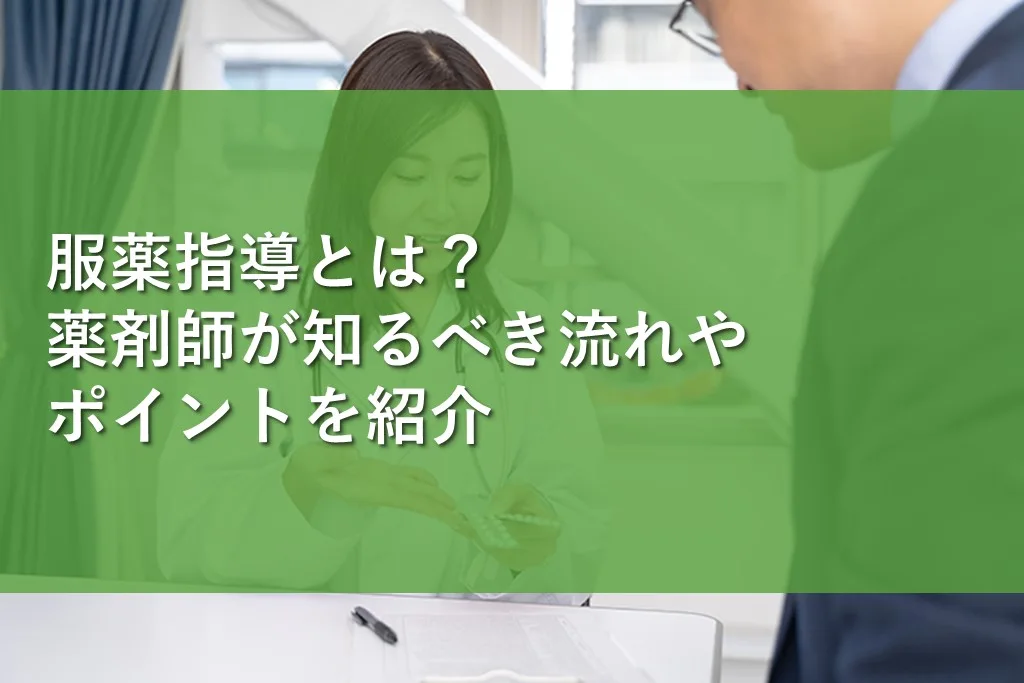
服薬指導とは、薬剤師が患者さんに薬の正しい使用方法や注意点を説明し、適切な服用を促すことです。
医師から処方された薬剤や市販の医薬品を使用した薬物療法で、十分な効能・効果を期待するためには、薬剤師による服薬指導が大切な役割を果たします。
副作用などの健康被害を未然に防ぐ意味でも、欠かせないプロセスといえるでしょう。
本記事では、服薬指導の目的や法的義務について触れたうえで、服薬指導の一連の流れと、効果的な指導を行うためのポイントを解説します。
服薬指導のコツを理解し、患者さんとのコミュニケーションを重視した丁寧な指導を心がけてみてください。
目次
服薬指導とは?
服薬指導とは、薬の適切な服用を促すことを目的として、薬剤師が患者さんに対し、正しい薬の使用方法や注意点などを説明することです。
服薬指導は、患者さんの自己判断による服用の休止や中止、服用量の増減などを防ぎ、安全に期待される治療効果を得るため、重要な役割を果たします。
薬剤師法第25条の2に示されているとおり、服薬指導は薬剤師が背負う法的義務です。
薬剤師法では、服薬指導を「販売・授与した薬剤に関する必要な情報を提供し、薬学の知識に基づいた指導を行うこと」と定義づけています。
さらに、ただ薬の使用方法を説明するだけでなく、患者さんの話を聞いてアドバイスを行うことも薬剤師の仕事の一つです。
患者さんのなかには、薬を使用するうえでの不安を医師には相談しづらいと感じている方もいるかもしれません。
服薬指導では丁寧なコミュニケーションが必要とされるため、患者さんからの質問をしっかりと聞き取り、薬剤師としての知識を活かして回答しましょう。
服薬指導の流れ
服薬指導の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 患者さんへ声かけする
- 症状を聞き取る
- 医薬品について説明する
- 患者さんからの質問を聞く
- クロージングする
患者さんに安心感を与えるため、薬剤師は声かけから、症状の聞き取りや医薬品の説明、質問への回答、クロージングまでを丁寧に進めることが大切です。
患者さんへ声かけする
服薬指導の第一歩は、患者さんへの声かけです。
患者さんの名前を呼び、投薬台へ来てもらうよう誘導しましょう。
調剤薬局によって声かけの方法は異なりますが、患者さんと対面すると、挨拶や「薬剤師の〇〇です」などの自己紹介を行います。
体調が良くない方や身体の不自由な方であれば、患者さんが座っている席まで薬剤師が薬を持っていき、服薬指導を行うなどの対応が必要になるかもしれません。
コミュニケーションを円滑に進めるために、できる限り患者さんのほうに体を向けてアイコンタクトを取りながら、はきはきと話をするよう意識してみてください。
症状を聞き取る
適切な服薬指導を行うためには、患者さんの現在の症状を聞き取ることが大切です。
処方薬や販売しようとしている市販の医薬品が、本当に適切かどうかを評価する必要があります。
調剤薬局の場合、初回来院であれば質問票を用いて次のような内容を聞き取りましょう。
- 治療中の疾患と症状
- アレルギー・既往症の有無
- 服薬中の薬やサプリメント
- 過去に合わなかった薬 など
継続的に通院している患者さんなら、前回から体調に異変はないか、薬を服用していて気になる症状(副作用)はなかったかを確認します。
聞き取った内容をもとに、薬剤師は服薬指導の内容を検討しましょう。
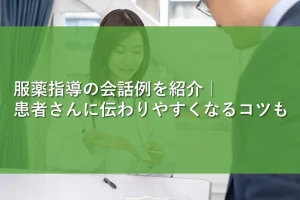
医薬品について説明する
薬剤師は、患者さんが正しく薬を服用できるように、必要な情報をわかりやすく解説しなければなりません。
効能・効果や服用方法、保管の仕方、飲み合わせや副作用の注意点など、提供すべき情報は多岐にわたります。
幾度となく通院している患者さんであっても、新しい薬が増えたときには、そのたびに詳しい情報を提供する必要があります。
聞き取りの段階で、服用中の薬や気になる症状、アレルギーなどが判明した場合には、起こる可能性のある副作用と飲み合わせに関する事項をきちんと理解してもらいましょう。
患者さんからの質問を聞く
ひととおりの説明を終えたら、患者さんから不明点や疑問点がないかを確認します。
患者さんが薬に対する抵抗感や不信感などを抱えたままだと、自己判断での服用中止などにつながりかねません。
アドヒアランスを高めるために、患者さんの不安と疑問を解消しておくことが重要です。
必要に応じて、副作用があらわれたときの対処方法や緊急時の連絡先も伝えておきましょう。
クロージングする
クロージングとは、服薬指導を終えて患者さんを見送ることです。
たとえ調剤薬局が混雑していても、患者さんへの対応をないがしろにしてはいけません。
「お大事になさってください」などの一言を添えて患者さんを見送ります。
適切なクロージングは相手の満足度や信頼に影響を与えるため、いかなる状況でも患者さんに寄り添った対応を心がけてみてください。
服薬指導のポイント
服薬指導を行う際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 患者さんの話をしっかり聞く
- 服薬指導にかける時間の長さを調整する
- 指導箋などを活用する
- 重要なことを中心に伝える
- 患者さんに伝わる言葉で話す
- 患者さんに合わせて説明を工夫する
順に詳しく解説します。
患者さんの話をしっかりと聞く
医薬品に関する説明を一方的にするのではなく、患者さんからの聞き取りを丁寧に行い、不安や疑問があるようなら客観的な視点から回答しましょう。
ときとして薬剤師は、添付文書にはないような情報を提供しなければならないこともあります。
副作用があらわれるときの前兆や、患者さんの意見を尊重したうえでの薬との向き合い方など、薬剤師として何ができるかを考えながら関わらなければなりません。
コミュニケーションを通じて、患者さんの生活習慣やライフスタイルを把握できた結果、より適した服薬指導を行いやすくなります。
服薬指導にかける時間の長さを調整する
薬剤師から患者さんへ説明すべき情報は多くありますが、服薬指導にかける時間は状況に応じて調節する必要があります。
患者さんの様子や調剤薬局の混雑具合を判断し、服薬指導の進め方を調整することも、薬剤師に求められるスキルの一つです。
例えば、薬の服用方法で悩みを抱えている患者さんに対して、淡々と簡潔な服薬指導をしてしまうと、不安感が強まったり不信感につながったりする可能性があります。
患者さんの状況や気持ちに合わせて、説明のボリューム、会話のテンポを変えるようにしましょう。
指導箋などを活用する
口頭での服薬指導だけでは、薬の服用方法や注意点を十分に理解してもらうことが難しいケースもあるため、必要に応じて指導箋などを活用しましょう。
医薬品メーカーが作成している指導箋を使うほか、薬袋にメモ書きを残したり、自作の説明書を活用したりする方法もあります。
指導箋などがあると、口頭での説明にかかる時間を短くできるだけでなく、患者さんが自宅に帰ってから薬の使い方を確認したいときにも、簡単に見返すことが可能です。
重要なことを中心に伝える
服薬指導では、一から十までをすべて説明しようとするのではなく、服用にあたって重要な事項から優先して伝えるようにしてみてください。
患者さんが説明を理解できなければ、服薬指導の目的は果たされません。
伝えるべきポイントを絞って、正確に伝える工夫が必要です。
患者さんから情報を聞き取りたいときにも、抽象的な会話をするより「決まったタイミングで薬を飲めていますか」など、より具体的な回答を得られる質問をしましょう。
患者さんに伝わる言葉で話す
服薬指導を行う際は、専門用語などの難しい用語はできるだけ使わずに、誰にでも伝わるような優しい表現へと置き換えるのがポイントです。
「頓服」なら「痛いときに薬を飲む」など、より簡単な言葉に言い換えることで、患者さんの理解が深まります。
患者さんに合わせて説明を工夫する
例えば子どもの患者さんが初めて薬を服用する場合は、患者さん本人の疑問やご家族の不安も聞き取り、安心して服用してもらえるように説明を工夫しましょう。
高齢の患者さんの場合、普段より大きな声でゆっくり話すと、説明に対する理解を得やすく、信頼にもつながります。
患者さんに伝わる服薬指導を実現するには、口調や話し方を使い分けることが大切です。
気配りのアンテナを張り、患者さんに合わせた服薬指導を心がけしましょう。
服薬指導の流れやポイントを知って参考にしよう
服薬指導とは、薬剤師から患者さんへ薬の正しい使用方法や注意点を解説することを指し、アドヒアランスの向上に寄与する重要な行為です。
薬剤師による服薬指導は法律で義務づけられており、患者さんに合わせたわかりやすい説明が求められます。
医薬品の使用方法をただ説明すれば良いわけではなく、患者さんの症状を聞き取ったり、疑問点に答えたりといった対応も薬剤師の仕事です。
丁寧なコミュニケーションを大切にし、患者さんに安心してもらえる服薬指導を心がけましょう。







