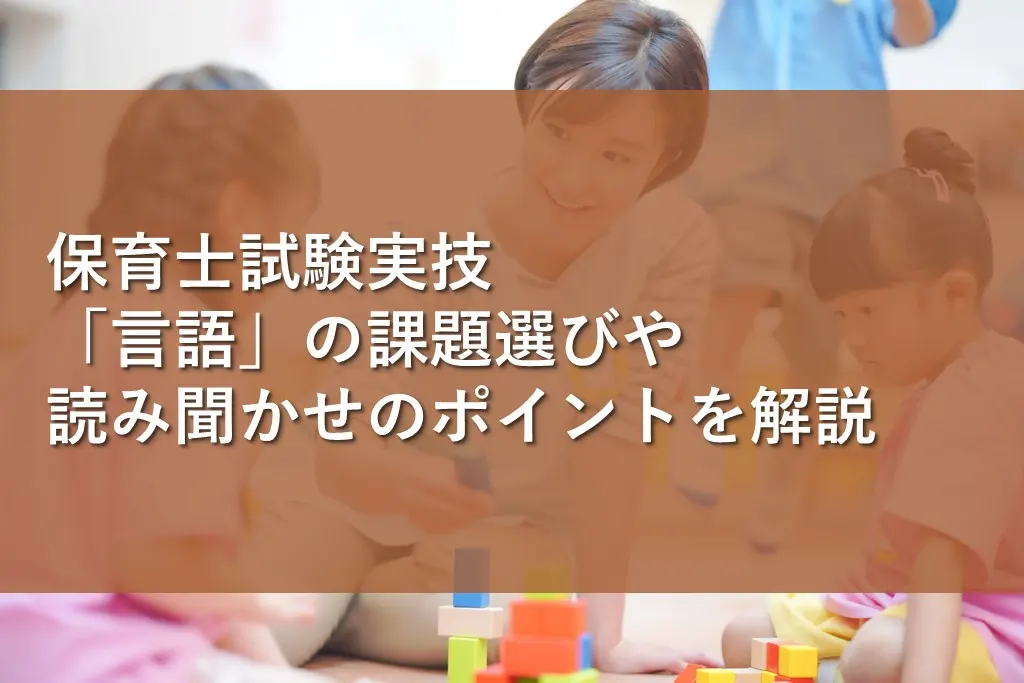
保育士試験の実技科目である「言語」では、指定された物語のなかから一つを選び、3歳児相手を想定して3分お話する必要があります。
課題作品として例年4つの物語が指定されますが、そのうちどの物語を選ぶべきかは悩みどころです。
選んだ物語は、自分なりにシナリオをアレンジしたうえで、台本をはじめとした道具を使わず発表しなければならないことを念頭に置いておきましょう。
本記事では、保育士実技試験における言語の課題選びポイントを詳しく解説します。
シナリオ作成のコツや読み聞かせのポイントも紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
保育士試験実技「言語」の課題の選び方

課題の選び方に正解はありませんが、迷ったときには次の2点を重要視してみましょう。
- 言いやすいセリフ回しの課題を選ぶ
- 自分がハマれるストーリーの課題を選ぶ
試験当日は絵本や台本といった道具は使用できないため、すらすらと話せるかどうか、覚えやすいストーリーかどうかを軸に選ぶのがおすすめです。
登場人物が多い物語だと、キャラクターを区別するのが難しくなる可能性があります。
ただし、キャラクターごとのセリフに特徴がある物語であれば、聞き手に情景を思い浮かべてもらいやすくなるでしょう。
また、お話をする際には「間」も大切になります。
子どもの期待やドキドキを駆り立てるような間を作るため、ストーリーにメリハリのある課題を選ぶというのも一つの方法です。
試験では、子どもたちとのコミュニケーションスキルや適切な関わり方ができているかどうかもチェックされるものと考えましょう。
自分の個性を活かしつつ、これらの能力をアピールするためにも、セリフやストーリーに魅力を感じる課題を選んでみてください。
保育士試験の実技分野に関して、詳しくはこちらの記事でも解説しています。
保育士試験の実技「言語」はシナリオ作成が重要
保育士試験の実技のうち、言語分野ではシナリオ作成が特に重要な意味を持ちます。
課題となる絵本を丸々読み聞かせしようとすると、制限時間の3分以内にはなかなか収まりません。
あらすじを理解したうえで、600~800文字程度のシナリオにまとめましょう。
この際、状況を説明するナレーションばかりだと、子どもが飽きやすくなります。
「ブーブー」「ドンドン」といった擬音語や繰り返しの表現(登場人物のセリフやおまじないの歌など)を適宜取り入れて、お話が単調にならないように工夫してみてください。
シナリオを作成する段階で、身振り手振りを加えるポイントも決めておくと良いでしょう。
保育士試験の実技「言語」の素話・読み聞かせポイント
保育士試験の実技で言語を受験する方に向けて、ここからは素話・読み聞かせのポイントを解説します。
覚えておきたいのは、以下の5点です。
- 適切な声量を意識する
- 抑揚をつける
- 声のトーンを使い分ける
- 身振り手振りを交える
- 話すスピードにも注意する
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
適切な声量を意識する
試験会場に子どもたちがいると想定し、その全員に聞こえるような声量で話すことが大切です。
つねに大きな声で話し続ける必要はなく、物語の展開に合わせて調整するよう意識しましょう。
例えば緊迫したシーンでは声を潜め、クライマックスでは声を大きくするというような工夫ができます。
実際に声を出しながら練習を繰り返し、声量をどのようにコントロールすべきか試行錯誤してみてください。
抑揚をつける
話し方に抑揚をつけると、単調な印象を与えにくくなるほか、聞き手が物語に入り込めます。
シナリオ全体を通してリズム感が良くなるようナレーションやセリフを構成すると、読み聞かせの際に抑揚をつけやすくなるでしょう。
物語のクライマックスシーンには、子どもが喜ぶような擬音語・セリフなどを盛り込みます。
また、子どもの表情を見ながら話すイメージで、シーンの切れ目ごとに一人ひとりと順番に視線を合わせるようにすると、聞き手と話し手に一体感が生まれるでしょう。
声のトーンを使い分ける
聞き手の理解を深めて関心を惹くためにも、声のトーンを上手に使い分けましょう。
ささやき声や悪役の低い声など、声のレパートリーを増やせばそれだけ物語に迫力が出ます。
「今はどの登場人物が話しているのか」「どのようなシーンなのか」など、さまざまな情報を伝えるためにも大切な要素です。
また、喜びや驚き、悲しみなどの感情を表現する際にも声のトーンを工夫しましょう。
例えば驚いたときのセリフを高い声で表現すれば、感情をリアルに伝えられます。
重要なメッセージやポイントを強調したいときにも、声の使い分けが効果的です。
身振り手振りを交える
身振り手振りを交えると、言葉だけでは伝えにくい情報や感情を補完でき、聞き手の理解と関心を高める助けにもなります。
淡々と情報を口頭で話すだけでは物語がリアルに感じられず、子どもが世界観に入り込めません。
キャラクターの動きやシーンの盛り上がりをジェスチャーで表現すれば、物語がより活き活きとしたものになります。
特に、セリフが少なくナレーションが大半となるお話は、身振り手振りを積極的に加えると良いでしょう。
話すスピードにも注意する
上記で触れた「3分間で600~800字程度」をシナリオのボリュームの目安とすると、一般的なスピーチよりも多少ゆっくり話すのが望ましいといえます。
速すぎると子どもたちが理解できず、遅すぎると飽きられてしまうでしょう。
物語の重要な場面やポイントでは声のトーンとともにスピードを落とす、勢いのあるセリフはテンポ良く話すなど、シーンに合わせて調整すると効果的です。
ストップウォッチで3分を計りながら練習し、どのシーンに時間を使うか検討しましょう。
保育士の「言語」実技試験はシナリオ作成と練習が重要
保育士試験の実技分野で言語を受験する場合、事前のシナリオ作成と入念な練習が欠かせません。
絵本の言い回しを必ずしも引用する必要はないため、聞き手として想定すべき子どもたちの興味を惹くようなアレンジを加えて作成しましょう。
完成したシナリオで練習する際には、棒読みにならないよう声のトーンや声量、話すスピードを意識することが大切です。
身振り手振りも効果的に取り入れながら、自分も物語を楽しむ気持ちで話すようにしてみてください。






