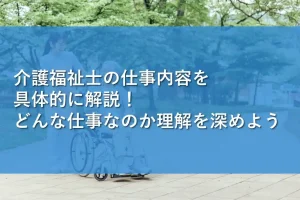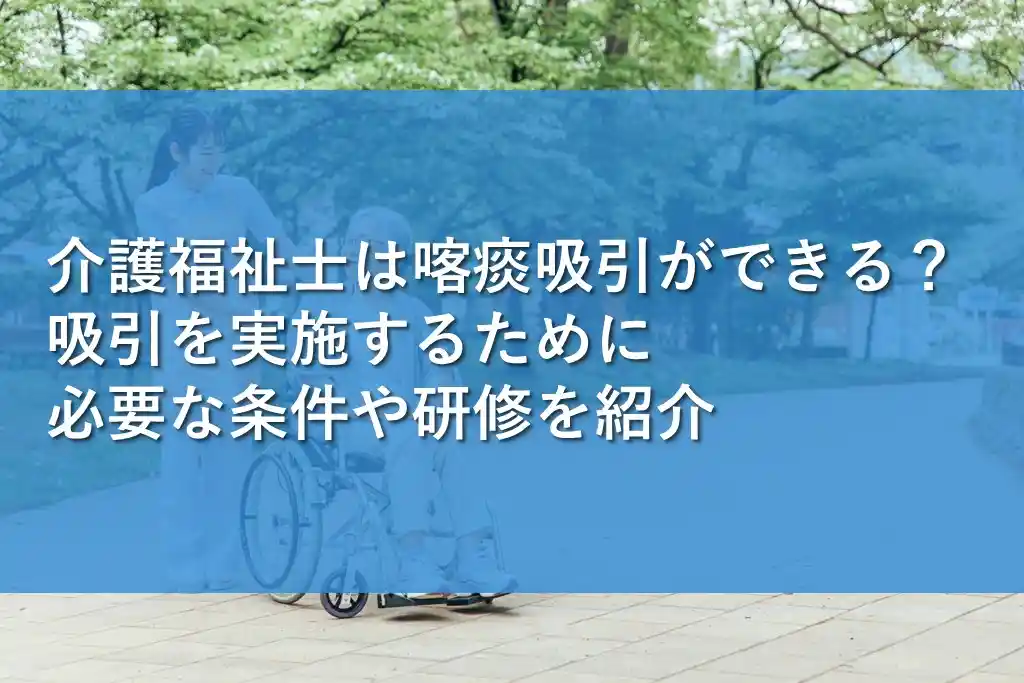
介護施設の利用者のなかには、痰をうまく出すことができないなど日常的なケアとして吸引を必要としている方もいます。
痰をご自身で出すことが難しいと、息苦しさなどの不快感が続きます。
吸引を適切に実施できるようになることで、そのような不快感を軽減させ、利用者の生活を直接的にサポートできます。
今回の記事では、介護福祉士は喀痰吸引ができるのか、また吸引を実施するために必要な条件や研修について紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
介護福祉士は喀痰吸引できる?

喀痰吸引は、もともと医師や看護師のみが実施できる医療ケアであり、介護福祉士は喀痰吸引の実施はできませんでした。
しかし「社会福祉士および介護福祉士法」の改正によって、2015年度から研修の受講など一定の条件を満たすことで、介護福祉士の喀痰吸引ができるように変更されたのです。
喀痰吸引を実施できるようになるために必要な流れについてみていきましょう。
介護福祉士が喀痰吸引を実施するには?
介護福祉士が喀痰吸引を実施するためには、まず必要な研修を受講しなければいけません。
研修の受講が修了したら、認定証や修了証が交付されます。
勤務先や登録を受ける介護福祉士が申請を行い、登録を受けることで、医師の指示のもと喀痰吸引の実施が可能です。
なお、喀痰吸引を実施するために必要な研修は、実務者研修の受講有無によって異なりますので、それぞれのケースで見ていきましょう。
実務者研修を受講済みの介護福祉士の場合
実務者研修を受講済みの介護福祉士の場合は、実地研修の受講が必要です。
実務者研修は介護福祉士国家試験の受験資格にもなっており、基本的には、以下に該当する方は実務者研修受講済みとなります。
- 2016年度以降の介護福祉士国家試験に合格者した方
- 2016年度以降の介護福祉士養成施設を卒業した方
実地研修は、都道府県知事に「登録喀痰吸引等事業者」として登録を受けた事業者(ご自身の勤務先も含む)で行います。
実地研修を行う流れとしては、まず勤務先の利用者に喀痰吸引研修として介護福祉士が喀痰吸引を行うことに対する同意の取得が必要です。
同意を取得できたら、連携している医療機関から指導をする看護師の派遣を要請し、その看護師指導のもと研修を開始していきます。
実地研修の内容
実地研修の具体的な内容としては以下のとおりです。
- 喀痰吸引:
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内部の喀痰吸引 - 経管栄養:
①胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
②経鼻経管栄養
まずはそれぞれの医療ケアに対する指導看護師のお手本を見て、実施時の手順や注意事項について学びます。
器材などを用いて演習を繰り返し、一連の手順を迷いなく実施できるようになってから、看護師確認のもと利用者に対して実践しましょう。
それぞれの手技を2回連続で「手順どおりに実施できる」と看護師が評価をしたら、実務研修は終了です。
実地研修の期間・費用
実地研修の費用は看護師の派遣元によって異なりますが、数万円程度に設定されています。
研修を無料で受けられる都道府県もありますので、勤務先に相談するとともに、都道府県のホームページなども見ておくと良いでしょう。
特に実施期間は決まっていませんが、口腔内の吸引は10回以上、その他の手技については20回以上実施しなければいけません。
ご自身の努力だけではなく、利用者の状況にもよるため、実施できる頻度によって修了するまでにかかる期間は異なってくるでしょう。
実務者研修を受講していない介護福祉士の場合
2015年度以前に介護福祉士の資格を取得した方など実務者研修を受講していない介護福祉士の場合は、喀痰吸引等研修の受講が必要です。
喀痰吸引等研修は、基本研修と実地研修がセットになった研修のことであり、先述した実地研修に加えて、講義や演習などが追加となります。
喀痰吸引等研修には、以下の3種類があります。
- 第1号研修
- 第2号研修
- 第3号研修
第1号研修・第2号研修
第1号研修・第2号研修は、どちらも不特定多数の人を対象に喀痰吸引が実施できるようになる研修です。
研修の内容としては、以下のようになります。
| 基本研修 | 講義 | 全部で50時間の講義があり、保険医療制度をはじめ高齢者や障がい者に対する喀痰吸引・経管栄養法の概要や方法・手順を学びます。 講義終了後には、筆記試験にて知識の確認が行われますので、ご自身で復習する必要があるでしょう。 |
| 演習 | 喀痰吸引・経管栄養法の手順ついてシミュレーターを使用して演習します。 加えて、救急蘇生法の演習も1回のみ行います。 |
|
| 実地研修 | 喀痰吸引・経管栄養法の研修(内容は先述した実地研修と同様です。) | |
なお、第1号研修と第2号研修は、実施できる医療的ケアに違いがあります。
第1号研修は対象となる医療的ケアをすべて実践できるようにしていきますが、第2号研修では気管カニューレ内部の喀痰吸引、経鼻経管栄養は取り扱わず、実施可能になる行為が一部に限定されます。
第3号研修
第3号研修は、第1号研修・第2号研修とは異なり、喀痰吸引を行える相手を特定の利用者に限定しています。
特定の利用者とは、ALSや筋ジストロフィーなどの重度障がい者などが対象です。
第1号・2号研修と比較して、喀痰吸引実施対象者を限定しているため、研修時間が短いことが特徴として挙げられます。
研修の内容は以下のとおりです。
| 基本研修 | 講義 | 全部で9時間の講義があります。 重度障がい者の特徴や喀痰吸引を中心に学びます。 講義終了後には、知識の確認をするため、筆記試験を受けなければいけません。 |
| 演習 | 特定の利用者を想定した演習をシミュレーターを使いながら1時間演習を実施したのち、ひととおり手順が実施できるようになるまで繰り返し練習します。 | |
| 実地研修 | 特定の利用者に絞った実地研修(内容は先述した実地研修と同様です。) | |
喀痰吸引等研修の期間・費用
喀痰吸引等研修の受講費用は選ぶスクールや研修内容によっても変わりますが、約13〜20万円程度です。
第3号研修は、受講内容が第1号研修・第2号研修と比較して少ないため、受講費用が安くなる傾向があります。
また、喀痰吸引等研修の一部となっている実地研修を勤務先で受講できるなど、ご自身で手配すると受講費用を抑えることができるでしょう。
受講スタイルは通学のほかにも、講義の部分はオンラインにて受講可能なスクールもあります。
ご自身のライフスタイルや予算に合ったスクールを選びましょう。
受講期間としては、基本研修のみであれば、約1〜2週間程度で終了する傾向があります。
そのあとの実地研修は、手技の実施回数が決められているため、3ヵ月程度かかることもあるでしょう。
社会福祉振興・試験センターへ登録申請を実施
研修の受講が終了したら、社会福祉振興・試験センターへ必要書類を提出し、喀痰吸引等行為の登録申請を行います。
提出が必要な書類は、実務者研修の受講有無によって変わります。
・登録事項変更届出書
・戸籍抄本の原本
(戸籍の個人事項証明書の原本または「本籍を記載した」住民票の原本でも可能)
・貼付用紙(振替払込受付証明書(お客さま用)の原本を貼り付けたもの)
・登録証の原本
・喀痰吸引等研修を修了した場合:喀痰吸引等研修修了証明書(証書)または認定特定行為業務従事者認定証
介護福祉士の吸引実施には施設の登録も必要
介護福祉士が介護現場で喀痰吸引を実施するためには、ご自身の登録だけではなく、勤務している施設も喀痰吸引等事業者への登録が必要です。
事業者の登録はそれぞれの都道府県で行います。
登録を受けている事業者は、都道府県のホームページなどで公表されていますので、これから吸引ができる介護福祉士になりたいと考えている方は、すでに登録事業者となっている施設を選ぶと良いでしょう。
介護福祉士は医師の指示のもと喀痰吸引を実施
介護福祉士の吸引実施には、医師の指示も必要です。
日常生活において喀痰吸引が必要であり、かつ介護福祉士による喀痰吸引が可能であると医師が判断した場合に吸引を実施できます。
事業者やご自身が喀痰吸引できるよう登録しているからといって、必要に応じてどのような利用者に対しても喀痰吸引が実施できるわけではないので、注意しましょう。
喀痰吸引実施前には、医師の指示を確認することを忘れないでください。
介護福祉士も一定の条件のもと喀痰吸引が可能
介護福祉士も実地研修や喀痰吸引研修を修了し、その旨を申請することによって、介護の現場で喀痰吸引が実施できるようになります。
介護福祉士として、より介護現場のニーズに応えられるような人材になるために、喀痰吸引技術の習得を検討してみてはいかがでしょうか。
また、介護福祉士の仕事内容は、こちらの記事で紹介しています。
通常の業務内容についても知りたい方はこちらの記事も見てみましょう。