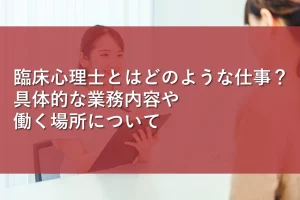臨床心理士やカウンセラーは、どちらも人々の心の健康をサポートする仕事です。
混同されやすい二つの言葉ですが、定義や必要となる資格に違いがあります。
医療分野や教育分野など、どの領域で活躍したいかを考えたうえで、現場で活かせる資格を取得すると良いでしょう。
本記事では、臨床心理士とカウンセラーの違いを定義や必要資格、職場、給料、キャリアアップなどの視点から解説します。
カウンセリング業に興味がある方は、キャリアの方向性を考える際のヒントにしてみてください。
目次
臨床心理士とカウンセラーの定義の違い

臨床心理士とカウンセラーは、どちらも人々の心理的な問題に寄り添う仕事です。
家庭環境や仕事など何らかの影響で悩みを抱えている方に対し、専門的な視点でアプローチしていきます。
では、臨床心理士とカウンセラーは何が異なるのか、定義の違いを確認してみましょう。
臨床心理士の定義
臨床心理士とは、臨床心理学に基づいて人々の心理的問題に寄り添い、問題解決に向けて支援を行う仕事です。
日本臨床心理士資格認定協会の民間資格を取得することで、臨床心理士になれます。
資格は5年ごとに更新が必要となり、生涯にわたった専門性の維持と向上、自己研鑽が求められるでしょう。
また、人々が抱えている問題の解決には、柔軟なアプローチが必要です。
ときには相談者だけではなく、ご家族や関係機関との連携を図りながら支援を行います。
カウンセラーの定義
カウンセラーは、広義では相談者や助言者ですが、主に心理カウンセラーのことを指します。
悩みを抱える相談者に対して、自己解決や自己理解などを行えるようにサポートするのが、カウンセラーの仕事です。
カウンセラー自体は資格がなくても名乗れますが、勤務先の専門性に合わせて資格を取得すると活躍しやすいでしょう。
国家資格の公認心理師や民間資格の臨床心理士、教育カウンセラー、産業カウンセラーなど、幅広いジャンルのカウンセラーがそれぞれの役割を果たしています。
臨床心理士とカウンセラーの資格・なり方の違い
臨床心理士とカウンセラーでは、必要な資格やなり方にも違いがあります。
カウンセラーとして働きたい場合、希望の勤務先に合わせた資格を取得すると就職や転職に役立つでしょう。
臨床心理士の資格・なり方
臨床心理士になるには資格が必須であり、日本臨床心理士資格認定協会による臨床心理士試験に合格する必要があります。
受験資格を得るには、下記のいずれかの条件を満たさなければならないため、試験に向けて計画的に行動するようにしましょう。
- 第一種指定大学院を修了
- 第二種指定大学院を修了後、1年以上の実務経験
- 専門職大学院を修了
臨床心理士試験では、第一次試験と第二次試験が実施され、専門職大学院を修了した方については第一次試験の論文が免除されます。
また、第二種指定大学院を修了した方は、1年以上の心理臨床経験が必要です。
心理臨床経験とは、教育機関や医療機関、心理相談機関などで給料を受け取りながら実務経験を積むことを意味します。
カウンセラーの資格・なり方
カウンセラーのなり方に法的な決まりはなく、カウンセリングスキルがあれば無資格でも名乗ることが可能です。
一方で専門性が高く、無資格者に相談したい人も限られてしまうでしょう。
就職や業務のためにも、民間のカウンセラー資格を取得するのが有効です。
資格の取得方法は、大学で心理学を専攻して臨床心理士や公認心理師を取得するルートのほか、民間スクールを受講するルートもあります。
資格によっては大学での特定単位が必須となりますが、通信教育の受講で取得できる資格もあるため、気になる資格の取得条件を調べてみましょう。
臨床心理士とカウンセラーの職場の違い
心の専門家として幅広い職場で働ける臨床心理士に対し、カウンセラーは勤務先に合わせて幅広い分野から特定の専門資格を取得するのが一般的です。
ここからは、臨床心理士とカウンセラーの職場の違いを解説します。
臨床心理士の職場
臨床心理士は、以下の領域に基づいたさまざまな関係機関が職場となります。
| 臨床心理士が活躍できる領域 | 職場例 |
| 医療・保健分野 | 病院、診療所、保健センター、保健所、老人保健施設 |
| 教育分野 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、公立教育相談機関 |
| 福祉分野 | 児童相談所、療育施設、DV相談支援センター、老人福祉施設 |
| 警察・法務・司法分野 | 家庭裁判所、少年院、刑務所、警察の相談室 |
| 産業・労働分野 | 公共職業安定所、企業の健康相談管理室、労務 |
職場によって相談者の悩みは異なりますが、臨床心理士の高い専門性は幅広い領域で活用できるでしょう。
カウンセラーの職場
カウンセラーは、取得した資格やスキルなど自分の専門性に合わせて職場を選べます。
例えば、次のような資格や職場が選択肢となるでしょう。
| 主な資格 | 職場一例 |
| 産業カウンセラー | 民間企業の相談室 |
| メンタルケア心理士 | 病院や企業などの相談室・相談室の開業 |
産業カウンセラーであれば、企業に勤める従業員の方を対象に支援します。
メンタルケア心理士は病院や企業のほか、開業をして自身が支援したい人と向き合うことも可能です。
臨床心理士とカウンセラーの給料・働き方の違い

勤務先・雇用形態によって、臨床心理士とカウンセラーでは給与や働き方にも違いがあります。
それぞれの給料の目安や働き方の違いを見てみましょう。
臨床心理士の給料・働き方
臨床心理士の働き方は勤務先によって違いがあります。
スクールカウンセラーとして勤務する場合の雇用形態は、ほとんどが非常勤です。
日本公認心理師協会の令和2年の調査によると、国家資格の公認心理師でも常勤が55.3%、その他は非常勤が占めているため、臨床心理士の正規雇用もあまり多くない傾向にあります。
スクールカウンセラーの月収は、24.8万円です。
年収は勤続年数が少ない20〜24歳で360.01万円、平均額が最も高い40〜44歳で691.52万円と差があります。
医療機関に勤めるカウンセラーの場合、全国の平均月収は23.3万円、平均年収が最も高いのは55〜59歳で540.42万円です。
カウンセラーの給料・働き方
臨床心理士以外の民間資格でカウンセラーとして働く場合、産業カウンセラーやシニア産業カウンセラーなどの働き方を選べます。
日本産業カウンセラー協会によると、2009年のカウンセラーの雇用形態としては契約社員が43.8%と多く、次いで正社員が21.9%、非常勤20.1%、パート・アルバイトが7.3%です。
カウンセラーの年収は、200万〜300万円未満が24%、300万〜400万円未満が21.8%、100万〜200万円未満が16.9%を占めています。
400万円以上を稼いでいる割合は、全体の24%という結果です。
臨床心理士とカウンセラーのキャリアアップの違い
臨床心理士とカウンセラーが働ける場所は多岐にわたりますが、正社員など雇用面での安定や給料アップをめざすには、キャリアアップが必要となるでしょう。
ここからは、臨床心理士とカウンセラーのキャリアアップの違いを解説します。
臨床心理士のキャリアアップ
臨床心理士のキャリアアップ方法には、次のようなものが考えられます。
- 国家資格である公認心理師を取得する
- 関連する資格を取得して専門性を高める
- より待遇が良い企業や病院へ転職する
- 相談室を開業する
臨床心理士としてさらに専門性を高めたいなら、公認心理師や民間資格の取得を検討してみてください。
資格の取得により資格手当を受け取れる可能性があるほか、転職で有利になる場合もあります。
また、正社員の求人や福利厚生が魅力的な病院・企業に転職することで、現状より高待遇で働けるでしょう。
さらに収入を上げたい場合は、独立して相談室を開業する方法もあります。
カウンセラーのキャリアアップ
カウンセラーのキャリアアップには、以下のような方法があります。
- 関連する資格を取得して専門性を高める
- 評判を上げてカウンセリングの依頼を受けられるようにする
- 相談室を開業する
臨床心理士や国家資格である公認心理師の受験要件を満たしている方は、資格取得によってさらに広い領域で働けるようになります。
民間資格でも、勤務先に合わせた資格を取得すると専門性を高められ、資格手当を受けられる可能性があるでしょう。
また、より良いカウンセラーとして経験を積み、評判を上げて人脈をもとに依頼を受けたり、独立して相談室を開業したりする方法もあります。
臨床心理士もカウンセラーの一種!自分の希望に合わせて資格を選ぼう
臨床心理士はカウンセラー業の一種であり、相談者に寄り添って心の悩みを解決へとサポートするのが仕事です。
臨床心理士になるには民間資格が必要ですが、自分の適性や支援対象に合わせて他の資格も取得し、キャリアアップをめざすことも可能です。
医療・福祉分野や教育分野はもちろんのこと、労働・産業分野など幅広い場所で心の専門家の役割は求められています。
自分自身が貢献したい領域をふまえ、勤務先で求められる資格を取得することで、専門性を活かして長く活躍できるでしょう。