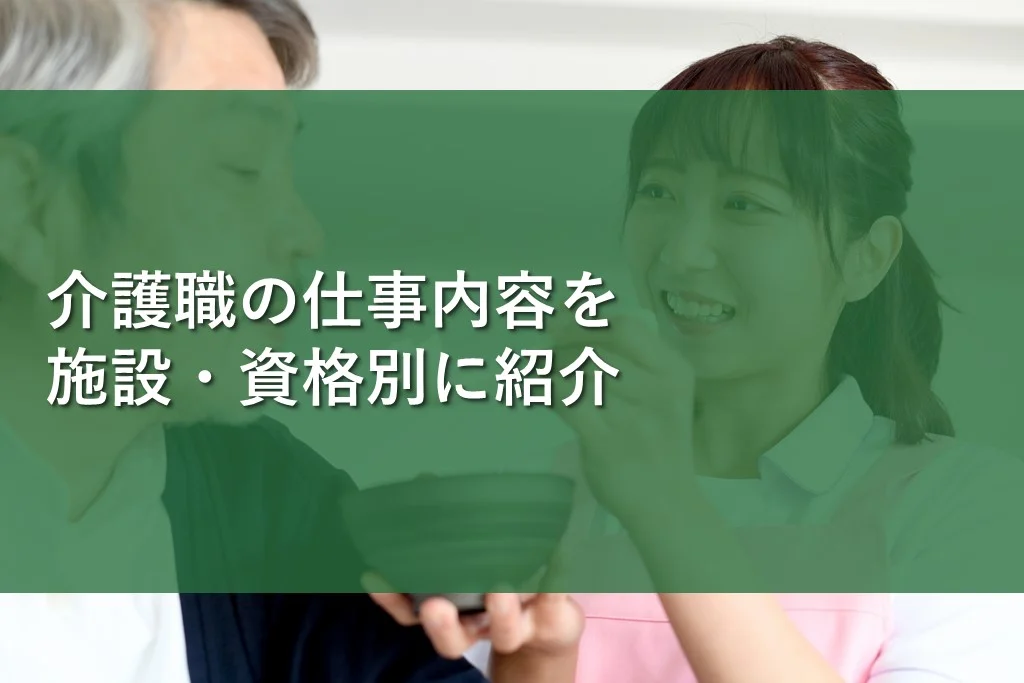
介護職の仕事内容は主に身体介護や生活援助、事務作業ですが、細かな部分は施設・資格により異なります。
仕事内容を把握せずに就職してしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔するかもしれません。
施設・資格ごとの仕事内容を理解し、就職・転職活動に臨みましょう。
この記事では介護職の仕事内容と8施設4資格の仕事内容を紹介しています。
最後まで読んでいただければ、入社後に任される仕事が具体的にイメージできるでしょう。
介護職に興味がある方や転職を考えている方は参考にしてください。
目次
介護職の仕事内容は?

介護職の仕事内容は以下の4つに分かれます。
- 身体介護
- 生活援助
- レクリエーション活動の企画・準備・実施
- 介護記録の作成
身体介護
身体介護は利用者の身体に直接触れる介護です。
具体例を紹介します。
- 床ずれ予防の体位変換や姿勢交換
- 歩行介助
- 車いすへの移乗
- 清拭
- 衣類の着脱
- 食事介助
- 入浴介助
- 整容介助
- 服薬介助
上記以外にも利用者の要支援・要介護状態により、さまざまな支援が必要です。
日常生活や社会生活を送るうえで身体介助が必要なケースもありますし、日常生活動作能力の向上のために行う場合もあります。
身体介護は、介護施設と訪問介護のどちらでも必要なため、介護職にとって基本的な介護スキルといえます。
ただ単にできない動作を手伝うだけでなく、利用者さんのできる能力を引き出したり、お互いの体に負担がかからない工夫をしたりするスキルが求められます。
車いすへの移乗や入浴介助時には、利用者さんの身体を持ち上げたり支えたりするため、肉体への負担が大きいです。
そのため、腰を痛める方も多く体力的にきついと感じるケースもあります。
身体介護には腰を痛めない方法があり、正しく実践できていれば腰をケアしつつ移乗や入浴介助ができます。
介護職で働く際は、先輩から教えてもらったりスクールで習ったりして、自分自身を守りつつ働きましょう。
生活援助
生活援助は利用者さんの家事を代行する介護サービスです。
生活援助の内容には以下のようなものがあります。
- ゴミ出し
- 部屋やトイレの掃除
- 洗濯
- ベッドメイク
- 料理、食器の後片付け
- 買い物代行
- 薬の受け取り
生活援助でサポートできる内容は、日常生活上必要な項目で一般的な家事のみです。
そのため、生活援助でできない家事もあります。
- 庭の草むしり
- 特別な行事の飾り付けや料理
- 利用者さん以外の食事を作る
- 利用者さん以外の部屋の掃除
- ペットの散歩
- タバコや酒の買い出し
- 一般的な掃除に含まれない行為(エアコン掃除や大掃除など)
上記は生活援助でできない家事の一例です。
利用者さんが困っているから助けてあげたいと思っても、安易に引き受けてはいけません。
トラブルの原因になるため、利用者さんにできない理由を説明して断るのが正しい行いです。
介護職員として生活援助を任された際は、できること・できないことをしっかり把握しておきましょう。
レクリエーション活動の企画・準備・実施
レクリエーションは介護施設やデイサービスで、利用者の身体能力向上、脳の活性化、コミュニケーションの促進を目的に実施されます。
身体能力の向上や脳の活性化、他人とのコミュニケーションが活発になることで、生きがいの発見や孤独感を減少することも目的です。
レクリエーションの具体例を紹介します。
| 分類 | ゲーム名 |
|---|---|
| 身体能力向上 | 体操 玉入れ 風船バレー ボウリング |
| 脳の活性化 | 折り紙 あやとり オセロ 計算ゲーム 間違い探し 後出しジャンケン |
| コミュニケーションの促進 | 伝言ゲーム カラオケ・合唱 |
介護施設やデイサービスで働く際は、レクリエーションの企画、準備、実施を任されるでしょう。
介護記録の作成
介護記録とは、介護サービスを利用者さんに提供した事実を記録したものです。
決まった書式はなく、事業所ごとに異なります。
記録の一例は以下のような内容です。
- 日時・場所
- サービス提供内容
- 利用者さんの状態、表情、会話内容
- 利用者さんの署名
食事介助やトイレ誘導、入浴介助などの介護サービスで確認できた内容を、客観的に記載します。
介護記録の作成は介護保険法にもとづく省令で義務付けられており、介護サービスを提供する介護事業者で働く場合は必須です。
介護記録は利用者さんを介護する際に職員間で共有され、より良い介護サービスの提供や、事故防止のために活用されます。
介護職員は身体を動かす仕事以外に事務仕事もこなさなければいけません。
介護職の仕事内容を施設別に紹介

介護職の仕事内容を施設別に紹介します。
紹介する施設は以下のとおりです。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- デイサービス
- 訪問介護
- 病院
順番に説明します。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームとは、常時介護が必要で自宅での生活が困難な高齢者に対して、生活の場を提供する施設です。
入所するためには要介護3以上が対象となるため、比較的介護度が高い利用者さんが多い特徴があります。
以下の内容が特別養護老人ホームで働く介護職員の主な仕事です。
- 入浴・排泄介助
- 食事介助
- 着替えや移動、移乗の介助
- 利用者さんの健康管理
- 利用者さんの身体機能の維持・回復
- ご家族への近況報告
- 掃除や洗濯
特別養護老人ホームで働くと介護スキルが身につき、一人の利用者さんに対し長期的なケアができます。
しかし、身体介助の業務が多く体力的な負担がかかることがデメリットです。
また、特別養護老人ホームでは看取りを受け入れている施設もあり、看取り経験を積めます。
介護スキルを磨きたい方や看取り経験をしたい方におすすめです。
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、要介護1以上の高齢者が在宅復帰をめざして生活する施設です。
仕事としては、「在宅復帰」を念頭に置き、利用者の介護を行います。
介護職員の仕事内容は身体介助が主ですが、他の介護施設と違う点は在宅復帰を目的に業務にあたることです。
介護老人保健施設は主に医療法人が運営母体となっており、病院と在宅の中間施設として活用されます。
医師や看護師、理学療法士などの医療スタッフの配置も充実しており、薬剤師や管理栄養士、歯科衛生士を含めて、さまざまな専門職種との連携が求められます。
介護老人保健施設で働くメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・医療ケアやリハビリに関する知識や経験が得られる ・「在宅復帰」という目標に向かってサポートできる ・利用者さんの介護度が低いので肉体的な負担は少ない ・医療スタッフが充実しており、多職種との連携が可能 |
・レクリエーションなどのイベントが少ない ・利用者さん一人と接する時間が限られる ・医療ケアがメインになりやすい |
介護だけでなく医療ケアやリハビリ、多職種連携も学びたい方や、在宅ケアを目的に支援したい方におすすめです。
グループホーム
グループホームは認知症の方が利用できる入所施設です。
施設の定員は1ユニット5~9人で最大3ユニットまでと決められているため、利用者さん一人に対してしっかりケアできます。
入居条件は要支援2以上なので、特別養護老人ホームに比べると身体介助の業務割合が少なく、肉体的負担が軽い傾向にあります。
しかし近年はグループホームでも、要介護3以上の割合が半数以上と介護が必要な利用者さんが増えており、ある程度の身体介護は必要です。
グループホームで働く際に大変なこととして挙げられるのは以下の点です。
- 理解するまで利用者さんの認知症症状への対応が大変
- 少人数特有の人間関係に悩まされる
- 夜勤で働く可能性があり、体調を崩しやすい
グループホームは認知症に特化した施設なので、認知症への理解を深めた状態で働き始めるのが良いでしょう。
一方、グループホームで働くメリットもあります。
- 認知症ケアの知識が身につく
- 身体的介護の負担が少ない
- アットホームな雰囲気のなかで働ける
認知症の利用者さんを対象に介護したい方や、少人数の職場で働きたい方におすすめです。
有料老人ホーム
有料老人ホームは以下の3種類に分けられ、入居条件が異なります。
施設別の入居条件は以下のとおりです。
| 施設名 | 入居条件 |
|---|---|
| 介護付き有料老人ホーム | 年齢:65歳以上 要介護度:自立~要介護5(施設により異なる) 医療ケア:入居希望の施設で対応できるレベルであること 認知症でも受け入れ可能だが暴力行為や自傷行為がある場合は不可 |
| 住宅型有料老人ホーム | 年齢:60歳もしくは65歳以上(ただし、場合によっては60歳以下でも可) 要介護度:自立~要介護5 |
| 健康型有料老人ホーム | 年齢:60歳以上 要介護度:原則自立 |
介護付き有料老人ホームで働く介護職員の仕事内容は、身体介助がメインで生活援助やレクリエーションも行います。
住宅型有料老人ホームは生活援助がメインの職場です。
住宅型有料老人ホームは施設内での介護サービスの提供を行っていないため、介護サービスが必要な利用者さんは外部サービスを依頼します。
そのため、施設で働く介護職員は、食事の配膳や片付け、環境整備が主な仕事内容です。
健康型有料老人ホームでは、基本的に自立の方が入居しているので、身体介助はほとんどありません。
種類ごとの仕事内容を理解し就職先を選びましょう。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は、以下の2つに分けられます。
- 一般的なサービス付き高齢者向け住宅
- サービス付き高齢者向け住宅(特定施設)
一般的なサービス付き高齢者向け住宅は、状況把握サービスと生活相談サービスを提供する賃貸住宅です。
特定施設は、都道府県の指定を受けた介護サービスが提供できる施設です。
特定施設と認められたサービス付き高齢者向け住宅では、以下の介護サービスを提供しています。
- 食事介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 起床・就寝介助
サービス付き高齢者住宅でも、施設の特徴によって介護職としての役割が変わるため、就職先の特徴は事前に調べておきましょう。
デイサービス
デイサービスは、自宅や入居施設で生活している要介護状態の65歳以上を対象に、食事や入浴などの介護サービスを提供します。
できる限り自宅で生活できるよう、介護サービス以外にも機能訓練やレクリエーションも実施しています。
デイサービスで働く職員の1日の流れは以下のとおりです。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:00~9:30 | 利用者の送迎業務 |
| 9:45~10:00 | 健康チェック |
| 10:00~10:15 | 朝会 |
| 10:15~12:00 | レクリエーション、機能訓練 |
| 12:00~14:00 | 昼食・口腔ケア、職員は交代で休憩 |
| 14:00~15:30 | レクリエーション |
| 15:30~16:00 | おやつ・お茶出し |
| 16:00~ | 帰宅準備 |
| 16:30~17:00 | 送迎 |
| 17:00~ | 業務報告 帰宅 |
デイサービスは夜勤がないため、日勤だけの仕事を希望している方におすすめです。
ただし、その分手当が少なく夜勤ありの介護施設に比べ給料が低い傾向にあります。
訪問介護
訪問介護は自宅で生活している要支援1以上の方です。
訪問介護施設で働く介護職員は、自立支援・要介護度の悪化防止を目的に身体介護や生活援助、通院介助を行います。
訪問介護の仕事に就くには以下の資格が必要です。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 介護福祉士
訪問介護は自分のライフスタイルに合わせた仕事ができるため、パート・アルバイトで働く場合は1日に2件または3件と仕事量の調整ができます。
現在無資格で、訪問介護をしたいと考えている方には「介護職員初任者研修」がおすすめです。
介護職員初任者研修は資格取得までの研修時間が他の資格より短く、研修内容も基礎的な内容となっています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。

病院
病院で働く介護職員の仕事内容は主に以下の3つです。
- 患者さんの身体介助
- 病院の環境整備
- 看護師のサポート
病院での身体介助は、手術後や麻痺、感染症、点滴など対象者の状態が介護施設とは異なります。
そのため、個々の状態にあわせた介入方法を考える必要があります。
病室の清掃やベッドシーツの交換作業も介護職員の仕事です。
看護師のサポートは主に以下の業務を行います。
- 医療器具の準備・洗浄
- 配膳業務
- 患者さんの診察の送迎
- 業務で使用する物品の発注・補充
病院で働く介護職員は医療の知識が得られる反面、介護職員としてキャリアアップしにくい傾向にあります。
医療に興味のある方におすすめの職場です。
介護職の仕事内容を資格別に紹介
介護職の仕事内容を資格別に紹介します。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 介護福祉士
- 介護支援専門員
順番に説明します。
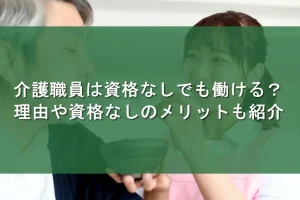
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修を取得すると以下の仕事ができます。
- 訪問介護業務
- 単独での身体介助
- 介護タクシーのドライバー
無資格の介護職員は単独での身体介助ができませんが、介護職員初任者研修を取得すれば可能です。
そのため、訪問介護や介護タクシーのドライバーができます。
介護タクシーのドライバーは、屋外で利用者さんの身体介助をしながら乗車させる場面があるため、単独での身体介助ができるスタッフでなければ務まりません。
介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修の資格を取得すると以下の仕事ができます。
- サービス提供責任者を任される
- 痰吸引・経管栄養ができる
サービス提供責任者は「サ責」とも呼ばれ、ケアマネジャーと訪問介護職員との間の調整役です。
ケアプランどおりの介護サービスを提供するには、どうしたら良いのかを考え指示を出します。
介護福祉士実務者研修を修了すれば、痰吸引と経管栄養を実施できるため、医療ケアが必要な介護現場で力を発揮できます。
また、介護福祉士実務者研修の資格を取得すれば、介護福祉士への挑戦も可能なので、さらなるキャリアアップも可能です。
介護福祉士
介護福祉士の資格を取得すると以下の仕事ができます。
- 相談・助言
- 社会活動支援
- チームマネジメント
介護業界唯一の国家資格である介護福祉士は、現場の仕事以外にも任される仕事が3つあります。
1つ目は、相談・助言の仕事です。
利用者さんやご家族、関係者に対して介護保険や要介護認定に関する相談や、介護サービス・福祉用具の選定に悩む方への助言を行います。
2つ目は社会活動支援です。
介護サービス利用者が孤立しないために、就労支援や地域活動の情報提供を行い、安定した生活ができるようサポートします。
3つ目はチームマネジメントです。
介護の現場で働く職員のリーダーとして、スタッフの指導や育成、業務管理をしてより良い介護サービスの提供を目標に、介護の質の向上をめざします。
介護支援専門員
介護専門員(以下ケアマネジャー)の主な仕事内容はケアプランの作成と給付管理です。
ケアプランは、利用者さんの介護必要度の悪化防止、自立生活を促進させるためにどの介護サービスを利用すれば良いのかを示したものです。
介護サービスを提供した介護事業者は、介護給付費を請求しなければいけません。
給付管理は、利用者さんが使用した介護サービス費用を国民健康保険団体連合会へ請求する業務です。
主にケアマネジャーが担当しますが、介護事務員が対応するケースもあります。
ケアマネジャーの資格取得には介護や医療に関する資格を取得したのち、5年以上の実務経験が必要です。
介護職として従事するには介護福祉士の資格が必要になり、一般的な介護業務とは仕事内容も異なります。
介護職のキャリアアップの一つとして理解しましょう。
介護職の仕事内容は施設と保有資格により異なる
介護職の仕事内容は主に以下の4つです。
- 身体介護
- 生活援助
- レクリエーション活動の企画・準備・実施
- 介護記録の作成
しかし、働く施設や保有資格により仕事内容は変わります。
介護職員として、利用者と積極的に関わっていきたいかどうかで、施設選びやめざす資格が異なります。
今回紹介した内容を参考に、自分の進むべき進路を決めましょう。







