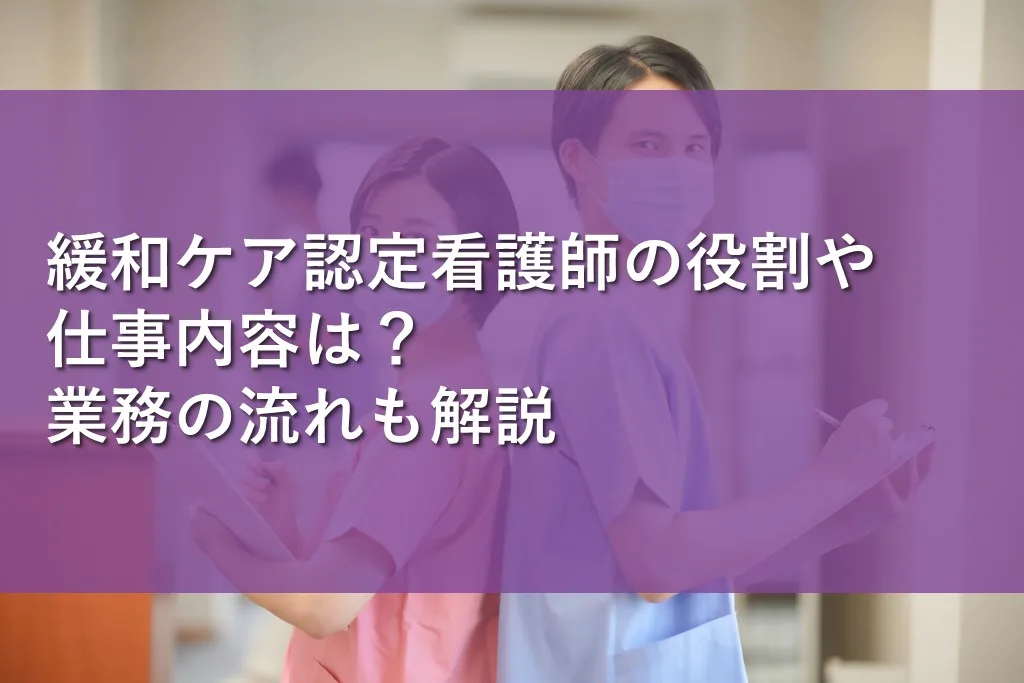
緩和ケア認定看護師は、認定看護師の一つで、主にがん患者さんの痛みや苦痛を和らげる緩和ケアを専門とする看護師です。
本記事では、緩和ケア認定看護師の役割や仕事内容、資格取得の方法やメリットなどを紹介していきます。
緩和ケア認定看護師についての、よくある質問にも回答しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
緩和ケア認定看護師とは?

認定看護師とは、看護師のなかでも、特定の分野で高度な技術と知識を持つことを証明する資格です。
そのなかの一つである緩和ケア認定看護師は、がん患者さんとそのご家族が抱える体や心のつらさ(全人的苦痛:トータルペイン)を和らげる緩和ケアのスペシャリストです。
がん患者さんは、がんと診断されたときから体に見られる変化はもちろん、精神的な苦痛にも悩まされます。
それを支えるご家族も、多くの悩みや不安を抱えているでしょう。
緩和ケア認定看護師は、上記のような苦痛を少しでも和らげ、一人ひとりのがん患者さんとご家族が自分らしい生活を継続できる状態をめざします。
緩和ケア認定看護師の役割
認定看護師の役割は、大きく分けて以下の3つです。
- 実践
- 指導
- 相談
それぞれ見ていきましょう。
実践
緩和ケア認定看護師の1つ目の役割は、緩和ケアに関する専門的な知識や技術を駆使して、がん患者さんに対する看護を実践することです。
また、がん患者さんのご家族に対しても、不安や悩みに対するケアを行います。
医師や薬剤師といった、ほかの医療職と連携することも、がん患者さんやご家族により良いケアを提供するために重要です。
指導
緩和ケア認定看護師の2つ目の役割は、培った知識と技術を活かし、他の看護師への指導を行うことです。
具体的には病院内の研修や教育プログラム、カンファレンスのなかで緩和ケアに関する勉強会を行い、看護師に対して教育を行います。
相談
緩和ケア認定看護師の3つ目の役割は、他の看護師や医療職の相談に乗り、緩和ケアに関わる適切な助言をすることです。
具体的には、麻薬の副作用や、患者さんやご家族との接し方などについて相談を受ける機会が多いでしょう。
緩和ケア認定看護師の仕事内容
ここでは、緩和ケア認定看護師の具体的な仕事内容を紹介します。
一日の業務の流れについても表で見ていきましょう。
緩和ケア認定看護師の主な活動
緩和ケア認定看護師の主な活動内容には、以下のようなものがあります。
- 患者さんやご家族に対する直接的なケア
- 病棟内や外来へのラウンド
- 看護師や医療スタッフからの相談対応
- カンファレンスへの参加
- 院内外での講師活動
このように、入院中の患者さんから外来まで、幅広い患者さんの対応を行います。
さらに、他のスタッフからの相談対応や、カンファレンスの参加、講師活動などを通して、病院全体の緩和ケアの底上げも求められるでしょう。
緩和ケア病棟における認定看護師の業務の流れ
下表は、緩和ケア病棟で働く緩和ケア認定看護師の1日のスケジュール例です。
| 時間 | 業務内容 |
|---|---|
| 8:30〜9:00 | 勤務開始、申し送り(患者さんの情報共有) |
| 9:00〜12:00 | 担当患者さんへの看護ケア |
| 12:00〜13:00 | 昼食介助 |
| 13:00〜14:00 | 昼休憩 |
| 14:00〜15:00 | 緩和ケアカンファレンス |
| 15:00〜16:30 | 担当患者さんへの看護ケア・相談業務 |
| 16:30〜17:30 | 夜勤者への申し送り、業務終了 |
大まかな業務の流れは通常の看護師とそれほど変わりありません。
しかし、どの場面においても、緩和ケア認定看護師としての専門性を発揮して、患者さんやご家族のトータルペインを和らげる業務を実践します。
緩和ケア認定看護師になるためには?

緩和ケア認定看護師になるためには、認定看護師を養成する教育機関で一定期間学ぶ必要があります。
ここでは資格取得の方法や取得の流れ、必要なカリキュラムを紹介します。
緩和ケア認定看護師の資格取得の流れ
緩和ケア認定看護師の資格取得までの流れは、以下のとおりです。
| 緩和ケア認定看護師の資格取得までの流れ |
|---|
| 看護師免許取得 ↓ 看護師としての5年以上の実務経験を得る(そのうち3年間は緩和ケア分野の実務経験) ↓ 緩和ケア認定看護師の教育機関に入学してカリキュラムを修了する ↓ 認定審査に合格する ↓ 認定看護師名簿に登録する |
このように、緩和ケア認定看護師をめざすためには、看護師として5年以上の実務経験が必要です。
さらに、そのうち3年は、緩和ケア分野の実務経験である必要があります。
また、特定の教育機関でしか必要なカリキュラムを受講できません。
具体的な教育機関については、のちほど紹介します。
緩和ケア認定看護師取得に必要なカリキュラム
緩和ケア認定看護師を取得するために、受講が必要なカリキュラムは以下のとおりです。
- 認定看護師に共通する科目
- 緩和ケア認定看護師の専門科目
- 臨地実習(現場での実習や研修会の立案など)
- 統合演習(事例発表)
共通科目では、高度な看護の実践に加え、指導や相談といった認定看護師に共通して必要な知識や技術を習得をします。
専門科目では緩和ケア認定看護師として、より専門的な知識や技術を学びます。
臨地実習や統合演習は、得られた知識や技術を実際の現場で実践しながら、理解を深める科目です。
2020年度から実施されている課程では、1年間に800時間程度の受講が必要になります。
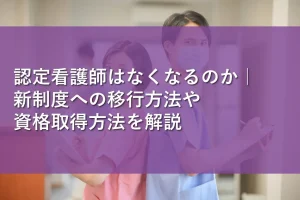
緩和ケア認定看護師になるメリット
ここでは、緩和ケア認定看護師の資格を取得することで得られるメリットを紹介します。
ここで紹介するメリットが、資格取得にかかる時間や費用に見合うかどうかを検討したうえで、めざすかどうかを決めると良いでしょう。
緩和ケアに関する高度な知識や技術が取得できる
緩和ケア認定看護師の資格を取得する課程や資格取得後の実践を通して、緩和ケアに関して専門的で高度な知識や技術が取得できます。
ほかの看護師を指導したり、さまざまな職種の相談に乗ったりすることでも、知識や技術はより深まるでしょう。
待遇面の優遇や昇進が期待できる
緩和ケア認定看護師の資格を取得すると、待遇面での優遇や昇進が期待できます。
緩和ケア認定看護師が所属している事実は、医療機関にとってアピール材料になり、がん患者さんにとってはその施設を選ぶ動機の一つになり得るでしょう。
施設にとって価値の高い存在であるぶん、高待遇で迎えられる可能性も高くなります。
また、緩和ケア認定看護師を病棟に配置することで算定できる加算があることも、待遇改善が期待できる要素です。
外部に講師として派遣されたり、ほかのスタッフを指導する立場になったりする機会が増えれば、キャリアアップにもつながるでしょう。
夜勤が少なくなるまたは免除される可能性がある
緩和ケア認定看護師は数が少ないため、できるだけ多くの患者さんやご家族、スタッフと関わることが求められます。
そのため、患者さんが起きている日中の業務の割合が増え、結果的に夜勤が少なくなる傾向にあります。
転職や復職に有利になる
緩和ケア認定看護師は、看護師のなかでも高い専門性を有している証明になります。
さらに、チームをまとめたり、指導・相談のスキルもあるものと認識されるため、転職や復職の際には有利に働くでしょう。
緩和ケア認定看護師に関するよくある疑問
ここでは、緩和ケア認定看護師に関してよく寄せられる、以下の3つの質問に回答していきます。
- 資格取得にかかる費用は?
- 資格を取得するための教育機関は?
- 資格取得後の更新は必要?
順番に見ていきましょう。
緩和ケア認定看護師になるのに必要な費用は?
認定看護師になるための費用は、一般的に100万円程度かかります。
内訳は、入試検定料、登録料、教育機関などの授業料などです。
また、緩和ケア認定看護師の教育機関は2023年時点で全国に3つしかありません。
教育機関の近くに引越して通う場合、費用の総額が200万円を超える可能性もあります。
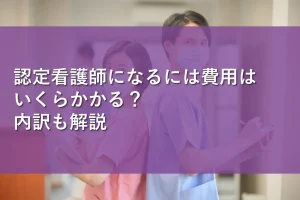
緩和ケア認定看護師の資格が取得ができる教育機関は?
緩和ケア認定看護師の教育機関のうち、現在開講しているものは以下のとおりです。
- 岩手医科大学附属病院高度看護研修センター(岩手県)
- 静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程 (静岡県)
- 久留米大学認定看護師教育センター(福岡県)
認定看護師の教育課程は特定行為研修が組み込まれていないA課程と特定行為研修が組み込まれているB課程があります。
A課程は2026年までの開講で、緩和ケアは現在開講していません。
上記の施設はB課程での教育が実施されている機関で、2023年現在では3施設のみになります。
緩和ケア認定看護師の資格取得後は資格の更新が必要?
緩和ケア認定看護師は資格取得後に5年ごとの更新があります。
更新のためには、看護実践の必要時間と自己研鑽の点数を満たさなければなりません。
具体的には、看護実践が2,000時間以上必要です。
自己研鑽は研修や学会への参加、研究などを実施した分だけポイントが付くようになっており、合計50点以上が必要になっています。
緩和ケア認定看護師は資格取得後も、より新しく専門性の高い知識や技術を学び続けなければなりません。
緩和ケア認定看護師の役割・仕事内容を理解して資格取得を検討しよう
緩和ケア認定看護師は、認定看護師の一つで、緩和ケアに関わる知識や技術の高さを証明する資格です。
取得することでキャリアアップにつながり、待遇の改善や、より待遇の良い職場への転職もめざしやすくなるでしょう。
ただし、取得するためには長い時間と、安くない費用が必要になります。
緩和ケア認定看護師の魅力と、資格取得に必要な時間や費用を考慮に入れ、将来自分のなりたい看護師像を明確にしたうえで、資格取得を検討するようにしましょう。






