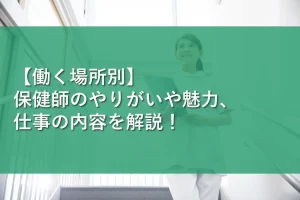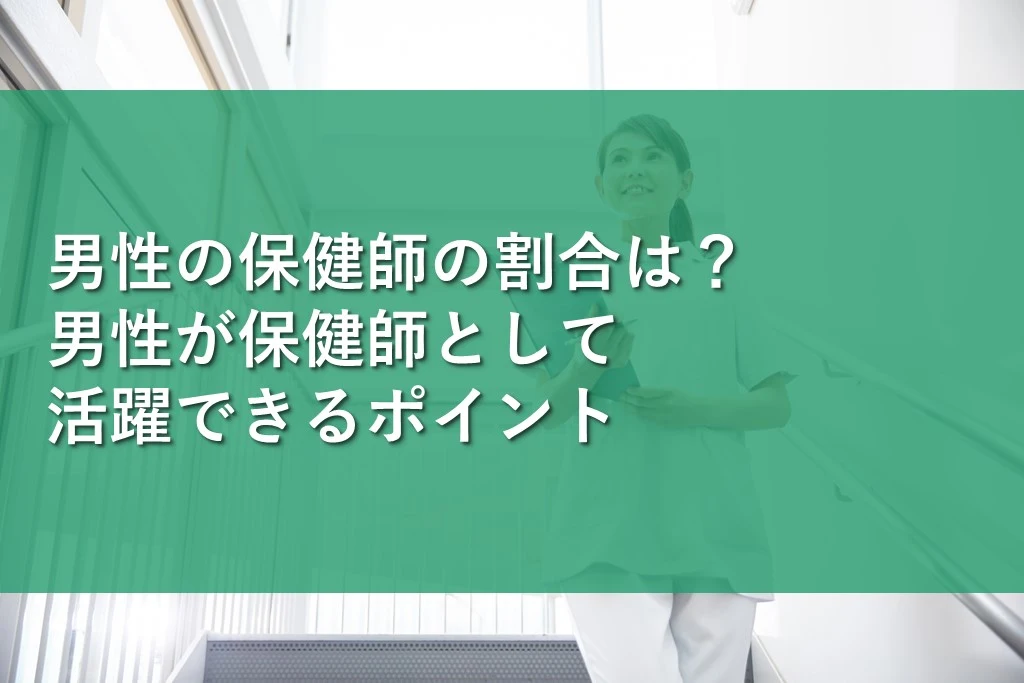
保健師と聞くと女性のイメージが強い仕事ですが、 実際には男性も活躍しています。
本記事では、男性が保健師をめざす際に意識するべき点や、活躍できるポイント、保健師の男女比などを紹介します。
目次
保健師の男女比

男性保健師は全体の1割 程度で、男女比は圧倒的に女性が多い職業です。
男女の年齢構成比では、女性は40代後半が多いのに対して、男性は20代後半〜40代前半が多く、特に20代後半の割合が高い構成となっています。
参考:保健師の活動基盤に関する基礎調査報告書
女性は年齢の高い保健師が多く、男性は若い方が多い傾向といえるでしょう。
保健師は男性でも十分働ける

保健師は女性が多い職業ですが、男性も安心して働くことができます。
保健師は元々保健婦と呼ばれ、女性限定の仕事でしたが、1993年(平成5年)の法改正 によって男性も働けるように変化しました。
男性保健師の歴史は30年弱でまだ浅いため女性が多い状況ですが、徐々に男性も増えてきています。
男性が保健師として活躍できる理由

男性保健師は具体的にどういった点で活躍できるのでしょうか。
2つのポイントにわけて見ていきましょう。
保健師は性別より経験やスキルが大事
利用者が保健師に求めていることは経験やスキルです。
女性が多い職業のため最初は男性保健師に驚く利用者もいるかもしれませんが、「しっかり知識を持っているから信頼できる」と思ってもらえれば、性別は関係ありません。
保健師は健康相談にのりアドバイスすることがメインの仕事となります。
そのため、利用者から健康上の悩みを聴く力や、幅広い知識を持って解決できるスキルが重要です。
お父さんの目線でサポートできる
保健師には、女性ならではの仕事もありますが、男性であることがいきる仕事もあります。
例えば子育てサポートの分野に目を向けてみましょう。
産後のお母さんの体調や、母乳・授乳に関わることなどは、女性保健師のほうが対応しやすい内容です。
一方で、お父さんへのフォローが必要なケースなどは、男性保健師が対応しやすい場面といえるでしょう。
特に近年は、国が主導となり男性の育休義務化を進める など、男性の育児参加が推奨されているため、お父さんをフォローする役割の重要性は増しています。
子育てサポートに限らずとも、保健師は老若男女問わず幅広い利用者を対象とするため、男性目線での対応が必要な場面は他にもあります。
男性が保健師資格を取得するメリット

男性も保健師として活躍できることがわかりました。
では、本章からは男性が保健師資格を取得するメリットを3点あげていきます。
長期的に安定して働ける
厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査によると、保健師の年収は443.6万円でした。
男性の年収は515万円です。
保健師の年収に関する詳細は以下の記事をご参照ください。
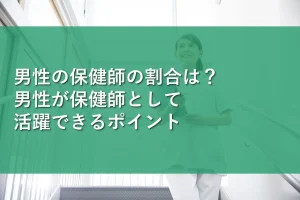
予防医療に携われる
医師や看護師が病気になったあとの処置をするのに対して、保健師は病気になる前の予防医療に携わることが特徴です。
感染症や精神疾患などが問題視される近年、予防医療は必要不可欠なものとして注目されています。
行政・企業・学校・病院などの幅広い分野から健康維持のサポートを行うには、女性からの視点だけではなく、男性からの視点も重要です。
男性が保健師資格を取得する際の注意点
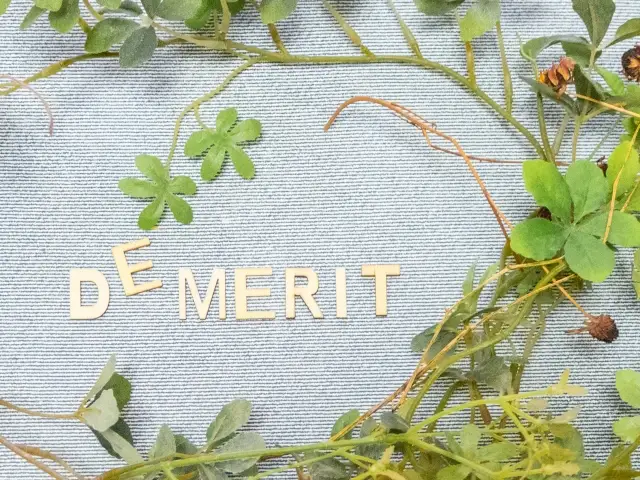
ここでは保健師資格を取得する際の注意点を紹介します。
まず、求人数が多くはありません。
ハローワークによると令和4年度の有効求人倍率は1.21倍で、看護師の有効求人倍率が2.53倍 あることと比較すると少ないといえます。
保健師は各職場に1〜2名程度しかいない場合もあり、大量募集することは少ないため、多くの求人から選ぶことが難しいでしょう。
男性が「保健師として条件の良い職場へすぐに就職したい」と思っても、募集状況を見ながら地道に就職活動をしていく必要があります。
また、平日の休みが取得しにくいことも難点です。
土日祝が休みというメリットはありますが、逆に平日休みを取ることは難しく、平日しかできない予定は調整する必要が出てきます。
こうした点を事前に理解しておくことが大切です。
男性が保健師資格をめざす際のポイント

最後に、男性が保健師になるにあたってはいくつかのポイントがあります。
母子業務についてなど4点を確認していきましょう。
保健師になるためのスケジュールをしっかりと組む
保健師になるためには、保健師免許と看護師免許の両方が必要です。
大学で両方の資格を同時に取得する、まず看護師として働きその経験を活かして保健師になるなど、さまざまなルートがあります。
その他にも、インターンシップへの参加や、公務員試験の勉強(行政保健師の場合)など、タスクが多いため、どういったルートで保健師をめざすのか、事前にしっかりとスケジュールを組みましょう。
自分に合った学校を選ぶ
保健師免許と看護師免許をどうやって取得するかを考え、学校を選びましょう。
同時に取得するためには、看護師教育課程に保健師教育課程を取り入れた総合カリキュラムを実施する4年制大学に進学するパターンがあります。
他には、短大や3年制専門学校で看護師免許を取得したあと、保健師養成学校に入るか大学に編入する形で保健師免許を取るパターンもあります。
自分の状況に合わせて適切な進学先を選択してください。
保健師資格を取得できる大学に関する詳細は以下の記事をご参照ください。
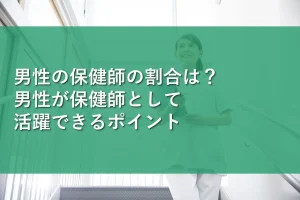
母子保健業務に携わる際は女性にサポートしてもらう
母子保健の分野では、子どもを持つお母さんが「同じ女性に対応してほしい」と思うこともあるため、女性の保健師にサポートしてもらいながら業務を進めていきましょう。
例えば、訪問指導の際には女性の保健師と2人体制で訪問したり、助産師や看護師と相談しながら進めることが必要です。
女性でないと相談しにくいことは女性スタッフに対応してもらい、男性としての意見が必要な際は適切なアドバイスをすると利用者にも信頼してもらえます。
相談できる相手を探す
女性が圧倒的に多い職場であるため、女性保健師のなかには男性が職場にいることに慣れない人もおり、職場によっては居心地が悪くなってしまう可能性もあります。
そういった状況に備えて、相談できる相手を作っておきましょう。
ご家族や友人など身近な人はもちろん、厚生労働省の総合労働相談コーナー といった公共の相談窓口の利用もできます。
男性保健師のメリット・デメリットを理解し満足のいくキャリアを構築しよう

保健師は女性が圧倒的に多い職業ですが、男性だからこそ活躍できる場面もあります。
老若男女の保健を行うには、女性目線だけでなく、男性目線も必要ですし、今後、積極的に育児参加するお父さんが増えれば、男性保健師の重要性もいっそう増すでしょう。
本記事で紹介した注意点やポイントもぜひ参考にしながら、保健師をめざすかを検討してください。