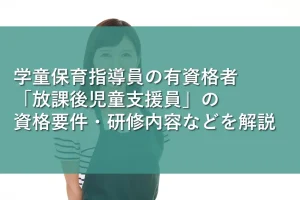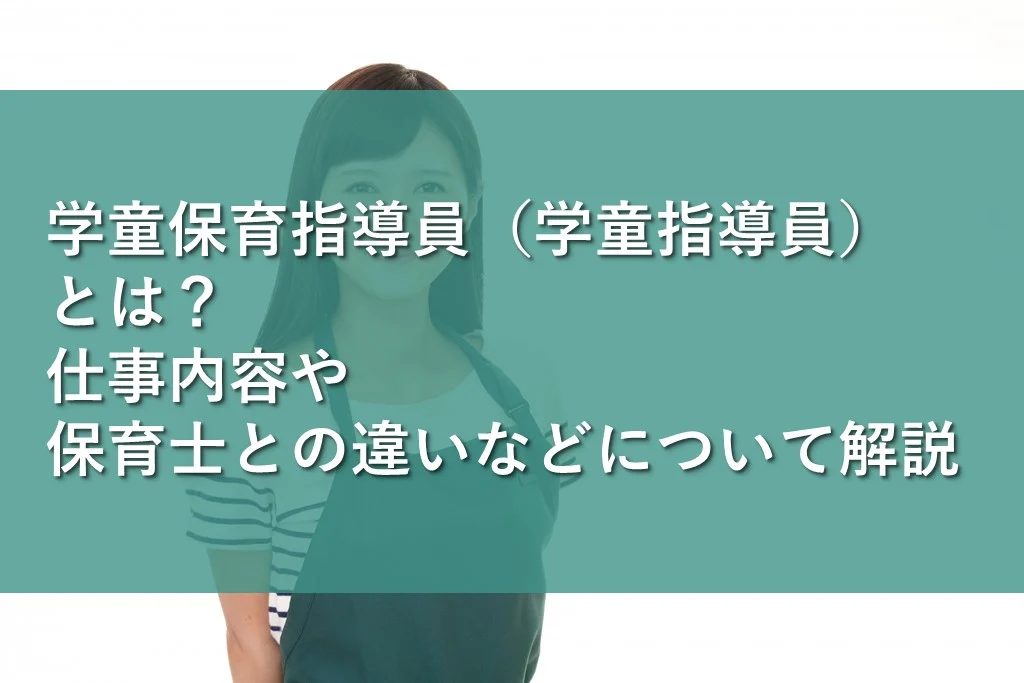
共働き世帯が増加の一途をたどる現在、学童へ注目が集まっていることをご存じでしょうか。
クラブ登録児童数も年々増えており、それと同時に学童の先生の需要も高まっています。
学童で働く先生は正確には学童保育指導員(学童指導員)と呼ばれ、子どもに安心安全な生活の場を提供して成長を見守る重要な存在です。
本記事では、学童保育指導員の仕事内容や保育士との違い、働くことのメリット・デメリットを解説します。
子どもと関わることが好きな方、子育て家庭の支援に興味がある方は、その魅力をチェックしてみましょう。
目次
学童保育指導員(学童指導員)とは?
学童保育指導員(学童指導員)とは、保護者が日中仕事などで家にいない家庭の小学生を対象に、学童保育施設で適切な援助を行う仕事です。
主に小学校の放課後や土曜日、春・夏・冬の長期休みに、学童保育施設または放課後児童クラブで子どもたちを預かります。
学童保育の役割は、親の仕事と子育ての両立を支援し、子どもに生活の場を提供することです。
したがって学童保育指導員は、子どもにとって身近に存在する頼れる大人であることが求められるでしょう。
学童保育指導員の仕事内容

学童保育指導員は、小学生の子どもが安心できる生活の場の提供、そして身近な頼れる存在であることをめざしています。
では、具体的にはどのような業務を行っているのでしょうか。
学童保育指導員の仕事内容や1日の業務の流れを解説します。
学童保育指導員の業務
学童で対象とする子どもについて、厚生労働省は次のように定めています。
- 保護者が仕事により日中家にいない、もしくは疾病・介護などにより日中に家庭での養育が難しい子ども
- 小学校に就学している
学童保育指導員の業務は、このような子どもたちの生活を援助することです。
業務内容としては次のようなものがあります。
- 子どもが学童に自主的に通い続けられるよう出欠席と精神面、肉体面の状態の把握
- 日常生活に必要な基本の生活習慣を習得するための援助
- 発達段階に応じて主体的に遊べるようサポート
- 子どもが自分の気持ちや意見を表現する手助け
- おやつの提供
- 安全に安心して過ごせる環境を整備
- 緊急時に子ども自らが適切な対応ができるよう援助
- 子どもの様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携
- 学校、地域関係者との連携
このように、ただ子どもを見守るだけでなく家庭や地域と連携したうえで健やかな成長をサポートする役割があります。
業務の流れ
施設や学校によって詳しいスケジュールは異なりますが、学童保育指導員の一般的な平日の業務の流れは以下のとおりです。
| 10:00(土曜や長期休暇中は8:00~) | 出勤、受け入れ準備 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | 児童来所 |
| 15:00 | おやつ提供 |
| 15:30 | 自由時間 |
| 17:30~ | 児童帰宅 |
| 18:30 | 施設閉所 |
| 19:00(土曜や長期休暇は~17:00) | 退勤 |
子どもと接する時間には、自主的に勉強するのを見守ったり、学年相応の遊びや他学年との交流をうながしたりします。
児童館などに併設した学童では、工作や調理実習などのイベント企画・準備も学童保育指導員が行うことになるでしょう。
子どもが帰ったあと、道具や備品のチェックと掃除、翌日のスケジュール確認をし、連絡事項を翌日の担当者に引き継ぎます。
子ども同士のトラブルや心配事を抱えた子がいる場合はそれも共有し、翌日以降の様子に注意することも大切な仕事の一つです。
学童保育指導員の雇用形態や勤務形態
学童保育指導員は正規職員が約34%、パート・アルバイトが約66%と、正規職員の割合は全体の3分の1程度です。
そのため、平日の勤務時間は3時間以上6時間未満という方が多いでしょう。
ただし土曜日や学校の休校日、長期休暇などのタイミングでは、勤務時間が8時間以上になることもあります。
公立の場合は閉所時間が比較的早く、小学校内や児童館内に設置されるケースが大半です。
一方、民立の児童クラブはビルの一角などにあり、19:00以降まで開所しているところも珍しくありません。
学童保育指導員として働くといっても、公立施設と民立施設のどちらで勤務するか、正規指導員かパート・アルバイトかなど、働き方の選択肢は多いといえるでしょう。
学童保育指導員と保育士の関係
子どもと関わることが好きで、学童保育指導員として働くか、保育士として働くか悩んでいる方もいるかもしれません。
あるいは、保育士から学童保育指導員への転職を検討することもあるでしょう。
ここでは、学童保育指導員と保育士の違いを解説します。
学童保育指導員と保育士の違い
学童保育指導員と保育士の違いには、対象とする子どもの年齢、働く時間、必要な資格の3点が挙げられます。
- 対象児童の年齢
学童保育指導員は小学生(6歳以上)、保育士は幼児(0〜6歳)が対象です。
幼児と比べて小学生は遊び方がよりダイナミックになるため、学童保育指導員もそれなりの体力が必要となるでしょう。
学童施設によっては宿題や勉強の指導を求められる場合もあり、教育の要素が強い点も特徴です。 - 勤務時間
先述のとおり、学童保育指導員は比較的朝の出勤時間が遅めといえます。
また、土曜日や長期休暇に仕事時間が長くなる点も大きな特徴です。
保育士の出勤時間は、早番だと7:00頃になります。 - 必要資格
学童保育指導員になるために必須の資格は特にありません。
ただし、正社員として働く学童保育指導員の多くは保育士や教員免許などを取得しています。
一方、保育士になるためには国家資格である「保育士資格」が必要です。
保育士から学童保育指導員への転職
「仕事と私生活の両立のため」「幼児の保育経験を活かし、もう少し年齢が高い子どもと関わりたい」などの理由で、保育士から学童保育指導員へ転職を希望する方は多くいます。
朝の早さや休みのとりにくさに苦労していた保育士の方が、比較的出勤時間が遅い学童保育指導員として家庭との両立を叶えるという働き方も可能です。
また、保育士の資格を持っていれば、研修を受けることで放課後児童支援員の資格を取得できます。
これにより、正規雇用での学童保育指導員をめざしやすくなるでしょう。
また、対象となる児童が大きいぶん体力が求められるため、男性のニーズも高く、男性保育士の転職も歓迎されやすいといえます。
学童保育指導員のやりがいや魅力

学童保育指導員として働くなかで、どのようなときにやりがいを感じられるのでしょうか。
学童保育指導員の仕事で求められる資質や魅力、キャリアアップについて解説します。
学童保育指導員に求められること
学童保育指導員に求められる資質には、次のようなものがあるでしょう。
- 子どもが好き
- コミュニケーション能力
- 臨機応変に対応できる
- 教育意欲がある
第一に、子どもと関わることが好き、子どもの成長にやりがいを感じられる素質が大切になります。
次に必要になるのが、コミュニケーション能力です。
学校や親、地域と連携をとることも学童の役割であるため、子どもはもちろん大人とも良好な関係を築ける人材は重宝されます。
ときには臨機応変さも重要になるでしょう。
学童では子ども同士の喧嘩や言い合い、体調不良といったイレギュラーな事態も起こり得ます。
そうした状況でも、焦らず冷静に対応しなければなりません。
また、学童は遊びだけでなく教育の場でもあります。
施設によっては子どもへ勉強指導を求められる場合もあることから、教育意欲が高い方にも適した仕事といえるでしょう。
学童保育指導員のメリットとデメリット
学童保育指導員として働くことには、仕事にメリハリがつけやすいこと、子どもの成長を見守れることなどのメリットがあります。
ただし、給料面でのデメリットがあることも覚えておきましょう。
学童保育指導員のメリット
学童保育は勤務開始時間が比較的遅く、混雑する時間に出勤する必要がありません。
また、残業や持ち帰りの仕事がほとんどない点も魅力です。
子どもと関わる時間と事務作業の時間がきっちり分かれており、メリハリをつけて仕事ができます。
さらに、子どもの成長を近くで見守っていられることも学童保育指導員のメリットです。
自分の子育て経験を活かせるため、やりがいにもつながるでしょう。
学童保育指導員のデメリット
学童保育指導員のデメリットとして、正社員の求人が少なく、パート・アルバイトが主な働き方という点があります。
正社員の求人は、資格の保有者・経験者に限られていることも珍しくありません。
正社員をめざすのであれば、後述の資格取得をめざすのがおすすめです。
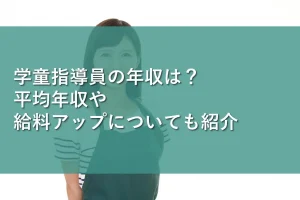
学童保育指導員のキャリアアップ
学童保育指導員としてキャリアアップしたいと考えるのならば、資格を取得するという選択肢があります。
例えば「放課後児童支援員」は、保育士や社会福祉士の資格や教員免許を持っている場合に取得をめざせる資格です。
放課後児童支援員になると、正社員の選択肢を選びやすくなって結果的に給料がアップしたり、さらなる資格取得につながったりといったメリットを享受できるかもしれません。
学童保育指導員の業務内容を知り「学童の先生」をめざそう
学童保育指導員の業務内容、保育士との違いについて解説しました。
パート・アルバイトでの雇用が多く、また出勤時間が遅めであることから、家庭と仕事を両立したい方にとっては働きやすい環境といえるでしょう。
子どもと関わりながら、地域の子育てを支援できるという意味でも魅力的な仕事です。
キャリアアップのためには資格取得を検討する必要がありますが、自分の成長につながる良いきっかけととらえることもできます。
保育士から転職する方も多いため、経験を活かして学童保育指導員の道も検討してみましょう。