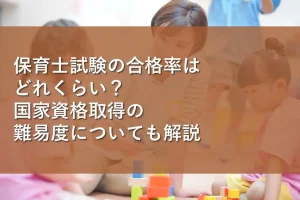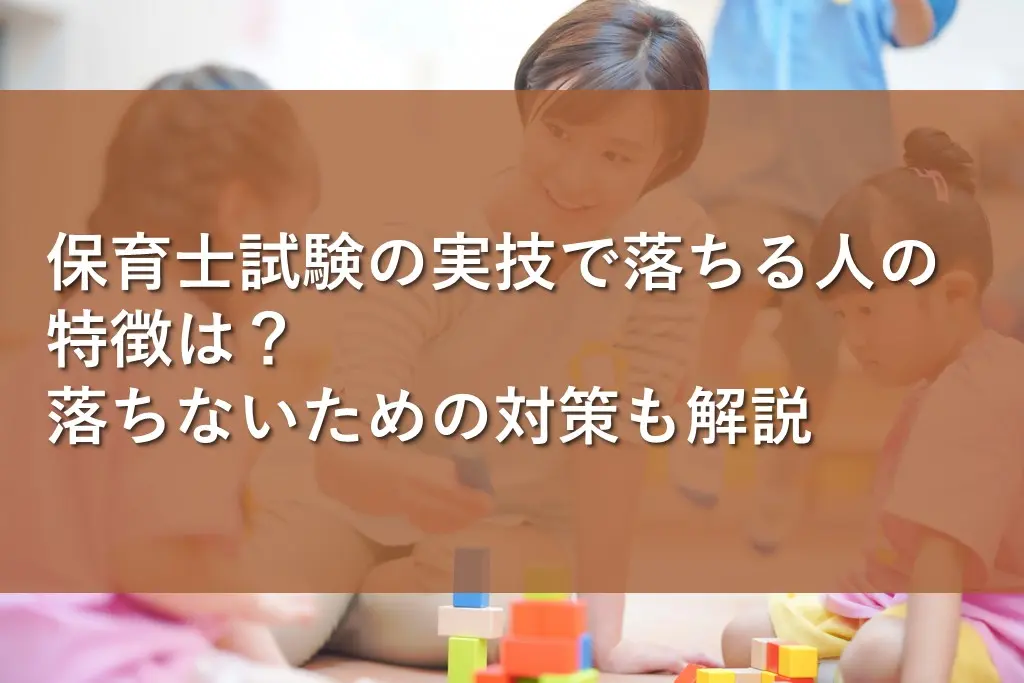
保育士試験に合格するためには、筆記試験と実技試験の両方に合格しなければなりません。
実技試験は、音楽・造形・言語の3分野のうち2分野を選んで受験し、それぞれの分野で50点満点中30点以上を獲得する必要があります。
この記事では、保育士試験の実技で落ちる人の特徴を紹介しています。
落ちないための対策も紹介しているので、保育士をめざしている人は参考にしてください。
目次
保育士試験の実技で落ちる人の特徴

実技試験で不合格になる人には、いくつかの理由が考えられます。
社会人のマナーを守っていて、大きなミスをしたわけでもないのに落ちる場合は、以下で紹介するような特徴があるかもしれません。
保育士実技試験の内容を詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしてください。
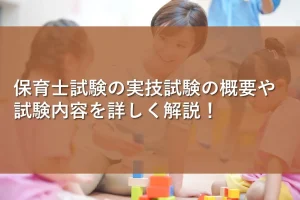
笑顔が作れない
実技試験に落ちる人の特徴として、笑顔が作れない人が挙げられます。
実技試験は試験官に見られながら行うため、緊張して笑顔が作れなくなってしまう人もいるのです。
試験の場であっても、実際に子どもたちに向けるような笑顔が作れなければ、保育士になってから子どもたちとうまく接することができないと思われてしまいかねません。
感情が入っていない
感情が入っていない演技も、試験官には不自然に見えます。
自分では良いと思っていても、ほかの人から見ると、歌や読み聞かせで歌詞やセリフを正しく伝えるだけになってしまっている人がいます。
ミスしないことだけを意識するのではなく、抑揚やリズム感を自分流に表現することが重要です。
対策をしない
実技の内容が得意なものだからといって対策しない人も、不合格になるおそれがあります。
保育士試験の実技は、制限時間があるものや、使える道具が制限されているものもあるため、対策なしでの合格は困難です。
合格するためには、得意な分野であっても十分な対策を行うようにしましょう。
保育士試験の実技で落ちないための対策
ここでは、保育士試験の実技で落ちないための対策を3つ紹介します。
家族や友人に披露する
実技試験の練習は、家族や友人に披露してみる方法がおすすめです。
一人で練習しているだけでは気付かないミスや違和感も、第三者に見てもらい、客観的なフィードバックをもらうことで把握することができるでしょう。
また、試験本番では試験管の目の前で弾き歌いや素話を行うため、人前で行うことに慣れていないと、緊張して練習どおりにできないおそれがあります。
ある程度練習を積んだ段階で家族や友人に見てもらい、感想やフィードバックをもらいましょう。
披露する相手がいない場合は、自分でビデオ録画して確認する方法もあります。
分野ごとに対策を行う
音楽・造形・言語の3分野は、求められるスキルも出題形式もそれぞれ異なります。
そのため、選択した分野に応じた対策が必要です。
例えば音楽・言語では事前に課題となる曲や物語が知らされますが、造形の場合は試験当日に課題が明かされます。
また、制限時間がある分野に関しては、時間内に仕上げられるよう、何度も練習して慣れておきましょう。
保育士試験の科目を知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
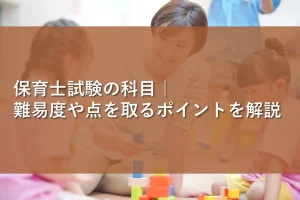
当日ミスしても諦めない
当日にミスしてしまった場合も、途中で諦めないことが重要です。
試験本番の緊張から、練習ではしなかったミスをしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、実技試験では、ミスが原因で不合格になるとは限りません。
むしろ、ミスのあとにどのような対応ができるかが重要です。
ミスをしたからといって、諦めたりパニックになったりせず、最後までやり抜きましょう。
保育士試験の実技で落ちた人はどうする?
保育士試験の実技で落ちた場合、筆記試験の合格から3年以内であれば、実技試験から再チャレンジすることが可能です。
筆記試験の合格には3年間の有効期限があります。
そのため、筆記試験に合格してから3年間は、筆記試験を受けず実技試験だけを受けることが可能です。
次の保育士試験は、実技の対策だけを行えば良いため、合格できる可能性も上がるでしょう。
保育士試験の合格率については、以下の記事で紹介しているので参考にしてください。
保育士の実技試験に落ちる人は対策不足が主な原因なのでしっかり備えよう
保育士の実技試験に落ちる人には、笑顔が作れていない、感情がこもっていないなどの特徴があります。
また、分野ごとの対策を行っていない人も注意が必要です。
実技試験は3分野の中から2分野を選びますが、得意な分野であっても十分な対策が必要です。
対策がある程度進んだら第三者に披露し、客観的なフィードバックをもらうと良いでしょう。
試験本番でミスしてしまった場合も、諦めずに最後までやり切ることが大切です。
実技試験に万が一落ちた場合でも、筆記試験に3年間の有効期限があるため、期間内に再チャレンジしましょう。