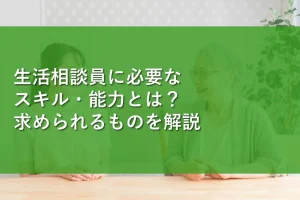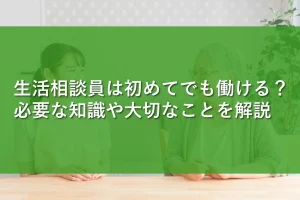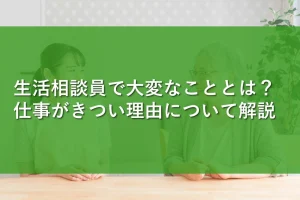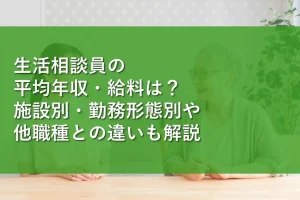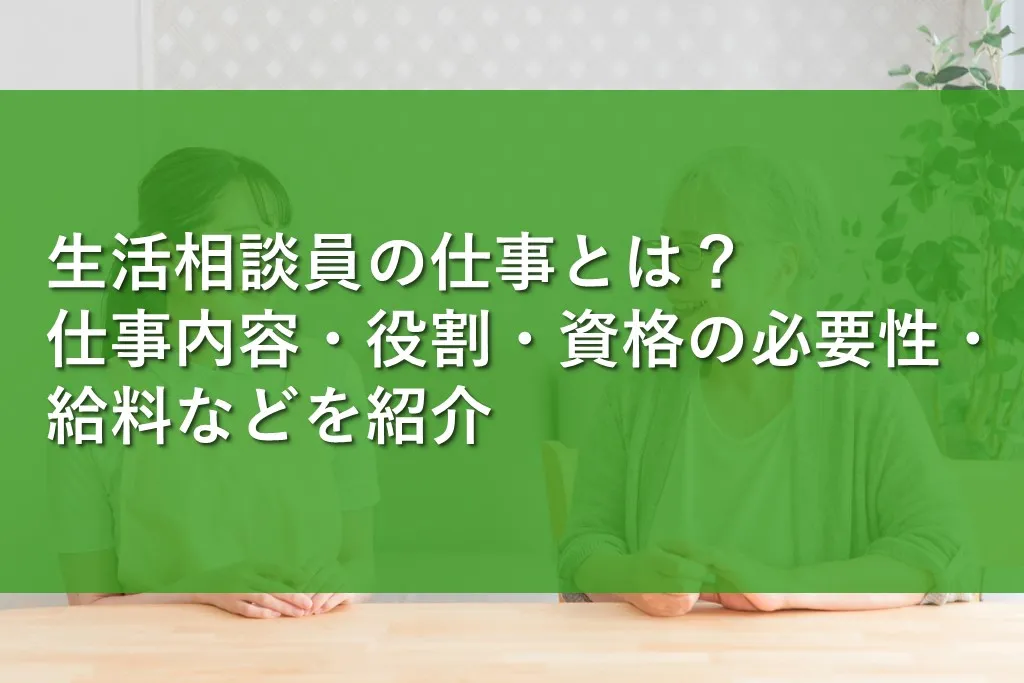
「生活相談員という職種は耳にしたことはあるけれど、実際どのような仕事を行っているの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
生活相談員は、施設入居のための説明や、利用者さんやそのご家族からの相談対応を通して、介護を必要とする方をサポートする役割を担っています。
今回の記事では、生活相談員の仕事に興味がある方に向けて、生活相談員の仕事内容や役割、なり方までをわかりやすく解説していきます。
生活相談員になる前に知っておきたいことばかりなので、参考にしてみてください。
目次
生活相談員とは?

生活相談員は、介護を必要としている方々が安心して生活を送れるよう支援する仕事です。
まずは、生活相談員の役割やケアマネジャーとの違いを見ていきましょう。
介護施設における窓口的な役割を担う
生活相談員は、老人福祉施設への入居希望者や利用者さん、そのご家族への説明・相談・連絡・面談、また主治医などとの連絡調整、介護サービスの手続きといった業務を行います。
施設の利用者さんが、快適かつ自立した日常生活を送るためには欠かせない存在です。
なお、ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。
ケアマネジャーとの違い
| 生活相談員 | ケアマネジャー | |
| おもな仕事内容 | 相談や連絡調整といった窓口 | ケアプランの作成 |
| 職場 | 老人福祉施設 | 居宅介護支援事業所や介護施設 |
| 必要な資格 | 以下のいずれかが必要(自治体による)
・社会福祉士 |
介護支援専門員 |
ケアマネジャーは、介護サービスを利用する方へ支援計画書(ケアプラン)を作成するのがおもな仕事です。
計画書を作成するうえで、利用者さんやそのご家族の要望を満たすために聞き込みをします。
一方で、上記で紹介した仕事内容のように生活相談員の活躍の場は幅広く、さまざまな場面で施設やケアマネジャーとの間に入ります。
生活相談員とケアマネジャーの違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参照ください。
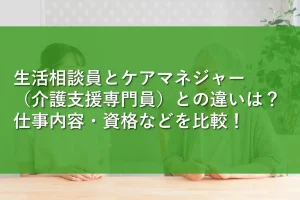
生活相談員の仕事について
生活相談員の仕事内容や勤務先、働き方などについて紹介していきます。
おもな勤務先
生活相談員のおもな勤務先は、介護を必要としている方々が利用する老人福祉施設です。
具体的には、以下のような施設が挙げられるでしょう。
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 老人介護支援センター
- 介護付き有料老人ホーム
- 短期入所生活介護施設(ショートステイ)
- 通所介護施設(デイサービス)
- 老人デイサービスセンター
施設の規模や種類によって、生活相談員の配置基準は異なります。
例えば、特別養護老人ホームでは、施設利用者100人に対して最低でも生活相談員一人の配置が求められます。
業務内容
生活相談員の仕事内容は、利用者さんやそのご家族と施設、医療機関、行政機関の間に入って行う業務が基本です。
具体的には、以下のような仕事内容があります。
- 入居希望者や利用者さん、そのご家族の対応(サービス説明、相談・面談・苦情対応)
- 介護サービス利用や入退所などにともなう手続き
- 状況に合わせ、主治医やケアマネジャー(介護支援専門員)との連絡調整
- 地域の保健・行政機関や医療施設などとの連携による支援策の検討
- 介護業務
なお、働いている施設によって、業務内容は少しずつ異なります。
厚生労働省の調査では、約7割の施設が生活相談員の他職種との兼務を認めている現状がありました。
そのため、生活指導員の仕事に加えて、他の職種の仕事も兼任することもあるでしょう。
仕事に求められるスキルや能力
生活相談員の仕事には、以下のスキルや能力が求められます。
- 職場環境への適応スキル
- 柔軟なコミュニケーションスキルと営業力
- 相手から信頼されるスキル
- 報連相が適切にできる仕事管理能力
- 自分なりの業務マニュアルを作成できる能力
生活相談員は、利用者さんやそのご家族をはじめ、施設内のスタッフやケアマネジャーを含む外部の他職種など、さまざまな立場の人とコミュニケーションを取り、連携しなければいけません。
相手の立場に応じたコミュニケーションを取りつつ、適切に情報を共有できるスキルが必要になるでしょう。
生活相談員に必要なスキルの詳細は、こちらの記事で紹介しています。
生活相談員をめざしている方は、参考にしてみてください。
働き方(雇用形態・勤務時間)
厚生労働省によると、生活相談員の雇用形態は9割近くが「正規社員・従業員」となっており、続いて「パートタイマー」「契約社員・期間従業員」「自営・フリーランス」の順となります。
生活相談員として活躍している方のほとんどが、フルタイムで働いていることがわかるでしょう。
また、生活相談員は利用者さんやご家族の相談対応などの窓口業務が多いことから、介護業務と兼任していない限りは9時から17時などの日中の仕事のみであり、早番や遅番はありません。
基本的に週休2日制ですが、入所機能のある施設であれば、土日の対応も必要になり、シフト制の勤務になるでしょう。
雇用形態や勤務時間は施設によって異なるため、入職前に事前に確認しておきましょう。
生活相談員のなり方
生活相談員は職種であり、専用の資格は存在しません。
とはいえ無資格で就ける職業ではなく、以下の資格要件が定められていることが一般的です。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
- 上記と同等以上の能力を有すると認められる者
自治体ごとに異なりますが、上記以外にも介護福祉士やケアマネジャーの資格を有している者も対象となる場合もあります。
その他、特定の業務内容における経験年数が定められているところもあるため、詳細は各自治体にお問い合わせください。
生活相談員の資格については、以下の記事で詳しく解説しています。
生活相談員について知っておきたいこと
生活相談員として働き始める前に、生活相談員の大変さややりがい、給料についても知っておくと、入職後のギャップも少ないでしょう。
業界未経験では難しい職業である
介護・福祉業界未経験では、生活相談員をめざすのは難しい現実があります。
生活相談員の仕事は、介護認定や福祉サービスの知識を持ったうえでの対応が求められるためです。
実際に、生活相談員になるための要件として、社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士の資格や介護職の実務経験を求めている自治体も多くあります。
未経験から生活相談員をめざす場合は、介護業界に関する基本的な知識を身につけつつ、介護職での現場経験を積むことを検討するのもおすすめです。
未経験から生活相談員をめざす際に知っておきたいことは、こちらの記事で詳細に解説しています。
やりがい・大変なこと
生活相談員は、利用者さんやそのご家族にとって、最初に相談する窓口的な存在です。
その後も利用者さんやそのご家族とやりとりをする機会が多く、悩みの相談にのるケースもあるでしょう。
介護の知識を用いて、適切なサービスを紹介したりアドバイスをすることで、直接的にサポートできたというやりがいを感じられるでしょう。
その一方で、生活相談員には以下のような大変さもあります。
- 職場での人間関係
- 利用者さんからのクレーム対応
- 業務範囲の広さ・業務量の多さ
抱える業務範囲が広く、多くの人とやりとりをしなければいけないため、すれ違いが発生してしまう機会もあるかもしれません。
そのような大変さを乗り越えた先に、支援した利用者さんから感謝の言葉を受けた際には、大きな喜びを感じられます。
生活相談員の大変さをより知りたい方は、こちらの記事を参照してみてください。
年収
2022年の介護従事者(常勤)の平均月給額を表にまとめました。
| 生活相談員・支援相談員 | 347,360円 |
| 介護職員 | 322,550円 |
| ケアマネジャー | 365,180円 |
| 事務職員 | 309,380円 |
参考:令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 厚生労働省老健局老人保健課
※介護職員等特定処遇改善加算および、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所の平均月給額
ケアマネジャーより若干低いものの、社会福祉士などの資格者が従事するため、介護職員や事務職員よりも給料は高くなっています。
介護職員や事務職員で働いている方のキャリアアップとして検討するのも良いかもしれません。
生活相談員の年収や処遇改善が気になる方は、以下の記事を参照してください。
将来性
利用者さんやそのご家族に選ばれる施設になるために、生活相談員の役割が必要とされるようになってきており、将来性は高いと考えられます。
実際に、令和4年度の生活相談員の有効求人倍率は3.74倍です。
これは、一人の求職者に対して3つ以上の求人があることを示しています。
老人福祉施設の規模にもよりますが、生活相談員は最低一人以上の配置が義務付けられているため、全国どこでも働けます。
欠員補充などの中途採用は頻繁に行われており、入職の機会は多い傾向です。
ただし、規模が小さい施設などは介護職と兼務しているところもあるので、専任で働きたい方は採用時に確認しましょう。
生活相談員について理解を深めてめざしてみよう
生活相談員は、介護施設の窓口的な存在であり、介護を必要としている人を支えられる仕事です。
介護サービスの専門的な知識が求められますが、知識を活かしつつ個別的な対応がうまくいった際には、大きなやりがいを感じられるでしょう。
生活相談員の働き方は、勤務先によって異なります。
生活相談員に興味がある方は、本記事の内容を参考に理解を深めてから、求人票などを見てみると良いでしょう。