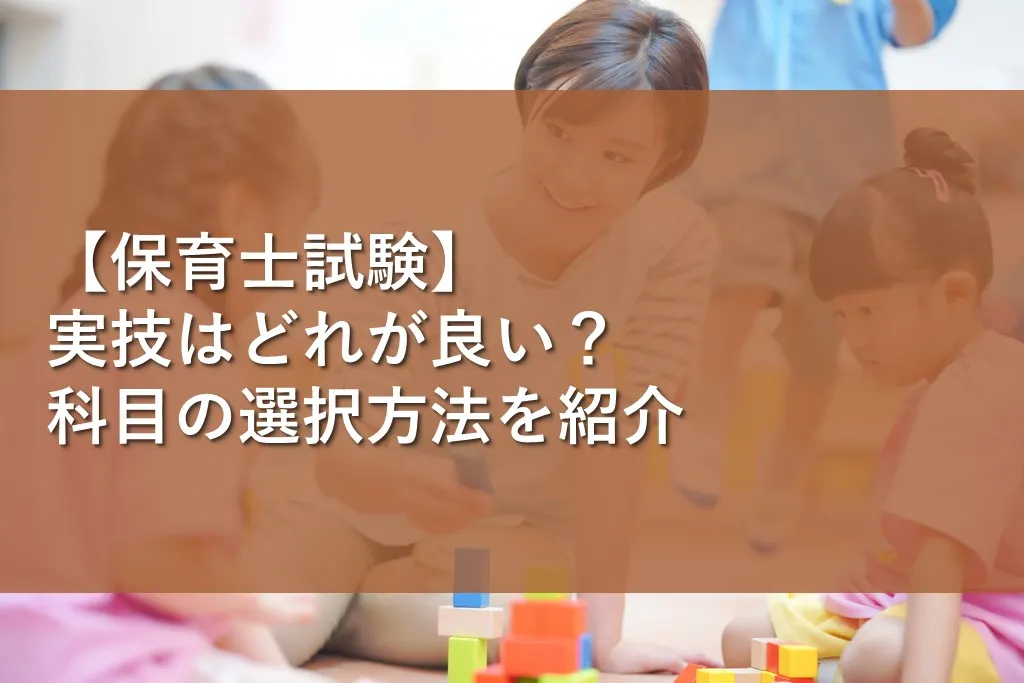
保育士試験の実技科目は受験申請前に決定する必要があるものの、「どれが良いのかわからない」「苦手科目がある」と悩んでしまう方は多いかもしれません。
受験申請後に科目の変更はできないため、なんとなくで決めるのではなく、自分自身で納得して選ぶことが大切です。
この記事では、保育士試験の実技科目の選び方について紹介します。
いずれも事前の対策が大切になるため、受験科目が決まったら当日に向けて練習を繰り返すようにしましょう。
目次
【保育士試験】実技科目はどれが良い?

保育士の実技試験は、筆記試験の合格後に実施される試験であり、以下の3科目のなかから2科目を選択して受験します。
- 「音楽」:ピアノ・アコーディオン・ギターのいずれかを選び課題曲を弾き歌いする
- 「造形」:試験中に指定された保育場面の絵を描く
- 「言語」:3歳児クラスの子どもに聞かせることを想定し、指定された物語を選んで3分間話す
なお、実技試験の採点方法は正式には公表されていません。
さらに、受かりやすいかどうかは個々のスキルにも左右されるため、一概に「この科目は楽/難しい」と断定することはできないといえます。
このこともふまえて、保育士試験の実技でどれが良いのか決めかねる場合は、以下の視点をヒントに選んでみましょう。
試験で取り組む実技科目の内容を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
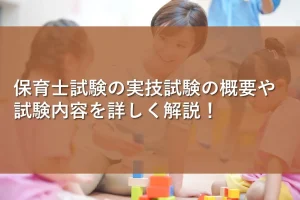
得意・不得意を考える
人によって科目の得意・不得意は異なり、得意なものであれば試験対策もしやすく、合格の確率を上げられます。
「小さい頃にピアノを習っていた」など楽譜や楽器に抵抗がない方は音楽を選ぶ、あるいは絵を描くのが苦手な方は造形以外の2科目を受験するといった選び方もできます。
言語については、人前で話すスキルや表現力に自信がある方におすすめです。
自身の得意・不得意を考慮し、実技試験の科目を絞り込むと良いでしょう。
試験対策のしやすさを考える
試験対策のしやすさを基準に科目を選択するのも、一つの方法です。
実技試験を受けるにあたっては、どの科目を選ぶにしても試験対策が必要になります。
例えば音楽を選択する場合、事前に楽器を使用して課題曲を練習しなければなりません。
楽器がない、音を出して練習できる環境がないような状況だと、実技試験の対策が十分にできず、不安な気持ちのまま試験本番を迎えてしまう可能性があります。
また、試験科目のなかで唯一、造形は試験当日まで課題内容がわかりません。
他の科目であれば、準備してきた課題をそのまま試験で披露できますが、造形は試験が始まってから課題と向き合う必要があります。
試験前の事前対策を万全にしておきたい方は、造形を選択肢から外すことを考えても良いでしょう。
保育士の試験に合格するためのポイントは、こちらの記事をご参照ください。
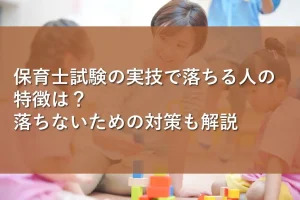
過去の試験問題を実践して決める
得意・不得意が特にないなど、どれを選んだら良いのか見当がつかない場合には、過去の試験問題を一通り実践してから決めましょう。
保育士試験の過去問題は「一般社団法人 全国保育士養成協議会」のホームページに掲載されています。
日常生活のなかで弾き歌いしたりテーマに沿った絵を描いたり、子どもに読み聞かせをする機会はなかなかないかもしれません。
実際に試験内容を実践してみることで、それぞれの科目と自身の相性が見えてくる可能性があります。
過去の試験問題にチャレンジする際は、以下のポイントを確認してみましょう。
実技試験の評価軸を確認する
先述したとおり保育士の実技試験の採点方法は公表されていませんが、評価軸は以下のようになっています。
- 「音楽」:歌や伴奏、リズムなどの点で保育士として豊かな表現ができること
- 「造形」:保育場面の状況を色使いや情景・人物描写を通して表現できること
- 「言語」:3歳児に対して適切な話し方・声の出し方・読み聞かせの表現ができること
試験内容は、この評価軸に則って評価されることを念頭に置いておきましょう。
対策を検討する
試験問題を実践すると、試験当日までに習得が必要なスキルが明らかになります。
試験当日までに、ある程度の余裕を持った対策スケジュールを立てられる科目を選ぶと安心です。
保育士試験は年に2回、以下の日程で実施されます。
後期試験:筆記試験は10月下旬、後期試験は12月上旬
筆記試験のあとに実技試験の対策を始める場合、練習できる期間は約2ヵ月です。
人によっては不得意な分野に取り組む必要も出てくるため、どのようなスケジュールでスキルを身につけるか検討しておきましょう。
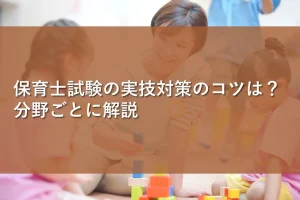
楽しんで練習できるかイメージする
試験対策には日々の地道な努力が必要になるため、楽器を弾くこと・絵を描くこと・読み聞かせの練習を楽しめるかどうかも重視してみてください。
これらを苦痛に感じてしまうと、せっかくの練習にも身が入らず、試験日までつらい時間になってしまいます。
十分に対策をして満足のいく試験結果を得るためにも、一度過去問に取り組んでみて、楽しく学べそうだと感じたものを選びましょう。
保育士実技試験の選択時のポイント

保育士試験の実技科目を決定するには、当日の試験内容だけでなく、対策についても念頭に置いてくことが大切です。
選択した科目によっては、与えられた課題のなかから実際に披露するものを選ばなければなりません。
以下の科目ごとのポイントを参考にしながら、自分の向き・不向きを考えてみてください。
音楽:自分のレベルに合った楽譜を用意
音楽を選択した場合は、指定された課題曲の演奏を練習する必要があります。
歌と同じ単旋律の演奏は採点不可となるため、注意しましょう。
当日は、自身で用意した課題曲の楽譜を持ち込むことも可能です。
同じ曲でも楽譜は複数種類あり、レベルの高い楽譜で練習してしまうと、試験日までに練習が間に合わない可能性もあります。
無理はせず、自身のレベルに合った楽譜を用意するようにしましょう。
造形:さまざまな保育場面を想定して練習
造形は試験前に課題がわからないため、どのような課題を提示されても試験時間内に対応できるよう、さまざまな保育場面を想定して絵の練習をしておきましょう。
今までの過去問を参考にするほか、保育園の1日の流れを検索して出てきた場面をイラストにする練習などが考えられます。
また、当日は45分という制限時間もあり、ノープランで描き始めると時間に間に合わないかもしれません。
登場人物の服装や表情、ポーズをある程度決めておくなど、当日迷わないためにも描く内容をある程度絞り、テーマに合わせて調整するのがおすすめです。
言語:物語のアレンジが必要
言語の試験では、課題になっている物語を3分間という制限時間のなかで発表しなければならず、物語自体を自身でアレンジする必要があります。
600字〜800字くらいのボリュームで、3歳児にも理解できる優しい表現を心がけるのがポイントです。
また、選ぶ物語によっても工夫すべき箇所は異なります。
登場人物が多い物語では人物によって声のトーンを使い分けたり、人物が少ない物語では状況をわかりやすくするために適宜ナレーションを入れたりしましょう。
保育士の実技試験はどれが良いか自分に合わせて検討しよう
保育士試験の実技科目には音楽・造形・言語の3つがあり、どれが良いのかは自身の得意・不得意などによっても変わります。
いずれも事前の対策が重要になるため、練習しやすいものや楽しく学べそうなものを選ぶと良いでしょう。
どうしても実技選択に迷う方は、全科目の過去問題に取り組んでみて決めるという手もあります。
筆記試験から実技試験までのあいだで対策をする場合、練習できる期間は約2ヵ月です。
自身のスキルに不安がある方は、計画的に対策をして合格をめざしましょう。






