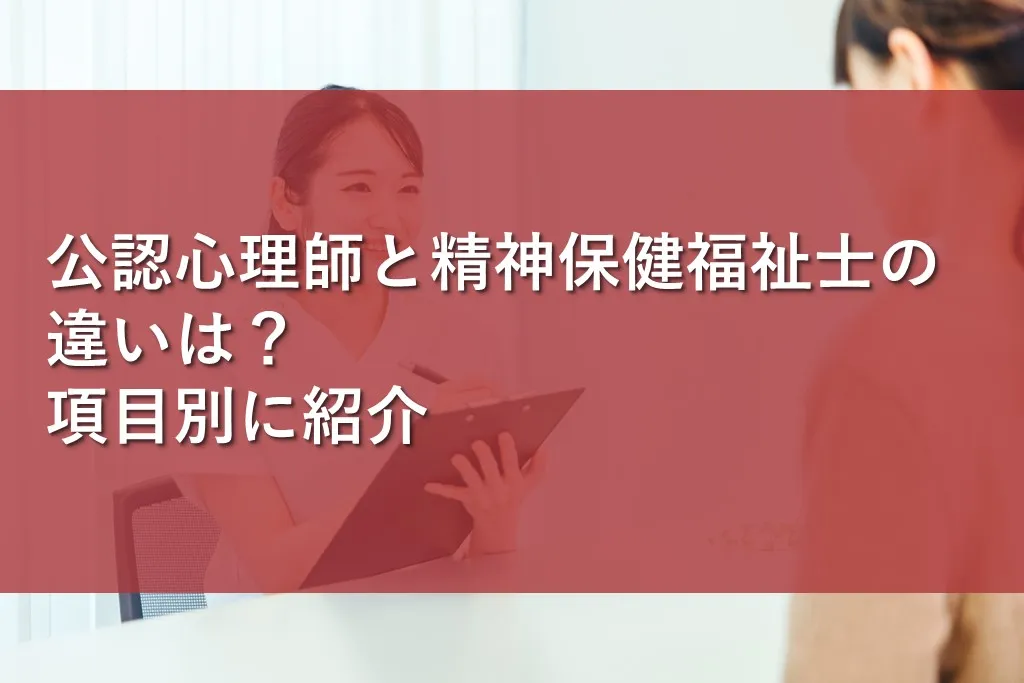
公認心理師と精神保健福祉士の仕事内容には、違いがあります。
仕事内容の違いを知っておかないと、資格を取って就職しても後悔するかもしれません。
仕事内容を理解したうえで、資格を取るならどちらが良いか判断したいのではないでしょうか。
この記事では、公認心理師と精神保健福祉士の仕事内容の違いを紹介します。
合わせて、公認心理師と精神保健福祉士の資格や受験資格などの違いを、項目別に紹介します。
目次
公認心理師と精神保健福祉士の仕事内容の違い

公認心理師と精神保健福祉士は、仕事内容に違いがあります。
公認心理師の仕事内容は、心理的な問題があって支援を望んでいるクライエントと呼ばれる相談者の心理状態を分析し、助言や指導を行うことです。
クライエントの性格や家庭環境など、カウンセリングを通してさまざまな情報を集めて、抱えている心の問題を把握して分析します。
行動観察や心理テストなどから、相談者の特性や問題を明らかにする心理査定や、さまざまな心理療法を行って問題解決をサポートする心理支援を行います。
精神保健福祉士の仕事内容は、精神障がい者に対して、地域社会や日常生活への適応のための相談対応や助言などのサポートを行うことです。
社会復帰などの目標を達成するために計画を作成し、必要に応じて行政などの支援サービスにもつなげます。
あらゆる人を支援する社会福祉士と違い、対象は精神障がい者がメインです。
公認心理師と精神保健福祉士の違いを項目別に紹介
公認心理師と精神保健福祉士は、項目別にどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、項目別の違いを紹介します。
資格
公認心理師と精神保健福祉士は、資格に違いがあります。
どちらも国家資格ではありますが、2017年9月に施行された公認心理師法で定められた公認心理師は、日本で初めての心理に関する資格です。
公認心理師は、厚生労働省と文部科学省が管轄しています。
ちなみに、心理に関する代表的な資格である臨床心理士は民間資格となっています。
精神保健福祉士は、おもに精神保健福祉分野で活躍する専門職の資格です。
1997年に施行された精神保健福祉士法にともなって誕生し、2012年から障害者総合支援法が制定されて、活躍の場が広がっています。
精神保健福祉士は、厚生労働省が管轄している国家資格です。
受験資格(受験ルート)
受験資格(受験ルート)も、公認心理師と精神保健福祉士で違います。
公認心理師の受験資格を得るには、4年制大学と大学院で定められた科目を履修するか、大学卒業後に定められた施設で2年以上の実務経験を積むことが必要です。
公認心理師法が施行された2017年9月以前に、定められた科目を大学院で履修していても受験資格が得られます。
精神保健福祉士の受験資格は、保健福祉系の4年制大学での指定科目の履修です。
他には、保健福祉系の2年制や3年制の短大で指定科目を履修して、相談援助の実務を2年や1年積むことでも受験資格が得られます。
受験のための履修科目
公認心理師と精神保健福祉士は、受験のための履修科目も違います。
公認心理師の大学での必須履修科目は、「公認心理師としての職責」や「心理学概論」、「臨床心理学概論」などの25種類です。
さらに大学院では、「保険医療分野における理論と支援の展開」や「福祉分野に関する理論と支援の展開」などの10種類を履修します。
精神保健福祉士の必須履修科目は、「医学概論」や「心理学と心理的支援」、「社会学と社会システム」など、22種類あります。
試験科目
試験科目も、公認心理師と精神保健福祉士で違います。
公認心理師の試験科目は、「公認心理師としての職責の自覚」や「問題解決能力と生涯学習」、「多職種連携・地域連携」などの24科目です。
「健康・医療に関する心理学」や「福祉に関する心理学」のような、さまざまな分野での心理学に関する科目もあります。
精神保健福祉士の試験科目は、「精神疾患とその治療」や「精神保健の課題と支援」、「精神保健福祉相談援助の基盤」などの17科目です。
「低所得者に対する支援と生活保護制度」など、制度に関する科目も含まれます。
就業先
公認心理師と精神保健福祉士の就業先は、重なる部分もあります。
公認心理師が働く場所は、精神科病院やクリニックなどの保健医療領域、児童相談所や療育施設などの福祉領域、学校や教育センターなどの教育領域です。
さらに、産業領域として民間企業や公共職業安定所など、司法領域として家庭裁判所などもあります。
精神保健福祉士の就業先は、障害者福祉や医療領域に多くありますが、児童福祉や教育、行政や司法領域まで広がっています。
精神保健福祉士が関与する範囲が、メンタルヘルスの問題を抱える人のサポートまでに広がっているためです。
公認心理師と精神保健福祉士の違いを知って職業選びの参考にしよう
公認心理師と精神保健福祉士の仕事内容には、違いがあります。
仕事内容の違いを知っておかないと、資格を取って就職しても後悔するかもしれません。
心理的な問題があって支援を望んでいる相談者に心理支援を行うのが公認心理師、精神障がい者の相談に応じるのが精神保健福祉士という違いがあります。
この記事で公認心理師と精神保健福祉士の違いを知り、職業選びの参考にしてください。







