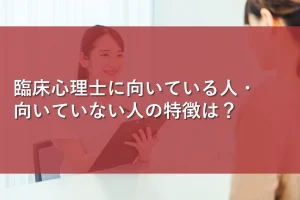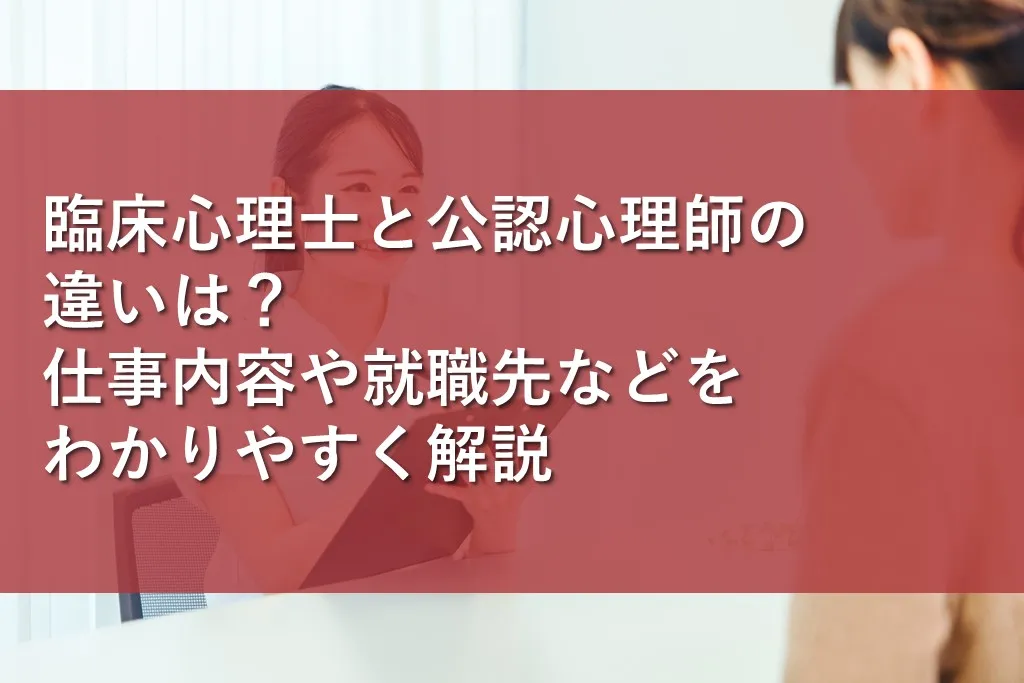
公認心理師と臨床心理士、両者とも「心理」という言葉がついていることで、人の心の悩みに寄り添う資格であることは想像できるかと思います。
この記事では、公認心理師と臨床心理士の役割や仕事内容、就職先などの違いを紹介します。
2つの資格の違いを知り、めざす資格を選ぶきっかけとして活用してください。
目次
公認心理師と臨床心理士の違い

公認心理師は公認心理師法が2017年に全面施行となった新しい資格であるのに対し、臨床心理士は1988年に施行された歴史の古い資格であり、設立された年数が大きく異なります。
現時点でも、必要な受検資格や法律上の定義・役割などに違いがあるため、それぞれについて紹介します。
役割の違い
公認心理師と臨床心理士では、法律上の定義が異なります。
公認心理師と臨床心理士、それぞれの役割の違いを見てみましょう。
法律上の定義の違い
公認心理師と臨床心理士の定義の違いを、以下に記載します。
【公認心理師】
公認心理師法では、公認心理師の業務範囲は以下のとおりと定義されています。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
引用:公認心理師法
【臨床心理士】
臨床心理士の手引きによると、臨床心理士の業務範囲は以下のとおりと定義されています。
第11条 臨床心理士は、学校教育法に基づいた大学、大学院教育で得られる高度な心理学的知識と技能を用いて臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助及びそれらの研究調査等の業務を行う。
引用:臨床心理士の手引き
どちらも心理的な支援を必要としている方への援助を専門業務としていますが、公認心理師は、広く国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的として心理相談に応じ、心理に関する教育活動や情報提供活動を行います。
また、業務を行うにあたり、支援を必要としている方の主治医の指示を受けなければならないことが法律で明記されており、臨床心理士と異なる点です。
一方臨床心理士は、心理検査や心理療法を用いた支援を専門業務とし、支援を必要としている方の心理状態の査定をしながら支援にあたります。
また、臨床心理学の調査研究をしたり、心理的情報を提供する地域援助活動を行ったりします。
臨床現場での扱いの違い
心理職が活躍する領域はさまざまですが、特に医療機関では公認心理師と臨床心理士の扱いが異なります。
2018年の4月以降、これまで「臨床心理技術者」と記されていた診療報酬上の心理職の範囲が「公認心理師」に統一されました。
これにより、臨床心理士では診療報酬を算定できなくなり、公認心理師が治療に加わることにより診療報酬が算定できるようになりました。
以降、公認心理師を要件とする診療報酬算定は年々増えていますので、臨床心理士との違いといえます。
両方の資格とも医療や教育、産業、福祉、司法の知識が必要であることは共通しています。今後、公認心理師の資格を保有している人が増えてくることが考えられ、それにともなって、公認心理師資格を持っていないとできない業務が増加する可能性があります。
以下の記事では、公認心理師と臨床心理士について、それぞれ詳しく記載していますので、この記事とあわせて参考にしてください。
仕事内容の違い
公認心理師と臨床心理士の仕事内容には大きな違いはありませんが、公認心理師法概要や公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会では、それぞれ以下のように仕事内容を定めています。
【公認心理師のおもな仕事内容】
- 心理状態の観察と結果の分析
- 心理に関する相談や助言、指導、援助等
- ご家族など関係者に対する相談や助言、指導、援助等
- 心の健康に関する教育、情報提供
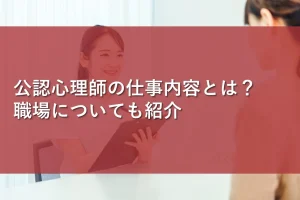
【臨床心理士のおもな仕事内容】
- 心理テストや観察面接などを通して行う臨床心理査定
- クライエントの心の支援を行う臨床心理面接
- 地域住民や学校、職場などを対象とした臨床心理的地域援助
- 上記に関する調査・研究
資格の違い
公認心理師と臨床心理士で最も大きな違いは資格でしょう。
公認心理師は国家資格ですが、臨床心理士は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格です。
公認心理師は大学と大学院で指定された科目を履修することにより、公認心理師試験の受験資格を得ることができます。
大学院の在学中に受検可能で、試験は筆記のみです。合格すれば、修了前に資格を得ることができます。
その他にも、大学で指定された科目を履修したうえで2年以上の実務経験を積むことや、それに等しい知識や技能があると認定されることで国家試験の受験資格を得ることが可能です。
特例措置として、2018~2022年の5年間は心理学を十分に学んでいない方にも広く受検資格が与えられ、2022年度の特例措置受検者は全体の90%以上を占めていました。
更新制度はなく、一度取得すれば生涯使うことのできる資格です。

一方、臨床心理士は指定の大学院を修了したり、医師免許取得後に心理臨床経験2年以上を有するなどの条件を満たしたりすれば、臨床心理士試験の受験資格を得ることが可能です。
大学院の在学中には受験できないため、修了したあとに受検することになります。
筆記試験と面接試験があり、合格すれば、翌年の4月から資格を得ることができます。
臨床心理士の資格は、5年毎に資格更新審査があります。
研修に参加するなどしてポイントを貯める必要があり、日々臨床心理士としての知識の向上が必要です。
| 公認心理師 | 臨床心理士 |
| 国家資格 | 民間資格(公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会) |
| 更新制度無し | 5年ごとの資格更新制度 |
| ・2017~2023年の登録者数合計:69,875名 ・受験者数:毎年10,000~30,000名程度 (第6回2023年は2,020名 ) |
・1988~2023年の認定数合計:40,749名 ・受験者数:毎年2,000名程度 |
※2023年12月時点
年収の違い
現時点では、臨床心理士と公認心理師の年収の細かな違いは不明です。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、「その他の保健医療従事者」として臨床心理士と公認心理師を含めた業種の平均年収を公表しています。
上記によると、公認心理師や臨床心理士を含む保健医療従事者の平均年収は、約443万円です。
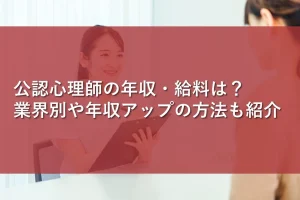
就職先の違い
公認心理師と臨床心理士の就職先は、現時点ではほぼ同じです。
以下に、公認心理師と臨床心理士のおもな就職先を記載します。
【公認心理師と臨床心理士の就職先】
- 介護老人保健施設
- 子ども・若者総合相談センター
- 学校
- 裁判所
- 生活支援センター
- 病院
- 児童相談所
- 障がい者センター
- 一般企業の健康管理室 など
公認心理師と臨床心理士のどちらを選ぶべき?

現時点では、公認心理師と臨床心理士どちらをめざしたほうが良いのかということは一概にはいえません。
別の見出しでも説明しているように、公認心理師と臨床心理士には資格に違いがあるため、資格を取得するにあたって、チャレンジしやすいほうを選ぶのも一つの手です。
また、公認心理師と臨床心理士はどちらも心理学について学ぶもので、両方とも大学院に進むことが主なルートであり、試験範囲が一部共通していることから、ダブルライセンスをめざすのもおすすめです。
公認心理師の活動調査では、公認心理師単独ライセンスの方は6.5%であり、臨床心理士を含む心理系の資格を持つ方は50.4%いることがわかっています。
臨床心理士は以前より存在する資格のため信頼度が高いですが、国家資格という魅力も相まって公認心理師の需要の高まりも期待できるでしょう。
臨床心理士と公認心理師の違いを知ろう
2017年に誕生した比較的新しい資格である公認心理師は国家資格で、臨床心理士は民間資格です。
どちらも心理的な支援を必要としている方への援助を専門業務としていて、ダブルライセンスの方もいます。
今後、公認心理師の業務上の立ち位置が確立されていくにつれ、2つの資格における業務上の違いが出る可能性があります。
どちらの資格の取得をめざしたほうが良いかといったことは、現時点では厳密にはいえませんが、自分の性格や能力と比較して、自分に向いている資格を選びましょう。