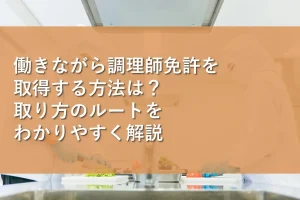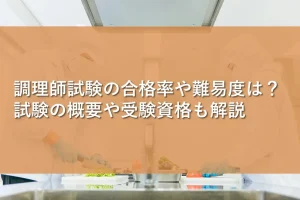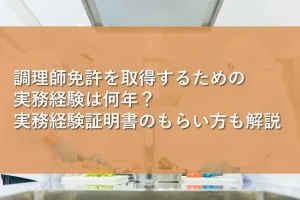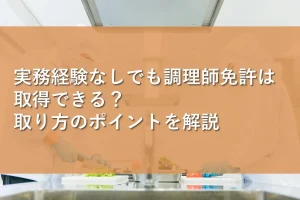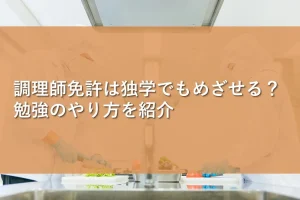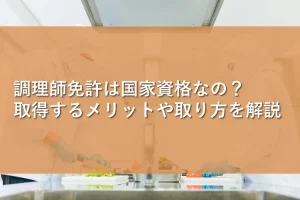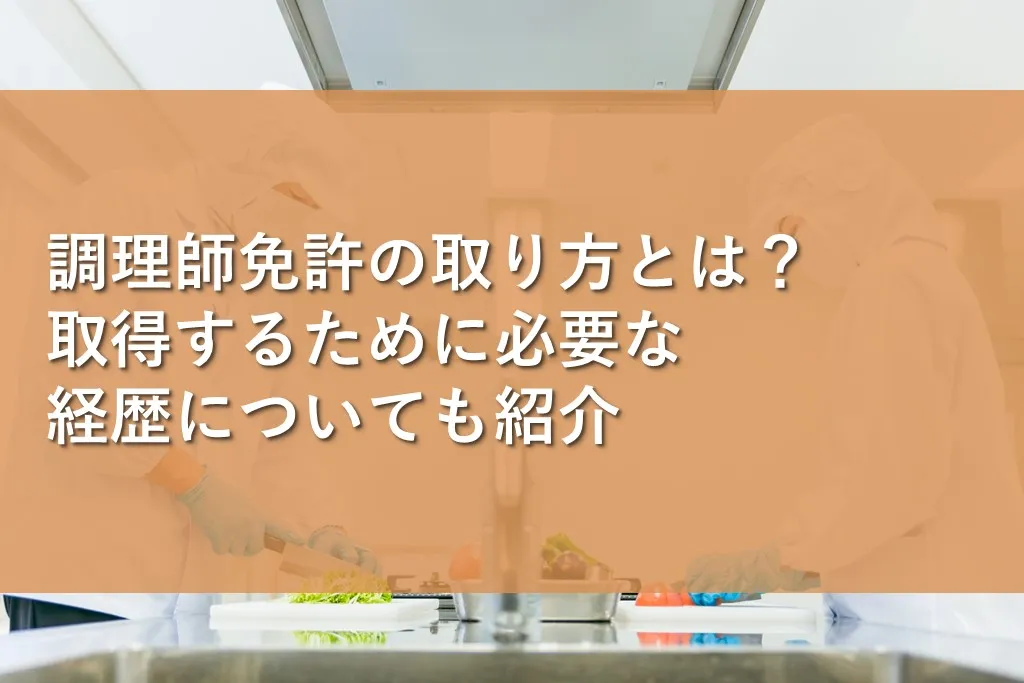
調理師免許は、食に関する知識や技術を有していると証明できる国家資格です。
将来、飲食業界で活躍したいと考えている場合、調理師免許を持っていると有利に働くことがあります。
しかし、調理師免許を取るには複数の条件があります。
そこでこの記事では、調理師免許の取り方を解説します。
ぜひ今後のキャリアプランの選択にご活用ください。
目次
調理師免許の取得方法と必要な資格

調理師免許の取得方法は、2つあります。
- 調理師養成施設を卒業
- 実務経験を積み、調理師試験に合格
調理師試験の受験資格は以下のとおりです。
- 学歴は中学校卒業以上
- 2年以上の調理業務
- 週4日以上かつ1日6時間以上の勤務
- 定められた施設で調理勤務していること
上記の条件を満たすと調理師試験を受けられるので、実務経験を積んでから調理師免許を取得する人もいます。
取得方法1.調理師養成施設を卒業する
厚生労働大臣の指定を受けた調理師養成施設で学び、必要な単位を履修したうえで卒業と同時に取得できるルートです。
住所地の都道府県知事に申請を出すことで免許が交付されます。
最短1年で資格取得をめざせ、調理師試験を受ける必要もありません。
実務経験なしで調理師免許取得をめざすならこのルートがおすすめです。
プロの講師陣から技術や知識を得られるので、効率的に資格取得を狙えます。
学校によっては、在学中に決まった講座や試験を受けることで、調理師免許以外の下記のような資格を取得できる場合もあります。
- 食育インストラクター
- 食品衛生責任者
- 全調協実技検定グレード1 など
ただし当然、費用の負担や学業による時間の拘束はともないます。
学費は学校によってそれぞれ差があります。
授業も主に午前中から夕方にかけて行われるので、長期でのパート・アルバイトや会社勤めと両立させるのはハードであると予想されるでしょう。
夜間部がある施設もありますが、実習は16時からなど夕方から始まるケースもあるので、勤務調整や家庭との調整が必要になります。
取得方法2.調理師試験に合格する
養成所に通わずに、受験資格を満たしたうえで調理師試験を受けて資格取得をめざす方法です。
試験に合格後、住所地の都道府県知事に申請すれば調理師免許が交付されます。
では、調理師試験は1年に何回、どのような内容で行われるのでしょうか?
調理師試験は、年に1回、各都道府県で行われます。
試験科目は、以下の6項目で、4択のマークシート式です。
- 調理理論
- 食品衛生学
- 公衆衛生学
- 栄養学
- 食品学
- 食文化概論
都道府県によって採点基準は異なりますが、合格するには全科目で6割の正答率を獲得しなければなりません。
なお、調理師試験には、受験に必要な一定の条件が設けられています。
調理師試験の受験資格とはどのような内容なのでしょうか?
次でそれぞれの要件を解説します。
受験に必要な資格1:中学校卒業以上の学歴である
調理師試験の受験資格の1つが、中学校卒業以上の学歴を持っていること、もしくは同等の学歴があることです。
中学卒業と同等の学歴を持つとは、学校教育法57条で定められている学校や課程を修了した者のことを指します。
また文部科学省が実施する就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験に合格すれば、中学卒業と同等の学歴を取得できます。
詳しくは文部科学省の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験でご確認ください。
受験に必要な資格2:2年以上の調理実務経験がある
調理師試験を受けるには、2年以上の調理実務経験が必要です。
調理師養成施設経由での資格取得では、実務経験を問われることはありません。
対して調理師試験を受験して資格を取得するためには、一定の学歴に加え、実務経験が必要となるのです。
なお、1つの勤務先で2年以上継続して実務経験を積む必要はなく、複数の勤務先の勤務期間を合算しても条件は整います。
ただし、同時に複数の勤務先で調理していた場合は、合算できません。
週4日以上かつ1日6時間以上の勤務経験
勤務日数や勤務時間などの実務内容にも規定があります。
週に4日以上、かつ1日6時間以上の勤務が必要です。
この条件は正職員以外のパート・アルバイトであっても同様です。
ちなみに大阪府や京都府などの関西広域連合では、「週4日以上かつ24時間以上(週4日×1日6時間、週5日×1日5時間、週6日×1日4時間など)」と規定されています。
受験予定地によって規定が若干異なる場合があるため、あらかじめ受験予定地の受験資格を確認しておきましょう。
定められた施設で勤務すること
調理実務経験と認められるには、調理師法施行規則で定められた施設で勤務していなければなりません。
定められた施設とは、以下のように定義されています。
- 飲食店営業(喫茶店は除く)
- 魚介類販売業(販売のみは除く)
- そうざい製造業
- 寄宿舎、学校、病院などの給食施設(1回20食以上または1日50食以上を継続して提供)
たとえばカフェなどのパート・アルバイトでは、お店の届け出が、喫茶店営業か飲食店営業かによって受験資格が得られるかどうかが異なります。
飲食店営業として届けており、実際に調理して食事を提供している施設での勤務であれば実務経験として認められます。
該当しない職場で勤務していたとならないよう、調理師免許の実務経験にあたる職場なのか確認が必要です。
食品製造や飲料調整など、業務内容によっては調理業務として認められないケースもあります。
勤務しているお店が調理師免許の実務経験にあたるかわからない場合は、以下の記事を読んで確認しておきましょう。
実務経験にあたる施設の具体例、調理業務従事証明書のもらい方などを詳しく説明しています。
調理師免許の取得にあたって知っておきたいこと
調理師試験は、都道府県ごとに年1回行われ、試験問題・実施日時は各都道府県によって異なります。
ただし、試験科目や出題範囲は全国で同じです。
試験問題は専門的かつ広範囲であるため、いずれの科目もまんべんなく勉強しましょう。
試験科目や出題範囲は?
調理師試験の科目は、以下の6つが出題されます。
- 公衆衛生学
- 食品学
- 栄養学
- 食品衛生学
- 調理理論
- 食文化概論
1科目でも平均点より低い点数を取ると、他の科目が満点だとしても不合格です。
合格するには、いずれの科目も偏りなく勉強する必要があります。
調理師試験に実技試験はなく、すべて筆記試験です。
問題数は全60問で、4択問題をマークシート形式で回答します。
調理師試験の試験内容・申し込み方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
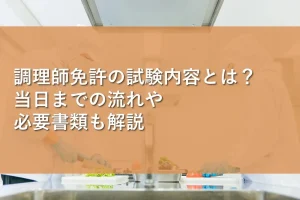
合格率はどのくらい?
調理師試験は都道府県によって問題が異なるため、合格率も各都道府県で違いがあります。
令和3年度の合格率の全国平均は約65%で、過去3年間の合格率の全国平均は65〜70%程度でした。
調理師免許の合格ボーダーラインは、全科目の合計点数に対して60%以上です。
ただし、1科目でも平均点を大幅に下回ると不合格になるので、得意な科目だけを勉強するのは避けましょう。
調理師試験の都道府県ごとの合格率・難易度に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
働きながらでも取得できる?
調理師免許を働きながら取得する方法は、次の4つです。
- 日中働きながら、調理師専門学校の夜間コースを卒業する
- 日中働いて実務経験を2年以上積み、独学で調理師試験に合格する
- 夜間働きながら、調理師専門学校の日中コースを卒業する
- 夜間働いて実務経験を2年以上積み、独学で調理師試験に合格する
大きく分けると、「調理師専門学校に通う方法」か「2年以上働いて実務経験を積んで試験を受ける方法」があります。
調理師免許を働きながら取る方法に関しては、以下の記事をご参照ください。
実務経験がなくても取得できる?
調理師免許取得は、現段階で実務経験がなくてもめざせます。
実務経験がない場合、以下の方法を取りましょう。
- 調理師専門学校を卒業する
- これから調理の実務経験を2年以上積み、調理師試験に合格する
調理師免許は、調理師専門学校に1年以上通学し、養成課程を終了すると取得できます。
専門学校に通学しない場合は、今後調理に関する実務を2年以上経験する必要があります。
実務経験がない方の調理師免許の取得方法に関しては、以下の記事をご参照ください。
実務経験と認められる店舗の例や働き方についても詳しく解説しています。
独学でもめざせるもの?
調理師免許取得は、独学でもめざせます。
ただし、調理師試験を受けるためには、まず調理の実務経験を2年以上積む必要があります。
先述したとおり、調理師試験の合格率は全国平均で約60%です。
参考書や問題集・過去問を利用し、試験対策を隅々まで行えば、独学でも合格できる可能性は十分あります。
とはいえ、調理師試験の出題範囲は広いので、独学で合格するには勉強にコツがいります。
実務経験を積みながら勉強する場合は、1日1〜2時間の学習を半年以上は続けると良いでしょう。
以下の記事では、調理師試験の独学での勉強法やおすすめテキスト・参考書を紹介しています。
調理師免許は国家資格に該当するの?
調理師免許は国家資格に該当します。
調理師は名称独占資格であり、調理師免許を所持していない人が調理師を名乗るのは法律で禁止されています。
この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0100000147
ただし、業務独占資格ではないので、調理師免許を持ってない場合でも調理業務は行えます。
調理師免許取得のメリットや取得方法に関しては、以下の記事をご覧ください。
現在のライフスタイルに合った調理師免許の取得を
調理師免許を取得するには、学校に通って卒業と同時に取得するか、実務経験を2年積んで試験に望むかの2パターンあります。
学校では学費や時間の拘束はあるものの、試験を受けることなく確実に資格が取得できるので効率的です。
試験を受ける場合は、実務経験を積みながら資格取得をめざせるので、金銭面の負担は少なく済みます。
しかし実務経験には細かな条件があり、試験に向けても独学や通信講座などで対策を施さなければなりません。
現在のライフスタイルを踏まえ、どちらが自分に合っているのか考えて、調理師免許の取得をめざしましょう。