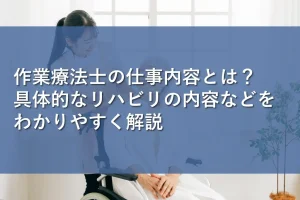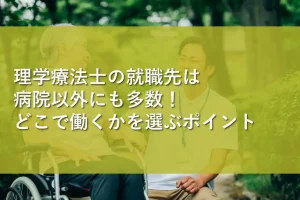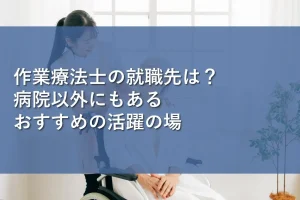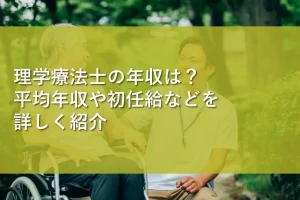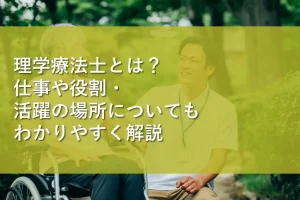作業療法士と理学療法士は似ているように感じるかもしれませんが、目的や仕事内容は大きく異なります。
今回は、理学療法士と作業療法士の違いを解説します。
また、両者の共通点についても併せて触れていくので、ぜひご参考ください。
目次
作業療法士と理学療法士の違い

作業療法士は、食事や入浴といった、日常生活をスムーズに送るための応用的動作のリハビリを主に行います。
一方で、理学療法士は、座る・立つなど基本的動作能力の回復をメインとしたリハビリを行うため、作業療法士とは専門となる領域が異なるのです。
他にも両者の違いはいくつかあります。主な違いは以下のとおりです。
| 理学療法士 | 作業療法士 | |
| 目的 | ● 基本的動作能力の改善・維持 ● 病気の悪化予防 |
● 応用動作の改善・維持 ● 社会活動への参加・適応 |
| 仕事内容 | ● 平行棒や手すり、補助具を利用した歩行 ● ベッドや椅子からの起き上がりや立ち上がり ● ベッドに横になる、寝返りをうつ |
● 食事:箸やスプーンの使い方 ● 入浴:頭や体を洗う ● 更衣:服やズボンを脱ぎ着する ● 排泄:ズボンを脱ぎ着して用を足す ● 料理:調理器具の使い方 |
| 働く場所 | ● 総合病院 ● 介護老人保健施設 ● 義肢装具や機器の開発 ● フィットネスクラブ |
● 総合病院 ● 精神科病棟 ● 小児病棟 ● 療養型施設 |
| 有資格者 | 192,327人(2021年度) | 99,776人(2020年度) |
| 試験科目 | 解剖学・生理学・運動学・病理学概論・臨床心理学・リハビリテーション医学・臨床医学大要・理学療法 | 解剖学・生理学・運動学・病理学概論・臨床心理学・リハビリテーション医学・臨床医学大要・作業療法 |
ここからは、理学療法士と作業療法士の違いをより具体的に解説します。
目的の違い
まずは、リハビリにおける理学療法士と作業療法士の目的の違いを解説します。
理学療法士
リハビリにおける理学療法士の目的は、基本的動作能力の改善・維持です。
基本的動作とは、起き上がる、立ち上がる、横たわる、寝返りをうつ、歩く、座るなどの動きのことです。
ケガや病気によって上記のような動きが難しくなった患者さんに対して、改善に向けたリハビリを行います。
特に高齢化が進む現代においては、高齢者の健康維持や、病気の悪化の予防などの役割も期待されています。
作業療法士
リハビリにおける作業療法士の目的は、応用動作の改善・維持と、社会活動へ参加・適応です。
応用動作とは、食事、洗顔、料理、字を書くなどの動きのことを指します。
社会活動とは、就労や就職、地域活動への参加などの事柄のことです。
手指の細かい動作などのリハビリを行い、その人が望んでいる生活の実現を目指すのが作業療法士の役割です。
また作業療法士は、精神科の患者さんの、社会復帰を目的とするリハビリにも携わります。
仕事内容の違い
理学療法士と作業療法士は、いずれも医師の指示のもと、患者さんのリハビリを行います。
ここではリハビリ内容の違いを解説します。
理学療法士
理学療法士が行うリハビリは、患者さんの筋肉や関節の動作能力を改善・維持させるための、運動療法や物理療法です。
下記にあげるものがその一例です。
- 平行棒や手すり、補助具を利用した歩行訓練
- ベッドや椅子からの起き上がる、立ち上がる練習
- ベッドへ横になる、寝返りをうつ練習
- マッサージや温熱刺激、電気刺激による物理療法
近年は高齢化に伴い、健康状態の維持を目的としたリハビリが増加傾向にあります。
また、理学療法士は身体動作の専門家として、スポーツ選手のケガ予防や、ケガからの復帰をサポートするリハビリを行うこともあります。
作業療法士
作業療法士が行うリハビリは、患者さんの応用動作を改善・維持し、社会活動への参加、適応を促すためのものです。
下記にあげるものがその一例です。
- 箸やスプーンを使う練習
- 入浴時に頭や体を洗う練習
- 服やズボンを脱ぎ着する練習
- ズボンを脱ぎ着して用を足す練習
- 調理器具を使う練習
リハビリは患者さんそれぞれの希望や悩みに寄り添って行い、場合によっては手工芸や仕事、遊びなどを取り入れることもあります。
また患者さんのなかには、それまであたり前に行えた生活動作ができなくなり、精神的ショックを受けている人もいます。
そのような患者さんの精神的ケアも作業療法士の仕事の一つです。
働く場所の違い
ここからは、理学療法士と作業療法士の働く場所の違いを解説します。
理学療法士
下記の表は理学療法士の働く場所を、6つの分野に分けてまとめたものです。
| 分野 | 働く場所 |
| 医療機関 | ● 総合病院、大学病院、整形外科病院 |
| 介護・福祉施設 | ● 介護老人保健施設 ● 特別養護老人ホーム ● 高齢者介護施設 ● 地域包括支援センター |
| 行政機関 | ● 保健センター ● 福祉センター |
| 企業 | ● 義肢装具や機器の開発 |
| スポーツトレーナー | ● プロチームや企業チーム |
| 教育・研究機関 | ● 理学療法学教育機関 ● 理学療法学研究施設 |
作業療法士
次に、作業療法士の働く場所を、主に4つの分野に分けてまとめました。
精神・小児分野まで、幅広い現場で活躍しています。
| 分野 | 働く場所 |
| 身体障がい | ● 総合病院、大学病院、整形外科病院 ● 身体障がい者福祉センター ● リハビリテーションセンター |
| 精神 | ● 精神科病院 ● 精神科デイケア ● 精神保健福祉センター ● 精神障がい者支援センター |
| 老年期 | ● 認知症専門病院 ● 療養型施設、老人保健施設 ● 特別養護老人ホーム ● 訪問看護ステーション |
| 発達障がい | ● 小児病棟 ● 発達障がい児支援センター ● 児童デイサービス ● 児童福祉施設 |
有資格者数の違い
理学療法士と作業療法士の有資格者は何人いるのでしょう。
下記の表は、作業療法士と理学療法士の有資格者数を年度別で示したものです。
| 年度 | 理学療法士(合格累計) | 作業療法士(有資格者数) |
| 2017年度 | 151,591人 | 84,947人 |
| 2018年度 | 161,476人 | 89,717人 |
| 2019年度 | 172,285人 | 94,255人 |
| 2020年度 | 182,893人 | 99,776人 |
| 2021年度 | 192,327人 | – |
また、理学療法士と作業療法士の両方で、毎年数千人以上も増加しています。
試験科目の違い
下記の表は、理学療法士と作業療法士の試験科目を示したものです。
| 理学療法士 | 作業療法士 | |
| 試験科目 | 解剖学・生理学・運動学・病理学概論・臨床心理学・リハビリテーション医学・臨床医学大要・理学療法 | 解剖学・生理学・運動学・病理学概論・臨床心理学・リハビリテーション医学・臨床医学大要・作業療法 |
試験科目は、理学療法と作業療法以外の科目は同じになります。
理学療法士も作業療法士も、国家試験は学校で学んだ内容がまんべんなく出されるため、短期間で学習して合格するのは困難です。
実技試験や実習で忙しくなるのを見越して、毎日の学習を復習し、国家試験対策につなげられるようにしましょう。
理学療法士と作業療法士の共通点
ここまでは、理学療法士と作業療法士の違いを解説しました。
次に、両者の共通するポイントを見てみましょう。
| 理学療法士 | 作業療法士 | |
| 平均年収 | 427万円 | 426万円 |
| 資格のとり方 | 高校 ↓ 大学・短大・養成施設・特別支援学校 ↓ 理学療法士国家試験 |
高校 ↓ 大学・短大・養成施設 ↓ 作業療法士国家試験 |
| 平均年齢 | 35歳 | 35歳 |
| 有効求人倍率 | 3.79倍 | 3.59倍 |
| 合格率 (2021年度) |
79.6% | 80.5% |
平均年収や資格取得の流れ、平均年齢などはほぼ同じです。
また有効求人倍率においては、理学療法士と作業療法士ともに求職者よりも求人数が多く、いずれも需要が十分にある職種といえます。
理学療法士と作業療法士の違いを理解して自分に合った職業を選ぼう
理学療法士は、「立つ・歩く」などの身体の大きな動きに対するリハビリの専門家で、作業療法士は、「食事動作・入浴動作」などの細かな動きに対するリハビリの専門家になります。
両者の違いを理解した上で、どちらを目指すのか判断してください。
また、理学療法士はPhysical Therapistの略称としてPTと呼ばれており、作業療法士のほか言語聴覚士とも比較されます。理学療法士の役割について気になる方は、こちらのページも確認してみてください。