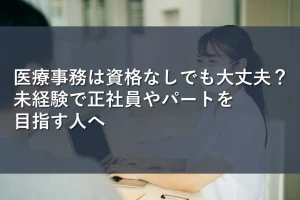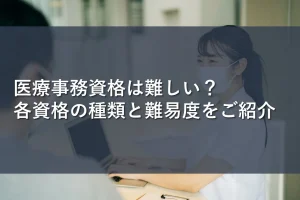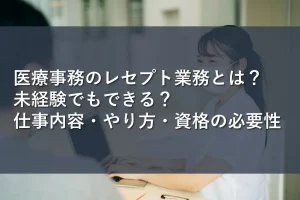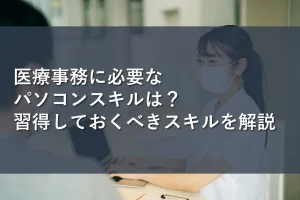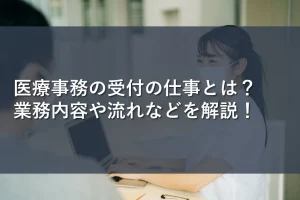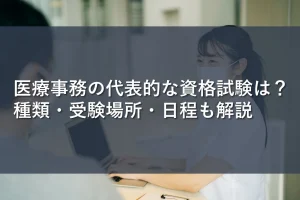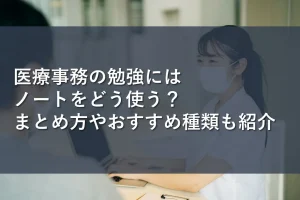会計・受付業務などを担い、医療機関の運営をサポートする医療事務は、無資格でも就業できる職種です。
とはいえ、医療事務の資格を取得することで、以下のようなメリットがあります。
- 採用に有利になる
- 資格手当が支給される
加えて、資格取得により医療事務の知識が身につき、仕事内容の理解も深まることから、資格取得に向けた勉強を考える方も少なくないでしょう。
しかし、資格取得にあたり「医療事務の勉強の仕方がわからない」「独学で資格取得できるの?」といった不安を感じることもあるかもしれません。
今回の記事では、医療事務の資格取得を検討している方に向けて、医療事務資格取得のための勉強法や学習すべき内容を紹介します。
まだ医療事務の資格取得を決めていない方は、こちらの記事を参考に資格取得の必要性について検討してみましょう。
目次
医療事務資格を取得するための勉強は難しい?

医療事務の資格は複数ありますが、どれも国家資格ではなく民間資格です。
医師や看護師などの国家資格には受験資格が設けられていますが、医療事務の資格は受験資格が設けられていないものも多く、資格取得のハードルは低いといえるでしょう。
医療事務の資格は種類によって合格率に約30%〜90%と差があり、試験の難易度は異なります。
また、教材や資料の持ち込みが可能な試験や自宅でも受験できる試験もあります。
試験内容は、レセプト(医療機関が発行する診療報酬の明細書)関連や医療保険・医療知識関連など、日常生活でなじみのない知識も問われるため、試験対策が必要です。
医療事務の資格の種類によって、試験内容や難易度は異なります。
どのような資格があるのか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみましょう。
医療事務の資格を取得するための勉強内容
医療事務の資格試験の出題形式・内容は、受験する試験によって異なりますが、おもに知識が問われるマークシート形式などの「学科」と、レセプト作成などの実践能力を測る「実技」があります。
医療事務の資格試験では、実際の業務に必要な知識・技術が身についているかを問われます。
そのため、出題内容も業務を行ううえで必要な基礎的な知識や実務的な内容が中心です。
それぞれの具体的な出題内容はおもに以下のとおりです。
【学科】
- 医療保険制度に関する基礎的な知識
- 医療事務知識
- 医療法の知識
- 医療用語や医学・薬学の基礎的な知識
- 診療報酬の知識
- 薬価基準の知識
- コンピューター関連の知識
【実技】
- レセプト作成・点検のスキル
- 患者さんへの接遇やマナーのスキル
| 資格取得に向けて必要な勉強内容 | 詳細 |
|---|---|
| レセプトに関する知識 | ・カルテの見方 ・レセプトの作成方法 ・医療保険制度の仕組み ・点検に関する知識や技術 など |
| 事務処理能力やパソコンスキル | ・書類やデータの整理などの基本的事務処理 ・ビジネスメールのやり取りの仕方 ・正確かつ、素早いタイピング |
| 窓口における対応に関する知識 | ・受付や会計業務、電話対応の仕方 ・正しい接遇マナーや言葉遣い ・伝わりやすい説明の仕方 |
医療事務の資格取得にはどのような勉強が必要なのか、具体的に見ていきましょう。
レセプトに関する知識
医療事務はレセプト(診療報酬明細書)を作成し、月に一度まとめて健康保険組合や共済組合、市区町村などの保険者に診療報酬請求を行います。
この業務を行うためには、レセプトの作成能力や医療保険制度の仕組みなどの知識が必要です。
診療報酬は、患者さんのカルテを見ながら、診療内容などをレセコン(レセプトコンピューター)に入力することで自動的に計算・集計され、診療報酬の集計結果からレセプトが作成されます。
そのため、カルテの見方やレセコンの操作方法を覚えることも大切です。
また、正確なレセプトを作成するために、医療事務にはレセプトの点検業務も求められます。
レセプトに間違いを見つけたら修正できるよう、点検に関する知識や技術も身につけていなければなりません。
事務処理能力やパソコンスキル
医療事務の仕事には、業者とやり取りをしたり書類を整理したりする業務もあるので、事務処理に関する知識も必要です。
患者さんの対応と並行するため、作業の正確さと同時に素早く処理する力も求められます。
また現在は、医療機関でも事務作業のIT化が進んでいます
どの医療機関でも当たり前のようにパソコンが使われているので、パソコンスキルも医療事務には必要不可欠です。
窓口における対応に関する知識
医療事務は、受付や会計業務、電話対応などの窓口業務も担います。
医療機関には応対マニュアルがないところも少なくありません。
自分の知識を活かして、臨機応変に対応していかなければならない場面が多々あります。
また、医療事務は患者さんと接する業務なので、接遇スキルやマナーも求められます。
患者さんやスタッフとのコミュニケーションに必要な、わかりやすく説明する力も磨いていかなければなりません。
医療事務の資格取得に向けたおすすめの勉強方法

医療事務の資格を取得するには、市販のテキストを使った独学、通信講座、専門学校・通学講座の3つの勉強方法があります。
それぞれの勉強方法にはメリットとデメリットがあるため、自分に合った学習方法を検討していきましょう。
| 勉強方法 | 特徴・向いている人 |
|---|---|
| 市販のテキストを使って独学 | ◆特徴 スケジュール管理や勉強の進め方など、すべてが自己管理のため挫折しやすいが、費用負担を抑えられる ◆向いている人 |
| 通信講座 | ◆特徴 独学よりも費用はかかるが、自分の好きなペースで、カリキュラムに沿って勉強を進められる ◆向いている人 |
| 医療事務の専門学校や通学講座 | ◆特徴 費用と時間がかかるが、学習スケジュールが確定・管理されているため挫折しにくい ◆向いている人 |
それぞれの勉強方法について詳しく解説していきます。
市販のテキストを使って独学
独学は市販のテキストや問題集を使って知識を身につける方法です。
独学の学習費用は問題集やテキストの購入費だけで済むので、気軽に始められます。
また、時間や場所の制約がなく自分のペースで勉強できるので、仕事や家事・育児などが忙しい人でも取り組みやすいこともメリットです。
ただし、勉強スケジュールを自己管理しなければならないので、忙しい、疲れたなどの理由で勉強しなくなってしまう人もいます。
強い意思を持って継続的に勉強できる人でないと、挫折しやすい点は独学のデメリットです。
また、独学用のテキストや問題集はたくさんあるので、どれを使って良いか迷ってしまうかもしれません。
学習時に効率よく勉強できなかったり、自分に合っていないテキストの場合は買い直したりするため、余計なお金がかかったりします。
独学におすすめのテキストや、試験問題集・過去問の入手方法は以下で紹介していますので、ぜひご参考ください。
通信講座で学ぶ
通信講座は独学よりも費用がかかりますが、試験対策に特化したテキストや問題集、講義の動画を通じて効率よく学ぶことができます。
勉強する時間や場所の制約は基本的になく、自分のペースで勉強を進められるので、忙しい人でも学びやすいでしょう。
試験までの学習カリキュラムやテキストが用意されており、手間なく計画的に勉強を進められる点もメリットです。
しかし、独学同様、気軽に取り組める反面、途中で投げ出してしまう人もいます。
通信講座で学習する際は、自分のモチベーションを保ちやすい講座を選ぶことが大事です。
気になる講座はサイトをチェックしたり資料請求をしたりして、教材の質やサポート内容などを細かく比較してみてください。
医療事務の専門学校や通学講座で学ぶ
医療事務資格を取得するための専門学校や通学スタイルの講座もあります。
学習スケジュールがしっかり管理され、勉強法も確立されているため、勉強の進め方がわからない、スケジュール管理が苦手で独学や通信講座では挫折しそうな人におすすめです。
専門学校や通学講座なら講師に直接質問できるので、疑問点をすぐに解消できるのもメリットです。
専門学校や通学講座のデメリットは費用と時間です。
通学講座の場合は10万円近く、専門学校となると100万円以上かかる場合もあり、独学や通信講座よりも費用がかかります。
また、通学が必要になるため、仕事や育児、介護などで忙しい人は利用しにくいでしょう。
卒業まで1~2年かかる場合もあり、資格を取るまでの期間は他の学習方法に比べて長くなってしまいます。
医療事務の勉強に関して知っておきたいこと
医療事務の勉強を始める前に、取得する資格を決める必要があります。
医療事務の資格の種類を絞ることで、試験の出題内容や特徴がわかり、勉強のやり方も決めやすいでしょう。
また、医療事務の勉強には、医療関連の法律や制度など少し難しくて気後れしてしまうような内容も含まれます。
医療事務未経験などで医療事務の知識がない場合は、最初に勉強する内容を知っておくと安心です。
勉強をする資格の種類
取得する資格試験に合わせて、勉強の方向性やスケジュールなどを決めていく必要があります。
そのため、まずはご自身が取得する資格の種類を決めていきましょう。
ここでは、医療事務の代表的な資格を4つご紹介します。
| 医療事務の代表的な4つの資格 | 詳細 |
|---|---|
| 医療事務技能審査試験 (メディカルクラーク) |
<特徴> ・医療事務の技能を問われる資格 ・医療事務のなかで最も受験者数の多い資格 ・認知度と信頼度が高いため採用に有利 <合格率>60~80% |
| 医療事務認定実務者試験 | <特徴> ・基本的な知識を有することを証明する資格 ・マークシート式の回答のため初心者でもチャレンジしやすい <合格率>60~80% |
| 医科 医療事務管理士技能認定試験 | <特徴> ・医療事務としての高い知識を有することを証明する資格 ・医療事務管理士として働くことができる ・待遇が良くなるケースもある <合格率>60~80% |
| 診療報酬請求事務能力認定試験 | <特徴> ・医療事務として就業している人のスキル向上を目的とした資格 ・医療事務資格のなかで最も難易度が高い ・資格手当がつくこともある <合格率>30〜40% |
今回ご紹介した資格以外にも、医療事務の資格は複数存在します。
こちらの記事を参考にして、医療事務の資格試験について種類ごとに概要を把握しておくと、ご自身に合った資格を見つけることができるでしょう。
受験初心者は何から勉強したほうがいいのか
独学で医療事務の資格取得をめざしている場合、まず何から勉強すれば良いのか悩んでしまう方も多いでしょう。
限られた勉強時間を有効に活用するために、まずは医療事務の専門用語の理解から始めることをおすすめします。
医療事務の試験問題には、「レセプト」「保険診療」「診療録」など、医療業界では基本的な用語ではあるものの、日常ではなじみのない用語が出てきます。
用語の意味を理解しなければ、問題の内容を理解できないでしょう。
そのため、まずは用語の理解から始め、ご自身の言葉で医療事務の専門用語を説明できる状態をめざしましょう。
なお、医療事務の資格取得にあたり、通信講座を検討する方においても、まず用語の意味だけご自身で勉強しておくと勉強内容が理解しやすくなります。
医療事務の資格を取得したいなら自分に合った勉強方法を選ぼう
医療事務の資格は、基本的に受験資格が定められていないため、誰でも挑戦できます。
まずは、それぞれの試験の内容や難易度を確認し、ご自身が取得する資格の種類を決めましょう。
医療事務の資格取得に必要な勉強内容は、どれも医療事務の業務に直結する大事な内容です。
未経験で実務に就いたばかりの頃は不明点が多いため、日々知識を深めたり、学んだ知識を確認できるよう、勉強のときからノートを取る癖をつけておくと就業してからも役立ちます。
医療事務のノートの取り方は、こちらの記事で紹介しています。
効率の良い学習ができるよう、勉強時に活用してみてください。